 介護士
介護士カイテクで副業してみたいけど、職場にバレるのが怖い……
収入の柱を増やしたい。
でも今の職場での立場を考えると、一歩踏み出せない。
その気持ち、痛いほどよくわかります。
結論から言うと、何の対策もしなければカイテクでの副業はバレる可能性があります。
でも、安心してください。
なぜバレるのか、その“理由”を理解して、正しい対策をすれば、リスクは限りなくゼロに近づけられます。
具体的にどんな場面で副業がバレやすいのか?
突き詰めると、ほぼこの4つに集約されます。
- 住民税の通知: 会社に届く住民税の決定通知書で、給与所得のズレから発覚するケース。
【住民税の支払い方法を変更すればOK】 - SNS・写真: 何気ない投稿から「あれ、この人うちの施設以外でも働いてる?」と気づかれるケース。
【SNSに投稿しなければOK】 - 他人に話す: 信用している相手に、副業していることを話してしまう。そこからウワサが広がる。
【誰にも言わなければOK】 - 過労・事故:働き過ぎて倒れたり、事故を起こしてバレるケース。
【無理をしなければOK】
上記の4つの原因さえしっかり押さえておけば、大半のリスクは回避できますよ。
この記事では、副業している介護士のぼくが、次の3つを徹底的に解説します。
- 副業がバレる理由
- バレないための10の対策
- 安全な副業の始め方
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー



詳しくはトップページのプロフィールに記載
副業がバレる“4つの理由”【原因と対策】



原因が分かれば、対策が見えてきます。
具体的に、バレる仕組みを掘り下げてみましょう。
住民税の通知で気づかれる仕組み
これが一番多いパターン。
会社員の場合、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」が一般的です。
副業で収入が増えると、その分住民税も増えます。
本業の会社に、市区町村から「あなたの会社の〇〇さんの住民税は、これだけの金額を天引きしてくださいね」という通知書が届きます。
その金額が、本業の給料から計算されるはずの金額より明らかに高いと、経理担当者が「おや?他に収入があるのかな?」と気づく、という仕組みです。
SNS・プロフィール・写真から身元がつながる
「まさか自分のSNSなんて見てないだろう」と思うかもしれませんが、意外なところから繋がります。
- 副業先の制服や名札が写った写真を投稿する
- 「〇〇市の特養で単発バイトなう」など、場所が特定できる投稿をする
- 本名や、本業で使っているニックネームをプロフィールに載せている
これらの情報が、本業の同僚や上司の目に触れる可能性はゼロではありません。特に、同僚とSNSで繋がっている場合は要注意です。
他人に話す
「この人は信用できるから大丈夫」
そう思って話してしまうと、ウワサは広まります。
なぜなら、人はウワサが好きだからです。
芸能人のスキャンダル、大好き。
職場内の不倫のウワサ、大好き。
とくに、いつも同じメンバーで仕事をしている、代わり映えのない環境ならなおさらです。
みんな刺激を求めているのです。
副業で収入が上がり、欲しかったブランド品を買うと嬉しくて、つい誰かに話したくなるのはわかります。
しかし、グッとこらえましょう。
自分で自分の首を絞めることになりますよ。
過労や事故で発覚するケース
これは直接バレる原因とは少し違いますが、結果的に問題が大きくなるケースです。
本業と副業の労働時間は通算して管理する必要があります。
たとえば、本業で週40時間働いた後、副業で8時間働けば、週48時間労働となります。
自分の限界を超えて無理な連勤を続けると、過労で倒れたり、仕事中に事故を起こしたりするリスクが高まります。
そうなった時、会社に副業の事実を伝えざるを得なくなり、安全配慮義務の観点から問題化してしまうのです。
これで安心!「バレない」ための10の対策



では、いよいよ具体的な対策です。
どれも難しいことではありません。
今日からできることばかりなので、ぜひチェックしてみてください。
①就業規則を読む(禁止/許可制/申請制の確認)
まずは敵を知ること。あなたの職場の就業規則を必ず確認しましょう。
「副業」に関する項目があるはずです。
- 禁止: 原則NG。それでもやりたい場合は、後述する章を参考に。
- 許可制/申請制: 上司や会社に申請すればOK。
- 規定なし: 基本的にはOKですが、念のため確認するのが無難です。
ルールを知らずに始めるのが一番危険です。
②副業は“離れたエリア”&“別の時間帯”が安心
人づてでバレる「現場かぶり」を避けるための最も有効な方法です。
- エリア: 本業の職場から、電車で2~3駅以上離れた場所を選ぶ。
- 時間帯: 本業が日勤メインなら、副業は夜勤や早朝にするなど、同僚と遭遇しにくい時間を選ぶ。
少し移動が大変でも、このひと手間で安心感が全く違います。
③プロフィールに個人特定情報を書かない
カイテクのプロフィールやSNSは、個人が特定できないように最小限の情報に留めましょう。
- 名前: 名字だけのひらがな表記や、ニックネームにする。
- 自己紹介: 経験年数や得意なケアなど、スキル面のアピールに留める。「〇〇法人で10年勤務」のような具体的な経歴は書かない。
④SNSの公開設定・顔出し・制服写真をやめる
もし介護の仕事について発信したいなら、専用の鍵付きアカウントを作りましょう。
- 公開設定: 友人・知人しか見られない設定にする。
- 顔出し: 極力避ける。載せるなら、スタンプで隠すか、後ろ姿にする。
- 制服・名札: 絶対に載せない。背景に施設名がわかるものが写り込んでいないかもチェック。
⑤知人への共有は最小限(うっかり拡散を防ぐ)
応援してほしい気持ちはわかりますが、副業のことは、本当に信頼できる人にだけ話しましょう。
同僚に話してしまうと、うっかり「〇〇さん、副業も頑張ってて偉いよね」なんて話が漏れるかもしれません。
⑥住民税の扱いを確認:普通徴収の選択可否など/税務の基本を理解)
税金の話は少し難しいですが、ここが一番のキモです。
副業の所得(カイテクは給与所得)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
その際、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択できます。
普通徴収を選択すれば、副業分の住民税の通知は自宅に届くため、会社にはバレません。
ちなにに、ぼくも普通徴収です。
納付書が自宅に届くので郵便局で支払っています。
ただし、自治体や会社の給与支払いの仕組みによっては、普通徴収が選べないこともあります。
事前に自分の市区町村のルールを確認しておくことが重要です。
⑦源泉徴収票・確定申告の書類管理(数字の整合性を保つ)
カイテクで働くと、源泉徴収票が発行されます。
確定申告をする際は、本業と副業、両方の源泉徴収票が必要です。
これらの書類はきちんと保管し、数字が食い違わないようにしましょう。
税務署からの問い合わせなどで、会社に連絡がいく事態は避けたいですからね。
⑧週の総労働時間を管理(無理な連勤をしない/事故・体調悪化防止)
自分の身を守るための、最も大切な対策です。
- 本業と副業を合わせて、週の労働時間は何時間か?
- 休日はきちんと確保できているか?
スマホのカレンダーアプリなどで労働時間を記録し、絶対に無理をしないこと。
本業の質を落とさないことが、副業を長く続ける秘訣です。
⑨守秘義務・個人情報に触れる投稿はしない
これは介護福祉士として、人として当然のことですが、改めて。
「今日担当した利用者さんが…」といった内容は、たとえ匿名でも絶対にSNSなどに書いてはいけません。
守秘義務違反は、副業がバレる以前に、あなたの社会的な信用を失う行為です。
⑩“副業の目的”と“撤退ライン”を決める
心理カウンセラーとして、これは強くお伝えしたいです。
「何のために副業をするのか」
「月いくら稼いだら、あるいはどんな状況になったら一旦ストップするか」を最初に決めましょう。
たとえば、「欲しいバッグを買うまで」「月に3万円まで」とかです。
目的が曖昧だと、ただ時給に流されて無理をしてしまったり、冷静な判断ができなかったりします。
目的と撤退ラインが明確であれば、精神的にも安定して取り組めます。
なぜ副業を禁止してる会社があるのか?:理由は本業への影響



そもそも、なぜ職場は副業を気にするのでしょうか?
一番の理由は「本業に支障が出ないか」です。
- 副業で疲れ果てて、日中のケアが疎かになる
- 夜勤明けにそのまま副業に行き、事故を起こす
- 副業先の情報を本業の職場で話してしまい、情報漏洩につながる
職場が心配しているのは、こういったことです。
つまり、就業規則を守り、本業のパフォーマンスを落とさない限り「過度に恐れる必要はない」という視点も大切です。
カイテクの働き方(単発・スポット)が副業に向く理由



なぜカイテクが介護職におすすめなのか。
理由は、「単発・スポット」という働き方にあります。
- シフトの縛りがない: 自分の休日や空き時間だけを選んで働ける。
- 人間関係がラク: その日限りの関係なので、面倒な派閥やしがらみがない。
- 本業との調整がカンタン: 「今月は忙しいからゼロ」「来月は余裕があるから3回」といった調整が自由自在。
- 面接・履歴書不要:面倒なことがないので、気軽に働ける。
継続的なアルバイトだと、どうしてもシフトの調整や人間関係で本業に影響が出がち。
ですが、カイテクなら自分の「体調」や「予定に」合わせられるので大丈夫。
ぼくがカイテクを副業に推す大きな理由です。
「カイテク」の招待コードをコピペする O7JzhuYB
\招待コード O7JzhuYB/
登録かんたん!履歴書・面接なしでラクラク
カイテクで副業の始め方【7ステップ】



「理論はわかった」
「じゃあ具体的にどう動けばいいの?」
という方のために、安全なスタートダッシュの方法を7つのステップにまとめました。
Step1 就業規則チェック
まずは、あなたの職場のルールブックである就業規則を確認。
もし「原則禁止」と書かれていても、すぐに諦める必要はありません。
信頼できる上司に「スキルアップのために、休日に月1回だけ外部で勉強させていただけませんか?」など、ポジティブな理由で相談してみるのも一つの手です。
それでも難しい場合は、副業OKの職場への転職を視野に入れる良い機会かもしれません。
Step2 収入目標と月の稼働時間を決める
「月3万円ほしいから、夜勤1回と日勤1回」
「お小遣いが月1万円増えればいいから、日勤1回だけ」
というように、具体的な目標と稼働時間を決めます。
「絶対に無理しない」ラインを先に決めておくことが、長く続けるコツです。
Step3 カイテクアプリをダウンロード
下のボタンから「公式アプリ」をダウンロードしましょう。
無料登録して、Step4に進みましょう。
「カイテク」の招待コードをコピペする O7JzhuYB
\招待コード O7JzhuYB/
登録かんたん!履歴書・面接なしでラクラク
Step4 勤務エリア・時間帯のフィルタ設定
カイテクのアプリで、仕事を探すエリアを設定します。
本業の職場がある近辺は避け、少し離れたエリアに設定しましょう。
時間帯も、同僚と遭遇しにくい休日や夜間などに絞って検索します。
Step5 プロフィール設定・SNSの見直し
カイテクに登録するプロフィールは、個人が特定されない範囲で、あなたの介護スキルが伝わる内容に。
そして、念のため自分のFacebookやX(旧Twitter)、Instagramの公開範囲や投稿内容を再チェックしましょう。
Step6 初回は小さくテスト(月1–2回)
いきなり全力で始めるのは危険です。
まずは月に1~2回から。
実際に働いてみて、
「体力的・精神的に無理はないか」
「職場の雰囲気はどうか」
「バレそうなリスクは感じないか」などを確認します。
このテスト期間で問題がなければ、少しずつ回数を増やしていきましょう。
関連記事はこちら
Step7 1か月働いたら振り返る
1か月働いてみたら、振り返りの時間を持ちましょう。
- 目標収入は達成できたか?
- 税金の準備は大丈夫か?(給与明細は保管しておく)
- 疲れは溜まっていないか?本業に影響は出ていないか?
この振り返りを毎月行うことで、あなたにとって最適な働き方が見つかります。
よくある「失敗例」と「対策例」



ヒヤッとする失敗例とその対策です。
1.同僚の知人がいる施設で勤務
「隣町だから大丈夫だろう」と高を括っていたら、同僚の知人が働いていて、世間話からバレそうになったケース。
【対策】
最低でも電車で2駅以上は離れたエリアを選びましょう。
また、いつも同じ曜日の同じ時間帯に働くと、「あの人、毎週水曜に来るよね」と覚えられやすくなるので、働く曜日を分散させるのも有効です。
2.制服・名札写真をSNSにUP
「新しい職場で頑張ってます!」というポジティブな投稿が仇になるケース。
制服のデザインや名札、背景に写り込んだ備品などから、意外と職場は特定できてしまいます。
【対策】
仕事に関する投稿をする際は、アカウントを鍵付きの非公開設定に。
投稿する写真からは、制服、名札、施設名がわかるポスターなど、特定につながる要素を徹底的に排除しましょう。
3.住民税の扱いを無理解
「よくわからないから」と税金の手続きを放置し、会社の経理から「給与、他にありますか?」と直接聞かれてしまうケース。
【対策】
副業所得が年間20万円を超えたなら、確定申告は必須です。
事前に「普通徴収」に変更しておきましょう。
確定申告が面倒なら、副業は年間20万円未満に抑えるのもあり。
4.連勤で体調悪化
「あと1回働けば目標金額に届くから…」と無理な連勤を重ね、本業の勤務中に体調を崩してしまったケース。
これが一番避けたい事態です。
【対策】
「休むことも仕事のうち」です。
体調が優れない時は、勇気を持って副業を休みましょう。
そして、そもそもその収入目標が今の自分に合っているのか、見直すことも大切です。
本業あっての副業、という大原則を忘れないでください。
副業禁止の職場でも“現実的に”できる?



就業規則で「副業禁止」と書かれていると、もう無理だと諦めてしまいますよね。
でも、少し立ち止まって考えてみましょう。
禁止の本当の理由は“本業の質”と“リスク管理”
会社が副業を禁止する本当の理由は、先にも述べた通り
「本業に支障をきたしてほしくない」
「情報漏洩や事故などのリスクを避けたい」
という2点に尽きます。
あなたを縛り付けたいわけではないのです。
質を落とさず、リスクを減らす働き方は可能
ということは、「本業の質を絶対に落とさず、会社が懸念するリスクを排除した働き方」なら、現実的に可能なのでは?と考えることもできます。
- 小さく始める: まずは月1回から。これなら疲労も溜まりにくい。
- 距離を取る: 物理的に離れたエリアで働く。これなら情報も混ざらない。
もちろん、規則を破ることを推奨するわけではありません。
しかし、どうしても収入が必要な場合や、スキルアップしたいという強い想いがあるなら、次の二択です。
- 細心の注意を払い、内緒で副業を始める
- 副業OKな会社に転職する
コソコソと副業するのがイヤなら、思い切って転職するのもありですよ。
介護業界は「売り手市場」です。
年齢に関係なく、かんたんに転職できます。
内緒で始めるか、転職して心おきなく始めるか。
あなたはどちらですか?
関連記事はこちら
不安を減らすチェックリスト



「副業禁止だけど、どうしても…」と考えているなら、下のチェックリストを活用してください。
一つでも「いいえ」があれば、今はまだ動くべき時ではありません。副業はやめてください。
チェックしてみよう
- 就業規則の内容と、禁止されている理由を理解したか?
- なぜ副業をしたいのか、目的は明確か?
- 本業のパフォーマンスを落とさないか?
- バレる三大要因(住民税、SNS、人づて)は理解できたか?
- 労働時間を管理し、過労にならない自信はあるか?
- 守秘義務を遵守し、仕事の話は一切外部に漏らさないか?
よくある質問Q&A
最後に、よくある質問をまとめました。
- 副業がバレる理由は?
-
よくある理由は、
①住民税、②SNS、③人づて、④過労・事故です。特に、会社に届く住民税の通知で気づかれることが多いですね。この3つに気をつければ、リスクはぐっと減りますよ。 - 住民税はどうすればいい?
-
確定申告の時に、副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、通知が自宅に届くので安心です。ただ、それができない場合もあるので、会社の経理から聞かれてもいいように、説明できる準備をしておくと、さらに安心ですね。
- SNSはやめたほうがいい?
-
やめる必要はありませんよ。ただ、誰でも見られる公開設定は避けて、信頼できる友人だけに公開するのがおすすめです。制服や名札が写った写真の投稿は絶対にやめましょう。
- どのくらい働くのが安全?
-
まずは月1~2回から、お試しで始めてみるのが一番安全です。体力的にも時間的にも「これなら全然余裕だな」と感じたら、少しずつ回数を増やしていくのがおすすめです。
- 職場が厳しい…それでもできる?
-
まずは就業規則を確認することが第一歩です。もし「禁止」と書かれていても、本業に支障が出ない範囲で、バレない対策を徹底して、小さく試している方もいます。ただ、リスクはゼロではないので、もし不安が強いなら、副業OKの職場に転職するのも前向きな選択肢です。
まとめ
バレるのは“理由”があるから。
理由を知れば、事前に対策できます。
具体的にどんな場面で副業がバレやすいのか、おさらいしましょう。
突き詰めると、ほぼこの4つに集約されます。
- 住民税の通知: 会社に届く住民税の決定通知書で、給与所得のズレから発覚するケース。
【住民税の支払い方法を変更すればOK】 - SNS・写真: 何気ない投稿から「あれ、この人うちの施設以外でも働いてる?」と気づかれるケース。
【SNSに投稿しなければOK】 - 他人に話す: 信用している相手に、副業していることを話してしまう。そこからウワサが広がる。
【誰にも言わなければOK】 - 過労・事故:働き過ぎて倒れたり、事故を起こしてバレるケース。
【無理をしなければOK】
まずは月1回から小さく始めて様子を見る。
問題がなければ少しずつ拡大。
今日からできる一歩で、あなたの未来は変わりますよ。
頑張るあなたを応援しています。
この機会に、あなたも「カイテク」に無料登録してみませんか?
招待コードをクリックしてコピーする
\ あなたのペースで働ける/
登録カンタン!履歴書・面接なしでラクラク


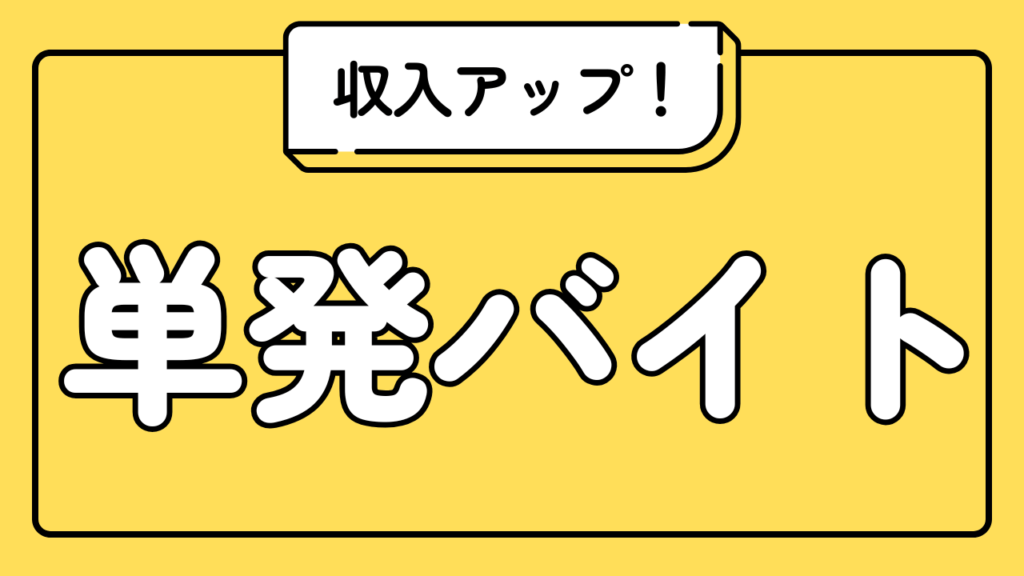
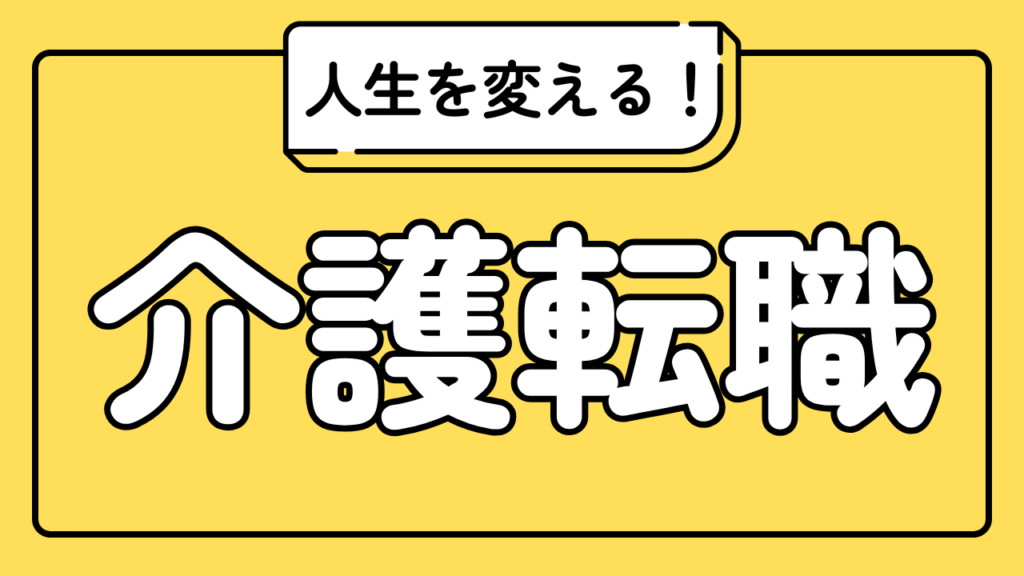


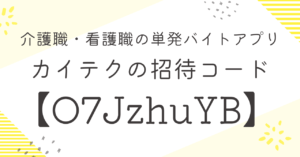



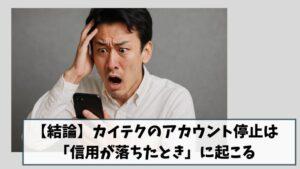
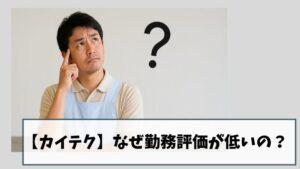

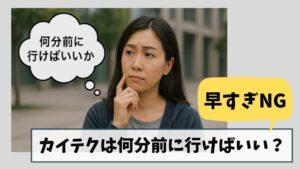

コメント