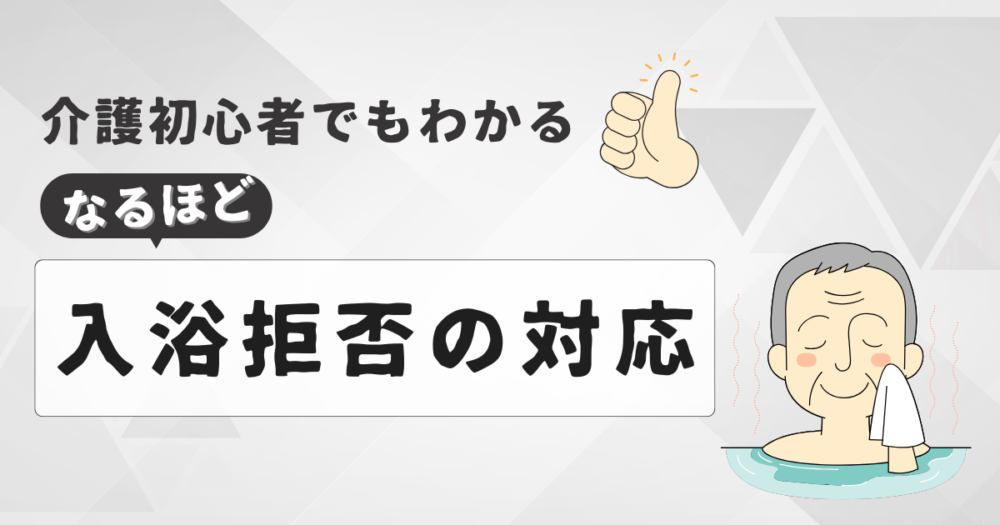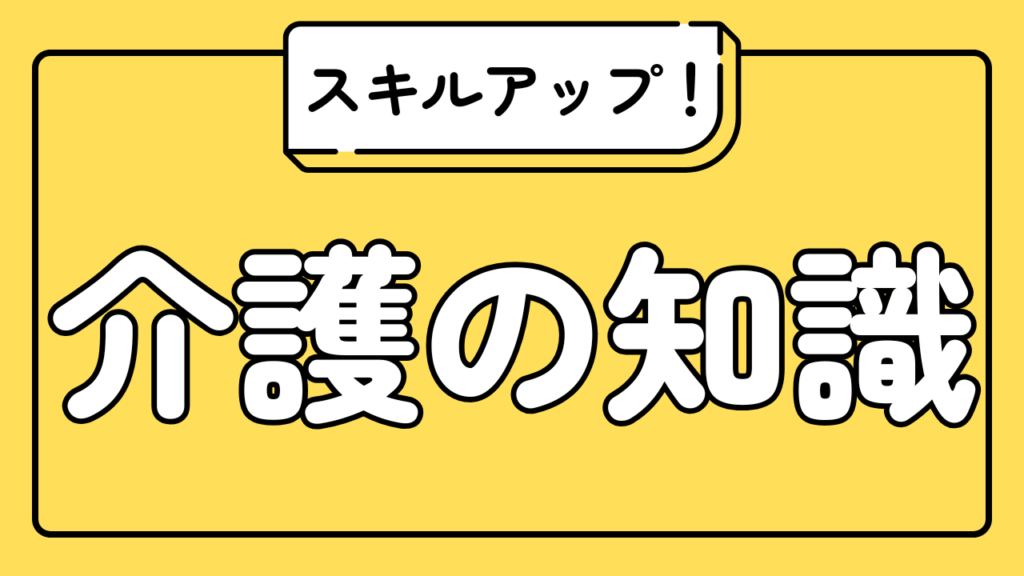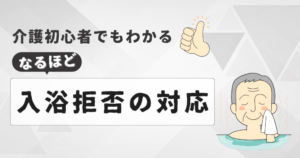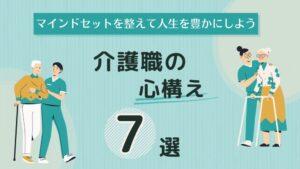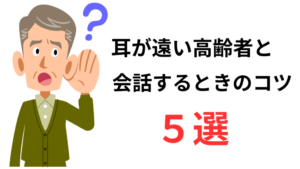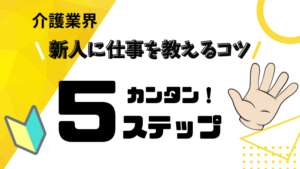当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
- 入浴をイヤがる主な理由は4つ:①体のこと(痛い・寒い)②気持ち(はずかしい・不安)③まわり(時間・部屋の寒さ)④声かけ(命令口調など)。
- コツは「少しずつ」と「安心」:手順を見せて、足湯→部分洗い→全身と段階アップ。タオルで体をかくす、同性の職員が手伝う、時間を変える、できたらしっかりほめる、などを試します。
- 記録して振り返る:できた回数・かかった時間・気分・肌のようすをメモ。ムリはせず、清拭や足湯などの代わりもOK。声かけ例:「今日は体ふくだけでOK」「5分だけ足湯しよう」
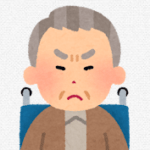 利用者さん
利用者さんお風呂に入りたくない!
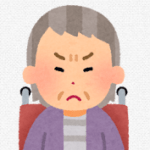
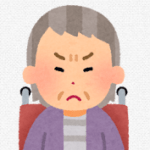
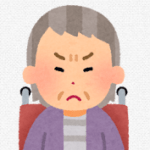
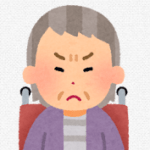
今日は絶対イヤ!
介護現場で本当に頭を悩ませる問題の一つが「入浴拒否」ですよね。
「昨日までは入ってくれたのに、今日はなぜ…」
「何を言っても『嫌だ』の一点張り…」
そんな経験、あなたにもありませんか?
利用者さんのためを思っているのに、拒否されると自分の介助がダメなのかと落ち込んだり、時間に追われて焦ってしまったり。
ぼくも若い頃は、力ずくで誘導しようとして失敗し、利用者さんとの関係をこじらせてしまった苦い経験があります。
でも、安心してください。入浴拒否には、必ず背景に「理由」があります。
入浴を拒否する理由さえ見抜ければ、対応の仕方は無限に見つかるんです。
この記事では、ぼくが15年以上の経験で培ってきた「入浴拒否への対応」の全てを、あなたに授けます。
単なるテクニック論ではありません。
- 原因の見立て方: なぜ拒否するのか?その本当の理由を見抜く「型」を伝授します。
- タイプ別アプローチ: 成功事例をもとに、あなたも明日から真似できる具体的な手順を解説します。
- 実践スクリプト: コピペOKの声かけテンプレで、もう言葉に悩みません。
- 関係性を壊さない: 入浴にこだわらない代替案や、やってはいけないNG行動もはっきりお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたは入浴拒否に対して自信を持って、落ち着いて対応できるようになっているはずです。
一緒に学んでいきましょう。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー



詳しくはトップページのプロフィールに記載
入浴拒否の「本当の理由」を見抜く:観察ポイントチェックリスト



入浴拒否の対応は「なぜ、その方は入浴を拒むのか?」という原因の仮説を立てることから始まります。いきなり説得しようとしても、空回りするだけです。まずは、名探偵になったつもりで、利用者さんをじっくり観察してみましょう。
ぼくが現場で使っているチェックリストです。これを頭に入れておくと、原因の見立てが格段にしやすくなりますよ。
身体要因
利用者さんの「今」の身体の状態はどうでしょうか?言葉にできない不調を抱えていることは本当に多いです。
- 痛み: 膝や腰が痛くて、浴槽をまたぐのが辛いのかもしれない。
- 寒さ: 脱衣所や浴室が寒くて、服を脱ぐのが億劫なのかもしれない。
- 疲労: レクリエーションで疲れて、今は休みたいだけなのかもしれない。
- 皮膚疾患: 湿疹や傷があって、お湯がしみるのかもしれない。
- 薬の副作用: 眠気やだるさを引き起こす薬を飲んでいないか。
- ふらつき: めまいがして、転ぶのが怖いのかもしれない。
心理要因
目に見えない「心」の中も、丁寧に想像してみましょう。特に認知症のある方は、様々な不安を抱えています。
- 不安: これから何をされるのか分からなくて怖い。
- 羞恥心: 人前で裸になるのが恥ずかしい。
- トラウマ: 過去に溺れかけた、お風呂で嫌な思いをした経験がある。
- 認知症による見当識障害: ここがどこか、あなたが誰か、なぜ服を脱ぐのかが理解できていない。
- 被害念慮: 「何か悪いことをされる」と思い込んでいる。
環境要因
利用者さんを取り巻く「環境」が、拒否の引き金になっていることもあります。
- 水温/室温: お湯が熱すぎたり、ぬるすぎたりしないか。室温は快適か。
- 時間帯: いつも入っている時間と違うことで、混乱していないか。
- スタッフの性別: 異性に体を洗われることに抵抗があるのかもしれない。
- 騒音: 他の利用者さんの声やシャワーの音が、不快に感じられていないか。
- 混雑: 人が多くて落ち着かないのかもしれない。
- 照明: 明るすぎて眩しい、または暗すぎて不安を感じていないか。
コミュニケーション要因
そして、一番見直しやすいのが、ぼくたち自身の「関わり方」です。
- 否定/命令口調: 「ダメです」「入りますよ」と一方的に伝えていないか。
- 説明不足: これから何をするのか、なぜそれが必要なのかを伝えているか。
- 選択肢なし: 「入る」か「入らないか」の二択しか提示していないのではないか。
- 急かし: こちらの都合で「早く、早く」と急かしていないか。
これらのチェックリストを使って、「Aさんは、最近膝が痛いと言っていたから、身体要因かな?」「Bさんは、新しい職員のぼくを見て不安そうだから、心理要因かも」といったように、原因の仮説を立ててみてください。
「仮説思考」こそが、プロへの第一歩です。
成功事例で学ぶ:タイプ別アプローチ



原因の仮説が立てられたら、次はいよいよアプローチです。
ここでは、ぼくが実際に経験した5つの成功事例を、あなたが現場で再現できるよう「Before→介入→After→記録」のテンプレートでご紹介します。
事例1:認知症で不安が強いAさん
- Before: 「お風呂?いや、さっき入ったから」と、入浴そのものを認識できず、スタッフが促すと「嫌だ!」と大声を出して拒否されていました。
- 介入:
- 見通し提示: 浴室の写真と時計のイラストが描かれたカードを見せ、「10時になったら、このお風呂で体を温めましょうね」と事前に伝える。タイマーをセットし、「ピピピと鳴ったらおしまいです」と終わりの見通しも提示。
- 手順の分割: 「まずはお部屋で上着を脱ぎましょうか」「次は脱衣所でズボンを…」と、一つの行動が終わってから次を伝えるスモールステップを徹底。
- 最後の一押しの褒め: 浴室に入れた時点で「すごい!ここまで来られましたね!」と具体的に褒め、行動を強化する。
- After: 拒否の頻度が週5回から週1回に減少。入浴にかかる時間も平均45分から30分に短縮。入浴後には「あー、気持ちよかった」という発言も聞かれるように。
- 記録例(SOAP):
- S: 「風呂は入らん」
- O: 居室にて入浴を促すも「入った」と強い拒否あり。写真カードで浴室への見通しを伝えると、少し落ち着かれ脱衣所まで移動可能。手順を分割して声かけすることで、洗体・洗髪まで完了。入浴後は「気持ちよかった」と笑顔あり。
- A: 認知症による見当識障害から、入浴という行為全体を理解できず不安を感じていた可能性。見通しの提示とスモールステップでの声かけが有効だったと考えられる。
- P: 次回も写真カードとタイマーを活用したアプローチを継続。本人の好きな演歌を浴室で流してみる。
事例2:皮膚トラブルが痛くて拒否するBさん
- Before: 乾燥による皮膚掻痒症があり、「お風呂に入ると体がかゆくなるから嫌だ」と拒否が続いていました。
- 介入:
- 段階付け: 無理に全身浴を勧めず、「今日は足だけでも温めませんか?」と足浴から提案。気持ちよさを感じてもらえた翌週は部分浴、その次に短時間の全身浴へとステップアップ。
- ぬるめ設定: お湯の温度を普段より1〜2度低い38〜39度に設定し、刺激を減らす。
- 保湿: 入浴後5分以内に、看護師処方の保湿剤を全身に塗布。「これで痒みが楽になりますよ」と効果を伝える。
- After: 週1回の足浴から始まり、2ヶ月後には週2回の全身浴が可能に。皮膚の乾燥状態も改善し、本人から「お風呂に入りたい」という発言も聞かれるようになった。
事例3:異性介助を嫌がるCさん
- Before: 男性スタッフが声をかけると、「男の人に体を触られたくない」と強い拒否を示されていました。
- 介入:
- 同性介助の確保: 勤務表を調整し、Cさんの入浴介助は必ず女性スタッフが担当する体制を組む。
- プライバシー保持: 洗体時も、洗う場所以外は必ずバスタオルで覆う「タオルワーク」を徹底。浴槽から出る際も、体にタオルをかけた状態で立てるように配慮。
- After: 異性介助への拒否はゼロに。安心して入浴されるようになり、スタッフとの信頼関係も向上した。
事例4:日中は拒否、夕方なら入れるDさん
- Before: 午前中の入浴を促すと、「まだ眠い」「気分が乗らない」と拒否が続いていました。
- 介入:
- 時間帯シフト: 本人の生活リズムを尊重し、比較的活動的になる夕食前の16時に変更。
- 小目標: 「夕飯の前に、5分だけ汗を流しませんか?」「今だけ・ここだけ・これだけ」と、目標を小さく限定的に伝える。
- After: 午前中は拒否していたのが嘘のように、夕方の入浴はスムーズに。生活リズムに合わせたケアの重要性を再認識した。
事例5:気力低下のEさん
- Before: うつ傾向があり、「何もしたくない」「面倒だ」と、全ての活動に対して意欲が低下し、入浴も拒否されていました。
- 介入:
- 意味づけ: 「お風呂に入ってさっぱりしたら、午後の散歩がもっと気持ちよくなりますよ」と、入浴を次の楽しい活動(散歩)と結びつけて提案。
- ペア支援: 声かけは馴染みのスタッフが行い、介助は別のスタッフが入るなど、役割を分担して心理的圧迫感を軽減。
- 達成感の言語化: 入浴後に「さっぱりしましたね!顔色も良くなりましたよ」と、ポジティブな変化を具体的に言葉にして伝える。
- After: 入浴が「義務」から「楽しみのための準備」へと意味合いが変わり、拒否が大幅に減少。本人の表情も明るくなった。
【3ステップ】入浴準備→声かけ→フォロー



事例を見てきましたが、これらを成功させるには共通の「型」があります。
それがこの「準備→声かけ→フォロー」の3ステップです。これを意識するだけで、あなたの介助は劇的に変わります。
ステップ1:準備(7つの環境調整)
利用者さんに声をかける前に、ぼくたちができることはたくさんあります。「おもてなし」の心で、最高の舞台を整えましょう。
- 室温/水温: 脱衣所は22〜25℃、浴室は25℃前後、お湯は40℃前後が目安。事前に温めておく。
- 滑り止め: 浴槽内や洗い場に滑り止めマットを敷き、安全を確保。
- 動線: 脱衣所から浴槽までの通り道に、障害物がないか確認。
- 照明: 明るさを確保し、不安感を取り除く。
- 物品先置き: 着替え、タオル、石鹸など、必要なものは全て手の届く場所に準備しておく。
- 緊急呼出: ナースコールの場所と動作を確認。
- 見守り配置: 必要に応じて、他のスタッフに応援を頼める体制を整えておく。
ステップ2:声かけテンプレ
準備が整ったら、いよいよ声かけです。
ポイントは「肯定→共感→選択肢→理由付け→小目標」の5つの要素を組み合わせることです。
基本の型: 「◯◯さん、お風呂に入りたくないんですね(肯定・共感)。でしたら、今日は足だけ温めるのと、温かいタオルで体を拭くの、どちらがいいですか?(選択肢)。体を温めると夜ぐっすり眠れますから(理由付け)、まずは5分だけ試してみませんか?(小目標)」
応用例:
- 「◯◯さん、今日は手を温めるだけにしましょう。3分で終わります。終わったら、ぼくと一緒に美味しいお茶にしましょう。」
- 「お風呂は嫌なんですね。分かります。じゃあ、背中だけ石鹸で流させてくれませんか?汗を流すと気持ちがいいですよ。」
ステップ3:フォロー
介助が終わったら、それで終わりではありません。
次につなげるフォローが何より重要です。
- 讃辞: 「気持ちよかったですね!」「ご協力ありがとうございました!」と、感謝とねぎらいの言葉をかける。
- 保清記録: 行ったケア(全身浴、部分浴、清拭など)と、その時の利用者さんの様子を正確に記録する。
- 次回の仮説更新: **「“うまくいった要因”を一言で残す」**のがプロの技です。例えば、「写真カードが有効だった」「演歌を流したら落ち着かれた」など、次のスタッフが見て分かるように記録しましょう。
入浴にこだわらない代替案



忘れてはいけないのは、ぼくたちの目的は「無理やりお風呂に入れること」ではなく、「利用者さんの心身の清潔を保ち、尊厳を守ること」だということです。
どうしても入浴が難しい日は、潔く切り替える勇気も必要です。
すぐ使える選択肢
- 清拭: 温かいタオルで全身を拭くだけでも、爽快感が得られ、血行も促進されます。
- 部分浴: 足浴、手浴、陰部洗浄、腋窩(脇の下)洗浄など、気になる部分だけでも清潔に。
- 洗髪キャップ: 水を使わずに頭皮の汚れを落とせる便利なグッズです。
- ドライシャンプー: 泡やスプレーで髪のべたつきを抑えます。
- 温タオル: 電子レンジや蒸し器で温めたタオルは、それだけでリラックス効果があります。
切替え基準
こんな時は、無理せず代替案に切り替えましょう。
- 体調不良: バイタルサイン(血圧、脈拍、体温)に異常がある時。
- 創部: 悪化の恐れがある傷や褥瘡がある時(医師・看護師に要確認)。
- 発熱: 37.5℃以上の発熱がある時。
- 転倒リスク: ふらつきが強く、安全が確保できないと判断した時。
これだけはNG:関係性を壊す地雷



良かれと思ってやったことが、利用者さんとの信頼関係を根底から壊してしまうことがあります。
以下の行動は「地雷」だと心得てください。
NGな対応
- 力づく: 無理やり腕を引っぱる、服を脱がせるなどの身体的拘束。
- 脅し: 「お風呂に入らないと、ご飯抜きですよ」といった脅迫的な言葉。
- 否定語連発: 「ダメ」「違う」「なんで分からないの」といった、相手を追い詰める言葉。
- 嘘の約束: 「すぐ終わるから」と言って、長時間拘束する。
- 同じ声かけの連打: 「さあ、行きましょう」と同じ言葉を何度も繰り返す。これは相手を追い詰めるだけです。
法倫理の基礎
介護は、常に利用者さんの「同意」のもとに行われるべきです。
- 同意の確認: どんなケアの前にも「〜してもよろしいですか?」と一声かける習慣を。
- 記録: 拒否があった場合、なぜ拒否があったのか、どう対応したのか、結果どうなったのかを客観的に記録することが、あなたの身を守ります。
- 家族説明: 拒否が続く場合は、その事実と対応策をご家族にしっかり説明し、理解を得ておくこと(インフォームドコンセント)。これが、後々のトラブルを防ぎます。
安全と根拠:初心者が押さえる感染対策&判断



安全と衛生は、介護の基本中の基本です。
特に初心者のうちは、判断に迷うこともあると思うので、基本をしっかり押さえておきましょう。
入浴頻度と皮膚ケアの目安
- 一般的に、高齢者の入浴は週2〜3回が目安とされていますが、個人の状態によります。
- 乾燥肌や痒みがある方には、熱いお湯や長湯は避け、ゴシゴシ洗いは厳禁です。
- 保湿剤は、皮膚が水分を一番含んでいる入浴後5〜10分以内に塗るのが最も効果的です。
医師・看護へのエスカレーション目安
自分の判断だけで進めず、専門職に相談・報告(エスカレーション)すべき状況です。
- 創傷・カテーテル: 褥瘡、傷、胃ろう、バルーンカテーテルなどがある方の入浴可否。
- 皮疹: 原因不明の発疹、水疱、ただれを発見した時。
- 発熱: 37.5℃以上の熱がある時。
- 転倒後: 頭を打った可能性がある場合など、入浴前に必ず報告。
介助者の感染対策
利用者さんだけでなく、ぼくたち自身を守るためにも必須です。
- 手指衛生: ケアの前後、手袋を外した後など、こまめな手洗い・手指消毒を。
- PPE(個人防護具): 必要に応じて、手袋、エプロン、マスクを着用。
- 浴室清掃: 定期的な清掃と換気で、カビや細菌の繁殖を防ぐ。
- 物品管理: タオルや着替えは、利用者さんごとに清潔なものを使用する。
家族・多職種連携のコツ



ぼくたち一人で抱え込む必要はありません。
チームで関わることで、最善のケアが見つかります。
ライフヒストリーを「入浴の意味」へ応用
ご家族から、その方の「生活史(ライフヒストリー)」を聞き出すことは、最高のヒントになります。
- 「昔はどんなお風呂が好きでしたか?」
- 「お風呂上がりに、何か楽しみにしていたことはありますか?」
- 「好きな石鹸の香りや、こだわりの入浴時間はありましたか?」
たとえば、
- 「昔は朝風呂が日課だった」と聞けば、入浴時間を朝に変えてみる。
- 「ひのきの香りが好きだった」と聞けば、ひのきの入浴剤を試してみる。
このように、その方にとっての「入浴の意味」を再現してあげることが、心を動かす鍵になります。
役割分担
- 介護職: 日々の様子や有効だった声かけを共有。
- 看護職: 皮膚状態のアセスメント、医療的観点からの入浴可否を判断。
- PT/OT(リハビリ職): 安全な移乗方法や、福祉用具の選定をアドバイス。
- ケアマネジャー: サービス担当者会議などで情報を集約し、ケアプランに反映。
情報共有フォーマット
口頭だけでなく、簡単なシートで共有すると、チーム全体のケアの質が上がります。
- 項目例: 「拒否要因の仮説」「有効だった声かけ・アプローチ」「安全上の配慮点」「次回試したいこと」などを一枚の紙にまとめて、情報共有ノートに挟んでおくだけでも効果絶大です。
記録テンプレ&評価指標



ケアは「やりっぱなし」ではいけません。
記録と評価を通じて、次のケアをより良いものにしていきましょう。
記録例
- SOAP/POSサンプル:
- #問題点: 入浴拒否
- S: 「風呂は嫌だ。面倒くさい」
- O: 14時、入浴を促すも居室から動かれず。好きな演歌を流し「5分だけ足湯だけでもどうですか?」と声かけしたところ、「それなら」と同意あり。足浴実施。表情穏やか。
- A: 全身浴へのハードルが高いが、好きな音楽と足浴という小目標の設定は有効だった。
- P: 次回も足浴から提案し、本人の気分が乗れば部分浴へと繋げていく。“有効だった一文”:「5分だけ足湯」
- ポイント: 何がうまくいったのか、特に「有効だった声かけの一文」を具体的に残すことで、他のスタッフも同じように成功体験を積みやすくなります。



KPI(重要業績評価指標)
難しく考える必要はありません。
ケアの成果を測る「ものさし」です。
- 入浴達成率: 週に何回、何らかの形で保清ができたか(全身浴、部分浴、清拭など)。
- 所要時間: 介助にかかった時間が短縮されているか。
- 満足度(表情・発言): 利用者さんの表情が明るくなったか。「気持ちよかった」などのポジティブな発言は増えたか。
- 皮膚状態: 皮膚トラブルが改善しているか。
毎週の振り返りチェック項目
- 今週、最も効果的だったアプローチは何か?
- 拒否が一番強かったのは、どんな状況だったか?
- チーム内で新しい情報を共有できたか?
- 次週、新しく試してみたいことはあるか?
よくある質問(Q&A)
現場でよく聞かれる質問に、Q&A形式でお答えします。
- 入浴は毎日必要?清拭に置き換える目安は?
-
毎日は必要ありません。高齢者の場合、皮脂の分泌が少ないため、洗いすぎはかえって皮膚トラブルの原因になります。週2〜3回が一般的です。本人の体調や気分が優れない日、拒否が強い日は、無理せず清拭や部分浴に切り替えましょう。
- 時間帯を変えるときのコツは?
-
本人が一番リラックスしている、あるいは活動的になっている時間帯を狙うのがコツです。食後すぐは避け、食間や就寝前などがおすすめです。一度試してダメでも、諦めずにいくつか他の時間帯も試してみましょう。
- 異性介助はどこまでOK?プライバシー配慮は?
-
原則として、本人が嫌がる異性介助は避けるべきです。やむを得ない場合は、必ず事前に「男性(女性)の私がお手伝いしてもよろしいですか?」と同意を得てください。介助中は、陰部など特にデリケートな部分は必ずタオルで隠すなど、最大限の配慮が求められます。
- 認知症で暴言が出るときの安全確保は?
-
まずは深追いせず、一度その場を離れてクールダウンしましょう。暴言は、不安や混乱のサインです。スタッフ一人で対応せず、必ず応援を呼び、複数名で対応してください。利用者さんとの物理的な距離を保ち、まずは落ち着いていただくことを最優先します。
- 介助者は何人必要?2名体制の判断は?
-
移乗や洗体時に転倒のリスクが高い方、体格の大きい方、認知症の周辺症状(BPSD)が見られる方などは、安全のために2名体制が望ましいです。アセスメントに基づき、ケアプランに位置づけておくことが重要です。
- 入浴後に疲れが強い場合の対策は?
-
長湯になっていないか、お湯の温度が高すぎないかを見直しましょう。入浴時間を短くしたり、シャワー浴や部分浴に切り替えたりするのも有効です。入浴後は、水分補給をしっかり行い、ゆっくり休める環境を整えてあげてください。
まとめ
- 入浴をイヤがる主な理由は4つ:①体のこと(痛い・寒い)②気持ち(はずかしい・不安)③まわり(時間・部屋の寒さ)④声かけ(命令口調など)。
- コツは「少しずつ」と「安心」:手順を見せて、足湯→部分洗い→全身と段階アップ。タオルで体をかくす、同性の職員が手伝う、時間を変える、できたらしっかりほめる、などを試します。
- 記録して振り返る:できた回数・かかった時間・気分・肌のようすをメモ。ムリはせず、清拭や足湯などの代わりもOK。声かけ例:「今日は体ふくだけでOK」「5分だけ足湯しよう」
ここまで、本当にお疲れ様でした。
入浴拒否の対応は、一つの「正解」があるわけではありません。
大切なのは、目の前の利用者さんをよく観察し、「なぜだろう?」と想像力を働かせ、仮説を立て、チームで試行錯誤していくプロセスそのものです。
あなたのその真摯な姿勢は、必ず利用者さんに伝わります。
最後に、今日からすぐに実践できるアクションプランをまとめました。
まずは、この中から一つでもいいので、試してみてください。
小さな一歩が、大きな変化を生み出します。
15分でできる環境調整3つ
- 利用者さんが来る前に、脱衣所と浴室を温めておく。
- 着替えとタオルを、順番通りに広げてセットしておく。
- 浴室に、その方の好きな音楽を小さな音で流しておく。
そのまま使える声かけフレーズ3つ
- 「お風呂はまた今度にして、今日は温かいタオルで体を拭きませんか?」
- 「5分だけ、足湯をしませんか?足が温まると、よく眠れますよ。」
- 「〇〇さんの好きな△△の石鹸、用意しましたよ。いい香りです。」
次回カンファで共有する“成功要因”の書き方
- 記録の片隅に、「(利用者さんの名前)さん、〇〇をしたら笑顔になった」と、うまくいった事実をメモしておく。
今日の学びが、あなたの介護を、そして利用者さんの笑顔を、少しでも増やすきっかけになることを、心から願っています。
一緒に頑張っていきましょう。
あなたを応援しています。
にほんブログ村
福祉・介護ランキング