結論:将来が見えない原因は「情報不足」と「選択肢の不明確さ」。
「このまま今の職場で働き続けて、本当に大丈夫なのかな…」
「給料も上がらないし、やりがいはあるけど、将来が不安…」
毎日、利用者さんのために一生懸命働いている中で、ふと、こんな気持ちになることはありませんか?
ぼくも15年以上、介護の現場にいますが、何度も同じような不安を感じてきました。
周りのスタッフはどんどん辞めていくし、自分だけが取り残されていくような感覚。
でも、大丈夫です。
不安の正体は、あなたに能力がないからではありません。
原因は、「情報が足りないこと」と「どんな選択肢があるか知らないこと」です。
この記事では、ぼく自身の経験と、心理カウンセラーとしての視点も交えながら、あなたの頭の中にあるモヤモヤを整理していきます。
難しい言葉は使いません。
一つひとつ、一緒に見ていきましょう。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載
なぜ将来が見えなくなるのか?
そもそも、なぜぼくたちは将来が見えなくなってしまうのでしょうか。
それには、介護現場特有の4つの理由があります。
理由1:情報が点在していて、比較ができない
「特養は大変そう」
「デイサービスは楽なのかな」
「訪問介護って一人で不安…」
こんな風に、断片的な情報は耳に入ってくるかもしれません。
でも、それぞれの働き方のメリット・デメリット、給与体系、キャリアパスまでを、ちゃんと比較できる情報って、実はほとんどないんです。
情報が点(てん)でバラバラになっているから、線としてつながらず、全体像が見えなくなってしまいます。
理由2:人間関係・忙しさで思考が止まりがち
毎日の記録、介助、レクリエーション、そして複雑な人間関係…。
心身ともにクタクタの状態で、自分の将来についてじっくり考える余裕なんて、なかなかないですよね。
心理学的に見ても、過度なストレスや疲労は、視野を狭くし、合理的な判断を難しくさせます。
「考えること自体が面倒くさい」と感じ、思考停止に陥ってしまうのは、ごく自然なことなんです。
理由3:「給料は上がらない」という思い込み
「介護職は給料が安い」「頑張っても評価されない」という言葉を、何度も耳にしてきたかもしれません。
確かに、何もしなければ給料は上がりにくいのが現実です。
でも、それは「絶対に上がらない」という意味ではありません。
- 資格の取り方
- 施設の選び方
- 働き方の工夫
上記のことを意識すれば、収入を上げられます。
「給料が上がらない」という思い込みが、あなたの可能性にフタをしてしまっているのです。
理由4:目標(期間・金額・役割)が数値化されていない
「いつまでに、いくらくらいの収入が欲しいのか」
「どんな役割(役職)になっていたいのか」
こうした具体的な目標がないと、ぼくたちはどこに向かって進めばいいのか分からなくなります。
ただ漠然と「将来が不安」と感じるだけで、具体的な行動に移せなくなってしまうのです。
誤解をほどく:よくある思い込みチェック



将来を考える上で、足かせになりがちな「思い込み」をここで一緒に解いていきましょう。
「資格がないと詰み」→段階的に積める現実的ルートはある
「どうせ自分は資格がないから…」と諦めていませんか?
大丈夫です。
介護の資格は、いきなり難関資格を目指す必要はありません。
- 介護職員初任者研修 → 実務者研修 → 介護福祉士
このように、働きながら段階的にステップアップできるルートがきちんと用意されています。
しかも、資格取得を支援してくれる職場もたくさんあります。
無資格から始めて、現場のスペシャリストになった方を、ぼくは何人も見てきました。
「年齢が高いと不利」→経験値が強みになる領域
「もう40代だから、新しいことなんて無理…」なんてことはありません。
むしろ、年齢を重ねて得た経験値は、介護現場では大きな強みになります。
特に、利用者さんやそのご家族とのコミュニケーション、予期せぬトラブルへの対応力、新人への指導など、経験がモノを言う場面は山ほどあります。
あなたの人生経験そのものが、価値になる仕事なんです。
「施設を変えても同じ」→施設種別×規模×加算体制で差が出る
「どこで働いても、介護の仕事は一緒でしょ?」これは、よくある誤解です。
実は、働く環境は、
- 施設の種類
- 規模
- 加算体制(※)
によって、給料も働きやすさも全く違います。
(※加算体制:専門的なケアなどを提供することで、国から事業所に追加で支払われる報酬のこと。これが職員の給与に反映されることがあります)
自分に合った環境を見つけるだけで、「こんなに働きやすい場所があったんだ!」と驚くことでしょう。
将来の選択肢マップ(キャリアの全体像)



では、具体的にどんな選択肢があるのか?
キャリアの全体像を地図のように見てみましょう。
あなたは、どの道に進みたいですか?
現場のスペシャリスト(認知症・口腔・排泄・リハ)
- 認知症ケア専門士
- レクリエーション介護士
- 福祉住環境コーディネーター
特定の分野の知識と技術を極める道です。
たとえば、「認知症ケア専門士」や「レクリエーション介護士」などを取得し、「この分野なら、あの人に聞け」と言われる存在になるキャリアです。
現場が好きで、利用者さんと深く関わりたい人に向いています。
リーダー/管理職
- ユニットリーダー
- 介護主任
- 施設長
チームをまとめるリーダーや、フロア全体を管理する主任、さらには施設長など、マネジメントの道に進むキャリアです。
スタッフの育成や、より良い職場環境づくりに興味がある人に向いています。
周辺職種・連携
- ケアマネ
- 生活相談員
- 採用・教育担当
直接的な身体介助だけでなく、ケアプランを作成する「ケアマネジャー」や、利用者さんやご家族の相談に乗る「生活相談員」、新しい仲間を採用したり、研修を担当する「採用・教育担当」など、現場経験を活かせる周辺職種はたくさんあります。
施設横断の働き方(単発・短期、派遣、スポット)
一つの施設に縛られず、様々な現場を経験する働き方です。
派遣会社に登録したり、スポット(単発)の仕事を探せるアプリを使ったりします。
「まずは色々な施設を見てみたい」「人間関係に縛られたくない」という人におすすめです。
副業・発信(講師、教材、ブログ/SNS)
介護の経験や知識を活かして、副業をする道もあります。
たとえば、介護職員初任者研修の講師をしたり、自身の経験をブログやSNSで発信したり。
介護の仕事と両立しながら、収入の柱を増やすことができます。
地域連携・小規模事業の立ち上げ
将来的には、自分で小規模なデイサービスや訪問介護事業所を立ち上げる、という選択肢もあります。
地域に根ざし、自分の理想とする介護を形にすることができます。
大きな夢ですが、決して不可能ではありません。
年収と働きやすさを両立する設計



「やりがいも大事だけど、やっぱり年収も働きやすさも譲れない…」 その気持ち、すごくよくわかります。
ここでは、その両方を手に入れるための具体的な考え方をお伝えします。
年収を伸ばす5つのポイント:夜勤・資格手当・加算理解・転職タイミング・副業/単発
年収を上げるには、主に5つのポイントがあります。
- 夜勤手当: やはり夜勤は収入アップの大きな要素です。回数や1回あたりの手当額は施設によって差があります。
- 資格手当: 介護福祉士やケアマネジャーなどの資格は、月々の給与に手当として反映されます。
- 加算の理解: 「処遇改善加算」など、職員の給与に直結する加算をしっかり取っている施設を選ぶことが重要です。
- 転職のタイミング: 経験を積んだり、資格を取得したタイミングは、より良い条件の職場へ移るチャンスです。
- 副業/単発: 休みの日に単発の仕事を入れるなど、本業以外の収入源を作ることも有効です。
働きやすさを上げる4条件:人員配置・教育体制・記録/ICT・管理者の方針
働きやすさは、この4つの条件で大きく変わります。
- 人員配置: 法律で定められた基準以上に、スタッフを多く配置しているかは、忙しさに直結します。
- 教育体制: 新人が入った時に、マンツーマンで教えてくれる先輩がいるか、定期的な研修があるかなど、学びの機会が保証されているかは重要です。
- 記録/ICT: 手書きの記録ばかりで時間がかかるのか、スマホやタブレットで簡単に入力できるのか。ICT化の進み具合で、業務効率は全く違います。
- 管理者の方針: 施設長や管理者が、スタッフの声に耳を傾け、働きやすい環境を作ろうとしてくれるか。これが一番大切かもしれません。
「時間単価」で比べる:残業・通勤・夜勤間隔まで含めて計算
給料の額面だけでなく、「時間単価」で考えるクセをつけましょう。
たとえば、
- A施設:月給25万円、残業月20時間、通勤60分
- B施設:月給24万円、残業ほぼゼロ、通勤20分
一見、A施設の方が給料は高いですが、残業時間や通勤時間という「拘束されている時間」まで含めて計算すると、実はB施設の方が「時間単価」は高い、というケースはよくあります。
(月給)÷(総労働時間+残業時間+通勤時間)= 実質的な時間単価
この視点を持つだけで、仕事選びの基準が変わってきます。
ケース別の年収レンジ
| キャリアパス | 年収レンジ(目安) | 到達までのステップ例 |
| 現場スペシャリスト | 350~500万円 | 介護福祉士取得後、認知症ケア専門士など複数の専門資格を取得。施設内で研修講師などを担当。 |
| リーダー/管理職 | 400~650万円 | 介護福祉士取得後、リーダー経験を積み、主任・相談員へ。その後、ケアマネや施設長を目指す。 |
| ケアマネジャー | 400~550万円 | 介護福祉士として5年以上の実務経験を積み、ケアマネジャー試験に合格。居宅または施設ケアマネとして勤務。 |
| Wワーク(本業+副業) | 380~500万円 | 本業で安定収入を得つつ、休日に単発バイトや、オンラインで介護に関する情報発信などで月5万円程度の副収入。 |
※あくまで一般的な目安であり、地域や施設によって異なります。
施設別・働き方:向いている人/向いていない人



自分に合った職場を見つけるために、代表的な施設の違いと、それぞれに向いている人の特徴を見ていきましょう。
特養/老健/グルホ/有料/デイ/訪問の違い
- 特養(特別養護老人ホーム): 終身利用が基本。医療ケアより生活支援が中心。体力が必要な場面も多い。
- 老健(介護老人保健施設): 在宅復帰を目指すリハビリ施設。多職種連携が活発。入退所が多く、慌ただしい。
- グルホ(グループホーム): 認知症の方が少人数で共同生活。家庭的な雰囲気で、一人ひとりと深く関われる。
- 有料(有料老人ホーム): 施設によってサービス内容や価格帯が多様。接遇マナーが重視される傾向。
- デイ(デイサービス): 日帰りで利用。レクや入浴が中心。夜勤がなく、日曜休みの場所も多い。
- 訪問(訪問介護): 利用者さんの自宅を訪問し、1対1でケア。自分のペースで働けるが、判断力と責任が求められる。
向いている人の特徴・合わない人のサイン
- テキパキ動きたい、多くの人と関わりたい人 → 特養、老健、大規模な有料・デイ
- 一人ひとりとじっくり向き合いたい人 → グルホ、小規模な有料、訪問
- 日中の時間で、規則正しく働きたい人 → デイサービス
- 自分の裁量で、自立して働きたい人 → 訪問介護
- 合わないサイン: 「早く終わらせること」ばかりが評価される、利用者さんとの対話の時間が全くない、と感じるなら、今の職場はあなたに合っていないのかもしれません。
ミスマッチを避ける見学・面接チェックリスト
見学や面接は、あなたが職場を「審査する」場でもあります。
ただ質問に答えるだけでなく、しっかりチェックしましょう。
<チェックリスト例>
- スタッフの表情: 笑顔はあるか?疲弊していないか?
- フロアの雰囲気: 職員同士の会話はあるか?怒鳴り声が聞こえないか?
- 掲示物: 研修の案内や、理念がきちんと掲示されているか?
- 質問: 「1日の残業は平均どれくらいですか?」「新人にはどのような研修制度がありますか?」など、働きやすさに関する質問を準備しておく。
3年・5年・10年のロードマップ(行動計画)
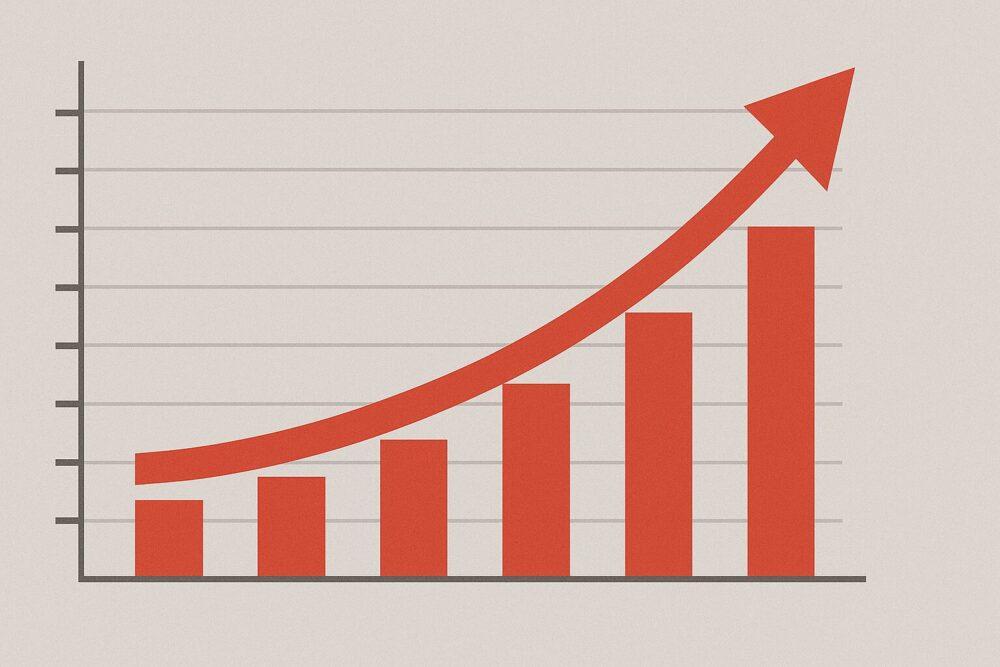
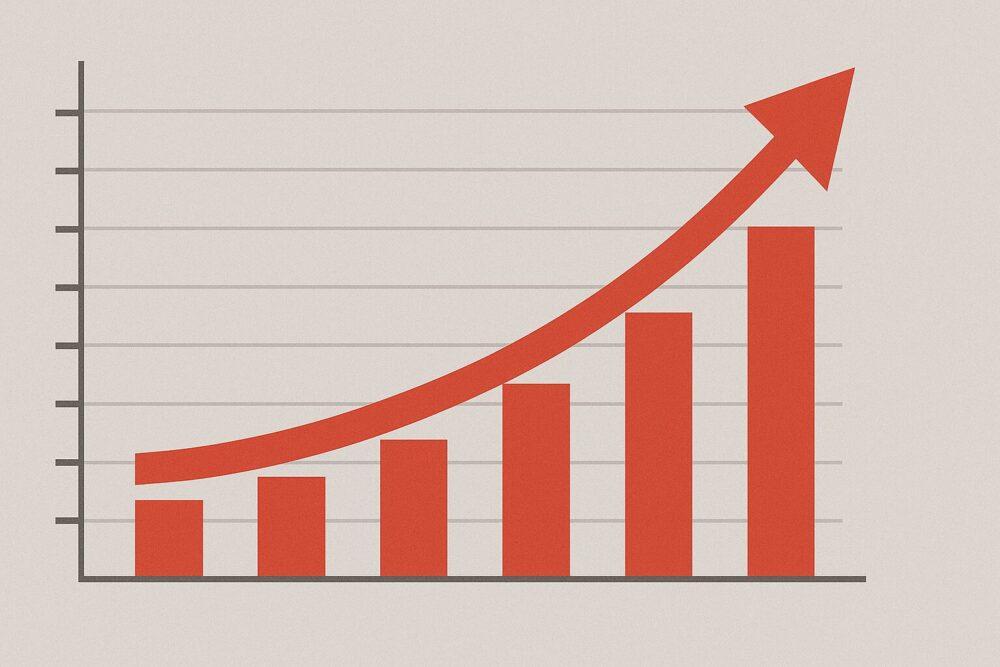
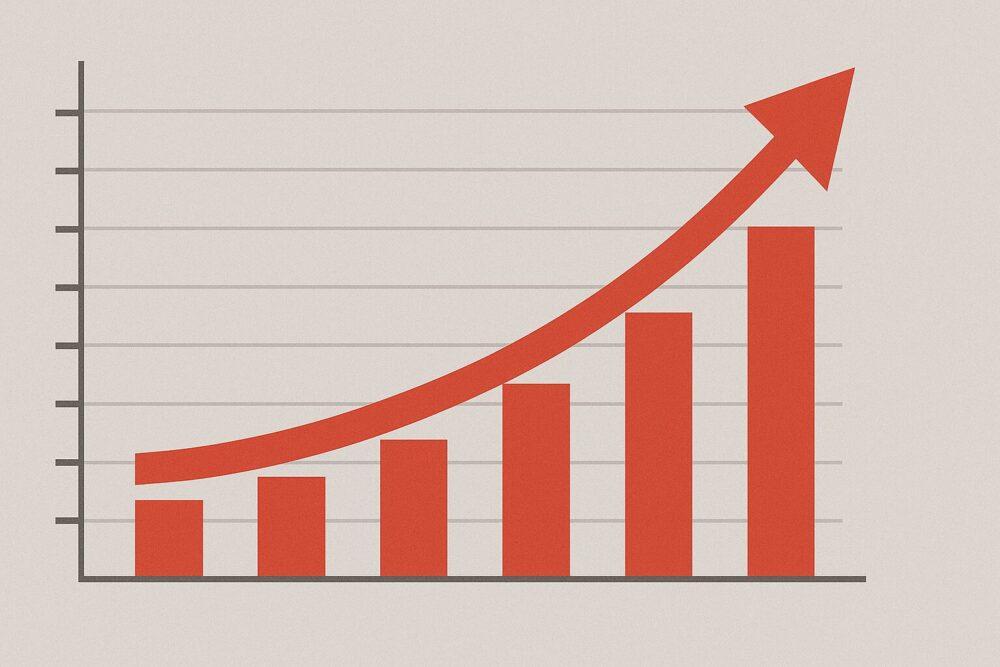
将来の地図を描くために、具体的な期間を区切って行動計画を立ててみましょう。
3年:土台を固める(記録力/事故ゼロ/強み1つ)
まずは、介護職としての基礎を固める時期です。
- 目標: 誰が見ても分かりやすい記録が書けるようになる。ヒヤリハットを減らし、事故ゼロを目指す。「入浴介助なら任せてください」など、何か一つでいいので、自分の強みを作る。
- 行動: 実務者研修を取得し、介護福祉士の受験資格を得る。
5年:役割を広げる(リーダー or 専門特化)
自分の適性に合わせて、キャリアの方向性を決める時期です。
- 目標(リーダーコース): チームリーダーとして、後輩の指導やシフト調整などを経験する。
- 目標(専門特化コース): 認知症ケアや看取りケアなど、特定の分野の研修に積極的に参加し、知識を深める。
- 行動: 介護福祉士を取得する。リーダー研修や、興味のある分野の資格(認知症ケア専門士など)の勉強を始める。
10年:運営・教育・地域づくりへ(複線化)
一つの専門性だけでなく、複数の役割を担う「複線化」を目指す時期です。
- 目標: 施設運営に関わる(主任・施設長)、新人教育の仕組みを作る、ケアマネとして地域と連携する、副業を始めるなど、自分の影響力の輪を広げる。
- 行動: ケアマネジャーや社会福祉士などの資格取得を検討する。経営やマネジメントに関する本を読む。
年次ごとの学び直し計画と資格ステップ
- 1~2年目: まずは初任者研修・実務者研修。現場の仕事を覚える。
- 3~5年目: 介護福祉士の取得を目指す。
- 6年目以降: ケアマネジャー、社会福祉士、精神保健福祉士、または認知症ケア専門士など、自分の進みたい道に合わせた資格を検討する。
今日からできる7日間アクション
「理屈は分かったけど、何から始めれば…」というあなたのために、今日から始められる具体的な7日間のアクションプランを用意しました。
- Day1:現状の棚卸し(疲れ・希望・強み) 紙とペンを用意して、「仕事の何に疲れている?」「本当はどんな働き方がしたい?」「自分のちょっとした強みは何だろう?」を書き出してみましょう。
- Day2:時間単価を計算 自分の給与明細と勤務記録を見て、「時間単価」を計算してみましょう。現実を知ることが第一歩です。
- Day3:施設種別の優先順位づけ 「施設・働き方カタログ」を参考に、自分に合いそうな施設の種類に1位、2位、3位と順位をつけてみましょう。
- Day4:経歴の言語化(職務経歴テンプレ) 今までどんな仕事をしてきたか、どんな工夫をしたかを書き出してみましょう。転職するしないに関わらず、自分のやってきたことを客観的に見ることは大切です。(※職務経歴書のテンプレートがあると親切です)
- Day5:見学アポ/質問シート準備 Day3で順位をつけた施設に、見学のお願いをしてみましょう。もしハードルが高ければ、まずは電話で問い合わせるだけでもOK。「見学・面接チェックリスト」を参考に、質問したいことをまとめておきましょう。
- Day6:求人比較表を作る 求人サイトを見て、気になる求人をいくつかピックアップし、「給与」「休日」「資格手当」「場所」などを一覧にしてみましょう。比較することで、条件の良し悪しが見えてきます。
- Day7:応募 or 異動相談/単発で試す 勇気を出して、求人に応募してみる。あるいは、今の職場で上司に異動の相談をしてみる。それが難しければ、まずは休みの日に「単発バイト」で他の施設を体験してみるのも、素晴らしい一歩です。
メンタルを守る:人間関係・ハラスメントの対処



将来を考える上で、心の健康は土台です。
ぼくも心理カウンセラーとして、多くの相談に乗ってきました。
ツラい人間関係から、自分の心を守る方法をお伝えします。
距離を取るルールを決める(関わる時間・チャネル固定)
苦手な人とは、物理的にも心理的にも距離を置くことが大切です。
「この人とは、仕事の申し送り以外では話さない」
「休憩時間は別の場所で過ごす」など、自分の中でルールを決めましょう。
関わる時間を意識的に減らすだけで、ストレスはかなり軽減されます。
記録の取り方(事実・日時・影響・対応/テンプレ配布)
もしハラスメントを受けているなら、必ず記録を取りましょう。
感情的に書くのではなく、「いつ、どこで、誰に、何を言われ(され)、どう感じ、どう対応したか」を客観的な事実として記録します。
記録が、後で誰かに相談する際に、あなたを守る強力な証拠になりますよ。
相談先一覧(社内/外部/公的機関)と切り出し方
一人で抱え込まないでください。
相談できる場所は必ずあります。
- 社内: 信頼できる上司や同僚、コンプライアンス窓口など。
- 外部: 地域の労働局、法テラス、NPO法人の相談窓口など。
- 切り出し方: 「少しお時間よろしいでしょうか。仕事のことでご相談したいことがあります」と、まずはアポイントを取るのがおすすめです。記録を見せながら話すと、状況が伝わりやすくなります。



公的データ・制度を根拠に意思決定する



自分のキャリアを考える時、個人の感覚だけでなく、客観的なデータを参考にすると、より確かな意思決定ができます。
人材需要/離職率の見方(公的資料へのナビ)
厚生労働省が公表している「介護労働実態調査」を見ると、どの施設形態で人が足りていないのか、離職率が高いのはどんな職場か、といったデータを知ることができます。
「介護労働安定センター」のウェブサイトなども参考になります。
こうしたデータは、将来性のある職場を選ぶ上での道しるべになるでしょう。
手当・加算の基礎知識(給与が増える仕組みの理解)
給与明細に書かれている「処遇改善手当」や「特定処遇改善手当」が、どういう仕組みで支払われているかを知っておきましょう。
こうした加算をしっかり算定し、職員に還元している事業所は、職員を大切にしている可能性が高いと言えます。
相談窓口・助成(職業相談、資格取得支援 など)
ハローワークでは、専門の相談員が無料でキャリア相談に乗ってくれます。
また、自治体によっては、介護福祉士などの資格取得費用を助成してくれる制度もありますよ。
使える制度は、積極的に活用しましょう。
事例:将来が見えなかった人が変わった3パターン



実際に、将来に悩んでいた方々が、どうやって道を切り拓いていったのか。
ぼくが働いている有料老人ホームに転職してきた人たちの、3つの事例を紹介します。
20代女性スタッフの事例
Aさん(26歳・女性)は、特養の忙しさと人間関係に疲れ果てていました。
- 入浴介助も流れ作業で次から次へ、イモ洗い状態
- 休憩中にはユニットリーダーが下ネタを連発するセクハラ三昧
転職先を「利用者さんとじっくり関われて、人間関係がいい職場」と整理したそうです。
有料老人ホームに見学に行き、雰囲気が合ったため転職。
「人間関係が最高で、ゆっくりと働ける」と、笑顔いっぱいで働いてくれています。
さらに、給料も上がったとのことで、一石三鳥ですね。
30代男性スタッフの事例
Bさん(35歳・男性)は、無資格でデイサービスに就職。
実務者研修、介護福祉士と資格を取得。
しかし、当時勤めていたデイサービスでは資格手当なし。
そこで、ぼくが働いている有料老人ホームに転職してきたわけです。
毎月、資格手当で1万8,000円アップ+夜勤手当5万円アップで、年収が80万円以上アップしたと喜んでいます。
40代:役職×教育担当でやりがい再設計
Cさん(48歳・女性)は、長年の経験はあるものの、パートで役職にはついていませんでした。
「このままでいいのか」と漠然とした不安を抱えていましたが、自分の強みが「新人さんに教えるのが得意」なことだと気づいたとのこと。
上司にその想いを伝え正社員になり、その後、フロアリーダー兼、新人教育担当という新しい役割を任されることに。
給与も上がり、何より「自分の経験が役に立っている」という大きなやりがいを見つけたとのことです。
よくある質問(Q&A)
- 今の職場で続けるべき?転職すべき?見極め方は?
-
「働きやすさを上げる4条件(人員配置・教育体制・ICT・管理者の方針)」が、改善される見込みがあるかどうかが一つの判断基準です。上司に相談しても「うちは変わらないよ」という反応であれば、転職を具体的に考え始めるタイミングかもしれません。
- 資格がない/勉強が苦手でも年収は上げられる?
-
はい、可能です。例えば、夜勤専従で働く、給与水準の高い都市部の施設を選ぶ、といった方法があります。また、資格がなくても「送迎ができる」「レクが得意」など、特定のスキルを評価してくれる職場もあります。
- 単発・スポットは不安定?社会保険はどうなる?
-
確かに単発だけでは不安定になりがちですが、本業と組み合わせることで収入の安定とリスク分散ができます。社会保険については、派遣会社によっては加入条件を満たせば加入できる場合があります。事前にしっかり確認しましょう。
- 人間関係がつらい。今すぐできる最初の一手は?
-
まずは「距離を取るルール」を自分の中で決めることです。そして、信頼できる人に「ちょっと聞いてほしいんだけど…」と話してみましょう。一人で抱え込まないことが、最初の一歩です。
- 何歳までキャリアアップできる?
-
介護業界に年齢制限はありません。50代、60代でケアマネジャーになったり、新しい分野の勉強を始めたりする方はたくさんいます。あなたの意欲次第で、キャリアアップはいつでも可能です。
- 面接で「忙しさ」や「教育体制」を見抜く質問は?
-
「月平均の残業時間はどれくらいですか?」「夜勤の体制(人数)を教えてください」「新人の方が入った場合、独り立ちまでの期間や教育プログラムはどのようになっていますか?」といった具体的な質問が有効です。「職員の平均年齢や勤続年数」を聞くのも、定着率を知る上で参考になります。
まとめ:将来は「見える化」と小さな実験で作れる
ここまで、本当に長い文章を読んでくださって、ありがとうございます。
介護の仕事の将来が見えないという不安は、決してあなた一人が感じているものではありません。
多くの仲間が、同じように悩み、道を探しています。
大切なのは、その不安を「仕方ない」と諦めるのではなく、「見える化」することです。
- キャリア地図で、どんな道があるのか全体像を知る。
- 年収や働きやすさで、職場を選ぶ基準を持つ。
- 7日間アクションで、今日からできる小さな一歩を踏み出す。
- どうしても辛いときは、一人で抱え込まずに相談する。
将来は、誰かが与えてくれるものではなく、あなた自身が「小さな実験」を繰り返しながら、作っていくものです。
次の一歩として、まずはできそうなことから試してみませんか?
- 気になる施設に見学の予約をしてみる。
- 休日に単発の仕事で、違う世界を覗いてみる。
- 職務経歴のテンプレートに、自分の経験を書き出してみる。
その小さな一歩が、あなたの「見えない将来」を照らす、確かな光になります。
ぼくは、あなたのことを心から応援しています。

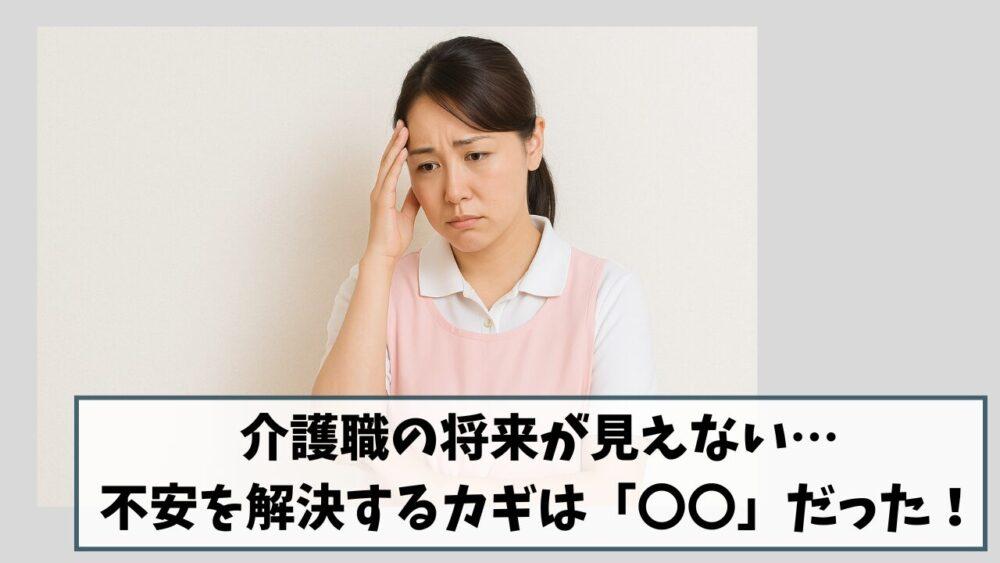
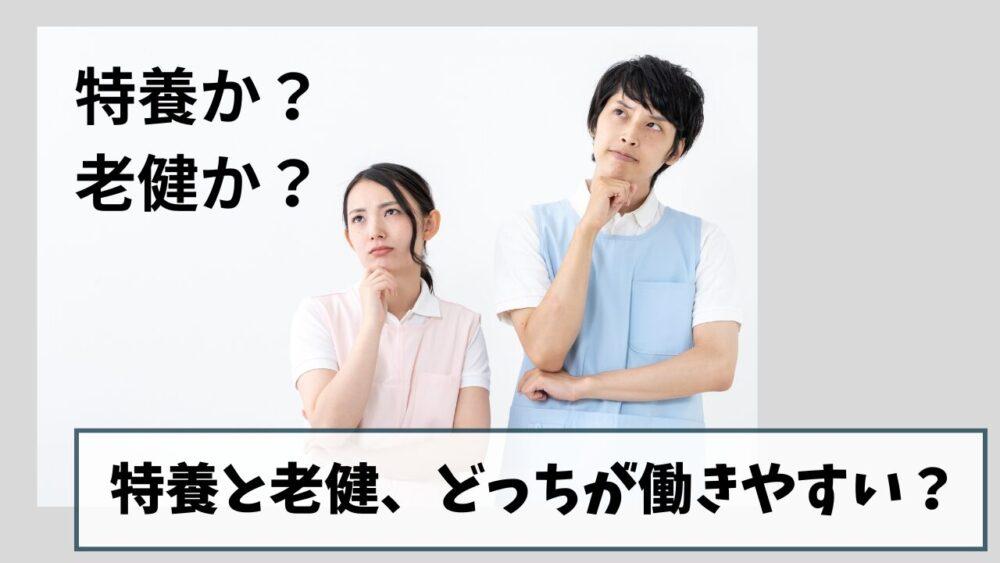

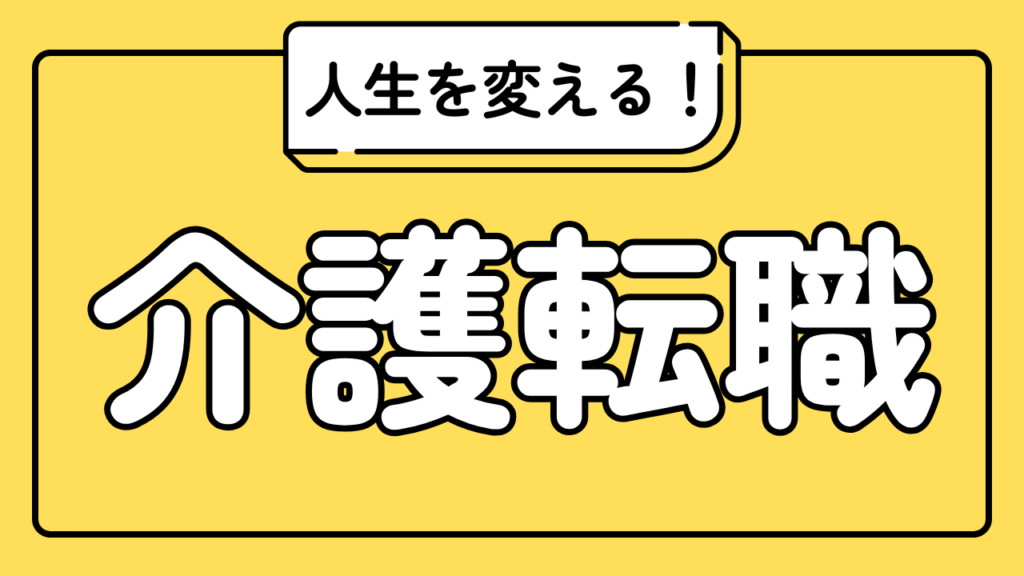

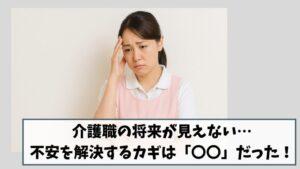




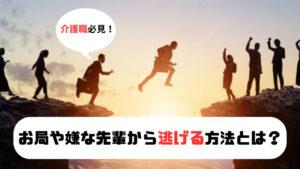
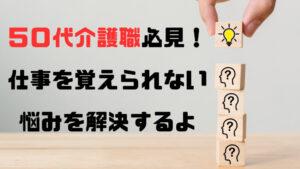
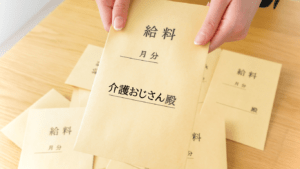
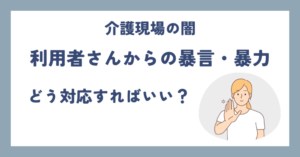

コメント