毎年聞こえてくるのが「あと一歩で落ちてしまった…」という声。
ぼくは介護士歴15年以上、現場の先輩として、後輩たちの相談に何度も乗ってきました。その中で、痛いほどわかったことがあります。
それは、不合格には「共通の理由」があるということ。
才能や記憶力の差ではありません。
多くの場合、勉強の進め方や本番での立ち回りに、ちょっとした「落とし穴」があるだけなんです。
この記事では、他人がハマった落とし穴を徹底的に分析し、あなたが同じ道をたどらないための具体的な方法を紹介します。
他人の失敗は、最高の教科書です。
この記事を読めば、あなたはその他人の失敗を「自分の合格装置」に変えることができるはず。
一緒に、一発合格への最短ルートを歩んでいきましょう。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載
結論:不合格の原因は3パターン



いきなり核心からお伝えします。
介護福祉士国家試験に落ちてしまう原因は、突き詰めるとたった3つのパターンに集約されます。
パターン①:勉強量はあるのに“得点源”を外した
「過去問を5周も解いたのに…」
これは本当によく聞く話です。
でも、ただ問題を解いて答えを覚えるだけの「作業」になっていませんか?
なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が不正解なのか。
その根拠を自分の言葉で説明できなければ、少し角度を変えた問題が出た瞬間に太刀打ちできません。
合格に必要なのは、勉強の”量”だけでなく、得点に直結する”質”なのです。
パターン②:物理的な学習時間不足(計画倒れ・優先順位ミス)
「仕事が不規則で、なかなか勉強時間が…」
これも痛いほどわかります。
夜勤明けの体で参考書を開くのは本当にしんどいですよね。
でも、合格する人も同じ条件で働いています。
違いは、計画の立て方と優先順位の付け方。
完璧な計画を立てて挫折するより、1日15分のスキマ時間でも確実に積み上げられる「現実的な計画」を立てられているかが、明暗を分けます。
パターン③:本番のミス(時間配分・緊張・見直し不全)
「模試ではA判定だったのに…」
本番の魔物にやられてしまうパターンです。
独特の緊張感で頭が真っ白になったり、難しい問題にこだわりすぎて時間配分を間違えたり。
見直しをしたつもりが、ただ問題を眺めるだけで終わってしまい、ケアレスミスを見逃してしまう。
これも、事前の「本番シミュレーション」が不足している典型的な例です。
最優先アクション:他人の失敗チェックリストで自分のリスクを10分診断
では、あなたに今日、まずやってほしいこと。
それは「自分の現在地」を客観的に知ることです。
後ほど紹介する「失敗チェックリスト」を使って、自分がどのパターンの罠にハマりそうか、たった10分で診断してみてください。
「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」
まずはそこから始めましょう。
不合格者に共通する7つの“落ちる要因”



なぜ、不合格者は先ほどの3つのパターンに陥ってしまうのか。
その背景には、多くの不合格者に共通する7つの具体的な「落ちる要因」が潜んでいます。
① 過去問の“周回の質”不足(解き直し・根拠言語化がない)
過去問をただ解くだけでは、それはただの答え合わせ。
大事なのは、「なぜ間違えたのか」「なぜこれが正解なのか」を、誰かに説明できるレベルで言語化することです。
不正解の選択肢が「どこが、どのように違うのか」まで説明できるようになって、初めてその問題をマスターしたと言えます。
② 科目バランス崩壊(頻出領域の取りこぼし)
介護福祉士の試験は、1点でも基準点に満たない科目があれば、合計点が合格ラインを超えていても不合格になります。
得意科目を伸ばすのも大事ですが、「苦手だから」と特定科目を後回しにするのは非常に危険です。
特に「人間の尊厳と自立」「介護の基本」といった基礎であり、かつ頻出の領域を落とすのは致命傷になりかねません。
③ 模試後の“改善ループ”が機能していない
模試は、自分の実力を測るためだけのものではありません。
自分の弱点をあぶり出すための「最高の診断ツール」です。
結果を見て一喜一憂するのではなく、「どの科目で」「どんな問題を」「なぜ」間違えたのかを徹底的に分析し、次の学習計画に反映させる。
この「模試→分析→改善」のループが回っていないと、同じ間違いを本番でも繰り返してしまいます。
④ 法改正・最新トピック対策の遅れ
介護保険法や障害者総合支援法は、定期的に改正されます。
こうした法改正に関する問題は、知っていれば確実に取れるボーナス問題。
逆に、対策が遅れていると、ここでライバルに差をつけられてしまいます。
最新の白書や統計データも同様です。
直前期に慌てないよう、常にアンテナを張っておく必要があります。
⑤ 記憶定着サイクル欠如(入力>出力の比重過多)
参考書を読んだり、講義動画を観たりする「インプット」ばかりに時間をかけていませんか?
人間の脳は、使わない情報はすぐに忘れてしまいます。
記憶を定着させるには、問題を解く、誰かに説明するなど「アウトプット」の機会を増やすことが不可欠です。
インプットとアウトプットの黄金比は「3:7」を意識しましょう。
⑥ 勤務シフトと学習計画のミスマッチ
「1日2時間勉強する!」と意気込んでも、不規則なシフト勤務では継続が難しいもの。
大切なのは、自分の勤務パターンに合わせた学習計画を立てることです。
「早番の日は出勤前に30分」
「夜勤の休憩中に15分だけ単語帳」など、無理なく実行できる「if-thenルール」を作れているかが鍵です。
⑦ 本番ストラテジー不在(配点×難易度の見切り)
125問を110分で解く試験では、戦略が不可欠です。
すべての問題を完璧に解こうとする必要はありません。
明らかに難解な問題や、自分の苦手分野の問題に時間をかけすぎて、解けるはずの基本的な問題を落とすのが一番もったいない。
「この問題は後回し」「これは捨てる」という冷静な「見切り」も、合格のためには立派な戦略なのです。
試験に落ちないために!:力を入れるポイント



試験に落ちないために、どこに力を入れるかを知るだけで合格する確率がグッと上がります。
詳しく見ていきましょう。
科目別の得点傾向・合格基準と近年の出題トレンド
介護福祉士国家試験は、総得点の約60%を基準とし、かつ指定された11科目群すべてで得点があることが合格の条件です。
データを見ると、例年「医療的ケア」や「総合問題」で得点差がつきやすい傾向にあります。
特に「医療的ケア」は範囲が限定的ながら、対策の有無がはっきり出る科目です。
また、近年は単なる知識を問う問題だけでなく、事例問題を通じて現場での応用力や判断力を問う問題が増えています。これは、ぼくたち介護職の専門性がより高く評価されるようになった証拠でもありますね。
合格者 vs 不合格者:学習時間の比較
これまで聞き取りをしてきた同僚の話を分析すると、合格者と不合格者の学習時間そのものに、実はそこまで大きな差はありませんでした。
差がついたのは「学習の質」です。
- 過去問演習量: 合格者は平均して過去問を5年分以上、3周以上解いていました。
- 模試の受験回数と活用法: 合格者の多くは模試を受験し、その結果を徹底的に分析して弱点克服に役立てていました。不合格者は模試を受けていなかったり、「受けっぱなし」の人が多い傾向が見られました。
直前期に伸びた人が実践した“出力中心”の学習比率
試験直前期にグッと成績を伸ばす人に共通しているのは、学習の比重を「アウトプット」に切り替えていることです。
具体的には、新しい知識を詰め込むインプットは全体の3割程度に抑え、残りの7割を「問題を解く」「間違えた理由を書き出す」「模擬試験を解く」といったアウトプットに費やしています。
これにより、知識が脳に定着し、本番での得点力に直結するのです。
不合格の事例【3選】



ここでは、ぼくが実際に見てきた典型的な失敗事例を3つご紹介します。
自分に当てはまるところがないか、チェックしてみてください。
| 事例 | 不合格の原因 | 対策 |
|---|---|---|
| Aさん(30代)真面目で勉強熱心。過去問を7周もしたが、2点差で不合格に。「解いた数」に満足し、なぜ間違えたかの分析が甘かった。 | ・勉強日誌が「◯時間やった」で終わっている。 ・模試で同じタイプの問題を繰り返し間違えている。 ・問題の根拠を尋ねられると、言葉に詰まる。 | ・過去問を解いたら、必ず「なぜ正解/不正解か」をノートに書き出す。 ・「解き直し専用ノート」を作り、間違えた問題だけを定期的に繰り返す。 |
| Bさん(20代)空いた時間を活用しようと計画したが、不規則なシフトでペースが乱れ、計画倒れ。後半に焦ってしまい、全範囲を網羅できなかった。 | ・「今日は疲れたから明日」が口癖になっている。 ・学習計画と実績の乖離が1週間以上続いている。 ・科目によって学習進捗に大きな偏りがある。 | ・「夜勤明けの仮眠前15分」など、勤務シフトに紐づけた学習時間を固定する。 ・完璧な計画より「最低限これだけはやる」というミニマムプランを立てる。 ・スマホアプリ等を活用し、5分のスキマ時間でも1問解ける環境を作る。 |
| Cさん(40代)経験豊富で知識にも自信あり。模試も悪くなかったが、本番で難しい事例問題に時間をかけすぎ、後半時間が足りなくなり、マークミスも発生。 | ・模試の自己採点で、時間があれば解けたはずの問題が多い。 ・「捨てる問題」の基準が決まっていない。 ・時間配分の練習をしたことがない。 | ・本番と同じ時間で過去問を解く練習を最低3回は行う。 ・「2分考えて分からなければ次に進む」など、自分なりの「見切りルール」を事前に決めておく。 ・解答用紙へのマークは、大問ごとにまとめて行うなど、自分に合った方法を確立する。 |
自己診断:あなたの不合格リスクは?(3分スクリーニング)



さあ、ここであなたの現在地を確認してみましょう。
以下の3つの指標について、自分に正直にA~Cで採点してみてください。
【指標1】学習の質(過去問・演習の質)
- A (3点): 解いた問題は、なぜその答えになるのか根拠を説明できる。
- B (2点): 正解の根拠はわかるが、不正解の選択肢については曖昧なことがある。
- C (1点): とにかく数をこなしている。正解を覚えるのが中心。
【指標2】学習の量(科目バランスと計画性)
- A (3点): ほぼ計画通りに進んでおり、全科目をバランス良く学習できている。
- B (2点): 計画に遅れが出ることがあり、やや苦手科目が手薄になっている。
- C (1点): 明確な計画がなく、得意科目や好きな科目ばかりやりがち。
【指標3】模試→改善(本番への備え)
- A (3点): 模試の結果を分析し、弱点リストを作って学習計画を修正している。
- B (2点): 模試の解き直しはしたが、次の計画にまでは反映できていない。
- C (1点): 模試を受けっぱなし。点数を見て一喜一憂しただけ。
【結果診断】
- 合計 8~9点(リスク低): 素晴らしい!合格への道を順調に進んでいます。今の学習法を維持しつつ、法改正などの最新情報のキャッチアップを怠らないようにしましょう。
- 合計 5~7点(リスク中): 黄色信号です。特に点数が低かった指標があなたの弱点。「計画性がない」なら学習計画の見直し、「学習の質が低い」なら根拠の言語化を意識するなど、具体的な対策に今すぐ着手しましょう。
- 合計 3~4点(リスク高): 赤信号!でも、今気づけて本当に良かった。このままでは危険です。一度立ち止まり、学習計画を根本から見直す必要があります。まずは「過去問1年分を、全選択肢の根拠を書き出しながら解いてみる」ことから始めて、学習の質を劇的に改善しましょう。
【介護福祉士】合格までのロードマップ



診断結果を踏まえ、ここからは具体的な対策ロードマップをお伝えします。
関連記事はこちら
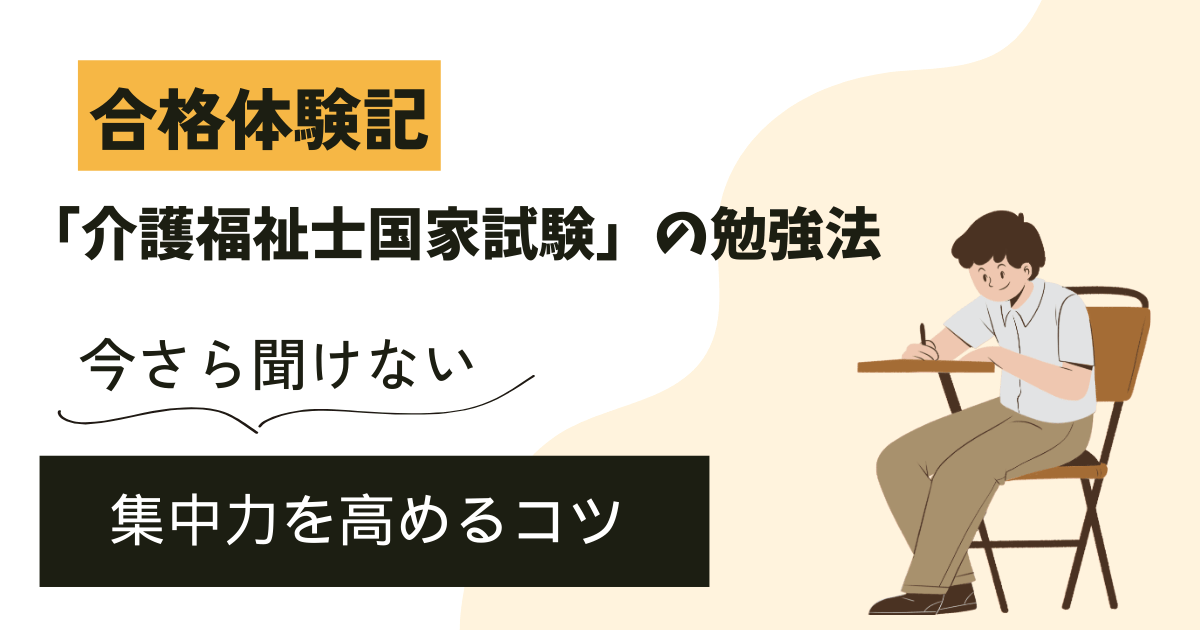
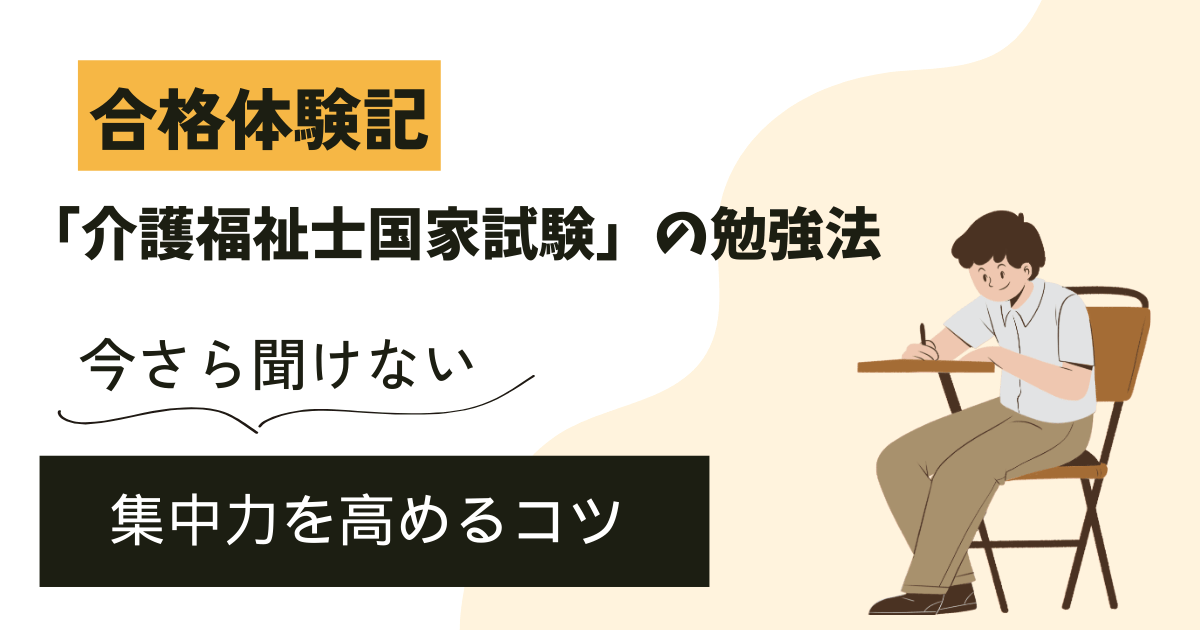
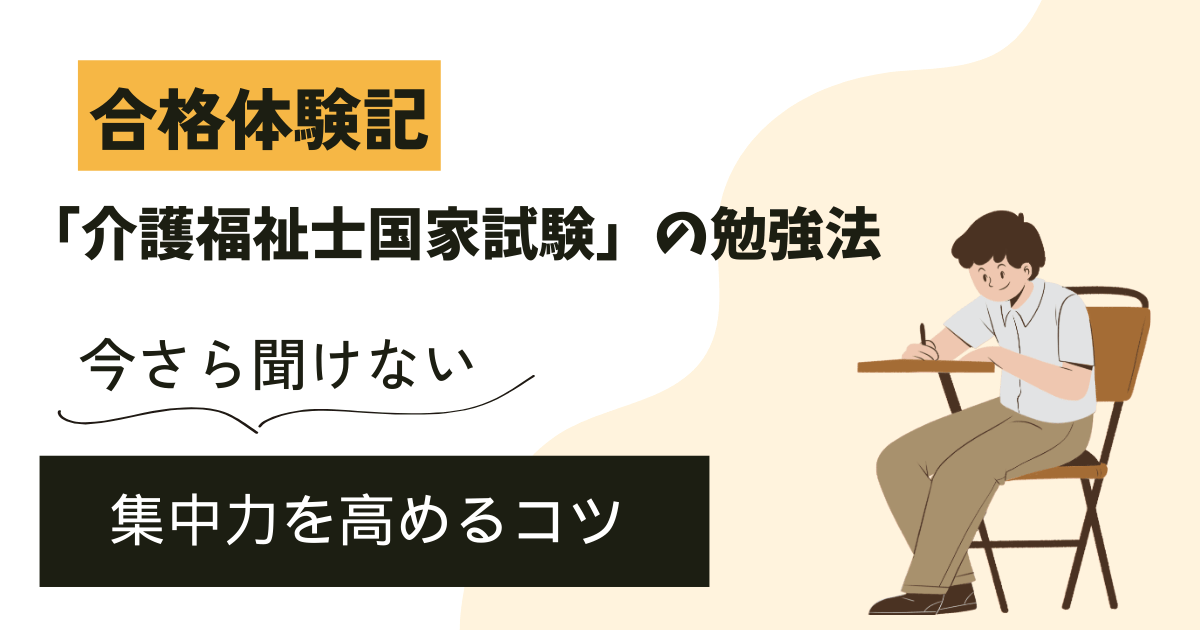
3か月前:頻出×配点の“得点源”固め(インプット3:アウトプット7)
この時期は、基礎固めと得点源の強化が最優先です。
- やるべきこと: 「人間の尊厳と自立」「介護の基本」「コミュニケーション技術」といった頻出科目と、配点の高い「総合問題」の過去問演習に集中します。
- 学習比率: インプット(参考書を読む)は3割、アウトプット(問題を解く・根拠を書き出す)を7割の意識で。
1か月前:弱点科目の“捨て問/拾い問”を線引き
全科目を完璧にするのは不可能です。
この時期は、効率的に合格点をクリアするための戦略を立てます。
- やるべきこと: 模試や過去問の結果から、自分の弱点科目を特定します。その中で、「時間をかければ解ける問題(拾い問)」と「どうやっても難しい問題(捨て問)」を自分なりに線引きする練習をしましょう。
1週間前:法改正・直近テーマの総点検
知識の最終確認と上乗せを行います。
- やるべきこと: 最新の法改正点、白書、統計データを総復習します。各種予備校などが提供する「直前対策講座」やまとめ資料を活用するのも効率的です。また、これまでに間違えた問題だけを集めた「お宝ノート」を繰り返し見直しましょう。
前日〜当日:時間配分表・見切り条件・見直しルール
最高のパフォーマンスを発揮するための最終準備です。
- やるべきこと:
- 時間配分: 「午前問題の事例問題までを◯分で」など、自分なりの時間配分表を作っておく。
- 見切り条件: 「2分考えても解法の糸口が見えなければチェックだけして次に進む」というルールを決めておく。
- 見直しルール: 残り10分は必ず見直しに充てる。見直す際は、計算問題や解答が分かれた迷った問題から優先的にチェックする。
忙しい人向け:スキマ学習セット(通勤・休憩・就寝前の固定メニュー)
まとまった時間が取れないあなたへ。
- 通勤中(電車・バス): スマホアプリで一問一答。音声教材を聞き流す。
- 休憩中(10~15分): 間違えた問題ノートを1ページだけ見直す。単語帳をチェックする。
- 就寝前(15分): その日学習した内容を、何も見ずに頭の中で思い出してみる(記憶の定着に効果絶大です)。
仕事と勉強を両立させるコツ
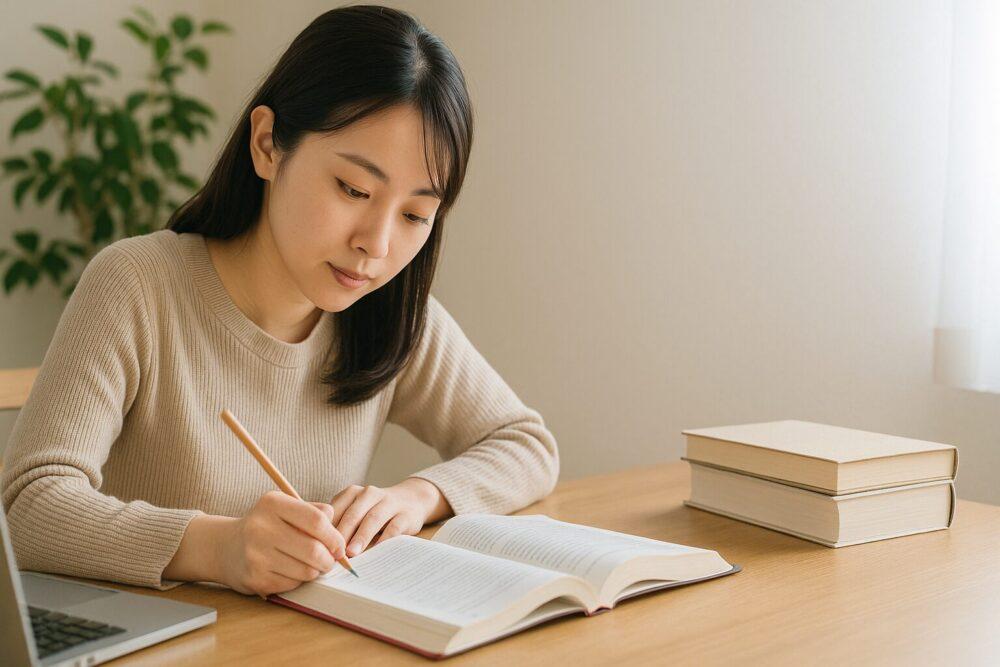
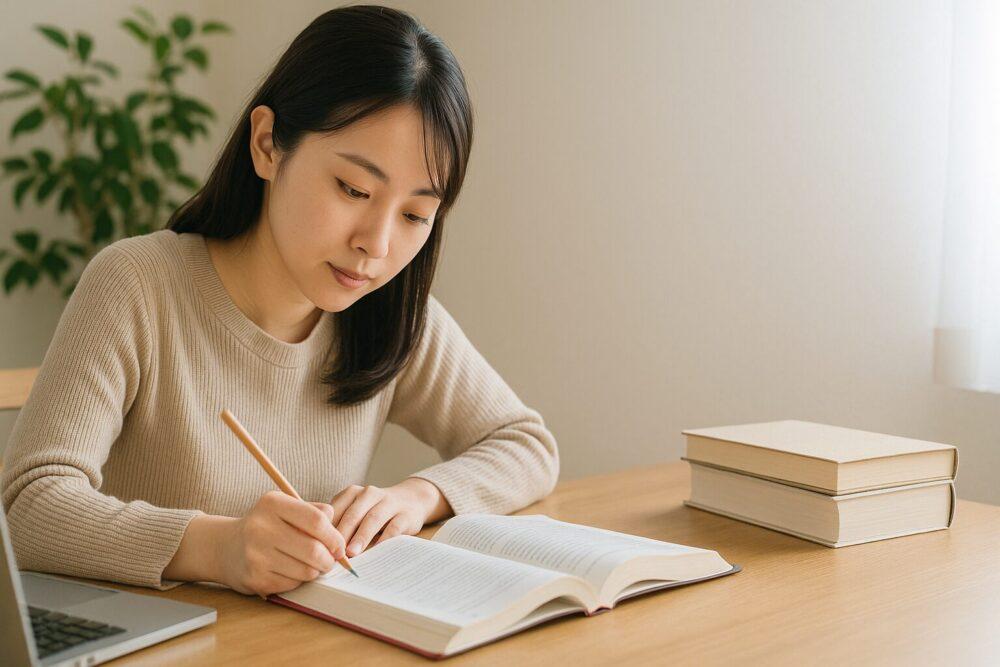
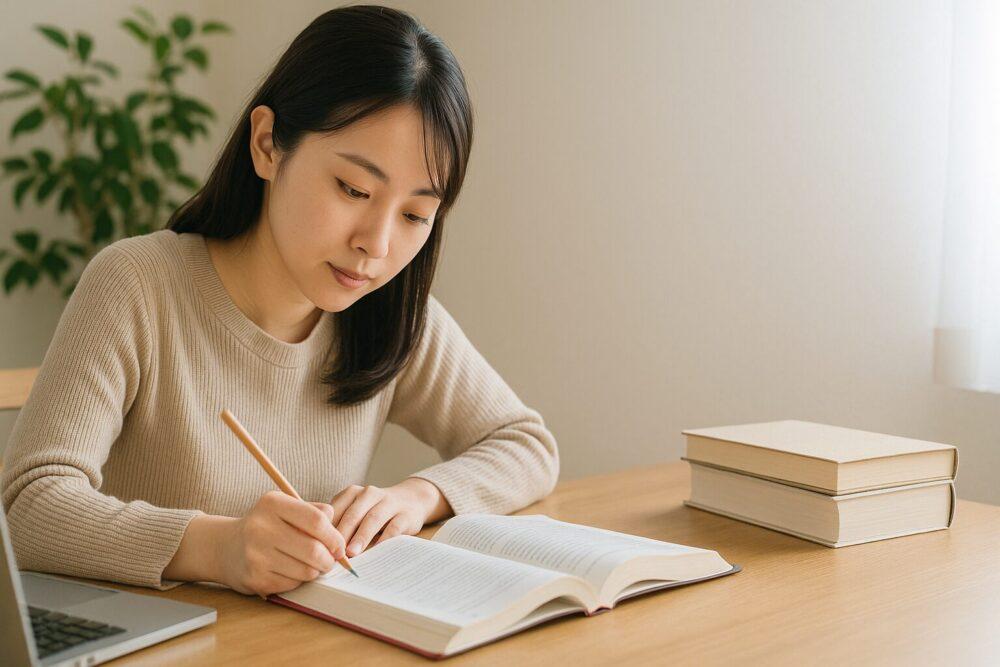
介護の仕事は、心身ともにタフさを求められます。
だからこそ、勉強との両立には工夫が必要です。
シフト制でも続く“固定スロット学習”の作り方
「毎日20時に勉強する」という時間固定の計画は、シフト制勤務では破綻しがちです。
おすすめは、行動とセットにする「固定スロット」方式。
- 「早番の日は、帰宅して着替えたらすぐ15分机に向かう」
- 「夜勤の仮眠前には、必ず単語帳を5分見る」
- 「休日は、朝食を食べたら1時間勉強する」 このように、生活習慣に学習を組み込むことで、意思の力に頼らずに継続できます。
家族・職場への協力依頼
一人で抱え込まず、周りの人に協力を求めることも大切です。
- 家族へ: 「◯月の試験に合格するために、これから◯ヶ月間、毎週土曜の午前中だけ集中して勉強させてほしい。その代わり、他の家事は積極的にやるから」
- 職場へ: (同僚や上司に)「今、介護福祉士の試験勉強をしています。もしシフトの交代などで相談させてもらうことがあったら、よろしくお願いします」 このように、具体的にお願いすることで、相手も協力しやすくなります。
費用を抑える教材選びと支援制度の活用
経済的な負担も無視できませんよね。
- 教材: 新品の参考書にこだわらず、フリマアプリで前年度のものを安く手に入れるのも一つの手です(ただし法改正には注意)。図書館で関連書籍を借りるのも良いでしょう。
- 支援制度: 自治体や法人によっては、資格取得支援制度(受験料や研修費用の補助など)があります。また、ハローワークの教育訓練給付制度の対象になる講座もあります。一度、自分の職場や自治体の制度を確認してみることを強くお勧めします。
メンタル設計:不安・焦りを“実行力”に変える方法



心理カウンセラーの視点から、受験期のメンタル管理術をお伝えします。
不安をなくすことはできません。
でも、不安を味方につけることは可能です。
事実と感情の分離→数字で管理
「なんだか不安だ…」という漠然とした感情は、行動を止めます。
まずは「事実」と「感情」を分けましょう。
「模試の点数が目標より20点低かった(事実)」→「だから不安だ(感情)」
事実は、数字で管理します。
「あと20点上げるには、苦手な医療的ケアで3点、総合問題で5点…」と分解することで、やるべきことが明確になり、不安が「課題」に変わります。
小目標×達成ログで自己効力感を積み上げる
「参考書を1冊終わらせる」という大きな目標だけでは、心が折れてしまいます。
「今日は過去問を5問解く」「今週中にこの単元を終わらせる」といった小さな目標(スモールステップ)を立て、達成できたらカレンダーに丸をつけるなど、「できたこと」を可視化しましょう。
この小さな成功体験の積み重ねが、「自分はできる」という自己効力感を育てます。
学習仲間・コミュニティの使い方
同じ目標を持つ仲間は心強い存在です。
しかし、使い方を間違えると「あの人はあんなに進んでる…」と焦りの原因にも。
おすすめは、「進捗を報告し合う」より「情報を交換する」関係です。
「この法改正、どう解釈してる?」「この問題の解説が分かりにくいんだけど、どう思う?」といった、具体的な情報交換の場として活用しましょう。
励まし合いも大切ですが、比較しすぎない距離感が大事です。
よくある質問(Q&A)
皆さんからよくいただく質問にお答えします。
- 他人の失敗談はどこまで参考にすべき?自分に落とし込むコツは?
-
他人の失敗談は、「こういう落とし穴があるのか」という危険マップとして活用するのがベストです。すべてを鵜呑みにするのではなく、「自分にもこの傾向があるかもしれない」と感じた部分を、先ほどの自己診断チェックリストなどを使って客観的に評価し、自分の学習計画の修正に役立ててください。
- 1日1〜2時間でも現実的に合格できる学習設計は?
-
十分可能です。鍵は**「学習の密度」**です。ダラダラと2時間机に向かうより、集中した1時間の方が効果的です。
- 最初の15分: 前日の復習(アウトプット)
- 次の30分: 新しい単元の学習(インプット&アウトプット)
- 最後の15分: その日学んだことに関する問題を解く(アウトプット) このように時間を区切り、アウトプット中心のメニューを組むことで、短時間でも合格力は着実に身につきます。
- 参考書中心とオンライン講座、失敗回避の観点での違いは?
-
- 参考書中心の失敗リスク: 「自己管理ができない」「モチベーションが続かない」「情報の取捨選択が難しい」。これを避けるには、厳格な学習計画と、進捗を共有できる仲間が必要です。
- オンライン講座の失敗リスク: 「受け身になってしまう」「視聴しただけで満足してしまう」。これを避けるには、講座とセットで必ず問題演習(アウトプット)の時間を確保することが不可欠です。 どちらが良いというより、ご自身のタイプに合わせて選ぶことが重要です。
- 本番で焦らないための時間配分は?
-
A4: これが絶対というものはありませんが、一つのモデルとして参考にしてください。
- 午前(110分 / 63問)
- 開始~60分:問1~事例問題前まで(1問1分ペース)
- 60分~95分:事例問題(1問3分ペース)
- 95分~110分:見直し・マークチェック
- 午後(110分 / 62問)
- 開始~50分:問68~総合問題前まで
- 50分~100分:総合問題(1問4分ペース)
- 100分~110分:見直し・マークチェック
この時間配分を元に、過去問演習で自分なりの時間配分を確立しておくことが、本番での焦りを防ぎます。
- 午前(110分 / 63問)
- 不合格がキャリアに与える影響は?
-
まず、万が一不合格だったとしても、あなたの介護職としての価値が下がるわけでは決してありません。その経験は、利用者さんの気持ちに寄り添う上で、必ず力になります。 キャリアへの影響も限定的です。資格手当がつかないなどはありますが、再挑戦すれば良いだけの話です。大切なのは、不合格の原因をしっかり分析し、次回の合格に繋げること。この「失敗から学ぶ力」こそ、介護現場で最も求められる資質の一つだと、ぼくは思います。
まとめ
長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。
ここまで読んでくださったあなたは、もう合格へ向けて大きな一歩を踏み出しています。
最後に、明日から実践してほしいことを3つのステップにまとめます。
① 失敗事例→自分用チェックリスト化
この記事で紹介した「落ちる要因」や「失敗事例」を元に、「自分は大丈夫か?」を問うオリジナルチェックリストを作ってみましょう。そして、それを週に一度、確認する習慣をつけてください。
② 弱点→週次計画に落とし込み(模試→修正のループ)
模試や日々の演習で見つかった弱点を、ただ「苦手だ」で終わらせない。「来週は、医療的ケアの演習にプラス30分時間を取ろう」というように、具体的なアクションとして翌週の計画に落とし込むのです。この小さな改善ループが、1ヶ月後、大きな差を生みます。
③ 得点源の最大化→当日運用ルールを事前に固定
自分の得意な科目・分野を「確実に得点する」ための戦略と、本番での「時間配分」「見切りルール」を、事前に紙に書き出して固定してしまいましょう。本番で迷った時、その一枚の紙があなたを冷静にさせてくれるお守りになります。
介護福祉士の国家試験は、あなたのこれまでの頑張りを形にするための、一つの大切なステップです。
でも、忘れないでください。
資格を取ることがゴールではありません。
その先にある、利用者さんのより良い暮らしと、あなた自身の成長こそが本当のゴールです。
ぼくは、現場で頑張るあなたが、自信を持ってそのスタートラインに立てるよう、心から応援しています。
あなたなら、きっと大丈夫。

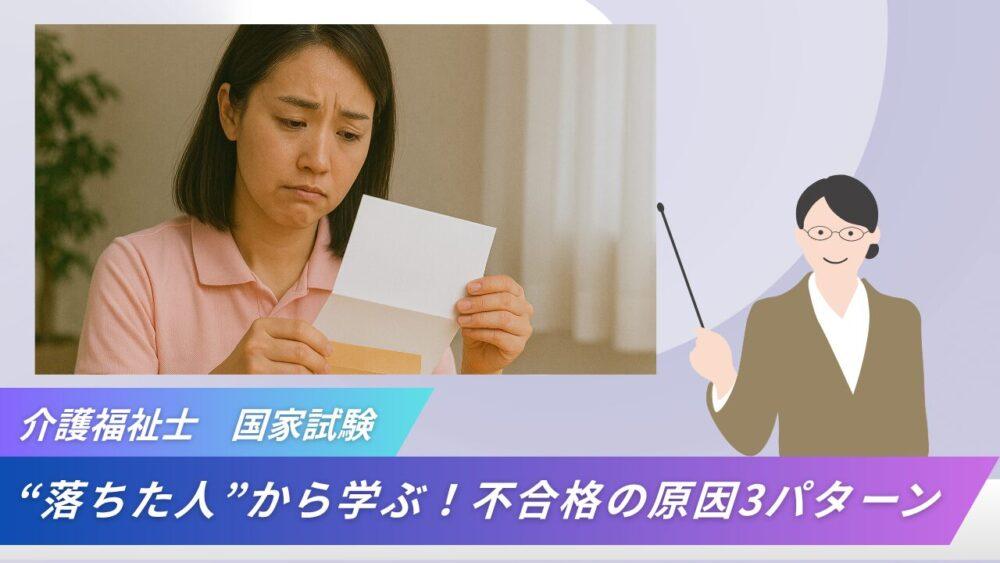
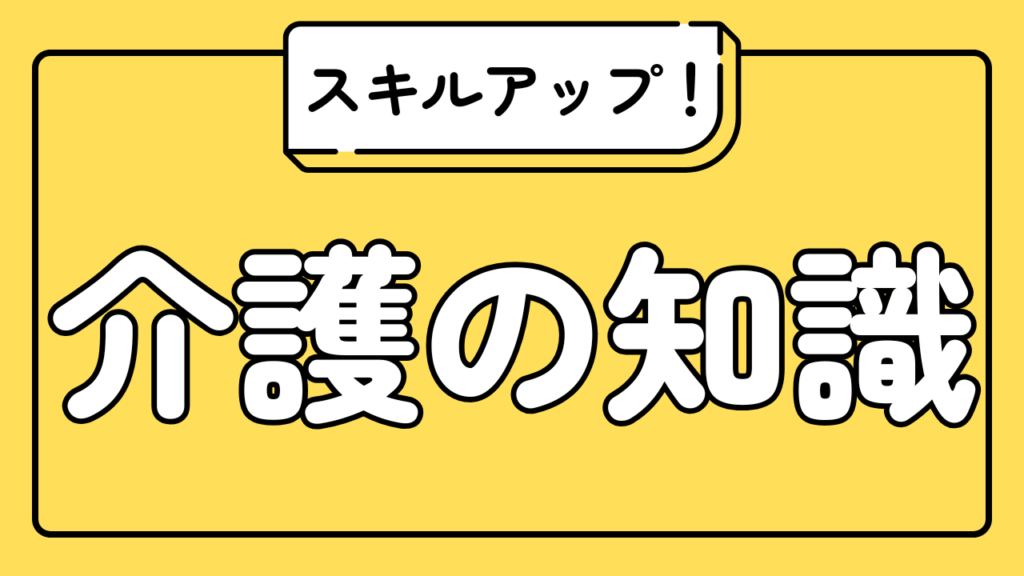


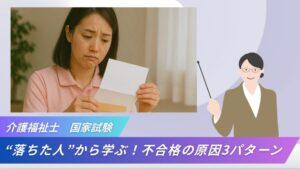
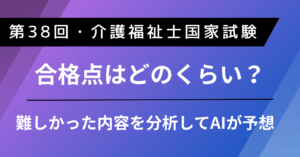


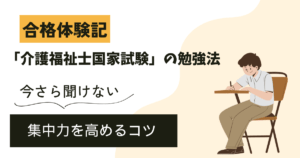
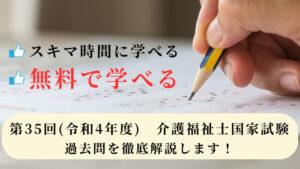

コメント