この特集では、季節の記憶を呼び起こす壁飾りアイデアを39枚の画像で紹介します。
台紙と色紙、少しの工夫で、フロアに“季節の雰囲気”を演出しましょう。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載
関連記事はこちら
1月の壁飾り
お正月①「門松 × 鶴 × 梅」



テーマ:和の正月飾り「門松 × 鶴 × 梅」
新しい年の始まりを祝う日本の伝統モチーフを、
落ち着いた色合いとシンプルな形で表現しています。
見る人に安心感と希望を与える作品です✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景の色
- 背景は薄いベージュやアイボリー系の紙を使うと、
緑の門松や赤い鶴・梅がきれいに引き立ちます。 - 白すぎる紙は冷たい印象になるので、少し温かみのある色合いを選びましょう。
💡背景が落ち着いていると、正月飾りの「和の高級感」が出ます。
② 門松の作り方(メインモチーフ)
- 門松は竹3本・松葉・梅・飾り扇の構成で作るとバランスが良いです🎍
- 竹は3段階(長・中・短)で、色を少しずつ変えると立体感が出ます。
→ 例:濃い緑・中緑・明るい緑の3色で作る。 - 扇はベージュ系で、中心に赤い菱形を入れるとアクセントになります。
- 下のリボンは黄色や金色の紙で作ると華やかさアップ✨
💡門松を右側に配置すると、作品全体の安定感が出ます。
③ 折り鶴の作り方
- 折り紙を折ったような形を紙で再現しましょう。
- 色は赤または朱色を使うと、お祝い感が強まります。
- 羽を少し上げた形にすると、「飛び立つ姿=新しい年への希望」を表現できます🕊️
💡左上に配置すると、右下の門松とのバランスが取れます。
④ 梅の花の作り方
- 梅は赤とピンクの2色で大小を作り、ランダムに並べます。
- 花芯(中心の模様)は黄色いペンや紙で描く(貼る)と可愛くなります🌸
- 3つ〜5つほど並べると、春の訪れを感じる柔らかい印象になります。
💡梅の配置は下に広がるように置くと、作品に“流れ”が生まれます。
⑤ 「1月」の文字デザイン
- 円形のベージュ台紙に、深い緑色の文字で「1月」と入れるのがポイント。
- 緑色を使うことで、門松との統一感が出ます。
- 円形にすることで柔らかさと安定感が加わります◎
💡右寄せに貼ると構図が整いやすいです。
⑥ 小物(太陽・雲)の配置
- 赤い丸は「初日の出」を、黄色い雲は「黄金の雲」を表現しています☀️
- 鶴の上あたりに置くと、空を飛んでいる構図になり自然です。
- 雲は左右どちらか一方に寄せて、空間のバランスをとりましょう。
💡全体を見て、空白が多いところを雲で埋めると美しく仕上がります。
お正月②「鏡餅」



テーマ:新年の喜び「感謝と福を届ける1月」
お年玉=「うれしい気持ち」
鏡餅=「無病息災」
橙=「代々(だいだい)続く幸せ」
という意味が込められています。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景の色
- 背景には薄いベージュやクリーム色を使うと、
白い鏡餅と赤いお年玉袋がよく映えます。 - 壁が白い場合は、少し濃い色の模造紙を使うと作品全体が引き立ちます。
💡温かみのある色を選ぶと、冬でも明るく感じます。
② 鏡餅の作り方(作品の中心)
- 白い丸を上・中・下の3段に重ねて貼ります。
- 下段を少し大きくすると、安定感が出ます。
- 台(四角い部分)は赤色またはオレンジ色で作ると華やかです。
- 下に敷く紅白の紙(四角い折り紙)を「折り返し模様」にすると本格的。
💡餅のふくらみを意識して、丸の輪郭を少し楕円形にすると立体感が出ます。
③ 橙(だいだい)の作り方
- 鏡餅の上にのせる**橙(だいだい)**は、丸い形にオレンジ色の紙で作ります。
- 葉っぱを1枚つけるだけで、ぐっと可愛らしくなります🍊
- 葉の向きを左右どちらかにずらすと自然な印象になります。
💡「だいだい=代々続く幸せ」の意味を伝えると、季節行事の学びにも◎。
④ お年玉袋の作り方
- 両側に貼る「お年玉袋」は、赤い長方形の紙を使い、
上部に丸みをつけて“封筒っぽさ”を出します。 - 黄色い紙で「お年玉」と大きく貼るのがポイント💰
- 左右の角度を少し傾けて貼ると、元気で動きのある印象に。
💡文字は一文字ずつ厚紙に貼ると、立体的で見栄えが良くなります。
⑤ 「1月」の文字
- 一番上に大きく赤文字で「1月」と書きましょう。
- 白い背景をつけることで、清潔感と目立ちやすさが出ます。
- 他のパーツが赤なので、「1月」は赤 × 白のコントラストで統一感を出すのがコツ。
💡フォントは角ばった文字よりも丸めの方が、やさしい印象になります。
⑥ 配置のバランス
- 真ん中に鏡餅を置き、その両脇にお年玉袋を対称に配置。
- 鏡餅の上部に「1月」を貼ると、視線が自然に中央へ向かいます。
- 下の余白を少し残すと、清潔で見やすいデザインになります。
💡全体を「三角構図(上が細く、下が広い形)」にまとめると安定感が出ます。
初日の出と富士山



テーマ:新年の象徴「初日の出 × 富士山」
日本の正月らしさを感じる「日の出」「富士山」「雲」を組み合わせた構図。
色のコントラスト(赤・青・黄)を意識することで、華やかで縁起の良い作品に仕上がります✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景の色選び
- 背景は薄いクリーム色やベージュがおすすめ。
→ 白い雪や黄色い光が引き立ち、暖かい雰囲気になります。 - 純白の紙を使うと冷たい印象になるため、少し温かみのある色を選ぶのがコツ。
💡ポイント:背景を貼る前に、富士山を中央に仮置きして全体バランスを確認!
② 富士山の作り方(作品の中心)
- 富士山の下半分は濃い青、上は白い雪で切り替えましょう。
- 雪の部分はギザギザを手でちぎるように切ると、自然な山肌になります🗻
- 富士山は画面の中央よりやや下に配置し、どっしりと構える印象に。
💡山の底辺をまっすぐにすると安定感が出ます。
③ 太陽(初日の出)
- 太陽は大きめの赤い円でOK!
- 富士山の左上に半分重ねることで「日の出」らしさが出ます。
- 赤は明るい朱色を選ぶと、正月らしい華やかさが増します🌞
💡丸の大きさは富士山の幅の2/3くらいがバランス良し。
④ 光の線(太陽の光)
- 黄色い細長い紙を放射状に貼り、太陽の輝きを表現します✨
- 長さを少しずつ変えると動きが出て、より自然な印象に。
- 光の数は奇数(7本・9本など)にするとデザイン的に安定します。
💡光を貼る前に、鉛筆で放射線を軽く下書きしておくときれいに配置できます。
⑤ 雲と空のグラデーション
- 雲は黄色とオレンジの2色で重ねるのがポイント。
→ 朝焼けの空を表現できます。 - 形は角のない曲線で、ふわっとした形に。
- 端にいくほど濃いオレンジを使うと、奥行きが出ます。
💡雲の配置は左右バランスを意識して、富士山の頂上を少し見せると◎。
⑥ 「1月」の文字
- 白い台紙に黒い文字で、シンプルに。
- 太くて読みやすいフォントを選ぶと遠くからでも見やすいです。
- 文字は右上に貼ると全体がスッキリまとまります。
💡赤や金の縁をつけるとお祝い感がアップします🎍
開運ダルマ



テーマ:新年の縁起物「開運 × だるま」
1月にふさわしい「福」「笑顔」「願いごと」を表現した作品です。
だるまのいろんな表情が可愛く、利用者さんの手作りにもぴったりです😊
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景の色と枠
- 背景は茶色の紙を使うと、だるまの赤がより目立ちます。
- 周囲には紅白の市松模様の枠をつけるのがポイント!
→ お正月らしい華やかさを簡単に出せます🎊 - 枠は赤と白を交互に貼り、角をきちんとそろえると仕上がりがきれいになります。
💡ポイント:枠だけで「正月っぽさ」を演出できる便利テクです。
② だるまの作り方(主役)
- だるまの本体は赤・黄の2色で作ると明るく見えます。
- 形は丸に近い楕円形でOK。下を少し平らにして安定感を出しましょう。
- 顔は丸い白紙を貼り、目・眉・口を黒いペンまたは紙で表現します。
- 表情を変えるのがコツ!😊😐😡😅など、いろんな表情を作ると可愛いです。
💡「福」の文字は金色または黄色にすると縁起が良くなります。
③ 「1月」と「開運」の文字
- 「1月」は大きく中央に配置。黄色×黒の縁取りで力強く見せます。
- 「開運」は黒文字で太く書き、背景の白部分にバランスよく貼ります。
- 文字の配置は上:開運、中央:1月、周り:だるま の三層構成にすると安定します。
💡筆文字風の太字を意識すると、お正月感が増します。
④ 配置のバランス
- だるまを左右均等に配置すると整った印象になります。
- 赤と黄色を交互に並べると、にぎやかで目を引く仕上がりに。
- 表情の違うだるまをランダムに置くと、動きが出て楽しくなります。
💡角の4か所に少し傾けて貼ると、遊び心のあるレイアウトに。
⑤ 材料と工夫
- だるまの顔は利用者さんに描いてもらうと、オリジナル感たっぷりに!
- 紙の厚さは、少し厚めの画用紙がおすすめ。貼りやすく型崩れしません。
- 背景の茶色が地味に感じるときは、うっすら金や白の丸シールを散らして「雪」や「光」を表現してもOK❄️✨
雪うさぎと椿



テーマ:新年を感じる冬の和風デザイン
1月は「お正月」や「新年のはじまり」をイメージして、
白うさぎ・椿・雪の結晶を組み合わせたデザインになっています。
清らかで落ち着いた雰囲気なので、介護施設や保育園にもぴったりです✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景選び
- 背景は淡いベージュやクリーム色を使うのがポイント。
→ 白うさぎと雪の結晶がはっきり映えます。 - 冬の冷たさよりも、あたたかさを感じる色合いにすると穏やかな印象になります。
💡真っ白な背景にすると雪が目立たなくなるので注意!
② うさぎの作り方
- 白い画用紙で作るうさぎは、体を丸く大きめにして可愛らしさを出します。
- 耳は少し長めにして、角度を変えて貼ると立体感が出ます。
- 目は赤い丸、鼻は小さめの赤い点で、シンプルでも印象的に🐇
- 足元に白い「雪の台紙」を敷くと、冬の雰囲気が自然に出ます。
💡うさぎの影をうっすらグレーの紙で重ねても、より立体的になります。
③ 椿(つばき)の作り方
- 椿は赤と緑のコントラストが命🌺
- 花びらは5枚を少し重ねて、真ん中に黄色の花芯を立体的に貼ります。
→ 花芯は黄色い紙を細かくちぎって丸めると、自然な質感になります。 - 葉っぱは濃い緑で、1枚ごとに折り線を入れてリアルに。
💡花を3つまとめて配置すると、バランスが良く華やかに見えます。
④ 雪の結晶の作り方
- 白い画用紙を折り紙のように折って切るだけで簡単に作れます❄️
- 大きさを変えて3〜5個ほど貼ると、自然な降雪感が出ます。
- 結晶の間隔は広めにとり、うさぎや椿が主役になるように配置します。
💡雪の結晶は、コピー用紙など薄めの紙の方が切りやすいです。
⑤ 「1月」の文字デザイン
- 赤い長方形の台紙に、**黒い文字で力強く書く(または切り貼り)**のがポイント。
- 四隅を斜めにカットすると、和風の“札”のような雰囲気になります。
- 文字は中央に大きく貼り、作品全体のまとまりを意識します。
💡「賀正」や「迎春」などに変えても、正月らしくて素敵です。
2月の壁飾り
節分①「鬼とおかめ」



テーマ:やさしい色合いの節分飾り
2月の行事「節分」をテーマに、**赤鬼とおかめ(福の神)**が登場する温かみのあるデザインです。
派手すぎず、落ち着いた色味で構成されているので、介護施設にもぴったりです✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景と色づかい
- 背景は薄いベージュやクリーム色の画用紙を使うと、全体が優しい印象に。
- 色味は「赤・黄・茶・緑・紺」などのくすみ系トーンで統一すると、上品に仕上がります。
- 色のコントラストが強すぎると鬼が怖く見えるので、やや淡めの赤を使うのがおすすめです。
💡ポイント:全体のトーンを合わせると、鬼もおかめも「やさしい節分」になります。
② 鬼の顔(左)
- 鬼の表情は怒り顔でもかわいく見えるように、
眉や口を「カーブ気味」にカットすると柔らかい印象に。 - 髪は黒ではなくこげ茶やオリーブ色にすると重くならず、温かい雰囲気に。
- 角は黄色とオレンジを重ねると立体感が出て◎。
💡「こわくない鬼」を意識すると、子どもや高齢者にも親しみやすくなります。
③ おかめ(右)
- おかめの顔は「丸み」を意識してカットし、笑顔を中心に描きましょう。
- 頬は淡いピンクの円を貼ると、やさしく明るい表情になります。
- 髪の毛は黒ではなく焦げ茶色を使うと、全体が柔らかく見えます。
💡目を細めた「にっこり笑顔」がポイント。鬼との対比が自然になります。
④ 枡と豆の作り方
- 枡(ます)は茶色の画用紙をベースに、濃淡を使い分けて立体的に見せます。
- 豆は薄いベージュやクリーム色の丸でOK。
→ パンチや丸シールで作ると時短になります。 - 枡の中にも外にも豆を貼ると、にぎやかで“まいた感じ”が出ます。
💡豆を数個だけ浮かせて貼る(ふちを少し浮かす)と、立体的に見えます。
⑤ 「2月」の文字
- 背景が淡いので、濃いめの紺色や黒っぽい色で文字を作るとくっきり見えます。
- 丸いベージュの台紙に文字を貼ると、中央が締まってバランスが良くなります。
- フォントは角が少ない太めの文字にすると、あたたかく見えます。
💡文字の位置を中心より少し上にすると、作品全体の安定感がアップします。
節分②「鬼と恵方巻」



テーマ:節分(鬼は外!福は内!)
2月といえば「節分」。
この壁飾りは、赤鬼と青鬼・豆まき・恵方巻きをモチーフにした、
季節感たっぷりのデザインです✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を選ぶ
- 背景は青や紺色の画用紙がオススメ!
→ 鬼の顔や豆が映えて、にぎやかに見えます。 - 落ち着いたトーンの青を選ぶと、赤鬼・青鬼の色がしっかり引き立ちます。
💡背景が暗めなので、文字や豆などは明るい色を使うとバランスが良くなります。
② 鬼の顔の作り方
- 鬼は赤鬼と青鬼を左右に配置しましょう。
→ 表情を変えると、より楽しくなります(例:片方は笑顔、もう片方は怒り顔など) - 髪の毛は黒いモコモコの形で作り、顔の上部に重ねます。
- 角は黄色の折り紙で作ると明るく、節分らしい雰囲気に!
- 目と眉を太めにすると、表情がはっきりして遠くからも見やすくなります👀
💡眉毛の角度を変えるだけで、怖くもかわいくもできます♪
③ 豆まきの豆を作る
- 豆は黄色やクリーム色の丸い紙でOK!
→ パンチや丸シールを使うと手軽にたくさん作れます。 - 大きさを2種類ほど混ぜると、動きが出て自然に見えます。
- 豆が“飛んでいる”ように、ランダムに配置すると楽しい雰囲気に✨
💡豆を貼る位置を少しずらすことで、勢いが感じられるデザインになります。
④ 枡(ます)の作り方
- 枡は茶色やベージュの画用紙で立体感を出しましょう。
- 横の板部分に濃い茶色を少し重ねると、木箱っぽく見えます。
- 枡の中に豆をたくさん入れて、「福がいっぱい」の雰囲気に!
💡豆を重ねて貼ると、立体的でリアルな仕上がりになります。
⑤ 恵方巻きを作る
- 恵方巻きは**黒(のり)・白(ごはん)・カラフル(具材)**で作ります。
- 具材はオレンジ(にんじん)、黄(たまご)、緑(きゅうり)などで色鮮やかに🍣
- 丸く見せるために、円の断面を少し重ねて貼りましょう。
💡2本並べて斜めに配置すると、見た目のバランスが良くなります。
⑥ 文字の配置
- 「2月」は大きく上中央に貼ると見やすいです。
- 鬼や豆の色に負けないように、明るいオレンジや黄色で作るのが◎
- 文字を少しずらして貼ると、元気な印象になります💪
バレンタイン



テーマ:感謝と愛を伝えるバレンタイン
2月といえば、バレンタインデーや「ありがとう」を伝える季節。
大きなハートとやさしい色づかいで、
見る人の気持ちをあたたかくするデザインです😊
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は淡いピンクの画用紙を使うと、全体がやわらかくなります。
- ピンクの上に赤や黄色を重ねると、温かみのある優しい印象になります。
- 「2月」の文字は薄紫でまとめて、上品さを出しましょう。
💡背景が派手すぎるとハートが目立たないので、シンプルにするのがコツです。
② 大きなハートの作り方
- 真ん中の赤いハートが作品の主役!
- 大きめに作って、中央にしっかり貼りましょう。
- 赤の画用紙を半分に折ってからハート型に切ると、左右対称にきれいに作れます✂️
- 紙の厚みは少しある方がしっかりして見えます。
💡ハートの下の角を少し尖らせると、形が引き締まってきれいです。
③ 文字の配置
- 「いつもありがとう」は黄色の文字で、赤いハートの上に貼ります。
- 文字を少し斜めにしたり、段差をつけて貼ると動きが出てかわいくなります。
- フォントは太めの丸文字がおすすめ。やさしい印象に仕上がります。
💡文字は1枚ずつ切ってから並べて位置を確認して貼ると、失敗が少ないです。
④ 小さなハートで飾りつけ
- 周囲に赤・ピンク・濃淡のあるハートを散らします💗
- 大きさを変えてランダムに貼ることで、ハートが舞っているように見えます。
- ハートの一部をはみ出すように貼ると、画面が広く感じられます。
- 左右のバランスをとりながら貼るのがコツです。
💡ハートを立体的にしたい場合は、真ん中を少し折って「ふくらみ」をつけて貼ると◎
⑤ 「2月」の文字位置
- 「2月」は上部中央に配置して、月ごとの季節感を出します。
- 背景の色が薄い場合は、白い長方形の台紙を敷くと見やすくなります。
💡数字と文字を別の色にしてもかわいい(例:2=紫、月=ピンク)
3月の壁飾り
ひな祭り



テーマ:ひなまつり(桃の節句)
3月といえば「ひなまつり」。
この壁飾りは、おだいりさまとおひなさまの優しい表情と、
舞い散る桜の花びらで春の訪れを表現しています。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を選ぶ
- 背景は淡いピンク色の画用紙を使うと、春らしく温かい印象になります。
- 背景に色をつけすぎず、主役の「おひなさま」が目立つようにしましょう。
- 「3月」の文字は濃いピンクやえんじ色で、落ち着いたアクセントを。
💡背景を先に決めてから人物や桜の位置を仮置きすると、バランスが取りやすいです。
② おだいりさまとおひなさまの配置
- 中央に並べて、おだいりさま(男雛)を左、おひなさま(女雛)を右に置きます。
(見る側から見て左が男雛、右が女雛) - 二人の目線が合うように少し内側に向けると、やさしい雰囲気に💗
- 顔のパーツは丸く、口は小さめにすると上品に見えます。
💡並べるときは「高さをそろえる」「顔の大きさを同じにする」だけで一気に整います!
③ 衣装のポイント
- 男雛は青や紺色系で落ち着いた印象に。
→ 袖に丸模様を入れると高貴な雰囲気になります。 - 女雛は赤やオレンジ系で華やかに。
→ 花柄を散らすと春らしくかわいくなります🌸 - 扇子や冠など、金色の折り紙を使うと豪華に見えます✨
💡服の裾を少し重ねて貼ると、立体感が出て自然です。
④ ぼんぼり(灯り)を作る
- 左右に1つずつ黒い支柱を置き、上に丸いぼんぼりを貼ります。
- 灯りの部分は薄いピンクの紙にして、全体にあたたかみを出します。
- 中心を少し濃くしてグラデーション風にすると本格的に見えます。
💡折り紙や和紙を使うと、柔らかい光の質感が出ます。
⑤ 桜の花びらで飾りつけ
- 背景全体に桜の花や花びらを散らして春を演出🌸
- 濃淡のピンクを混ぜて貼ると、奥行きが出て華やかになります。
- 花の向きを変えて、風に舞っているように配置しましょう。
💡大きな桜は外側に、小さい花は中央付近に貼るとバランスが良く見えます。
⑥ 全体の構成
- 上部:「3月」+花びら
- 中央:おひなさま・おだいりさま・ぼんぼり
- 下部:桜の花で土台を彩る
この上下3分割構成を意識すると、どこに貼っても見やすく整った印象になります。
💡中央に余白を残すことで、人物がより引き立ちます。
てんとう虫と菜の花
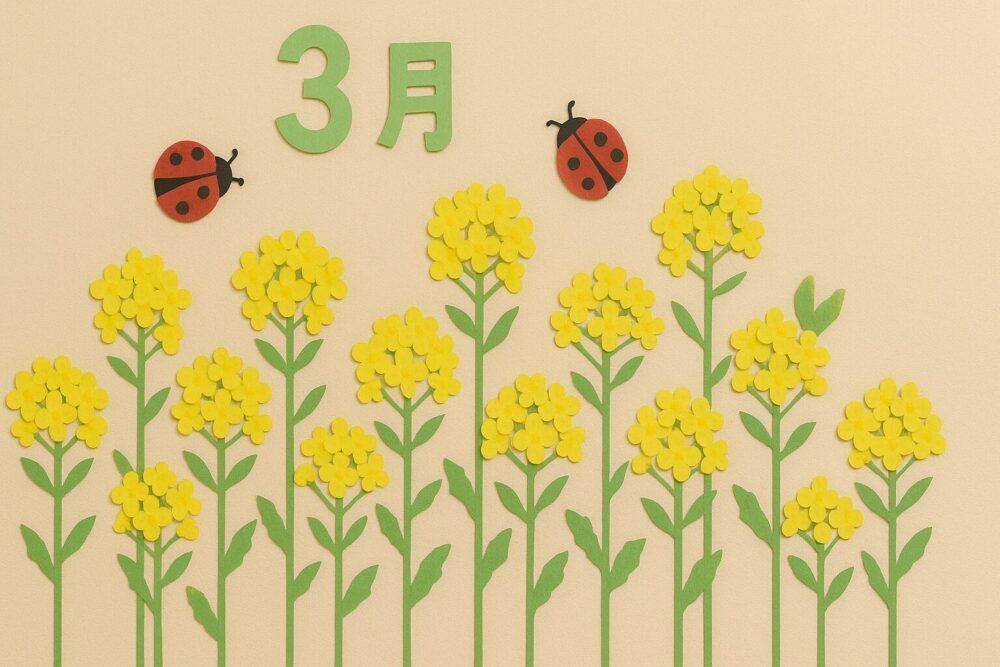
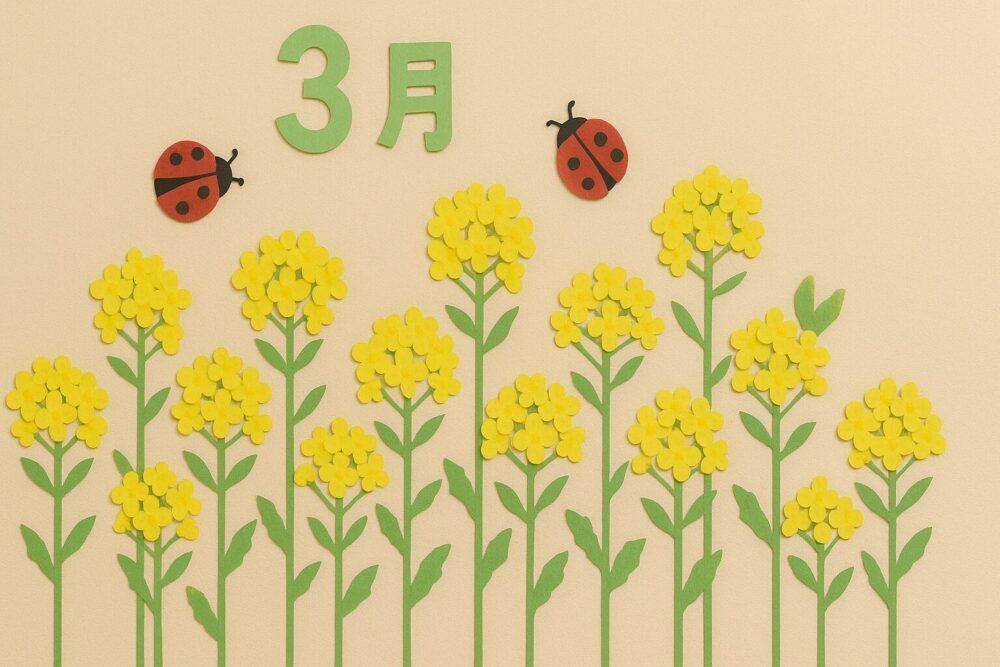
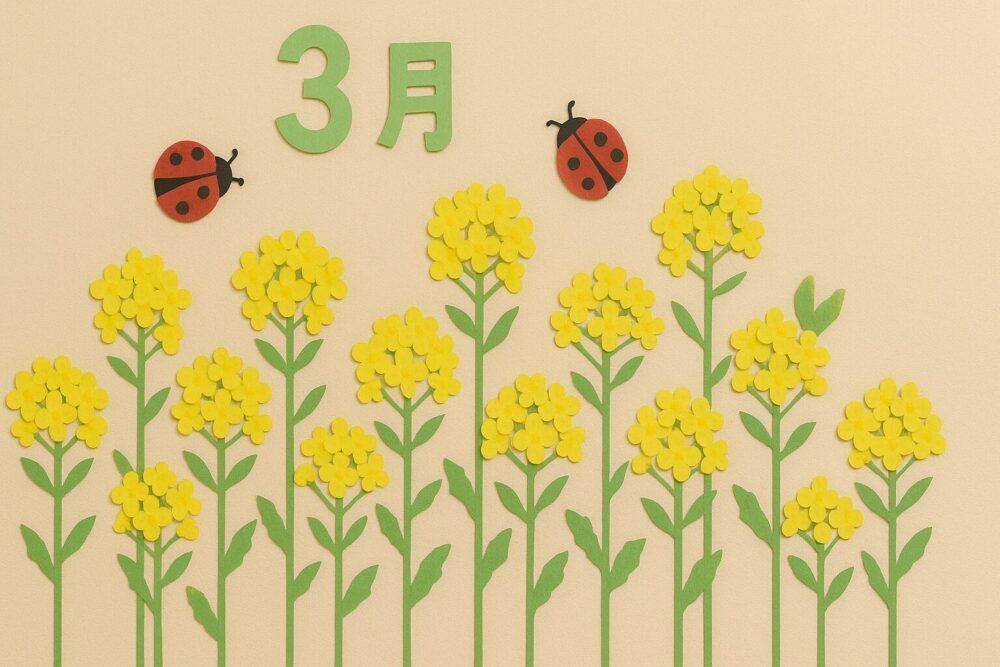
テーマ:春の始まりを感じる菜の花畑
3月は冬が終わり、春が少しずつやってくる季節。
「黄色の菜の花」と「てんとう虫」で、明るく元気な印象に仕上げます。
見ているだけで、ぽかぽか陽気を感じられる壁飾りです🌞
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を決める
- 背景はベージュや淡いクリーム色を使うと、菜の花の黄色がよく映えます。
- 春らしい柔らかい色味を選ぶことで、全体が明るくやさしい印象に。
- 「3月」の文字は緑色にして、自然の中の新芽をイメージしましょう🌿
💡文字は中央やや上に配置するとバランスがとれます。
② 菜の花の作り方
- 花の部分は小さな丸を4~5枚ずつ重ねて1輪の花にします。
- 黄色の画用紙をパンチや丸型テンプレートで量産しておくと便利です✨
- いくつかの花を重ねて、丸いかたまりに見えるように貼るのがポイント。
- 花びらを少しずつずらして重ねると、ふんわり立体的になります。
💡全体で10本前後の茎を作ると、ボリューム感が出て見栄えがします!
③ 茎と葉の配置
- 茎は細めの緑色の画用紙で、まっすぐ長く切ります。
- 長短をつけて並べると、自然な菜の花畑に見えます。
- 葉は左右に開くように貼ると、風にそよぐ感じになります🌿
- 花の位置は段差をつけて貼ると立体感が出てきます。
💡下の部分に少し重なりをつけて、群生しているように見せましょう。
④ てんとう虫を作る
- てんとう虫は赤×黒でアクセントに🐞
- 背中を赤、顔と線を黒で作り、黒丸の斑点をバランスよく配置します。
- 小さくて簡単な形なので、利用者さんにも貼ってもらいやすいパーツです。
- 向きを少し変えて(右向き・左向き)貼ると、動きが出ます。
💡1匹だけだと寂しいので、2〜3匹飛ばすのがちょうど良いです♪
⑤ 全体のバランス
- 上部:「3月」とてんとう虫
- 中央〜下部:菜の花畑
この上下の構成を意識すると、まとまりのある作品になります。
菜の花の高さにリズムをつけて、ゆるやかな波のようなラインにすると自然に見えます。
💡中央が少し高くなるように配置すると、写真映えも抜群です📸
4月の壁飾り
さくらと小鳥
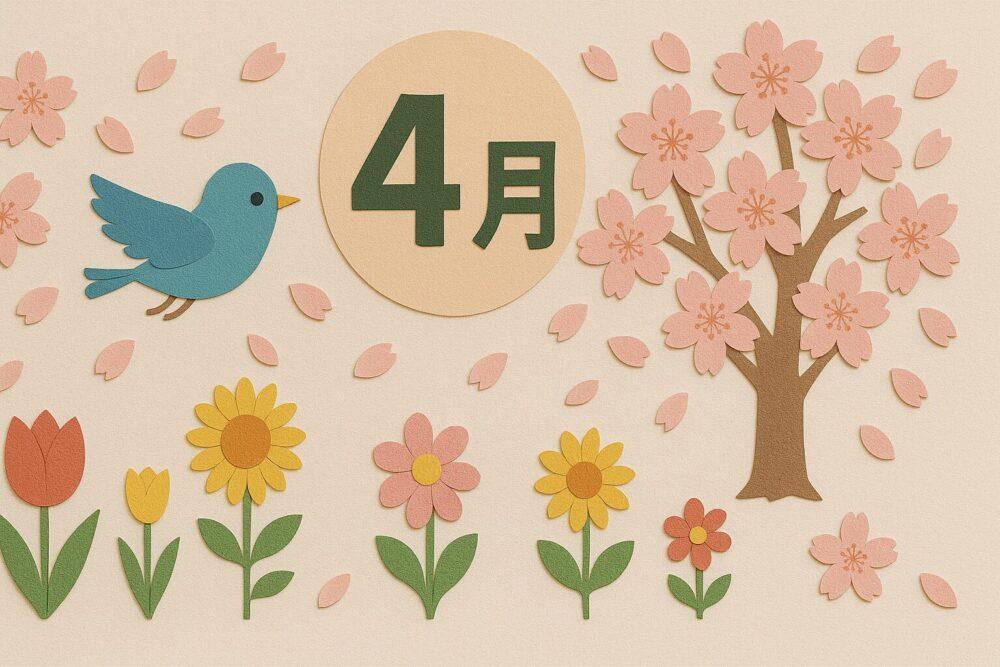
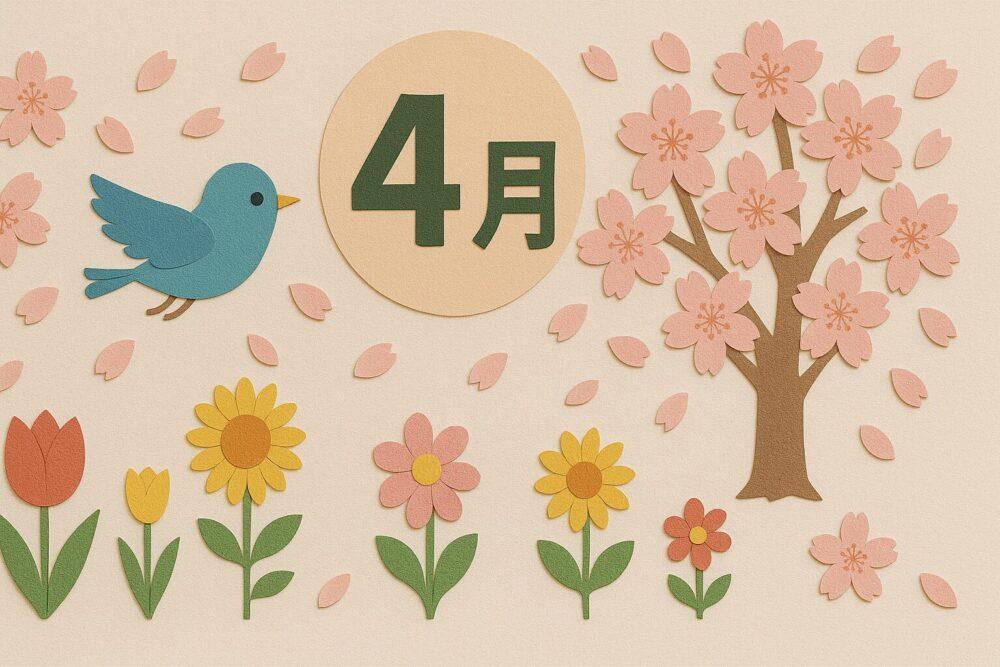
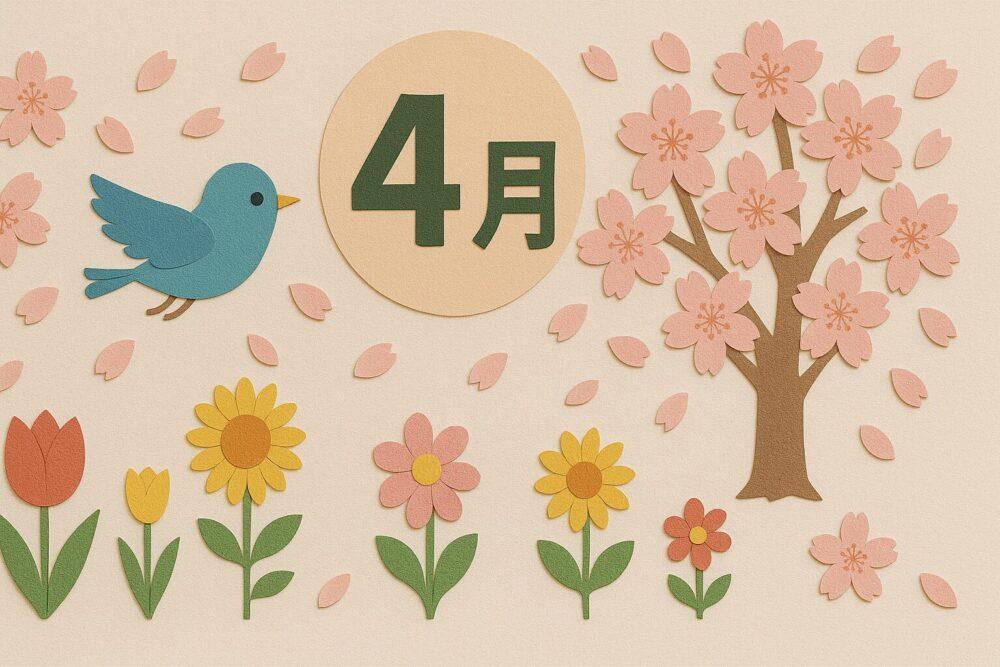
テーマ:春の訪れと新しい季節のスタート
満開の桜の下を小鳥が飛び、色とりどりの花が咲く —
春のやさしさやあたたかさを感じる壁飾りです。
4月の始まりにぴったりな、落ち着いた色味と優しい雰囲気が特徴です。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景と「4月」の文字
- 背景はベージュや淡いクリーム色を使うと、全体がやわらかくまとまります。
- 「4月」は緑色の文字をピンクの丸の上にのせると、春らしいコントラストになります🌸
- 丸い台紙を使うことで、作品全体にやさしい印象を与えます。
💡「月」の文字を少し右寄せにすると、デザインに動きが出てバランスがよくなります。
② 桜の木を作る
- 幹は茶色の画用紙を使い、枝を左右に伸ばしてバランスをとります。
- 幹はまっすぐよりも少しカーブさせると自然に見えます🌳
- 桜の花は淡いピンクの花びらを重ね貼りして立体感を出すのがポイント。
- 花の中心に線を書いたり、スタンプを押すとリアルに仕上がります。
💡花の向きや大きさを変えて貼ると、風に揺れているような自然な雰囲気に。
③ 花びらを散らす
- 木のまわりに舞い散る花びらをバランスよく配置します。
- 花びらは大きさを3段階(大・中・小)にして、上から下へ流れるように貼るのがコツ。
- 枚数は多すぎず、空間にリズムが出るようにしましょう。
💡右下方向に流すように貼ると「春風」を感じるデザインになります。
④ 小鳥を作る
- 鳥は水色〜青緑系で作ると、桜のピンクとよく合います🐦
- 羽の部分を別パーツにして、少し浮かせて貼ると立体感アップ!
- くちばしや足を小さく黄色で入れると、全体が引き締まります。
- 目は黒い丸シールかペンで描いてOK。
💡鳥の向きを「木に向かって飛んでいる」方向にすると、ストーリー性が出ます。
⑤ 下の花畑を作る
- 花はチューリップ・マーガレット風・デイジー風などを混ぜてカラフルに🌼
- 色は赤・黄・オレンジ・ピンクの4色が春らしくておすすめ。
- 葉の形を少し変えると、いろんな花が咲いている雰囲気に。
💡花の高さを少しずつ変えると、自然な草原のように見えます。
⑥ 全体のバランス
- 左上:小鳥と桜吹雪
- 中央:4月の文字
- 右:桜の木
- 下:花畑
この「斜め構成」を意識すると、全体に動きが出て美しい作品になります🌸
💡完成後に花びらを少し重ねて貼ると、全体がつながって見えて一体感が出ます。
春のピクニック



テーマ:春のぽかぽかピクニック
4月といえば「お花見」🌸
春らしい色づかいで、桜・お弁当・蝶・草花を組み合わせ、
「外でのんびり過ごすあたたかい春の日」を表現します。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を作る
- 背景は水色の画用紙で、春の空を表現します☀️
- 雲を白い画用紙で大小数個切って貼ると、空に動きが出ます。
- 「4月」の文字はオレンジ色で明るく目立たせましょう。
→ 数字を大きく、月の字を少し小さめにするとバランスがきれいです。
💡背景を貼る前に「空」「地面」「文字」の位置をざっくり決めておくと失敗しません!
② 丘と芝生をつくる
- 下半分に黄緑色の画用紙を貼って草原を表現します🌿
- 丘の上部をゆるやかなカーブにカットすると、やさしい印象に。
- 直線に切らず、少し波打たせると自然な景色になります。
💡緑のトーンを2種類使うと奥行きが出ます!
③ 桜の花びらを散らす
- ピンクの画用紙で桜の花を大小さまざまに作ります🌸
- 中心に黄色い丸を貼ると、より春らしい明るさに。
- 花の向きをランダムにして、風に舞っているような配置にしましょう。
💡同じサイズの桜ばかりだと単調になるので、大小3パターンを作るのがおすすめ!
④ ピクニックセットを作る
- レジャーシートは赤と白のチェック柄(市松模様でもOK)。
→ 紙に赤い線を引くだけでもチェック柄に見えます✨ - お弁当バスケットは茶色系の画用紙で。
→ ふたの部分を別パーツにして、少し立体的に貼るとリアルです。 - 飲み物(ペットボトル)やサンドイッチなど、明るい色を使うと華やかに。
💡お弁当の上に影になるように薄い紙を1枚重ねると、奥行きが出て上級者感!
⑤ 花とちょうちょで飾りつけ
- 草むらに赤・黄色・白の花を等間隔で貼りましょう🌼
- 花びらの数は3~5枚にするとバランスが良いです。
- ちょうちょは紫・黄色・ピンクなど、パステル系で春らしく🦋
- 羽の模様を丸やハートにしても可愛く仕上がります。
💡ちょうちょを斜めに貼ると、飛んでいるように見えます!
⑥ 全体のバランス
- 上部:桜の花びらを舞わせて華やかに
- 中央:お花見シートと「4月」の文字
- 下部:お花畑で色のリズムを出す
この「上・中・下の3層構成」を意識すると、見やすくまとまります🌸
💡左右対称ではなく、やや右寄り・左寄りに配置すると自然で動きのある印象に。
ちょうちょの行進



テーマ:春の訪れと新しいスタート
4月は新しい季節の始まり。
「あたたかな陽ざしと花の香りの中を飛ぶちょうちょ」をテーマに、
見た人がやさしい気持ちになれる春らしい作品を目指します✨
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を作る
- 背景は水色の画用紙で、春の青空をイメージ☀️
- 雲は白い画用紙をふんわり丸く切り、大小を混ぜて配置すると自然に見えます。
- 「4月」の文字はオレンジや黄色など明るい色で目立たせましょう。
💡上部に余白をつくることで、空の広がりを感じられます!
② 丘と草原を作る
- 下半分に明るい黄緑色の画用紙を貼って丘を表現します。
- ふんわりとしたカーブをつけると、やさしい印象になります🌿
- 直線ではなく「ゆるやかな山なり」にするのがコツ。
💡地面の形を少し傾けると動きが出て、作品がのっぺりしません。
③ 花を作る
- 花は5枚花びらの形で、赤・黄色・白などカラフルに🌼
- 花びらは同じ形でも、花芯(真ん中の色)を変えるとバリエーションが出ます。
- 花をランダムに配置し、同じ色が並ばないようにすると自然です。
💡お花の葉っぱを付けることで、全体にまとまりが出ます。
④ ちょうちょを作る
- 羽は黄色・ピンク・水色など明るい色を使い、春らしく。
- 羽の形を左右で変えると、飛んでいるような動きが出ます🦋
- 触角を細く長めに作ると、軽やかな雰囲気になります。
- 胴体は茶色で統一すると全体がまとまります。
💡左右交互に向きを変えて貼ると、空を舞っているように見えます!
⑤ 桜の花びらで季節感アップ
- 背景にピンクの桜の花びらを散らして、4月らしさをプラス🌸
- 花びらの大きさを少しずつ変えて、遠近感を出すとより自然に。
- 花の中心に黄色の丸を貼ると、柔らかい印象になります。
💡桜をちょうど真ん中ではなく、空の左右に散らすのがバランスのコツ。
⑥ 全体のバランス
- 上:空と桜
- 中:ちょうちょ
- 下:花と丘
この「三層構成」を意識すると、まとまりのある春の景色になります。
特にちょうちょが花の上を飛んでいる構図を意識すると自然でかわいい印象になります。
💡目線が左から右に流れるように並べると、作品全体が動いて見えます。
5月の壁飾り
鯉のぼり



テーマ:5月の空を泳ぐ 鯉のぼり
こどもの日の象徴である 鯉のぼりをカラフルに飾って、
「元気にすくすく育ってほしい」という願いを表現する作品です✨
青・赤・緑の3匹を中心に、まわりの花で明るくにぎやかに仕上げましょう!
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景と「5月」の文字
- 背景は壁の色をそのまま生かすか、淡い水色の画用紙を使うと空のような雰囲気になります☀️
- 「5月」の文字は濃い緑でまとめると、自然な印象に。
- 文字を上部中央に配置すると全体が引き締まります。
💡背景をすっきりさせることで、鯉のぼりの色がより映えます!
② 鯉のぼりをつくる
- 3色(青・赤・緑)の画用紙を使って親子の鯉のぼりを作ります。
- 青:お父さん鯉のぼり
- 赤:お母さん鯉のぼり
- 緑:子ども鯉のぼり - うろこは同系色の明るい紙を半円に切り、重ねて貼ると立体感が出ます。
- 目は大きく丸くして、黒目を少しずらすと表情がいきいきします🐟
💡うろこは少し重ねるように貼ると、風に泳ぐような動きが出ます!
③ 鯉のぼりの竿とひも
- 竿は茶色の画用紙をまっすぐ長く切って作ります。
- てっぺんには**黄色い丸(風車や太陽をイメージ)**をつけると明るく仕上がります☀️
- ひも部分は細い紙や毛糸を使うと、よりリアルに見えます。
💡竿を少し斜めにして貼ると、風を受けてなびいているように見えます!
④ 花と葉っぱで彩りをプラス
- 周りに桜やツツジ風の花をカラフルに散らして季節感を演出🌸
- 花の形は5枚花びらが基本。ピンク・黄・紫・水色など明るい色を使うと華やかです。
- 緑の葉を加えると全体のバランスが整います。
💡花を円形に並べると、「空に鯉のぼりが泳ぐ明るい風景」になります。
⑤ 全体のバランス
- 竿を左側に置き、右に向かって鯉のぼりを並べると動きが自然です。
- 大きい順(青→赤→緑)に並べると安定感が出ます。
- 花は上下左右に散らして、余白を埋めすぎないようにしましょう。
💡貼る前に一度並べて「風が通るような空間」を意識するとキレイに仕上がります。
兜と金太郎



テーマ:こどもの日「元気いっぱい金太郎」
5月の代表的な行事「こどもの日」にぴったりの作品です🎉
元気でたくましい金太郎と、立派な兜を並べて飾ることで、「健やかな成長」を願う気持ちを表現できます。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景と「5月」の文字
- 背景は壁の色を活かして、明るくすっきりとした印象に。
- 「5月」の文字は大きめに、黒や緑など濃い色で目立たせます。
- 背景を青や水色の画用紙にしても、晴れやかな雰囲気になります☀️
💡背景に雲やこいのぼりを追加しても季節感がアップ!
② 金太郎をつくる
- 金太郎の体は肌色、髪は黒い画用紙で作ります。
- 特徴の「まさかり」と「赤い前掛け」はしっかり目立たせましょう。
- 前掛けの「金」の文字は金色の折り紙などで作ると豪華に✨
- 表情は大きな笑顔で、元気で明るい印象を意識します。
💡ほっぺをピンクの丸で貼ると、より可愛らしくなります!
③ 兜(かぶと)をつくる
- 大きい兜は濃い青+金の組み合わせで勇ましさを出します。
- 小さい兜は白や銀色でアクセントにすると全体が締まります。
- 立体感を出すために、角や縁部分を少し浮かせて貼ると◎
- 紐の部分は細い紙を使って、実際に結んだように見せるとリアルです。
💡兜の中央(鍬形部分)は左右対称に貼るとバランスがきれいに整います。
④ 草や地面をつくる
- 下に黄緑色の台紙を敷くと、自然な足元の雰囲気が出ます。
- 草はギザギザ型に切った紙をランダムに配置すると動きが出ます。
- 石や影を加えると、全体が立体的に見えて◎
💡「地面の上を金太郎が歩いている」構図を意識すると自然な配置になります。
⑤ 全体の配置バランス
- 金太郎を右側、兜を左側に置くと見た目のバランスが良くなります。
- 「5月」の文字を上部に配置して、中央をすっきり見せましょう。
- 余白をうまく残すことで、主役(人形と兜)が引き立ちます。
💡人物が左を向く場合は、右に兜を置いても◎(視線の先に余白があると自然に見えます)
森と小川



テーマ:さわやかな5月の森と小川
5月といえば、新緑がまぶしい季節🍃
自然の豊かさや心地よい風を感じられるように、いろんな“みどり”の色を使って立体的に表現するのがポイントです。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は淡い水色の画用紙を使って、晴れた初夏の空をイメージします。
- 「5月」の文字は濃い緑にして、自然の爽やかさを表現。
- 上部に白い雲を貼ると、のどかな雰囲気が出ます☁️
💡空の色を少し明るめにすると、全体がさわやかで明るい印象になります。
② 木をつくる
- 木の幹は茶色の細長い画用紙で作ります。
- 葉っぱの部分は、3〜4種類の緑色を使うのがポイント🌿
- 明るい緑・濃い緑を交互に配置すると、奥行きと立体感が出ます。
- 木の形はすべて同じにせず、少しずつ大きさを変えると自然に見えます。
💡木の重なり方を前後で変えると「森の奥行き感」が出て、見応えのある作品になります。
③ 小川をつくる
- 小川は水色の紙をゆるやかにカーブさせて貼ります。
- 流れの線を白のペンや細い紙で描き加えると、水の動きが出てリアルに!
- 小川の幅を手前を太く・奥を細くすると、奥行きが強調されます。
💡「水の流れ」を感じるように曲線をやわらかく描くのがコツです。
④ 草や石を配置する
- 草は三角やギザギザ型に切って、ランダムに貼ります。
- 明るい緑・濃い緑を混ぜて使うと自然に見えます。
- 石はグレーの画用紙を楕円形に切り、ところどころに置いてアクセントにします。
💡草の向きや高さを少し変えると、自然な「野原」の感じになります。
⑤ 全体のバランス
- 小川を中心にして、左右に木や草を配置すると安定感のある構図になります。
- 奥の木を濃い色、手前を明るい色にすると遠近感が出ます。
- 上に「雲」、下に「草と小川」で、上下のバランスがとれます。
💡真ん中に小川が通る構図は“見た目がすっきり”して、どんな壁にも合います!
6月の壁飾り
「てるてる坊主」と「あじさい」



テーマ:雨の日もニコニコ「てるてる坊主とあじさい」
梅雨の6月を明るくしてくれる、てるてる坊主とカラフルなあじさいが主役の壁飾りです。
見ているだけで笑顔になれるような、やさしい色づかいと表情がポイントです🌸🌧
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は薄い水色の画用紙を使って、雨空を表現します。
- 「6月」の文字は大きく太めに、赤い紙で作って元気な印象に。
- 背景に雨粒をバランスよく散らして貼ると、季節感がぐっとアップします。
💡雨粒は同じ形でも大きさを少し変えると自然で動きのある印象に!
② てるてる坊主をつくる
- 顔の部分は白い画用紙の円を使い、輪郭を黒で縁取りするとハッキリします。
- 表情は笑顔・ニコニコ顔など、明るい雰囲気に。
- リボンを色違いで(青・ピンクなど)つけると可愛らしさがアップ🎀
- 雨の中でも元気なイメージを出すため、左右対称に2体並べるとバランスが良いです。
💡ほっぺをピンクの丸で加えると、さらに温かい印象になります。
③ あじさいをつくる
- あじさいの花は**丸い土台(紫・青)**の上に、小さな四角の花びらを貼って作ります。
- 花びらはピンク・紫・水色など、3〜4色を混ぜて貼るのがポイント。
- 四角を少し重ねて貼ると、立体感が出てふんわりした仕上がりになります。
- 葉っぱは濃い緑で、大きめに作ると全体が引き締まります🌿
💡花びらを1枚ずつずらして貼ると「本物のあじさい」に近づきます!
④ 全体のバランス
- てるてる坊主を上の左右に配置し、中央に「6月」の文字を置くと安定感があります。
- あじさいは下に広く並べて、作品全体を明るく彩ります。
- 雨粒をあじさいの間にも少し入れると、しっとりした雰囲気に。
💡背景がさみしい場合は、雲や虹を足してもかわいくなります🌈
⑤ 色使いのコツ
- 梅雨らしい青系・紫系のトーンを中心にまとめると季節感が出ます。
- てるてる坊主のリボンや「6月」の文字をビビッドカラーにして、全体を明るく見せましょう。
💡白とパステル色を多めに使うと、やさしく癒し系の仕上がりに。
かたつむりの散歩



テーマ:梅雨を楽しく「かたつむりとあじさい」
6月といえば、雨とかたつむり、そして色とりどりのあじさい!
しっとりした梅雨の雰囲気を明るく、ほのぼのした表情で表現するのがポイントです☔🌸
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は薄い水色の画用紙を使い、雨の日の空を表現します。
- 「6月」の文字は、紫や青など“梅雨らしい色”で目立つように大きく。
- 上から雨粒をランダムに貼ると、自然な「雨降り感」が出ます。
💡雨粒の大きさを少しずつ変えると、奥行きのあるデザインになります。
② あじさいをつくる
- 花びらはピンク・青・紫などの丸やしずく型を使って表現。
- 1つのあじさいに同系色の紙を数種類混ぜると、立体感が出ます。
- 花びらの中心に白い丸を貼ると、より可愛らしくなります。
- 葉っぱは濃い緑で、少し重ねて貼ると自然な印象に🌿
💡丸シールを中心に使うと、貼りやすくて高齢者にも作業しやすいです。
③ かたつむりをつくる
- 体は茶色や黄色の画用紙、殻はピンク・オレンジ・黄色などの渦巻き模様で作ります。
- 渦巻きを別紙で作って貼ると立体感が出ます。
- 顔は笑顔にして、表情をやさしく可愛くするのがポイント😊
- 2匹並べると「親子」や「お友だち」のように見えて温かみが出ます。
💡目と口の位置を少し変えるだけで個性が出ます。向かい合わせにして会話しているようにするのもおすすめ!
④ 土と草をつくる
- 下部の地面は黄土色で橋のようにカーブさせると柔らかい印象になります。
- 草はギザギザ型に切った緑の画用紙で作ります。
- 草の上にあじさいを置くと、全体が引き締まります🌱
💡地面をカーブにすると、自然な奥行きが出て立体的に見えます。
⑤ 全体のバランス
- 上半分に雨粒、下半分にあじさいとかたつむりを配置してバランスを取ります。
- 雨の中でも明るい色を多めに使うと、 cheerful な印象に仕上がります。
- 「6月」の文字は中央上に配置して、作品のまとまりを出します。
💡雨粒の色は2~3色混ぜると、動きのある雨空を演出できます。
傘と長靴



テーマ:梅雨を楽しく「カラフル長靴と傘の壁飾り」
6月といえば雨の季節。
雨の日も楽しく過ごせるように、カラフルな傘と長靴で明るい雰囲気に仕上げるのがポイントです。
見ているだけで「雨の日も悪くないな」と感じられるデザインです🌈
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は水色の画用紙を使って雨空を表現します。
- 下の部分に薄い緑の紙を貼って「地面」を作ります。
- 「6月」の文字は、見やすいように濃い青色の太文字にします。
- 文字の周りにカラフルな丸を飾ると、ポップで楽しい印象になります。
💡ポイント:水色を基調にしつつ、アクセントカラー(黄色・ピンク)を散らすと明るくなります!
② 雨粒をつくる
- 雨粒は水色の画用紙をしずく型に切って貼ります。
- 大きさを少し変えると、自然な「雨の流れ」が表現できます。
- 雨粒の位置は、全体に散らすように配置しましょう。
💡同じ方向にしずくの尖った部分を向けると、雨が降っているように見えます。
③ 傘をつくる
- 傘は3色以上のカラフルな配色にすると華やかになります。
例:黄色×ピンク×青 - 柄(え)は茶色の細長い紙で作り、少し斜めに貼ると自然な動きが出ます。
- 傘の模様(ドットやボーダー)をつけると、より可愛くなります☂️
💡折り紙や包装紙を使うと模様に変化が出て、仕上がりがワンランクアップ!
④ 長靴をつくる
- 長靴は左右ペアで作り、4足くらい並べるとリズム感が出ます。
- 黄色・オレンジ・青・ピンクなど、雨の日に映えるビビッドカラーを使いましょう。
- 模様(ドットやボーダー)を入れると個性が出て楽しいです。
- 長靴の底を少し濃い色で貼ると、立体的に見えます。
💡ペアを少しずらして貼ると、自然な「置き方」に見えます。
⑤ 全体のバランス
- 傘を右上、長靴を下に並べると安定感のある構図になります。
- 空いた部分に雨粒を散らして、全体に「動き」を出しましょう。
- 全体の色合いが重くならないよう、明るい色を中心に配置するのがコツです。
💡地面に少し水たまりのような模様を入れてもリアルでかわいいです。
7月の壁飾り
七夕



テーマ:願いを込めて「七夕の夜」
7月といえば七夕!
織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)が天の川で出会う、ロマンチックで夢のある壁飾りです✨
色とりどりの短冊が揺れる竹笹と、星が輝く夜空がポイントです。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は濃い紺色や藍色の画用紙を使って夜空を表現します。
- 紙全体を覆うように貼ることで、星や人物が明るく映えます。
- 右上に「7月」の文字を黄色で大きく配置すると、作品全体が引き締まります。
💡ポイント:黒よりも少し青みのある背景が、優しくて落ち着いた印象になります。
② 竹笹(たけざさ)をつくる
- 笹の枝は緑の画用紙を細長く切り、しなやかなカーブをつけて貼ります。
- 葉は少し重ねて、立体感を出すのがコツ。
- 枝の向きを左右交互に変えると、自然な笹の形に見えます。
💡笹の緑は濃淡2色を使うと、よりリアルになります。
③ 短冊と飾りをつける
- 短冊は赤・青・黄・紫・ピンクなどカラフルに!
- 縦長の長方形に切って、笹に吊るすように貼ります。
- 飾りの種類(提灯や吹き流し)を加えると、より七夕らしい雰囲気に。
💡利用者さんや子どもたちに「願いごと」を書いてもらってもOK!
④ 織姫と彦星をつくる
- 織姫(左):ピンクや赤系の着物でやさしい雰囲気に。
- 彦星(右):緑や青系の着物で爽やかにまとめます。
- 両手を広げて向かい合うように配置すると、「再会の喜び」が伝わります。
- ほっぺや表情を可愛く描くと、温かみが出ます😊
💡キャラクターを少し斜めにすると動きが出て、生き生きした印象になります。
⑤ 天の川と星を飾る
- 天の川は水色や銀色の紙を波のような形に切って貼るのがコツ。
- 星は大・中・小の黄色い星をランダムに配置。
- 大きな星を中央に置くと、全体が華やかになります。
💡星の数を多くしすぎないと、バランスが整います。
海水浴



テーマ:夏本番!「海で遊ぶ子ども」
7月といえば海・スイカ・太陽!
夏の明るさや楽しさを表現した壁飾り。
見ているだけで元気になるような、にぎやかで爽やかなデザインが特徴です。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 空と海と砂浜の3層構造で作ります。
- 空:水色の画用紙
- 海:青の画用紙(ゆるい波型に切ると自然)
- 砂浜:ベージュや薄茶色の画用紙
- 背景を分けるときは、曲線で区切るとやわらかい印象になります。
💡ポイント:海と空の境界を直線ではなく波線にすると動きが出ます。
② 太陽と雲をつくる
- 太陽はオレンジと黄色の二重構造で、元気な笑顔を描きます☀️
- 雲は水色や白の紙でふんわり形を切り取り、空の隅に貼ります。
- バランスを見ながら、太陽を右上に配置すると明るい印象になります。
💡太陽の顔をにっこりさせると、全体が優しい雰囲気に。
③ 子どもをつくる
- 肌色の紙で体を切り抜き、青い水着を貼ります。
- 顔は黒髪+大きな目+赤いほっぺで表情豊かに。
- バランスをとるため、中心より少し右側に配置します。
💡ほっぺをピンクで貼ると、明るくかわいく見えます!
④ 海のアイテムを加える
- ビーチボール、スイカ、パラソル、ヒトデなどを色鮮やかに配置。
- 色のコントラストを意識して、赤・黄・青をバランスよく散らすとまとまります。
- ビーチボールの線は正確でなくてもOK。丸みを意識して貼ると自然に見えます。
💡「スイカ」は三角に切ったり、模様を描いたりして個性を出しましょう🍉
⑤ 星を貼ってにぎやかに
- 背景の空いている部分に黄色い星をランダムに配置。
- 夜空というより“キラキラした夏空”を表現します。
💡大・中・小のサイズを混ぜるとバランスが取れます。
あさがお



テーマ:夏の訪れを感じる「朝顔の鉢植え」
7月の季節感を代表する**朝顔(あさがお)**をモチーフにした、爽やかで落ち着いた壁飾りです。
カラフルな花と緑の葉のコントラストが美しく、見ているだけで涼しさを感じられます。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は濃い青(紺色)の画用紙を使うと、朝顔の花の色が引き立ちます。
- 全体的に夜明け前〜朝方の雰囲気をイメージして、静かな夏の朝を演出します。
- 「7月」の文字は黄色やオレンジで作ると、明るく季節感が出ます。
💡ポイント:背景が暗いと花の色が映え、清涼感がアップします。
② 鉢植えを作る
- 鉢の部分は茶色やオレンジ系で作りましょう。
- 下の部分を少し大きめにして、安定感のある形にすると見栄えが良いです。
- 鉢の底に影をつけるように、濃い茶色を少し重ねても立体感が出ます。
💡「鉢」を貼る位置は下から1/4あたりがバランス◎
③ 支柱(あさがおの網)をつくる
- 細長い茶色の紙を格子状に貼って、つるが絡まる支柱を表現します。
- 横線と縦線の間隔をそろえると整った印象になります。
- 少しズラして貼ると、自然な立体感が出ます。
💡格子の間隔を広く取りすぎないのがポイント。花とのバランスを見て。
④ 花の作り方
- 朝顔の花はピンク・青・紫など、明るく優しい色を使います。
- 花びらは円形にして、中央に白い星形模様を重ね貼りします。
- 花びらの端を少し重ねることで、ふっくらした立体感が出ます。
💡同じ色を並べすぎず、「色のばらつき」を意識して配置しましょう。
⑤ 葉っぱとつるを作る
- 葉は濃い緑と薄い緑の2色を組み合わせると自然に見えます。
- ハート形に切ると可愛らしい印象に。
- つるは細く長く切って、格子や花の間を通すように貼りましょう。
💡つるが全体をつなぐ「流れ」を作ると、自然で美しい構図になります。
8月の壁飾り
花火大会



テーマ:夏の夜を彩る「花火大会と縁日」
夜空に咲く花火と、浴衣を着た人たちの笑顔を描いた夏の風情あふれる壁飾りです。
見る人に「懐かしい夏の思い出」を感じてもらえる温かい作品になります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を作る
- 背景は黒の画用紙を使用。
夜空をイメージすることで花火や浴衣の色が映えます。 - 下部に**川や地面(青・茶色の紙)**を貼ると、風景に奥行きが出ます。
- 川辺の草を緑の画用紙で貼ると、全体のバランスがよくなります。
💡ポイント:黒い背景はのりの跡が目立ちやすいので、スティックのりを少なめに使いましょう。
② 花火を作る
- 花火は赤・黄・青・紫などのカラフルな紙を放射状に貼ります。
- 大きさの異なる花火を数個作り、高低差をつけて配置すると動きが出ます。
- 星や火の粉を散らすと、よりリアルに。
- 花火の中心を白や黄色で強調すると、パッと開いた感じになります。
💡ポイント:重ね貼りで立体感を出すと迫力がアップ!
③ 屋台と提灯を作る
- 屋台は赤と白のしま模様で「夏祭りらしさ」を表現。
- 提灯は丸い形にして、中央に黒い線を入れると本物っぽく見えます。
- 2〜3個並べると、縁日のにぎやかさが伝わります。
💡中に小さな食べ物(りんご飴・綿あめなど)を描いても楽しいです。
④ 浴衣の子どもたちを作る
- 人物は淡い色の画用紙を使って、笑顔を大きく描くのがポイント。
- 男の子は青系、女の子はピンク系の浴衣でバランスをとると華やか。
- 手に「りんご飴」「チョコバナナ」などを持たせると可愛らしさが増します。
💡頬にうすいピンクを貼ると、表情がより明るくなります。
⑤ 「8月」の文字
- 赤やオレンジなどの暖色系で作ると、夜空の中で目立ちます。
- 左上など空いたスペースに配置して、全体を引き締めましょう。
金魚



テーマ:夏祭りの風物詩「金魚すくい」
8月といえば夏祭り!
水の中を泳ぐ金魚とポイ(すくい網)を表現した、見た目にも涼しい壁飾りです。
シンプルな構成ですが、配色のコントラストが美しく、季節感をしっかり演出できます。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は**濃い青(紺色)**の画用紙を使うと、水の冷たさが引き立ちます。
- ベースを暗めにして、上に貼る「水面の円形部分」を明るい水色で作ると、金魚がより目立ちます。
- 可能なら、背景の端に小さな波線を入れると動きが出ます。
💡ポイント:全体のトーンを“涼しげ”にするのがコツ!
② 水の部分(たらい)をつくる
- 円形のたらいは、明るい水色+グレーの縁で作ります。
- 水の中に**波模様(濃い水色)**を数本入れると、金魚が泳いでいる感じに。
- 気泡(白い丸)を貼ると、さらにリアルになります。
💡たらいの形は正円よりも少し横長にすると、立体感が出ます。
③ 金魚の作り方
- 赤やオレンジの画用紙で、体・ひれ・しっぽを切り分けて貼ります。
- パーツを少しずつ重ねると、動きが出て本物らしく見えます。
- 目は黒丸でシンプルに。貼る位置をずらすと、表情が生まれます。
💡3匹以上泳がせると、にぎやかでバランスが良くなります。
④ ポイ(すくい網)の作り方
- 枠は薄いベージュ、持ち手は黒またはこげ茶で作るとリアルです。
- 網の部分は白い紙を丸く切るだけでOK。
- 少し金魚の近くに貼ると、「今まさにすくっている」ような動きが感じられます。
💡ポイを少し斜めに配置すると臨場感アップ!
⑤ 「8月」の文字
- 黄色やオレンジで作ると、金魚の赤と相性が良く、明るい印象になります。
- 右上に配置すると全体が引き締まります。
風鈴



テーマ:涼を感じる「風鈴のある夏の部屋」
8月の暑さの中でも、見て涼しい・心地よい音を想像できるような壁飾りです。
すだれと風鈴を組み合わせることで、日本の夏らしい情緒が伝わります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景(すだれ)をつくる
- 背景全体に茶色系の画用紙を使い、すだれのような横線を貼って作ります。
- 細長い帯状の紙を間隔をあけて貼ると、立体感が出ます。
- 濃淡2色の茶色を使うと「竹の質感」っぽく見えておすすめです。
💡ポイント:線を少しずつずらして貼ると、自然な陰影が生まれます。
② 風鈴の部分をつくる
- 風鈴の「ガラス部分」は水色や青系の画用紙で作ります。
- 丸を半分に切ったような形を2枚重ね、奥行きを表現しましょう。
- 吊るすひもは黒い紙を細く切って貼ります。
💡風鈴の中の部分(舌:ぜつ)を黒で描くと、リアルさが増します。
③ 短冊(たんざく)の作り方
- 薄い青や白の画用紙を使用。
- 下の方に花や金魚などの模様をワンポイントで貼ると可愛くなります。
- 風に揺れているように、少し斜めに貼るのがコツ。
💡短冊の先を丸くカットするとやさしい印象になります。
④ 「8月」の文字
- 黄色やオレンジなど、明るく元気な色を使うと季節感が出ます。
- 右上など空いたスペースにバランスよく配置しましょう。
うちわ



テーマ:夏を感じる「うちわアート」
8月らしい季節感をたっぷり詰め込んだ作品です。
スイカ、金魚、花火、ひまわり、朝顔などをモチーフにしたうちわを並べることで、見て楽しい・作って楽しい夏の壁飾りになります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を整える
- 背景はベージュや薄い黄色の画用紙がオススメ。
どんな色のうちわでも映えやすく、明るい印象になります。 - 壁に貼るときは、左右対称ではなくランダムに並べると自然な動きが出ます。
💡ポイント:背景に「風鈴」や「流れる風」を描き足しても爽やかさアップ!
② うちわの形を作る
- まずうちわのベース(白や淡い色)を作り、取っ手部分を薄茶色で切って貼ります。
- 厚めの画用紙や工作用紙を使うと、しっかりした仕上がりになります。
- 形は丸すぎないよう、少し縦に長い楕円形にすると本物らしいです。
💡うちわを少し重ねるように貼ると、立体感が出ます。
③ 絵柄を貼る(テーマごとに分担してもOK!)
🔹花火
- 濃い青や紺の紙を背景にして、黄色・赤・オレンジで花火を描きます。
- 細く切った紙を放射状に貼ると、キレイに仕上がります。
🔹金魚
- 赤・オレンジ・青の画用紙で金魚を作ります。
- 泳ぐ向きをバラバラにして、水の流れを感じさせる配置に。
- 青い波模様を背景に入れると、より涼しげです。
🔹朝顔
- 花びらは赤・青・紫、中心を白で抜くと立体感が出ます。
- 緑のツルを細く切って貼り、流れるように配置しましょう。
🔹スイカ・ひまわり・タコ
- スイカは赤と緑のコントラストが夏らしさを引き立てます。
- ひまわりは中心を茶色にして、花びらを黄色で放射状に貼ります。
- タコは赤色でシンプルに!目をつけると可愛らしいアクセントになります。
💡利用者さんに好きなモチーフを選んでもらい、それぞれのうちわを作るのも楽しいです。
④ 「8月」の文字をつける
- 黄色やオレンジなど、明るい暖色系で作ると元気な印象になります。
- 壁の中央やや上に配置して、季節感をしっかり伝えましょう。
9月の壁飾り
お月見



テーマ:十五夜(お月見)を楽しむ秋の夜
9月といえば「お月見」。
満月、うさぎ、すすき、お団子を組み合わせて、秋の静けさと季節感を表現する壁飾りです。
やさしい色づかいで、年配の方にも親しみやすいデザインになっています。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は濃い紺色や深い青色の画用紙を使い、夜空をイメージします。
- 濃い色の上に黄色や白を貼ると、コントラストが美しくなります。
- 壁に貼るときは、なるべく明るい照明の下に飾ると、月の黄色がより映えます。
💡ポイント:下地に薄い雲や星を入れると、さらに夜空らしくなります。
② 月の作り方
- 満月は黄色の丸い紙で作ります。
- 少し大きめにして、左上か右上に配置するとバランスが良いです。
- 丸が歪まないように、型紙を使ってカットするのがおすすめ。
💡少し金色の紙を使うと、輝く月のように見えます✨。
③ すすきの作り方
- 茎は細長い緑の紙で作り、穂は黄色やベージュで表現します。
- 穂は細く切り込みを入れて、少し広げながら貼るとリアルに見えます。
- 角度を変えて何本か並べると、風に揺れているように見えて美しいです。
💡穂の先を少しカールさせると、やわらかく自然な仕上がりになります。
④ お団子と台
- お団子は白い丸を9個作り、ピラミッド型に重ねて貼るのが基本。
- 上:1個
- 中:2個
- 下:3個
- さらに下に3個を加えてもOK(バランスを見て調整)
- 台は茶色の紙で作り、黄色の紙で「布(かけ紙)」を表現します。
💡団子の並べ方を利用者さんと一緒に考えると、会話が弾みます。
⑤ うさぎの作り方
- 白い画用紙で切り抜き、黒い目をつけます。
- 耳は長めに、体のラインをやさしいカーブで描くとかわいらしくなります。
- お団子のほうを見上げるように配置すると、「お月見している姿」に見えます🐇。
💡耳の内側をほんのりピンクに塗ると、あたたかみが増します。
⑥ 「9月」の文字
- 赤やオレンジの暖色系で大きく作ると、夜空の中で目立ちます。
- 左上に貼ると全体のバランスがよく、月との位置関係も自然になります。
赤とんぼ
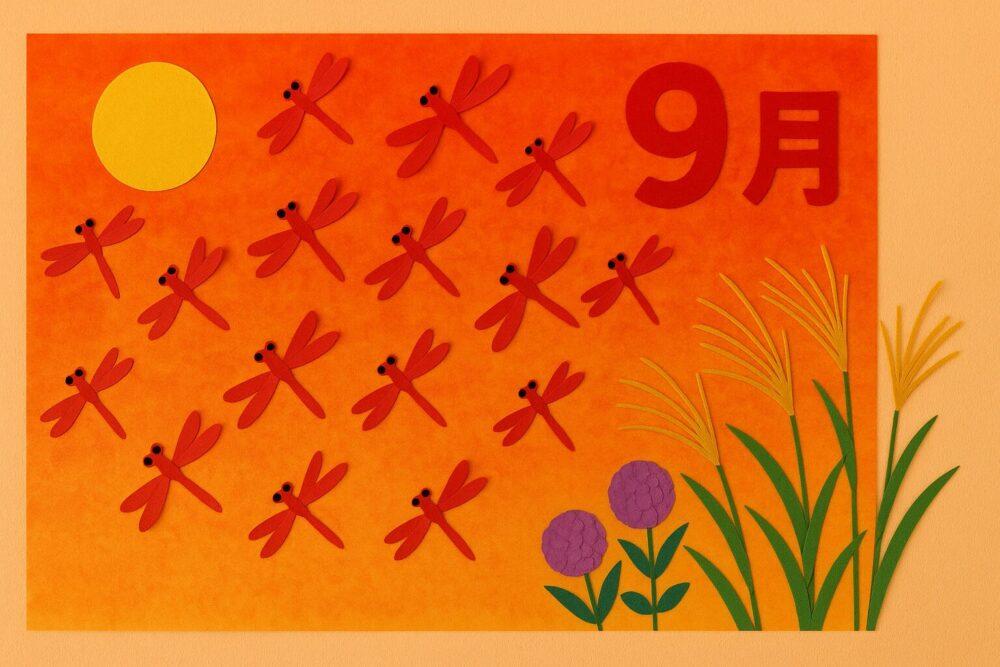
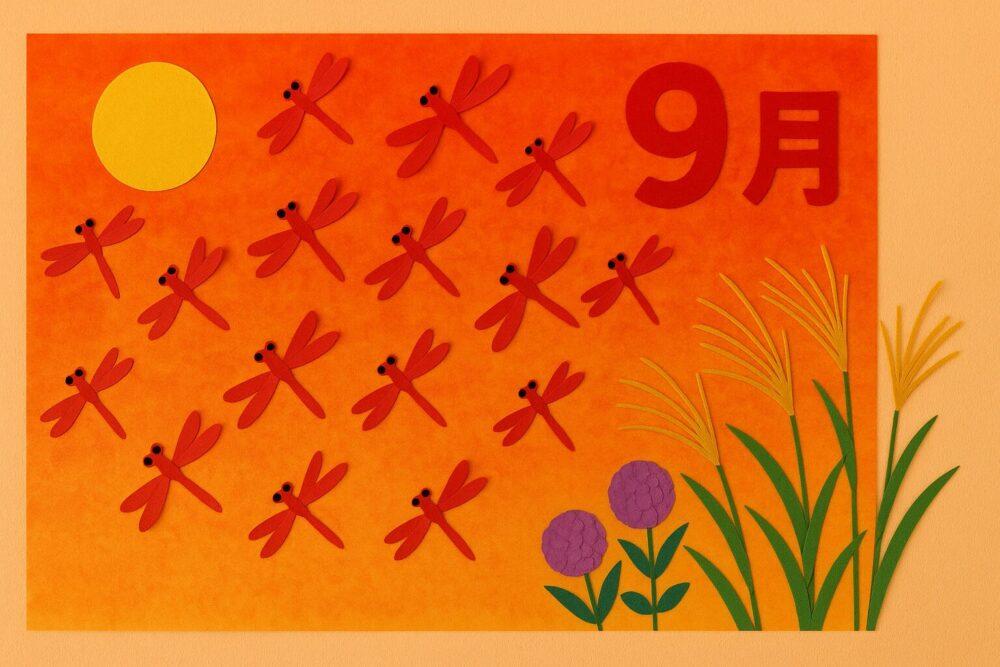
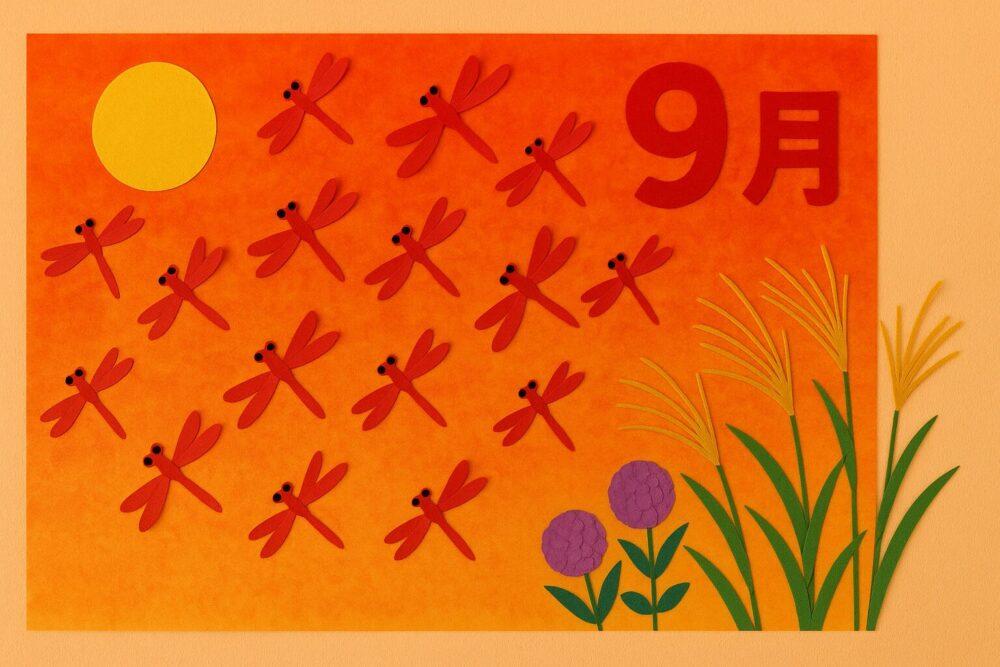
テーマ:夕焼けに舞う「赤とんぼ」
9月らしい秋の風景と郷愁(きょうしゅう)を感じさせる壁飾りです。
赤とんぼの群れとススキの組み合わせで、見た人の心がホッとする作品になります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景はオレンジの画用紙や、黄色から赤へのグラデーション紙を使うと夕焼け感が出ます。
- 壁に貼るときは、目線より少し上に配置すると、空を見上げるような印象になります。
- 余白をあけすぎず、トンボが舞う空を広く見せるようにバランスを調整しましょう。
💡ポイント:背景の上部に赤みを強く、下部に明るめの色を使うと奥行きが出ます。
② 赤とんぼの作り方
- 羽と体は赤い画用紙を使用します。
- 羽は4枚、体は細長くカットして貼ります。
- 目は黒い丸シールや黒画用紙で作り、白目をつけると表情が生まれます。
- 飛ぶ方向を変えて貼ると、自然な群れの動きが表現できます。
💡体を少し斜めに貼ると「ふわり」と飛んでいるように見えます。
③ ススキと草の作り方
- 茎は緑の細長い紙、穂は黄色の紙で作ります。
- 穂は細く切り込みを入れて、少し広げるように貼ると本物のようになります。
- 高さを変えて数本立てると、風に揺れる秋草の雰囲気が出ます。
💡黄色に金色や薄茶色を混ぜると、よりリアルな秋らしさになります。
④ 花(アザミ・菊)の作り方
- 紫の花は、丸い紙をちぎって貼ると柔らかい立体感が出ます。
- 葉は濃い緑を使い、下に向かって広がるように配置します。
- 全体の右下に花をまとめて貼ると、構図のバランスが取れます。
⑤ 「9月」の文字と太陽
- 「9月」は赤や茶色系で、背景と馴染む暖色系を選びましょう。
- 太陽は黄色の円形を使い、左上に貼ると全体が引き締まります。
- 文字と太陽の間に少し空間を作ると、スッキリとした印象になります。
収穫の稲穂
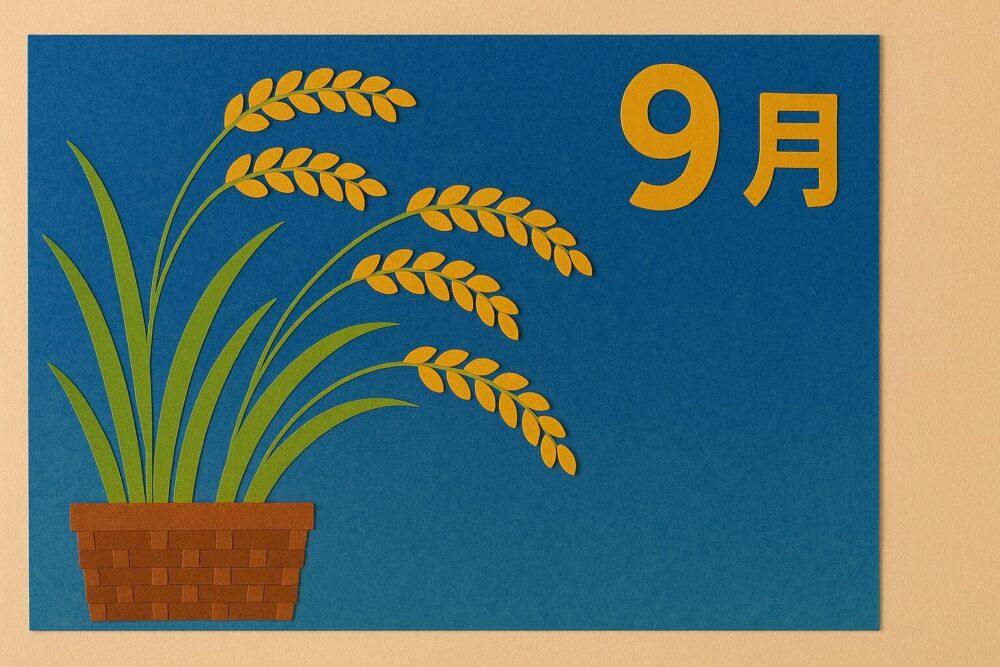
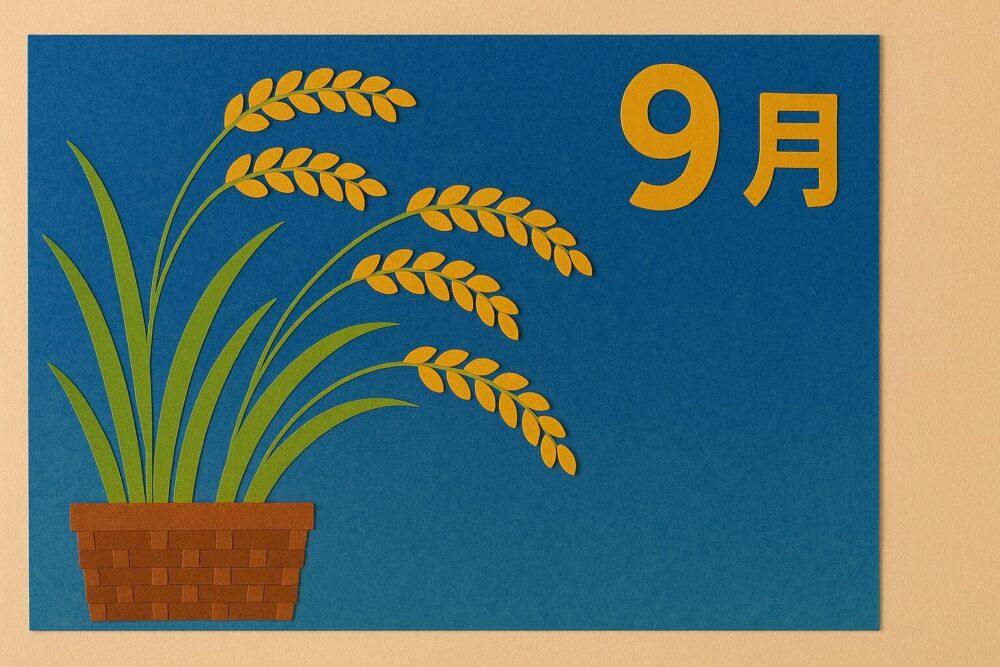
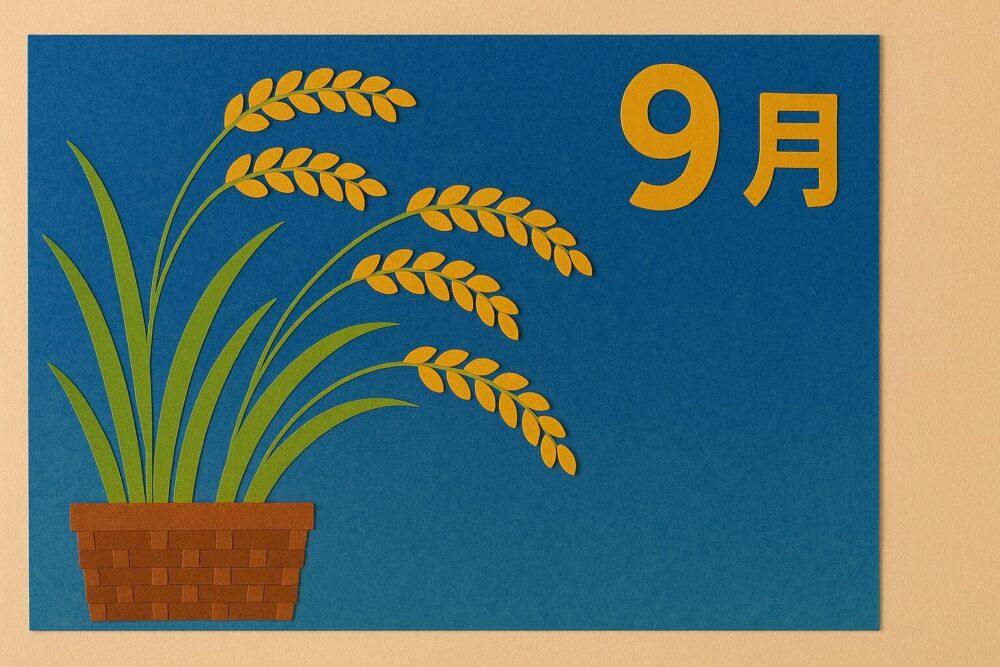
テーマ:実りの秋を感じる「稲穂」
9月といえば、実りの秋。
黄金色の稲穂が風に揺れる様子をシンプルに表現した、落ち着いた雰囲気の壁飾りです。
高齢者の方にも懐かしさを感じてもらえる作品になります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を整える
- 背景は濃い青や紺色の画用紙を使うと、黄金色の稲穂がよく映えます。
- 夜明けや夕暮れをイメージした青のグラデーション背景もおすすめ。
- 壁に貼るときは、目線より少し上の高さに設置するとバランスよく見えます。
💡ポイント:背景の一部に雲や月を加えると、秋の夜長の雰囲気も出せます。
② 稲穂の作り方
- 穂の部分は黄色または金色の画用紙で作ります。
- 一粒ずつ楕円形に切り、カーブを描くように貼ると自然な形に。
- 5〜6本ほど束ねて貼ると、ボリューム感が出て見栄えがよくなります。
- 穂先を少し左右に傾けると、風になびくように見えます。
💡難しい方には、あらかじめ稲穂の形を線で描いて下書きしておくと貼りやすいです。
③ 葉の作り方
- 葉は細長い緑色の紙を使い、長さを変えて数枚作ります。
- 貼るときは、外側に向かって広がるように配置すると自然な流れが出ます。
- 下に重ねて貼ると、立体的で奥行きのある見た目になります。
💡葉の先を少し丸めると、柔らかい印象になります。
④ 鉢(プランター)部分
- 茶色の紙で四角形を作り、レンガ風に模様を入れると本格的に見えます。
- 上のふちを濃い茶色にすると、立体感が出ます。
- 壁に貼る際は、鉢の底を水平にして、安定した構図にしましょう。
⑤ 「9月」の文字
- 黄色い文字を使うと、稲穂との統一感が出ます。
- 背景が暗いので、少し大きめで読みやすい文字にするとバランスが良いです。
- 上の右側に配置して、作品全体を引き締めます。
コスモス畑



テーマ:秋の風にゆれる「コスモス畑」
9月を代表する花「コスモス」をテーマにした壁飾りです。
やさしい色合いとシンプルな形で、見ているだけで穏やかな気持ちになれるデザインです。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景はベージュや淡いピンク色を使うと、花の色がきれいに映えます。
- 下部分に緑の画用紙を波型に切って貼ると、草むらや丘のような雰囲気になります。
- 草の高さを少しずつ変えると、遠近感が出て自然な印象に。
💡ポイント:緑の濃淡を少し混ぜるとより立体的に見えます。
② コスモスの花を作る
- 花びらはピンク・白・濃ピンク・赤紫など4色ほど用意。
- 1つの花に8枚の花びらを貼るとバランスよく見えます。
- 花びらを少し重ねて放射状に貼り、真ん中に黄色い丸を貼るとコスモスらしくなります。
- 花びらの先を少し丸めたり、少し反らせると柔らかく見えます。
💡作業が難しい方には、あらかじめ花の形に切ったパーツを配ると安心です。
③ 茎と葉っぱを作る
- 茎は細長い緑の紙を使い、長さを変えて貼るとリズムが出ます。
- 葉っぱは細長い三角形を2枚組み合わせて貼りましょう。
- たくさん貼りすぎず、花が主役になるバランスを意識します。
💡「小さいつぼみ」や「葉っぱだけの茎」を混ぜると、自然な畑のように見えます。
④ 「9月」の文字
- 見やすいように青い台紙に白文字、または黄色い背景に青文字を使うと◎。
- 作品の左上または中央上部に貼ると、全体が引き締まります。
- 季節ごとに同じサイズの数字を使うと年間通して統一感が出ます。
⑤ 配置と仕上げの工夫
- コスモスを高低差をつけて貼ると、風に揺れているように見えます。
- 同じ色が隣り合わないようにランダムに配置すると、自然な花畑に。
- 花びらの縁を薄ピンクのクレヨンでなぞると、やさしいグラデーションになります🌼。
10月の壁飾り
ハロウィン
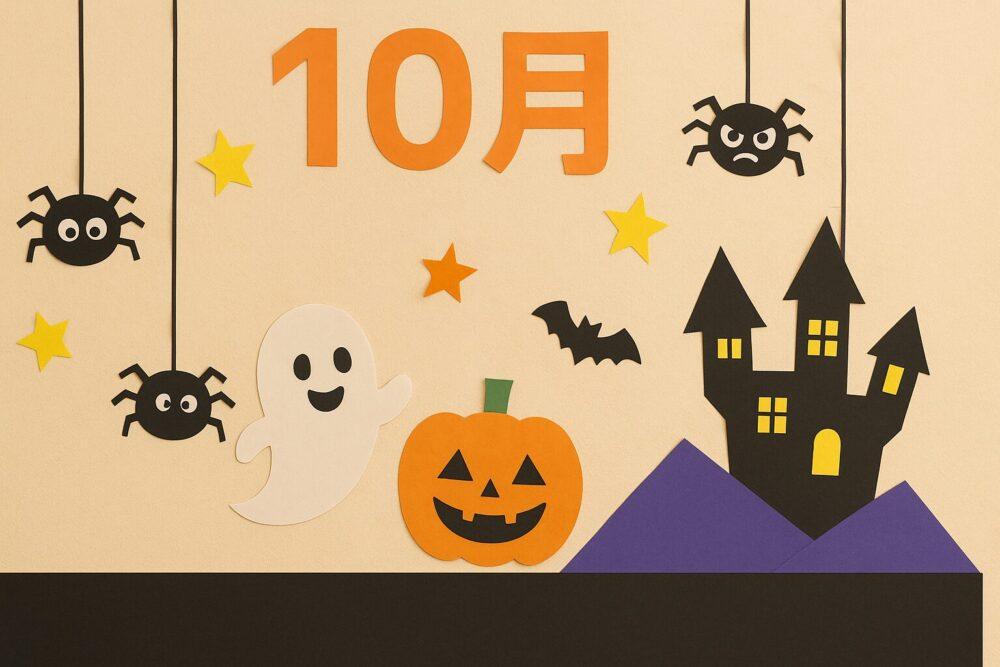
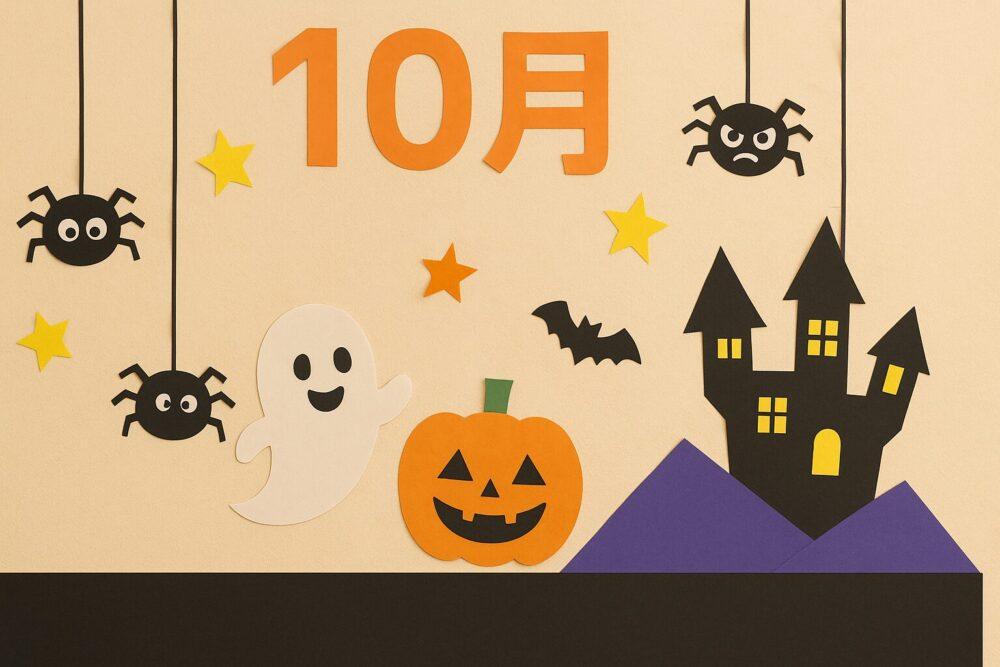
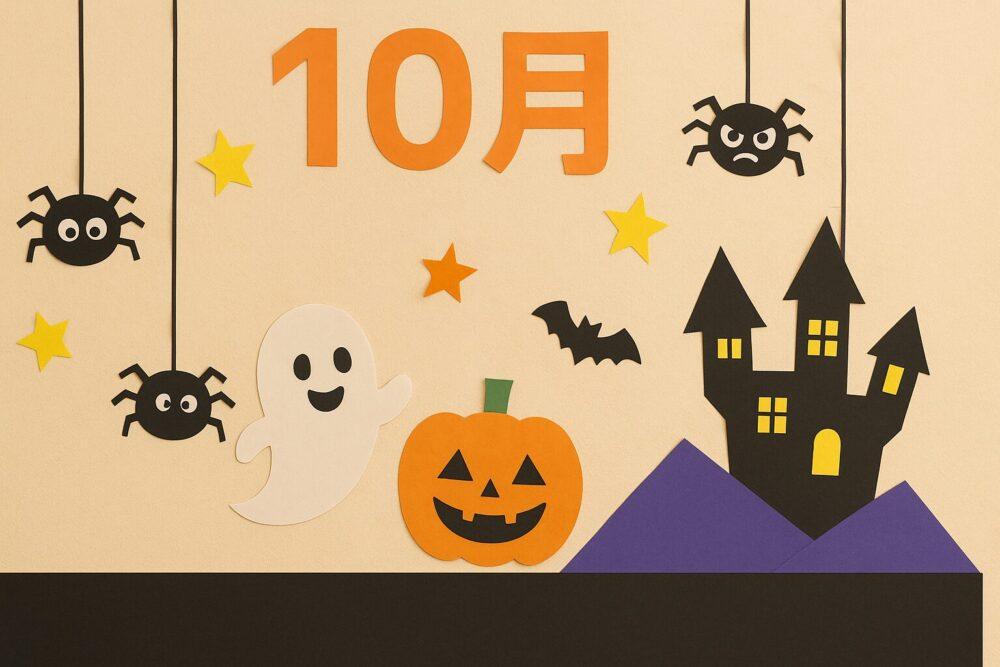
テーマ:ちょっとドキドキ「ハロウィンナイト」
10月といえばハロウィン!
おばけ・かぼちゃ・こうもり・お城・クモなど、かわいくて怖すぎないデザインにすることで、高齢者の方にも親しみやすい雰囲気になります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を整える
- 背景はベージュや薄オレンジ色など、落ち着いたトーンを使います。
- 夜の雰囲気を出したいときは、下部分に黒い紙を貼って地面に見立てると◎。
- 壁全体を暗くしすぎないことで、明るく楽しい印象になります。
💡ポイント:背景に星をちりばめると、夜空の雰囲気がよりきれいに見えます。
② メインモチーフを作る
🎃ジャック・オ・ランタン
- オレンジの画用紙を使い、丸みのある形に切るとやさしい印象になります。
- 目・鼻・口は黒の紙で三角・ギザギザなど自由にカット。
- 口角を上げるとかわいい笑顔、下げるとちょっとこわい顔になります。
👻おばけ
- 白い紙を丸みを帯びた形に切り、にっこり顔をつけます。
- 手を上げたポーズにすると、動きが出て楽しい雰囲気に。
🕷️クモ
- 黒い紙で丸を作り、足は細長く切った紙を8本貼ります。
- 糸を吊るしているように黒い毛糸や糸を上から垂らすとリアルです。
- 目をつけると表情豊かになり、かわいく仕上がります。
🦇こうもり・🏰お城
- こうもりは黒い紙で切り抜き、羽を少し折って立体的に貼ると◎。
- お城は黒い画用紙で作り、窓を黄色にすると光っているように見えます。
③ 「10月」の文字
- オレンジ色の大きな文字で季節感を出します。
- 壁の上部中央に貼ると見やすく、全体のバランスが取れます。
- 濃い背景の場合は、白や黄色の紙を下に敷いて縁取りしてもOKです。
④ 色のバランス
- オレンジ・黒・黄色・紫をメインカラーに統一。
- 同じ色が偏らないように、左右に散らして貼ると美しくまとまります。
- 星や葉っぱなど、小物でアクセントをつけると華やかです⭐。
どんぐり家族



テーマ:秋の森の仲間たち「どんぐり家族」
10月の季節をかわいく表現した作品です。
家族のように手をつないだどんぐりたちは、温かさ・つながり・安心感を感じさせるデザインです。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を準備する
- 背景は薄いベージュやクリーム色を使うと、どんぐりの茶色が映えます。
- 下部分に緑の台紙を貼って「草むら」や「野原」を表現します。
- 壁に貼るときは、やや中央より下に配置すると、安定感が出ます。
💡背景を少しカーブさせるようにカットすると、やさしい印象に。
② どんぐりを作る
- 茶色の画用紙を卵型に切り、帽子の部分を少し濃い茶色で重ねます。
- 帽子には斜めの線を描いて「網目模様」を入れるとリアルです。
- 顔のパーツ(目・口・ほっぺ)は、黒やピンクの丸シールを使うと簡単できれい。
- 表情はそれぞれ変えると、家族の個性が出て楽しい雰囲気になります。
💡目を少し斜めにしたり、口を笑顔にしたりして“性格”を出すのがコツ!
③ 手足・リボン・蝶ネクタイ
- 手足は細い茶色の紙を貼り、つないでいるポーズにします。
- リボンは赤・オレンジ・黄など、明るい色を選ぶと可愛く仕上がります。
- 男の子には蝶ネクタイを、女の子にはリボンをつけて家族らしさを演出🎀。
💡立体感を出すなら、リボンの真ん中を少し丸めて貼ると◎。
④ 「10月」の文字
- 濃い茶色の文字で統一感を持たせましょう。
- 背景の黄色台紙に貼ると、秋らしい温かみが増します。
- バランスを見ながら、上中央に大きめに配置すると見やすいです。
⑤ 落ち葉の飾り
- 赤・オレンジ・黄・茶の画用紙で、もみじ・いちょう・かえでなどを作ります。
- 大きさを変えて散らすと、動きが出て華やかに。
- どんぐりの周りを囲うように貼ると、家族を包み込むようなあたたかい雰囲気に。
収穫かご



テーマ:実りの秋を感じる「収穫かご」
10月の季節感を表す果物・野菜・きのこ・木の実を集めた温かみのある作品です。
秋らしい色をたっぷり使って、見た人の気持ちまでほっこりするように仕上げましょう。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- 背景は淡いベージュやクリーム色を使うと、秋の色合いがよく映えます。
- シンプルな背景にすることで、収穫物の色が際立ちます。
- 空間が寂しい場合は、落ち葉を舞わせるように配置すると華やかになります🍁。
💡ポイント:壁の色が暗い場合は、背景に1枚白い模造紙を貼ると明るく見えます。
② かごの作り方
- かごは茶色の画用紙を使い、楕円形にカット。
- ふちの部分を少し濃い色にして重ね貼りすると立体感が出ます。
- クレヨンで横線を入れると、木目のような温かい雰囲気になります。
③ 果物と野菜を作る
- 柿・ぶどう・さつまいも・栗・きのこなど、秋の定番を選びましょう。
- 色の組み合わせが重要!
- 柿 → オレンジ
- ぶどう → 紫
- さつまいも → 赤紫
- きのこ → 茶色とベージュ
- 栗 → 茶とこげ茶
- 丸や楕円など、やさしい形で作ると温かみのある印象になります。
💡ポイント:少し大きさを変えると、バランスがとれて自然に見えます。
④ 「10月」の文字
- 見やすくするために黒字×黄色の背景でコントラストを強くします。
- 壁の上部中央に配置して、季節がひと目で分かるように。
- 他の月とデザインを統一すると、年間を通して飾りやすくなります。
⑤ 仕上げの飾り
- 赤・黄・茶の折り紙でもみじや落ち葉を作り、全体に散らします。
- 葉っぱを1〜2枚だけ浮かせて貼ると、風に舞っているような立体感が出ます。
- 金色の折り紙を少し入れると、秋の光を感じる華やかさになります✨。
11月の壁飾り
紅葉と落ち葉
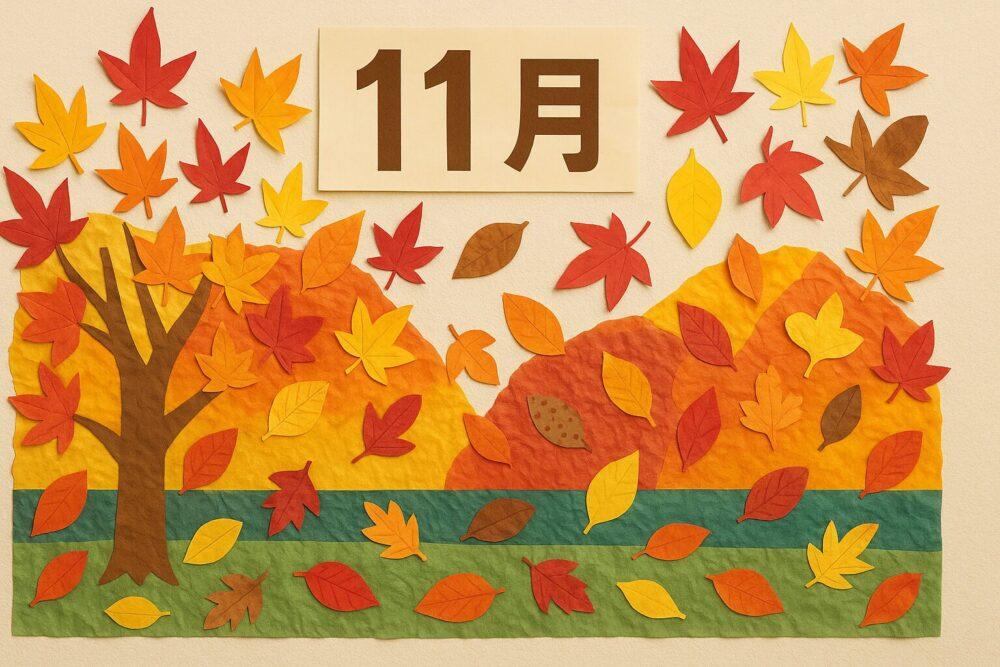
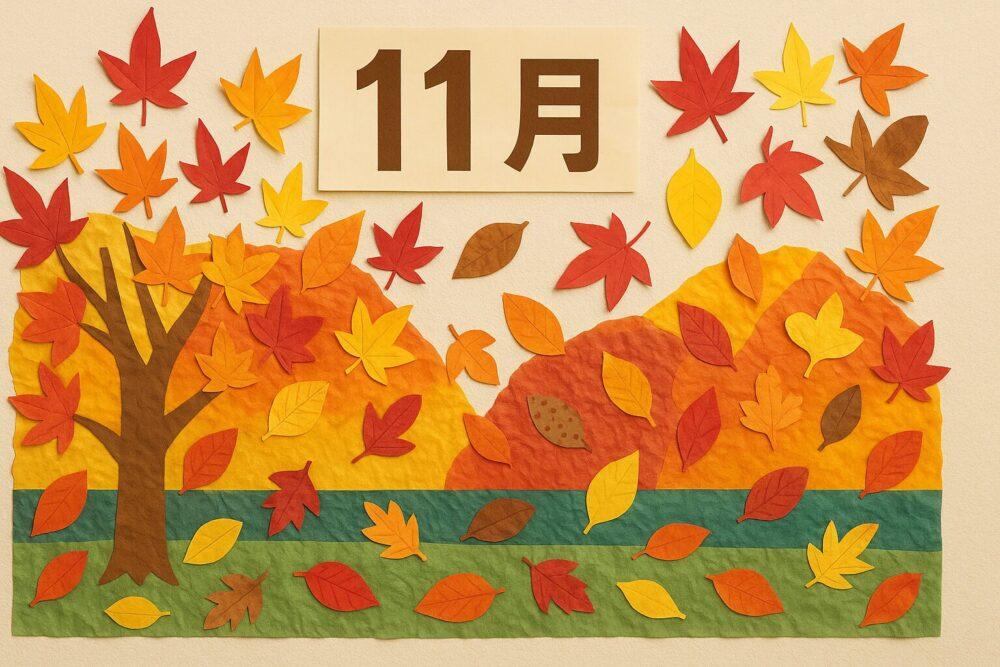
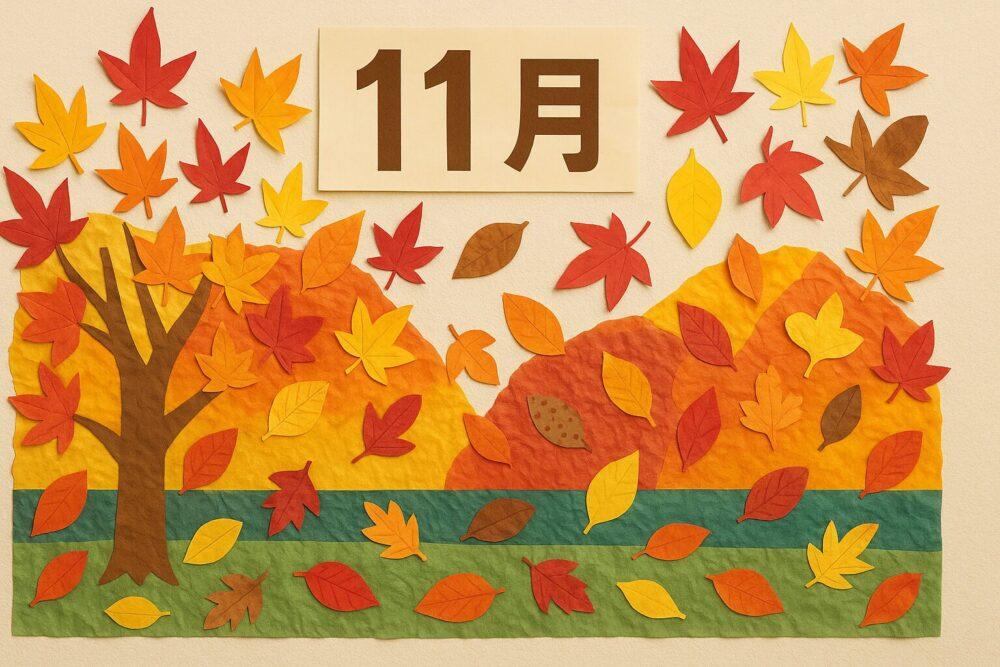
テーマ:秋の深まりを感じる「紅葉の山と落ち葉」
11月の自然をモチーフにした作品です。
暖かい色合い(赤・橙・黄・茶)を使い、見ているだけで心がほっとするような秋の景色を作ります。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景をつくる
- ベースは薄いベージュや黄みがかった色を選ぶと紅葉の色が映えます。
- 山や地面はオレンジ・黄・緑などを組み合わせて貼り、遠近感を出しましょう。
- 山の境目をゆるやかな曲線にすると自然な景色になります。
💡山の部分は和紙やちぎり紙を使うと、やわらかい質感になります。
② 木をつくる
- 幹は茶色い画用紙を使用します。まっすぐではなく、少し枝分かれさせるとリアル。
- 木の形を台紙の左か右に寄せて貼ると、バランスが取りやすいです。
- 幹にクレヨンで軽く線を入れると、木目っぽく仕上がります。
③ 葉っぱをつくる
- 紅葉・いちょう・落ち葉など、色や形を変えて数種類作るのがポイント。
- 赤・オレンジ・黄・茶の4色を中心に、少しずつ大きさを変えて切ります。
- 枚数を多めに作って、「空から舞う葉」「地面に落ちた葉」に分けて貼ると自然。
💡葉っぱをランダムに配置し、1〜2枚だけ空中に浮かせると動きが出ます。
④ 「11月」の文字
- 目立たせたいので濃い茶色で大きめに作ります。
- 背景の明るい色(ベージュなど)の上に貼ると読みやすくなります。
- 季節ごとに同じフォントで作っておくと、統一感が出て見栄えが良くなります。
⑤ 飾りの仕上げ
- 葉っぱの一部を軽くカールさせて貼ると、風に舞う感じになります。
- 全体に立体感を出すために、葉の下にスポンジテープや丸めた紙を入れて少し浮かせても◎。
- 最後に金色の折り紙を小さくちぎって散らすと、日差しのきらめきが表現できます✨。
いちょう並木



テーマ:秋の深まりを感じる「いちょう並木」
11月らしい落ち着いた黄色と茶色を使って、秋の穏やかな風景を表現します。
見た人が「ほっとする」「散歩したくなる」ような温かい雰囲気を目指しましょう。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を準備する
- 背景は水色の画用紙を使い、澄んだ秋空をイメージします。
- 雲は白い画用紙をふんわりカットして貼ると、空に奥行きが出ます。
- 背景の下半分には黄土色や薄茶色の紙を使い、道や地面を表現します。
💡ポイント:空と地面の境を波型にカットすると、自然な遠近感が出ます。
② いちょうの木を作る
- 幹:茶色い画用紙で作ります。太さを変えると遠近感が出ます。
- 葉:黄色の画用紙を使い、3〜4段に重ね貼りすると立体的になります。
- 木の高さに変化をつけると、奥行きのある「並木道」になります。
💡ポイント:葉っぱはギザギザに切らず、丸みを持たせるとやさしい印象に。
③ いちょうの葉を散らす
- 木から舞い落ちるように、ランダムに配置します。
- 上部に舞う葉、下部に落ち葉を貼ると動きのある構図になります。
- 色味を少し変えて(黄色+黄橙色など)貼ると、自然な仕上がりに。
💡おすすめ:少しカールさせて貼ると、本当に落ちているように見えます。
④ 「11月」の文字
- 太めの茶色の画用紙でカットし、上部中央に貼ります。
- 他の色より濃い色を選ぶと全体が引き締まります。
- 角張ったフォントよりも丸みのある形にすると、やわらかい印象に。
⑤ 仕上げの工夫
- いちょうの葉に黄色いフェルトを使うと、温かみが増します。
- 少し金色やオレンジの紙を混ぜると、陽の光が差しているように見えます。
- 地面の一部に落ち葉を重ねて貼ると、厚みが出て立体的です。
焼き芋屋さん



テーマ:秋の香り「やきいも屋さん」
11月の季節感を楽しめる、あたたかい色合いと親しみやすいモチーフの壁飾りです。
見た人が思わず「おいしそう」「懐かしい」と感じるような作品にしましょう。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を決める
- 背景はベージュや淡い黄色など、温かみのある色を選びます。
- どんな色の壁にもなじみやすく、秋の雰囲気を引き立てます。
- 背景が寂しいときは、紅葉や落ち葉を追加すると華やかになります🍁。
② 屋台の作り方
- 屋台本体は茶色の画用紙で作ります。木目のように線を描くとリアルになります。
- タイヤは黒の丸い紙を切って貼ります。真ん中に円を重ねると立体的に見えます。
- 屋根は赤・オレンジ・えんじ色など暖色系の折り紙を交互に並べて「のれん風」に。
→ この部分が全体のアクセントになります!
💡ポイント:屋台の角を少し丸くすると、優しい印象に仕上がります。
③ 焼きいもを作る
- 芋の皮は赤紫色の折り紙、中身は黄色の画用紙を使用します。
- 丸みを帯びた形にカットして、断面が見えるように貼るのがポイント。
- 黄色部分にオレンジクレヨンで軽く色をつけると、焼けた感じが出て◎。
💡立体感を出すには、裏に小さく丸めた紙を貼って少し浮かせるのもおすすめ。
④ 「やきいも」「11月」「あつあつ」の文字
- 太くて丸みのある文字にすると、親しみやすい印象になります。
- 「やきいも」は茶色系、「11月」は濃い茶色で統一感を出しましょう。
- 「あつあつ」の吹き出しを入れると、楽しい雰囲気が生まれます。
💡おすすめ:吹き出しを2つ作って「ほくほく」「いいにおい」などの文字も追加すると可愛いです。
⑤ 飾り(もみじ・いちょう)で彩る
- 赤・オレンジ・黄色の画用紙で作ったもみじを周囲に散らすと華やかになります。
- 枚数は奇数(3枚・5枚・7枚)にすると、自然でバランスよく見えます。
- 落ち葉の形を少しずつ変えると、動きが感じられます🍂。
12月の壁飾り
クリスマス



テーマ「楽しいクリスマス」
作り方はこちら【クリック】
材料(基本)
- 画用紙:赤・緑(濃淡)・白・黒・肌色・黄・オレンジ・青・紫
- 両面テープ+マスキングテープ(壁面保護用)/スティックのり
- ハサミ/カッター(直線は定規+カッターで時短)
- 厚紙1~2枚(サンタとツリーの“芯”用)
- 丸型パンチ(直径2.5~3cm:オーナメント・雪)※あると超時短
色と紙の選び方
- 文字・主役(サンタ・ツリー)は“濃色+無地”でくっきり。
- 雪・髭・袋は純白ではなく“オフ白”にすると温かい印象。
- ラメ粉は落ちやすいので不使用(清掃・誤飲対策)。
- 立体は「紙2~3枚重ね」まで。厚すぎると剥がれやすい。
目安サイズ(全体 幅160cm×高さ90cm想定・比率だけ真似でOK)
- 「12月」:縦15cm程度、太めゴシックで読みやすく
- サンタ:縦50~55cm(主役は“顔の大きさ”を手のひら2枚分)
- ツリー:縦70cm、段を3層(下大・中・上小)
- プレゼント:大25cm角/中20cm角/小15cm角
- 星:7~10cm(大小混ぜる)
- 雪の地面:高さ15~18cm、雲形を連結
配置のコツ(見やすさ優先)
- Zの流れで視線誘導:左上「12月」→中央サンタ→右ツリー。
- 奥行きの錯覚:プレゼントは“手前に大、奥に小”。
- 色のバランス:左(暖色多め)×右(緑多め)で左右差を出す。
- ぶら下げ装飾(リボン・ガーランド)は通路側に出っ張らせない。
作り方(パーツ別・簡単手順)
1) サンタ(芯+重ね貼りで形が崩れない)
- 芯を作る:厚紙で人型シルエット(頭~足)を一枚。
- 赤の服を芯に貼る → 裾・袖・帽子ふちの白帯を上から重ねる。
- 顔(肌色の楕円)→ 眉・目(黒丸)→ ほっぺ(薄ピンク丸)→ 鼻(小楕円)。
- 髭・口周りは“2パーツ”に分けて重ねると立体感UP。
- 手袋・ベルト・靴(黒)、バックル(黄)を大きめでくっきり。
- ポーズは両手を上げて“V”字に。手先は角を丸めて安全。
2) ツリー
- 幹(茶)→ 三角を3段(濃緑→中緑→緑)で下から重ねる。
- オーナメントは丸パンチで量産(赤・黄・緑・オレンジ)。
- 左右に均等配置+一部を“半分だけ”縁から出してリズム感。
- 最上部の大きい星(黄 10cm)で締める。
3) プレゼント
- 色の違う四角を3サイズ作る。
- リボンは太め帯(幅3cm)+蝶結びシルエットを別パーツで。
- 小箱を手前、背の高い箱を奥にして重なりを作る。
4) 星&ガーランド・リボン
- 星は5角形テンプレを使い、色を偏らせない(暖色3:寒色2くらい)。
- 緑のガーランドは“波”を大きく、垂れ角度を左右で変えると生きる。
- リボンは「本体」「影(少し濃い赤)」の2枚重ねで存在感UP。
5) 雪とサンタの袋
- 雪の地面は雲形を3~4枚つなげ“段差”を少し付ける。
- 袋はオフ白+口元に細い紐(黒or濃灰)。影用に薄グレーを半月形で。
6) 「12月」文字
- 15cm角グリッドに下書き→太ゴシックで切り出す。
- 影(同形を5mmズラし)を敷くと遠目でも読みやすい。
雪だるま



テーマ:冬の楽しみ「雪だるま作り」
子どもが雪だるまを作っている様子を通して、12月らしい季節感を表現する壁飾りです。
作り方はこちら【クリック】
作るときのポイント
① 背景を作る
- 背景は水色の画用紙を使って、冬の空を表現します。
- 白い丸い紙(パンチ穴やシールでもOK)を散らして雪を降らせるように貼ります。
- 余白があると寒々しく見えるので、全体にまんべんなく雪を配置するのがコツです。
💡ポイント:画用紙のつなぎ目は雲形や雪の形で隠すときれいです。
② 雪だるまを作る
- 白い画用紙を丸く切り、大小2つを貼り合わせて体を作ります。
- 目・鼻・ボタンは黒やオレンジの丸シールでOK。
- 帽子やマフラーを折り紙で作ると色が映え、表情の違う雪だるまにできます。
💡立体感を出すなら、帽子の端を少し浮かせて貼る。
③ 子どもの作り方
- 肌色・赤・オレンジ・黄・青などを使って元気な色合いにしましょう。
- ニット帽・手袋・マフラーなどをつけると、より冬らしくなります。
- 雪を丸めている姿を、体を少し前に傾けて貼ると「動き」が出ます。
💡笑顔の口やほっぺを描くと、優しい印象になります。
④ 「12月」の文字
- 目立たせるために赤い画用紙で大きくカット。
- 壁の上部に貼って、季節をしっかり感じられるようにします。
- 太くて丸みのある文字にすると温かい印象になります。
⑤ 飾り付けの工夫
- 雪だるまのまわりに雪の結晶を貼ると華やかになります。
- 余白には綿やフェルトを貼ると、ふんわりとした冬の質感に。
- 銀色や白のモールを飾ると光が反射してきれいです✨
雪の結晶
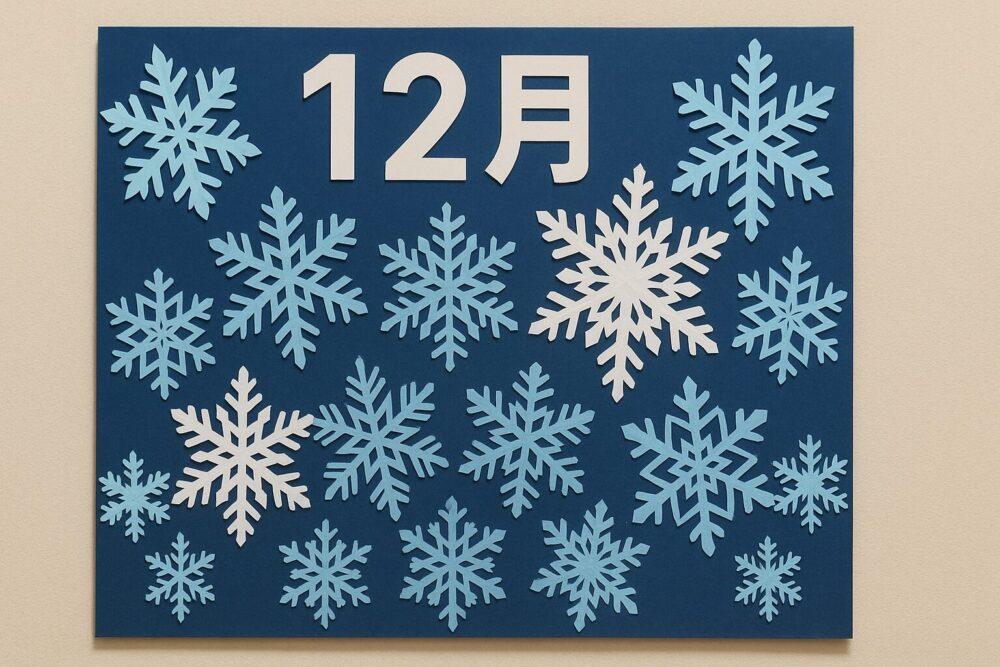
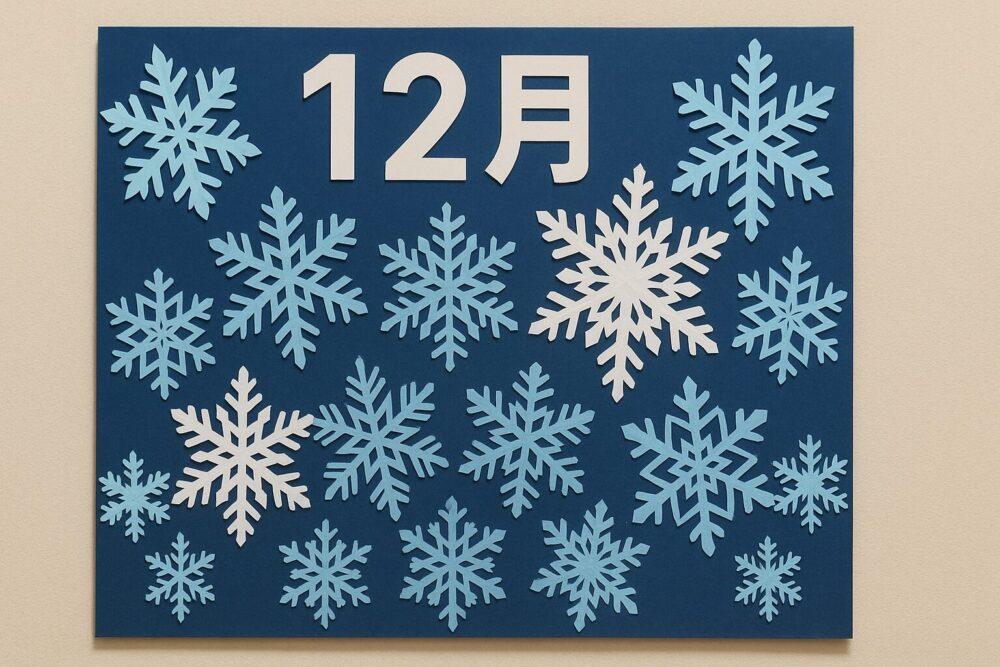
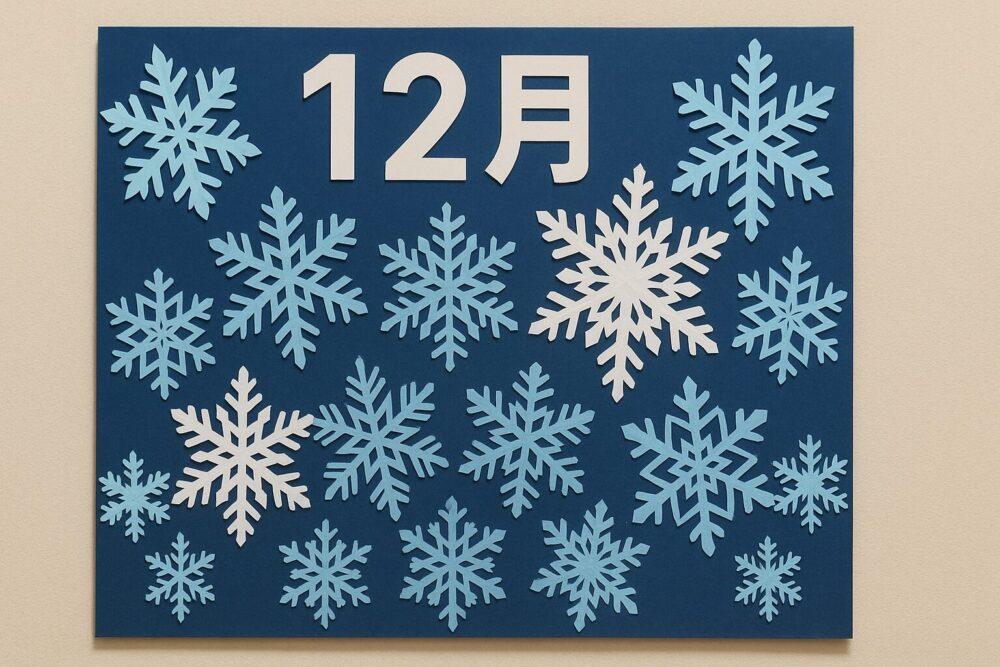
テーマ:冬の静けさと美しさを感じる「氷の結晶」
青と白を基調にして、寒さの中にある清らかさ・静けさを表現します。
作るときのポイントはこちら
作るときのポイント
① 背景の色を選ぶ
- 濃い青や紺色を使うと、雪の白がより映えて綺麗です。
- 壁全体に画用紙や模造紙を貼り、余白を残さずスッキリと見せましょう。
💡ワンポイント:ライトブルーを混ぜると、やさしい印象になります。
② 雪の結晶の作り方
- 白・水色・薄青の折り紙を使用します。
- 正方形の紙を三角に3回折って、ハサミで細かく切り込みを入れます。
- 広げると、個性豊かな結晶模様になります。
💡難しい人には、あらかじめ切り込みラインを描いておくと安心です。
③ 配置のコツ
- 大・中・小サイズをバランスよく散らすと立体感が出ます。
- 結晶が重ならないように間隔をとり、舞い散るように配置しましょう。
- 真ん中に大きな結晶を置くと、全体のバランスが整います。
💡色の濃淡をランダムに混ぜると、奥行きが出て美しくなります。
④ 「12月」の文字
- 太めのフォントで白や銀色にすると、雪景色の中でもはっきり見えます。
- 上部中央に配置して、タイトルとして目立たせましょう。
⑤ 仕上げの工夫
- ラメシートや銀のモールを少し加えると、光に反射して華やかに✨
- 背景に薄く白の丸を貼って「雪が降っている」表現もおすすめ。
- 結晶の一部を少し浮かせて貼ると、影ができて立体的に見えます。


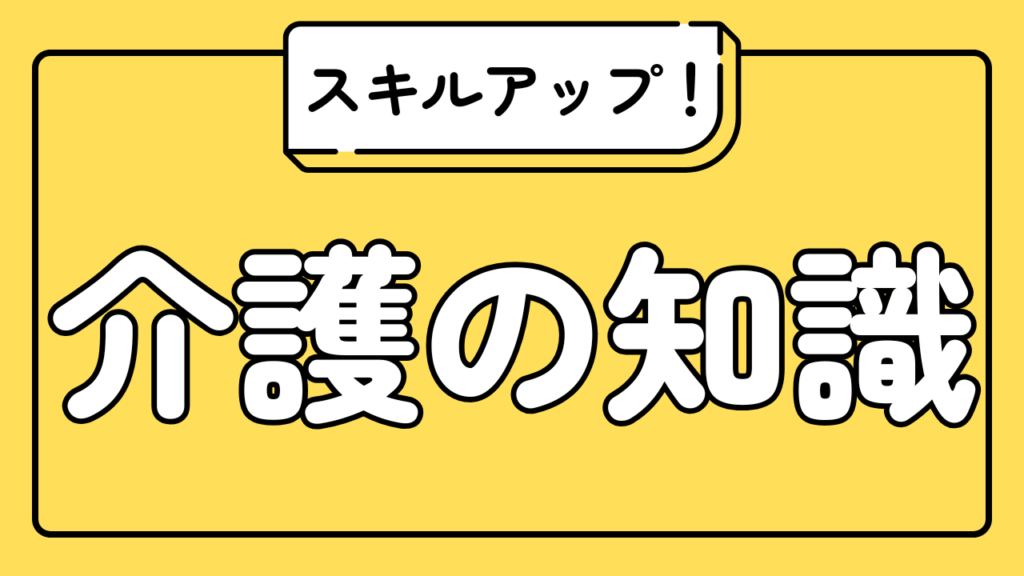




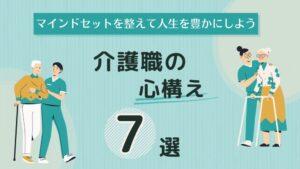
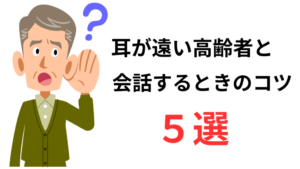



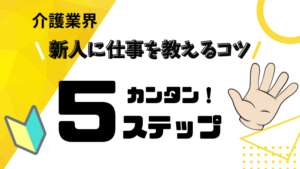


コメント