 介護士
介護士あれ、さっき〇〇さんのこと、看護師さんに伝えたはずなのに…




報告したら『なんで早く言わないの!』って怒られた…
看護師さんとの連携がむずかしいと思ったこと、
一度や二度じゃないですよね。
ぼくも15年以上この仕事をしていますが、昔はしょっちゅうでした。
一生懸命に利用者のさんのことを伝えているのに、なぜかうまく伝わらない。
むしろ、関係がギスギスしてしまう。
これって、
伝え方が下手だからとか、
相手が意地悪だから、
という単純な話じゃないんです。
実は、介護士と看護師とでは、物事を見るレンズが少しだけ違う。
じゃあ、その「違い」とは何でしょう?
介護士と看護師の視点の違いは次のとおり。
- 情報の細かさ:
ぼくたち介護士は「食事を半分残された」という生活全体の事実を見ます。
一方、看護師さんは「なぜ半分残したのか?血糖値は?既往歴は?」と、医療的な原因を探ります。
見ている情報の細かさが違うんですね。 - 優先度のズレ:
ぼくたちは、レクリエーションや入浴介助など、時間で決まっている業務の優先度が高いです。
でも看護師さんは、急変リスクや医療処置の緊急度を最優先にします。
お互いの「今、一番大事なこと」が違うんです。
この記事を読めばどうなるのか?
この記事では、介護士と看護師の「すれ違い」をなくし、今日からすぐに使える具体的な方法をまとめました。
この記事を読めば、あなたと看護師さんの連携がスムーズになります。
難しい理論は一切ありません。
必要な部分だけ拾い読みしても大丈夫です。
これまでの苦手を克服して、自信を持って働けるようになりませんか?
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー



詳しくはトップページのプロフィールに記載
【結論】看護師との連携は「型×仕組み×関係」で決まる



いきなり結論から言いますね。
介護士と看護師の連携は、個人のセンスや相性の問題ではありません。
うまくいくかどうかは、次の3つの掛け算で決まります。
「型」×「仕組み」×「関係」
これが、ぼくが15年間でたどり着いた答えです。
- 型=話し方・書き方の共通ルール
誰が伝えても同じように伝わる「話し方の順番」や「言葉の選び方」です。
これがあるだけで、解釈のズレが劇的に減ります。 - 仕組み=記録・掲示・ツールの整備
忙しい時や忘れてしまいそうな時でも、情報が自然と共有される「仕掛け」のこと。
個人の記憶力に頼らないから、ミスが起こりにくくなります。 - 関係=日常の一言と感謝で信頼貯金を作る
いざという時に「〇〇さんが言うなら、すぐ行かなきゃ!」と思ってもらえるような、日々の信頼関係です。
信頼貯金は、特別なことではなく、小さな「ありがとう」の積み重ねで作れます。
この3つを少しずつ実践してみてください。
あなたの現場の「伝わらない…」は、驚くほどなくなっていきますよ。
看護師に伝えるときのコツ



急いでいる看護師さんに、ダラダラと状況説明を始めてしまい、「で、結論はなに?」と言われた経験はありませんか?
そんなときは、次の伝え方をしてください。
SBAR(エスバー):簡潔に伝える型
医療現場で使われるSBAR(エスバー)という報告方法を、介護現場向けに超カンタンにしたものです。
結論(S):「〇〇さんのことで依頼です」
背景(B):「発熱37.8℃、昼食半分」
評価(A):「脱水ぎみ、尿量少」
依頼(R):「今診てもらえますか?必要物品ありますか?」
この順番で話すだけで相手は、
- 「何の話か」
- 「どれくらい急ぐのか」
- 「何をすればいいか」
が一瞬でわかります。
【例:申し送りで】
(S)〇〇さんの件で報告と依頼です。
(B)昨夜から37.8℃の発熱があり、昼食も半分しか召し上がれていません。
(A)少しぐったりしていて、脱水が心配です。尿の回数も減っています。
(R)ラウンドの際に、一度状態を確認してもらえますか?
【例:急変時に】
(S)△△さんが転倒しました!応援お願いします!
(B)先ほどトイレに向かう途中で、尻もちをつかれました。
(A)意識ははっきりしていますが、右足を痛がっています。
(R)すぐに来てもらえますか?バイタルセットを持ってきます。
この型を意識して、「で、何が言いたいの?」から卒業しましょう。
2. NG→OK言い換え
ついカッとなったり、焦ったりすると、言葉にトゲが混じってしまいます。
それが「感情ノイズ」
相手に嫌な印象を与え、協力的な関係を壊してしまいます。
心理カウンセラーの視点から、少しだけ言葉を変えて、スムーズな関係を作るコツをお伝えします。
- NG:「さっき言いましたよね?」 (相手を責めるニュアンス)
OK:「重ねて確認させてください。〇〇の件で合っていますか?」 (自分の確認、というスタンスに変える) - NG:「忙しいのに無理です」 (一方的な拒絶)
OK:「申し訳ありません、今は△△さんの対応中でして、10分後ならすぐに向かえます」 (できない理由と、代替案をセットで示す) - NG:「たぶん大丈夫だと思います」 (曖昧で無責任な印象)
OK:「記録では〇〇とありますが、ご本人の様子を見ると少し心配です。一緒に確認してもらえませんか?」 (事実と自分の評価を分け、相談の形にする)
ポイントは、次の3つです。
- 相手を責めない
- 事実と感情を分ける
- 相談・提案の形にする
3. 伝達ミスを防ぐ仕組み
個人の頑張りだけに頼っていると、忙しいときほどミスは起こります。
そこで、誰がやっても同じように情報が伝わる「仕組み」を作りましょう。
- 共通メモ(申し送りノートなど)
「観察項目」「特変」「依頼事項」など、書く順番や項目をフォーマット化します。
人によって書き方がバラバラだと、読む側はどこに重要な情報があるか探すのが大変です。
誰が見ても同じ順、同じ言葉で情報が追えるようにします。 - タイムライン運用
ホワイトボードや共有ノートに、時系列で出来事を書いていきます。
その際、【至急】【本日中】【情報共有】といった優先度タグを付けるのがコツ。
誰がいつ、何をすべきかが一目でわかります。 - 見える化ボード
スタッフルームの壁に、特に注意が必要な情報を一覧で貼り出します。
- 感染症情報(誰が、何の感染症で、いつまで隔離か)
- 転倒ハイリスク者(特に注意すべき時間帯や動作)
- 褥瘡(床ずれ)部位(誰の、どこに、どんな処置が必要か)
- 水分摂取目標(誰が、1日に何ml必要か)
これがあるだけで、「あの人、どうだっけ?」という確認の手間が省け、新人さんでもすぐに注意点がわかります。
4. 記録のテンプレ
記録は、あとから見た人が状況を再現できることがゴールです。
以下の順番で書くことを意識すると、
誰が読んでも分かりやすい記録になります。
- 観察(客観的な事実)
- 体温/SpO2/血圧:
- 表情/活気:
- 食事摂取量:
- 水分摂取量:
- 排泄(回数/性状):
- 歩行状態/ADL:
- 皮膚の状態:
- 変化(いつもと違う点)
- いつから:
- どれくらい:
- 頻度:
- 取った対応(介護職としてやったこと)
- (例:クーリング、水分摂取促し、体位変換、ご家族へ状況連絡など)
- 依頼・指示(看護師などへの報告)
- 誰に:
- いつ:
- どう伝えたか:
- 指示・了承の有無:
【例文1:軽い発熱】
14:00 訪室時、顔面紅潮あり検温。
体温37.6℃、SpO2 97%
活気は普段通り。
昼食は全量摂取。
ポカリスエットを100ml飲んでいただく。
14:10に〇〇看護師へ現状を報告し、
15時のラウンドで状態確認の指示あり。
【例文2:転倒後見守り】
9:30 居室にて椅子から立ち上がる際にバランスを崩し尻もち。
打撲や外傷なし。
本人「大丈夫」とのこと。
9:35 △△看護師へ報告。
訪室し状態確認、鎮痛剤使用せず様子観察の方針となる。
1時間おきに訪室し、痛みや歩行状態の変化がないか確認する。
この型に沿って書けば、
「何が書いてあるかわからない」と言われることはなくなります。
場面別「連携のコツ」とテンプレ



申し送りのコツ
ダラダラ長い申し送りは、聞く側の集中力を奪います。
30秒で終わらせる意識で、要点を3つに絞りましょう。
- 要点3つ:
①結論(一番伝えたいこと)
②リスク(注意すべきこと)
③依頼(やってほしいこと)
【テンプレ】
お疲れ様です。
申し送りします。
一番のポイントは〇〇さんの件です。
△△のリスクがあるので、□□の対応をお願いします。その他、特変は…」
関連記事はこちら
急変時(夜勤でも迷わない)
夜勤帯など、一人で判断に迷うときは焦りますよね。でも、順番さえ間違えなければ大丈夫です。
- 手順:
①まず観察3点(意識・呼吸・皮膚の色)
②次にバイタル測定、
③看護師への呼び出し
【テンプレ】
夜勤の介護士、〇〇です。
△△号室の□□さんが急変です!
(①観察したこと)
呼吸が速く、SpO2が82%です。
(②バイタル)酸素の準備をしながら、すぐに対応をお願いできますか?」
何を、どの順番で伝えるか決めておくだけで、パニックにならずに行動できます。
関連記事はこちら
褥瘡・スキンケア
「ちょっと赤い」「じゅくじゅくしてる」など、人によって表現が違うと、状態の変化が分かりません。
言葉をそろえましょう。
- 観察の言葉を統一する:
- 赤み(発赤): 指で押して消えるか、消えないか
- びらん: 皮がむけている状態
- 滲出液: 汁が出ているか、その色や量
- 痛みスケール: 本人が痛みを10段階でどれくらい訴えているか
【報告の例文】
〇〇さんの仙骨部の褥瘡についてです。
昨日までは500円玉大の『発赤』でしたが、本日確認したところ、一部『びらん』になっています。
体位変換の計画について、指示をいただけますか?
夜勤引継ぎのコツ:重要なことが抜けない5行サマリ
長い夜勤の出来事をすべて伝えようとすると、重要なことが抜けてしまいます。
要点を5行でまとめましょう。
- 最重要リスク者
(例:〇〇様、夜間不穏あり注意) - 急変の可能性
(例:△△様、微熱継続中、朝のバイタル要確認) - 看護師への依頼事項
(例:□□様の眠前の薬、残薬報告済み) - 家族への連絡事項
(例:◇◇様ご家族へ、明朝9時に看護師から連絡予定) - 未完了タスク
(例:汚物室の清掃、お願いします)
これを引継ぎノートの最初に書くだけで、日勤者はすぐに動けます。
関係づくり:小さな信頼貯金の作り方



緊急時や困難なケースでスムーズに協力してもらうには、日々の「信頼貯金」がものを言います。
これは、ごまをするのとは違います。
プロ同士として、お互いを尊重する姿勢を示すことです。
先に“合意”を取る返し方
何かを依頼されたり、指示されたりしたとき、ただ「はい、わかりました」で終わらせていませんか?
「承知しました。〇〇という方針で進めますね。その他に注意点はありますか?」
こう返すだけで、
「ちゃんと理解してくれたな」
「一緒に考えてくれているな」
という安心感を相手に与えることができます。
感謝を伝える
「ありがとうございました」だけでは、何に感謝しているか伝わりません。
「先ほどはありがとうございました。〇〇さんの件、あの判断をしてもらえたおかげで、すごく落ち着きました。本当に助かりました」
このように具体的に伝えることで、相手の自己肯定感も上がり、「またこの人のために頑張ろう」と思ってもらえます。
揉めたあとに効く“振り返り1分ミーティング”
意見がぶつかった後、気まずいままにしていませんか?
そんなときこそ、関係を良くするチャンスです。
「先ほどはすみません。少し落ち着いて考えたのですが、〇〇看護師が言っていた△△のリスクは、私には見えていませんでした。今後は□□の視点も持つようにします。ご指摘ありがとうございました」
上記のように、自分に足りなかった視点を認め、感謝を伝えることで関係が良くなります。
まさに「雨降って地固まる」
つまり、もめごとや失敗などの後、かえって物事が落ち着き、前よりもよい状態になるわけです。
【事例3選】失敗→改善のビフォーアフター



ケース1:発熱の伝達漏れ
- Before: 介護士「〇〇さん、なんか熱っぽいですよー」→ 看護師「ふーん、あとで見るわ」(緊急度が伝わらず、対応が遅れる)
- After: 介護士「〇〇さんの件で報告です。14時に38.2℃の発熱、悪寒を訴えています。ぐったりしているので、至急診てもらえませんか?」→ 看護師「わかった、すぐ行く!」
- 仕組み改善: 「38.0℃以上の発熱は、SBAR形式で即時報告」というルールを徹底した。
ケース2:褥瘡処置の認識ズレ
- Before: 介護士A「お尻が赤いです」→ 介護士B「まあ、いつものことじゃない?」→ 看護師「なんで悪化するまで報告しないの!」
- After: 介護士「〇〇さんの仙骨部、昨日まではなかった5cm大の発赤あり。指で押しても消えません。看護師さんに報告します」
- 仕組み改善: 褥瘡のステージがわかる写真と、「観察の言葉」を一覧にして脱衣所に掲示した。
ケース3:夜間転倒の予兆見逃し
- Before: 夜勤引継ぎ「〇〇さん、昨日よく寝れてなかったみたいです」→ 日勤「そうなんだ」(具体的なリスクとして伝わらず、日中の見守りが手薄に)
- After: 「最重要リスク:〇〇様。夜間2回トイレでふらつきあり。センサーマット設置。日中も歩行の見守り強化をお願いします」
- 仕組み改善: 夜勤引継ぎノートの最初に「5行サマリ」を書く欄を作成した。
連携チェックリスト



日々の業務の前に、頭の中でチェックしてみてください。
【介護士と看護師の連携チェックリスト】
話し方
- 報告は「結論」から伝えているか?(SBAR)
- 自分の評価(~と思う)と事実を分けているか?
- 依頼(~してほしい)は具体的で明確か?
- NGワードをOKワードに言い換えようと意識したか?
記録
- 5W1H(いつ/誰が/どこで/何を/なぜ/どうした)がわかるか?
- 看護師への報告や指示の内容まで書いているか?
- テンプレートの順番(観察→変化→対応→依頼)で書けているか?
場面別の“抜け”確認
- 申し送り: 要点3つ(結論/リスク/依頼)に絞ったか?
- 急変時: 観察→バイタル→報告の順番を守れているか?
- 服薬: ダブルチェックや残薬の報告を徹底したか?
- スキンケア: 統一された言葉で状態を表現したか?
- 夜勤引継ぎ: 5行サマリでリスクを伝えたか?
関係づくり
- 今日、誰かに具体的な感謝を伝えたか?
- 指示を受けたとき「〇〇で進めます。他に注意点は?」と返したか?
- 意見がぶつかった後、振り返りをしようと試みたか?
よくある反論に対する答え



「理想はわかるけど、うちの職場では…」と感じた方もいるかもしれません。
よくある反論にお答えします。
- 「忙しくて、いちいち言い換えている余裕がない」
→ 答え: 実は逆です。「型」に当てはめることで、何を言うか悩む時間がなくなり、報告はむしろ短くなります。
「10秒要約」は、そのための時短テクニックです。 - 「人によって基準が違うから、結局伝わらない」
→ 答え: だからこそ、「共通チェック表」や「言葉の統一」が必要です。
個人の感覚のズレを、共通の物差しで圧縮していくイメージ。
まずは褥瘡の観察用語だけでもそろえてみませんか? - 「どうしても言いにくい、苦手な相手がいる」
→ 答え: 苦手な相手にこそ、「先に合意を取るフレーズ(〇〇で進めますが、他に注意点は?)」が効きます。
相手の意見を尊重する姿勢を見せつつ、会話の主導権を握れます。
また、報告は「事実」に限定しましょう。
「〇〇さんが痛いと言っています」という事実に、自分の感情や推測は混ぜないのがコツです。
よくある質問(Q&A)
- 忙しくてSBAR(エスバー)なんて、いちいち言っていられません。
-
最初は難しく感じるかもしれませんが、心の中で「結論は?」「理由は?」「どう思う?」「で、お願いは?」と4つを唱えるだけでも大丈夫です。
実は、要点を整理するので報告時間は短くなります。慣れれば10秒で終わりますよ。 - どうしても言い方がきつい、高圧的な看護師さんがいて萎縮してしまいます。
-
よくわかります。そういう相手にこそ、「型」があなたを守ります。
感情的にならず、淡々と事実(バイタル数値など)をSBARの型で報告することに徹しましょう。
そして、「この方針で進めますが、他に指示はありますか?」と先に合意を取るフレーズで、相手の土俵に乗らず、こちらのペースで会話を終える練習をしてみてください - 自分たちの連携がうまくいっているか、どうやって測ればいいですか?
-
いくつかの指標があります。たとえば、「申し送りの平均時間が短くなった」「転倒や誤薬などのインシデント件数が減った」「夜勤中の看護師への緊急コール回数が減った」などです。
また、職員向けに「他職種との連携のしやすさ」について無記名のミニアンケートを取ってみるのも、客観的な指標になりますよ。
まとめ
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
介護士と看護師の連携は、永遠のテーマのようにも思えます。
でも、今日お伝えした「型」「仕組み」「関係」という3つを意識すれば、必ず改善できます。
結論
もう一度、大事なことを繰り返しますね。
介護士と看護師の連携は、
センスや相性ではなく、「型」と「仕組み」で成り立っています。
今日からぜひ、
の3つだけでも意識してみてください。
これだけで、あなたの職場の伝達漏れと、人間関係のギスギスは確実に減っていきます。
伝え方のおさらい
- 依頼: 「〇〇看護師、至急の依頼です。△△さんのSpO2が89%で、息が荒いです。すぐに対応お願いできますか?」
- 共有: 「□□さんの水分目標1,000mlに対し、本日15時時点で600mlです。夕食後に経口補水ゼリーで200ml補う計画です。他に注意点はありますか?」
- 感謝: 「先ほどの〇〇さんの対応、ありがとうございました。適切な対応のおかげで、ご家族も安心されていました。本当に助かりました」
- 介護士:利用者さんの「暮らし」を支える視点
- 看護師:利用者さんの「命」を守る医療の視点
どちらが偉いわけでもなく、どちらも不可欠です。
お互いの専門性を最大限に活かすための「共通言語」が連携のコツ。
この記事が、あなたの助けになれば幸いです。
頑張るあなたを、心から応援しています。
では、また。
こちらも読まれています



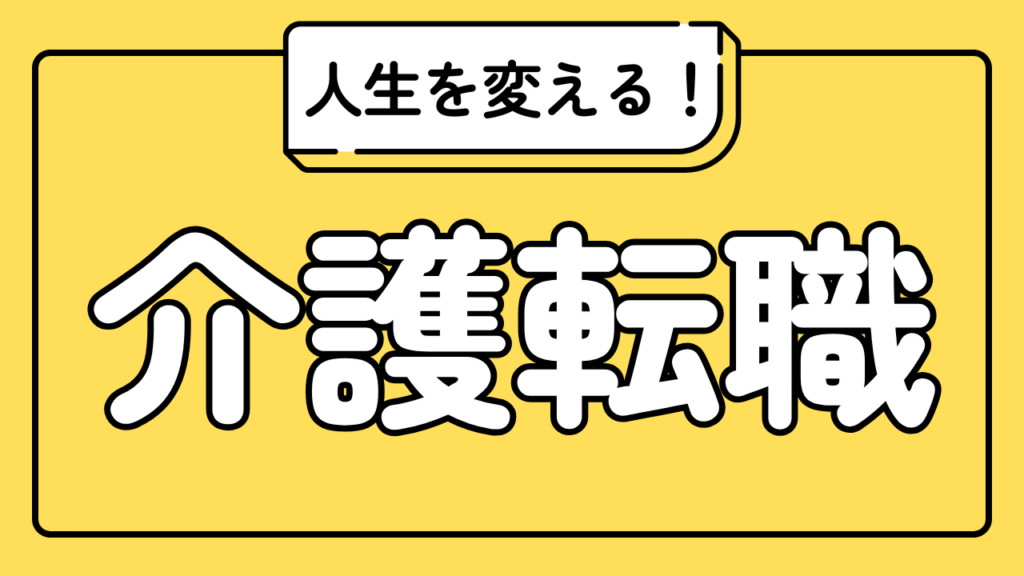


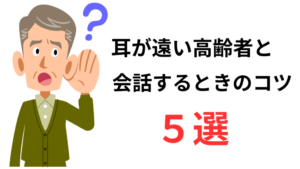




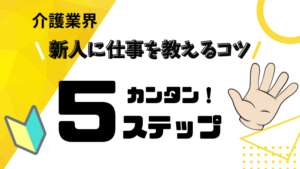

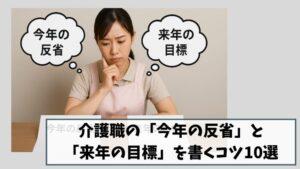

コメント