 介護士
介護士ちゃんと伝えたつもりなのに……




あの情報、聞きそびれた……
こんな経験、誰にでもありますよね。
忙しい現場では、申し送りのわずかなミスが、利用者さんの不利益や大きな事故につながりかねません。
この記事では、ぼくが長年の経験でたどり着いた、誰でも・すぐに・確実に情報共有できる申し送りの「型」を、余すところなくお伝えします。
この記事を読めば、あなたの申し送りが、劇的に変わります。
さっそく見ていきましょう。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY



詳しくはトップページのプロフィールに記載
【結論】情報漏れゼロの申し送りは「SBAR+5W1H」で誰でも再現できる



結論から言います。
相手に伝わる申し送りは、医療・看護の現場で生まれた報告フレームワーク「SBAR(エスバー)」に、ビジネスの基本「5W1H」を組み合わせることで、誰でも実現できます。
「また新しい横文字か…」と身構える必要はありません。
一度この「型」を覚えてしまえば、驚くほど思考が整理され、伝えたいことがスムーズに言葉になります。
情報漏れや伝達ミスは、面白いようにゼロになりますよ。
現場で即使える!申し送り成功のコツ5選



まずは、今日からすぐに使える具体的なテクニックをご紹介します。
SBARフレームで要点を整理する
SBAR(エスバー)とは、Situation(状況)、Background(背景)、Assessment(評価)、Recommendation(提案)の頭文字を取った報告の型です。
- S(状況): 「誰が」「どうした」という、今起きている事実。
- 例:「夜勤帯の佐藤さんについて報告します。2時に訪室した際、38.5度の発熱がありました」
- B(背景): 状況を理解するために必要な既往歴や普段の様子。
- 例:「佐藤さんは3日前の受診で風邪気味と診断されています。普段の平熱は36.5度です」
- A(評価): 観察結果から、専門職としてどう判断したか。
- 例:「顔色が悪く、発汗も見られます。意識は清明ですが、軽度の脱水が疑われます」
- R(提案): 次の勤務者にしてほしいこと、具体的な依頼。
- 例:「日勤帯でも1時間おきの検温と、経口補水液での水分補給をお願いします。看護師にも報告済みです」
この順番で話すだけで、聞き手は状況をスムーズに理解できます。
5W1Hで抜け漏れを防ぐ
SBARの各項目を、さらに「5W1H」でチェックすると、情報の抜け漏れが防げます。
- When: いつ(時間)
- Where: どこで
- Who: 誰が
- What: 何を
- Why: なぜ
- How: どのように
「佐藤さんが (Who)、2時に (When)、居室で (Where)…」のように、頭の中でパズルのピースを埋める感覚で情報を整理できます。
観察→解釈→指示の順で並べる
申し送りでは、「事実」と「意見」を分けることが鉄則です。
- 観察(事実): 「〇〇さんが食堂でAさんに怒鳴っていた」
- 解釈(意見): 「(おそらく、席のことでトラブルになったのだと思う)」
- 指示(依頼): 「日中、お二人の席を少し離して様子を見てください」
「〇〇さんがAさんとトラブっていた」と解釈から話すと、事実が曖昧になります。
まずは誰が見ても同じ客観的な事実(観察)から伝えましょう。
ICTツール(LINE WORKS/Teams)で“非同期共有”
口頭での申し送りは、言った・言わない問題が起きがちです。
可能であれば、LINE WORKSやMicrosoft Teamsのようなビジネスチャットツールを導入し、テキストで記録を残しましょう。
これなら、休憩中や出勤前など、各自のタイミングで情報を確認できる「非同期共有」が可能です。写真や動画も共有できるため、褥瘡の状態変化などを正確に伝えられます。
利用者視点・尊厳キーワードを必ず入れる
最後に、これが一番大切かもしれません。
申し送りは、利用者さんという「一人の人間」に関する情報のバトンリレーです。業務報告で終わらせず、その人らしさや尊厳に触れる一言を加えましょう。
「佐藤さん、熱で辛そうでしたが、『迷惑かけてごめんね』と、ぼくを気遣ってくださいました。」
この一言があるだけで、次のスタッフは「佐藤さんは、しんどい時も人に優しくできる素敵な方なんだな。しっかりケアしてあげよう」と、温かい気持ちでケアに入れます。
尊厳に触れる一言が、介護の質を高める鍵となるのです。
こちらも読まれています



【シーン別例文集】そのまま使えるテンプレート15選
ここでは、SBARを使って作成したシーン別の申し送り例文を5つご紹介します。
1. 体調変化/バイタル異常時
- S: 鈴木様、14時のバイタル測定で血圧が180/100と高値でした。
- B: 普段は140/80前後です。降圧剤は朝食後に服用済みです。
- A: ご本人に頭痛やめまい等の自覚症状はありませんが、やや顔が赤らんでいます。
- R: 16時にもう一度測定し、看護師に報告してください。臥床して静かに過ごせるよう声かけをお願いします。
2. 排泄介助トラブル発生時
- S: 山田様、10時のトイレ介助時、リハビリパンツ内に多量の軟便が見られました。
- B: 3日前から便秘で、昨夜下剤を服用しています。
- A: 臀部に軽度の発赤がありましたが、表皮剥離はありません。ご本人は「お腹がすっきりした」と話されています。
- R: 皮膚トラブル予防のため、次の排泄時も清拭と軟膏塗布を丁寧にお願いします。水分摂取も促してください。
3. 認知症BPSDの行動変化
- S: 高橋様が、15時頃から「家に帰る」と落ち着かないご様子です。
- B: 今日はご家族の面会がない日で、レクリエーションにも参加されませんでした。
- A: 強い不安感からくる行動と思われます。無理な制止は逆効果と判断しました。
- R: まずはお話を聞いて共感し、お茶をお出しするなどして気分転換を図ってみてください。状況が変わらなければ、リーダーに相談してください。
4. 家族対応・苦情発生時
- S: 中村様のご長男から、「父の衣類が汚れていることが多い」とご意見がありました。
- B: 中村様は食事の際にこぼされることが多く、エプロンを嫌がられることがあります。
- A: 私たちの配慮が不足していた点をお詫びし、今後の対策(食後の着替え確認、お好みの柄のエプロンを探す等)を検討するとお伝えしました。
- R: 全員で中村様の食事介助後の衣類チェックを徹底しましょう。また、良さそうなエプロンがあれば情報共有をお願いします。
5. 緊急搬送/看取り期
- S: 伊藤様、20時に呼吸困難を訴えられ、救急搬送となりました。
- B: 看取り期の方で、ご家族とは延命治療は行わない方針を確認済みでした。
- A: SPO2が80%台まで低下し、意識レベルも低下したため、嘱託医に連絡し指示を仰ぎ、救急要請と判断しました。
- R: 搬送先の病院名と連絡先はホワイトボードに記載済みです。ご家族へは看護師から連絡済みですが、夜間帯に状況変化の連絡が入る可能性があります。
6. 転倒・転落発生時
- S(状況): 10時半頃、木村様がリビングで椅子から立ち上がる際に転倒されました。
- B(背景): 木村様は普段から歩行器を使用されていますが、その時は側に置いてある新聞を取ろうと、歩行器を使わずに立ち上がろうとされたようです。
- A(評価): 看護師がすぐに状態を確認しました。外傷や痛みの訴えはなく、バイタルも安定しています。意識も清明です。ただし、念のため経過観察が必要です。
- R(提案): 今後24時間は、1時間ごとに意識状態や痛みの有無を確認してください。立ち上がりの際は、必ずナースコールを押していただくよう、ご本人に再度お伝えしました。日勤帯でも声かけの徹底をお願いします。
7. 食事・水分摂取量の変化
- S(状況): 佐々木様の昼食ですが、主食・副菜ともに全粥を2口召し上がったのみでした。
- B(背景): 3日前から食欲不振が続いています。今朝の水分摂取量も300mlと、目標の半分以下です。
- A(評価): 義歯の不具合や口腔内の痛みは訴えられていません。ご本人からは「なんとなく、食欲がわかない」とのお話がありました。軽度の脱水や体調不良の前兆かもしれません。
- R(提案): 午後のおやつ時に、お好きなゼリーやプリンを提供して、少しでも栄養が摂れるか試してみてください。水分摂取も、お茶だけでなくイオン飲料なども提案し、こまめに促してください。摂取量は必ず記録をお願いします。
8. 褥瘡の発見・処置
- S(状況): 午後の体位交換の際、渡辺様の仙骨部に直径2cmの発赤を発見しました。
- B(背景): 渡辺様は一日中ベッドで過ごされることが多く、褥瘡発生のリスクが高い方です。
- A(評価): 発赤のみで、皮膚の損傷や水疱はありません。ステージⅠの褥瘡と判断し、看護師に報告しました。
- R(提案): 看護師の指示で、保護フィルムを貼付済みです。体圧分散マットレスの圧設定も再調整しました。2時間ごとの体位交換を徹底し、特に仙骨部が圧迫されないよう注意してください。
9. 入浴拒否への対応
- S(状況): 本日入浴日だった加藤様ですが、「今日は入りたくない」と強い拒否がありました。
- B(背景): 加藤様は、特に寒い日や気分が乗らない時に入浴を拒否される傾向があります。
- A(評価): 無理強いはせず、ご本人の意思を尊重しました。代わりに、温かいタオルで全身の清拭を行い、更衣を済ませています。
- R(提案): 清拭の際、ご本人は「これなら気持ちいいね」と仰っていました。次の入浴日には、脱衣所を十分に温めておく、好きな音楽をかけるなどの環境調整を試してみてください。まずは足湯から誘ってみるのも良いかもしれません。
10. レクリエーションでの様子
- S(状況): 本日の午後の風船バレーで、普段はあまり参加されない小林様が、笑顔で参加されていました。
- B(背景): 小林様は、お孫さんがバレーボールをやっていると以前お話しされていました。
- A(評価): 風船バレーが、お孫さんの記憶と結びつき、楽しい気持ちになられたのかもしれません。周りの方とも自然に会話されていました。
- R(提案): 今後のレクでも、小林様が興味を持てそうな活動(ボールを使うものなど)を企画に取り入れてみてください。活動後のティータイムなどで「お孫さんのバレー、今度お話聞かせてくださいね」と声をかけると、良いコミュニケーションに繋がるかもしれません。
11. 他職種からの伝達事項
- S(状況): リハビリの理学療法士さんから、石井様に関する伝達事項です。
- B(背景): 石井様は現在、屋内歩行の安定化を目指してリハビリ中です。
- A(評価): 「最近、居室内での移動時に少しふらつきが見られるため、ポータブルトイレの使用も検討してはどうか」とのことでした。
- R(提案): 夜間帯だけでもポータブルトイレを設置し、ご本人の意向を確認してみてください。日中のトイレ誘導も、これまで以上に丁寧にお願いします。検討結果を、次回のカンファレンスで理学療法士さんにフィードバックしましょう。
12. 物品破損・紛失の報告
- S(状況): 斉藤様が使用されているテレビのリモコンが見当たらなくなっています。
- B(背景): 15時頃、ご本人から「リモコンがない」と申し出がありました。ご本人と一緒にベッド周りや棚などを探しましたが、見つかりませんでした。
- A(評価): 誤って他の利用者様の居室に持ち込まれたか、リネン類に紛れてしまった可能性があります。
- R(提案): 各スタッフ、訪室の際に気にかけて探してみてください。また、洗濯室のリネン類の中も確認をお願いします。見つからない場合は、ご家族に連絡し、対応を相談する必要があります。
13. ご家族からの差し入れ
- S(状況): 本日面会に来られた、近藤様のご家族から、手作りの煮物の差し入れがありました。
- B(背景): 近藤様は嚥下機能にやや低下が見られ、食事は刻み食を提供しています。
- A(評価): 差し入れの煮物は、具材が大きく、近藤様がそのまま召し上がるにはリスクが高いと判断しました。
- R(提案): ご家族には感謝をお伝えした上で、嚥下状態についてご説明し、厨房で細かく刻んでから提供させていただく旨をご了承いただきました。夕食時に提供しますので、食事介助の際は誤嚥に十分注意してください。
14. 利用者同士のトラブル
- S(状況): 食堂で、A様とB様がテレビのチャンネルのことで口論になっていました。
- B(背景): A様は時代劇を、B様は野球中継を見たかったようです。お二人とも、ご自身の希望が通らないと大声を出されることがあります。
- A(評価): すぐに間に入り、まずはお互いの気持ちをお聞きしました。今回は、共有スペースのため、ニュース番組に切り替えることで一旦落ち着いていただきました。
- R(提案): お二人が同じ時間帯に食堂で過ごされる際は、少し距離を置いた席にご案内するなどの配慮をお願いします。また、テレビ以外の楽しみ(新聞や雑誌など)をそれぞれに提案してみるのも良い方法です。
15. 見守り強化の依頼
- S(状況): 新しく入所された吉田様について、見守りの強化をお願いします。
- B(背景): 吉田様は環境の変化にまだ慣れておらず、夜間に落ち着きなく歩き回ることがあります。認知症の診断も受けています。
- A(評価): ご自身の居室が分からなくなることがあり、転倒や他の居室への立ち入りのリスクが高い状態です。
- R(提案): 夜間は特に、30分に一度は訪室し、お声がけをしてください。ベッドの足元にセンサーマットを設置済みです。日中も、フロアを移動される際は、職員が付き添うようにしてください。
良い例・悪い例で比較!NGワード&改善ポイント



申し送りの質がどう変わるのか、ビフォーアフターで見てみましょう。
【ビフォー】悪い申し送り
- 「田中さん、なんか調子悪そうでした。熱もちょっと高くて。後よろしくです。」
【アフター】良い申し送り
- S(状況): 田中さん、14時に37.8度の発熱がありました。
- B(背景): 昨夜から少し咳が出ていました。平熱は36.6度です。
- A(評価): 若干の倦怠感を訴えていますが、食事は半量摂取。活気は普段よりありません。
- R(提案): 水分補給を促しつつ、16時に再検温をお願いします。38度を超えるようなら看護師に報告してください。
NGワードと改善ポイント
- NG:「なんか」「〜みたい」「〜っぽい」 → 改善: 具体的な観察事実(顔色が赤い、咳込んでいる等)を伝える。
- NG:「ちょっと」「少し」 → 改善: 数値で示す(熱が37.8度、食事を半量摂取等)。
- NG:「よろしくです」 → 改善: 具体的に何をしてほしいのか(再検温、報告の基準等)を明確に伝える。
申し送りが介護の質を左右する3つの理由



なぜ、ぼくがここまで「申し送り」にこだわるのか。
それは、申し送りの質が、そのまま介護の質、ひいては利用者さんの生活の質に直結するからです。
ヒヤリハットの約7割が情報共有ミスから起こる
ドキッとするデータがあります。
医療現場のヒヤリハットや事故事例を分析すると、その原因の多くがコミュニケーションエラー、つまり「言ったはず」「聞いていない」といった情報共有のミスに起因しているのです。
米国 (Joint Commission)の調査では、実に7割近くがこれに該当するとも言われています。引用元:Sentinel Events Increased in 2022, Fall Reports Up Sharply
申し送りは、単なる業務報告ではありません。
利用者さんの命と安全を守るための、重要なリスクマネジメントなんです。
介護保険法の運営基準が求める情報伝達義務
実は、適切な情報伝達は、法律でも定められた私たちの「義務」です。
たとえば、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の第38条には、サービス提供の記録について定められており、その情報を職員間で共有し、一貫したケアを提供することが求められています。
(記録の整備)第三十八条 2 指定訪問介護事業者は、(中略)サービス提供の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
これは「記録を残せ」というだけでなく、「記録を元に、質の高いケアを継続的に提供せよ」というメッセージです。申し送りは、この法的義務を果たすための根幹業務と言えます。
IC(インフォームド・コンセント)と家族クレーム削減のエビデンス
心理カウンセラーの視点から見ても、申し送りは重要です。
適切な情報共有は、チーム内での「IC(インフォームド・コンセント/説明と同意)」を円滑にします。
「田中さん、昨夜から微熱があって。今日の入浴は見送った方が良いと判断しました」 この申し送り一つで、チーム全員が「なぜ田中さんは今日お風呂に入らないのか」を理解し、統一した対応ができます。
これができていないと、スタッフごとに言うことが違い、利用者さんやご家族は「誰を信じたらいいの?」と混乱し、不信感を抱きます。
家族からのクレームの多くは、小さな連携ミスが積み重なって生まれるのです。丁寧な申し送りは、結果的に私たち介護職自身を守ることにも繋がります。
【根拠】厚労省調査と事故事例で見る「申し送りミス」のリスク



言葉だけでは、リスクの大きさは伝わりにくいかもしれません。 厚生労働省が公表している介護事故の報告書を見ると、情報連携の不備が招いた悲しい事例が数多く報告されています。
【実際の事故事例(要約)】
- 事例: アレルギー情報(そば)の申し送りが、調理担当と食事介助担当の間で途切れ、アナフィラキシーショックが発生。救急搬送に至る。
- 原因: 口頭での申し送りに頼り、記録での確認を怠った。担当者間の連携不足。
このような事例は、決して他人事ではありません。 「忙しかったから」「知っていると思ったから」という些細な油断が、取り返しのつかない事態を引き起こすのです。
より詳しいデータや報告書は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
一次情報に触れることで、リスクへの意識がさらに高まるでしょう。
申し送りでよくある質問(Q&A)
最後に、現場でよく聞かれる質問にお答えします。
- 夜勤→日勤の引継ぎを3分で済ませる方法は?
-
事前の準備が9割です。勤務中にSBARの型を意識してメモを取っておき、引継ぎ時はそのメモを読むだけにします。「えーっと…」と考える時間をなくすのがコツです。特に報告事項がない利用者さんについては「特変なし」で済ませ、報告すべき事柄に集中しましょう。
- 新人が長文になりがち…どう指導する?
-
まずは一生懸命伝えようとしている姿勢を褒めてあげてください。その上で、「SBARの型で話してみようか」「この中で、次の人が一番知りたい『結論』と『やってほしいこと』はどれかな?」と、情報の優先順位付けを一緒に練習してあげるのが効果的です。事実と感想を分けて話す練習も有効です。
- 口頭と記録、どちらを優先すべき?
-
両方重要ですが、役割が違います。記録は「証拠・事実」として残すもの、口頭は「ニュアンスや温度感」を補足するものと考えてください。基本は記録を正とし、口頭では記録だけでは伝わらない表情や声のトーンなどを補足説明するのが理想です。緊急時は、まず口頭で伝え、後から速やかに記録しましょう。
- 個人情報保護はどこまで?
-
申し送りで話す内容は、あくまで「ケアに必要な情報」に限定されます。ケアに関係のないプライベートな情報(家族の職業や経済状況など)を、興味本位で共有するのはNGです。また、申し送りは必ず関係者のみがいる空間で行い、外部に情報が漏れないよう細心の注意を払いましょう。
まとめ
申し送りは、単なる作業ではありません。
利用者さんの情報を、想いと共に次の仲間へつなぐバトンリレーです。
今回ご紹介した「SBAR+5W1H」という型は、あなたの思考を整理し、伝えたいことを的確に言語化する最強のツールになります。
そして、「利用者さん視点」というスパイスを加えることで、あなたの申し送りは、ただの情報伝達から、温かい心のこもったコミュニケーションへと進化します。
明日からの申し送りが、あなたにとっても、チームの仲間にとっても、そして何より利用者さんにとっても、より良いものになることを、心から願っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
では、また。

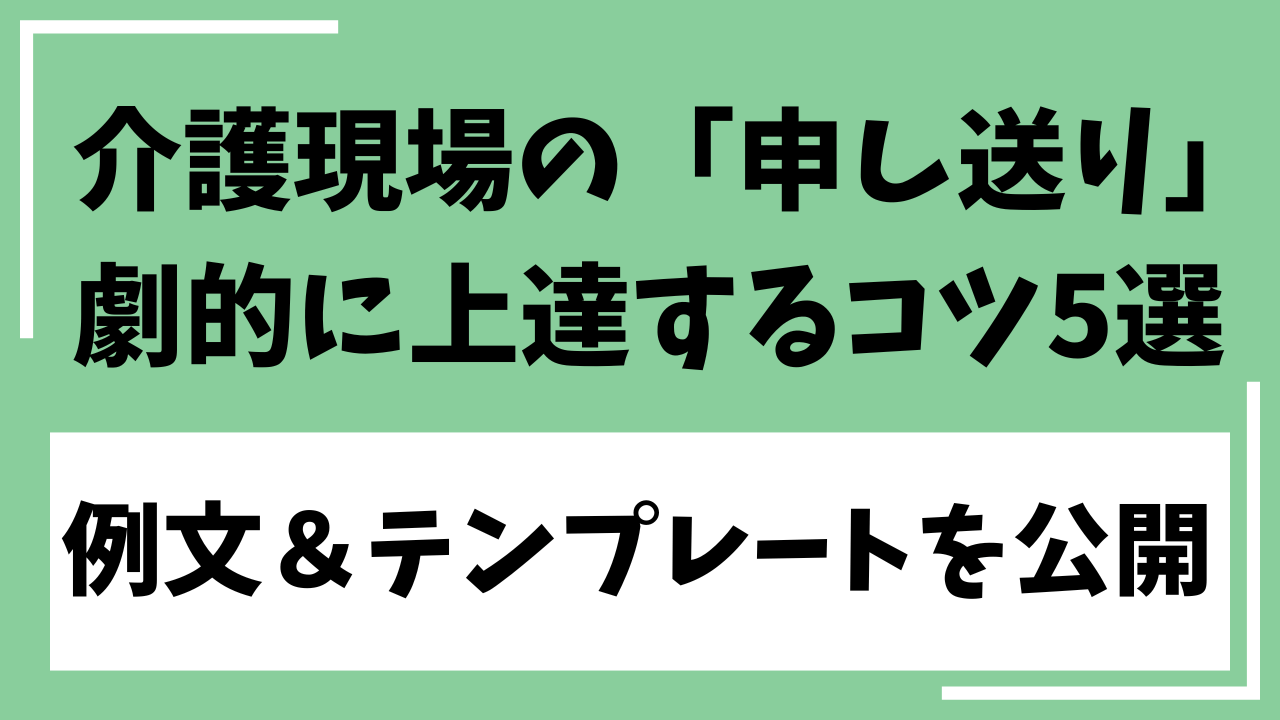
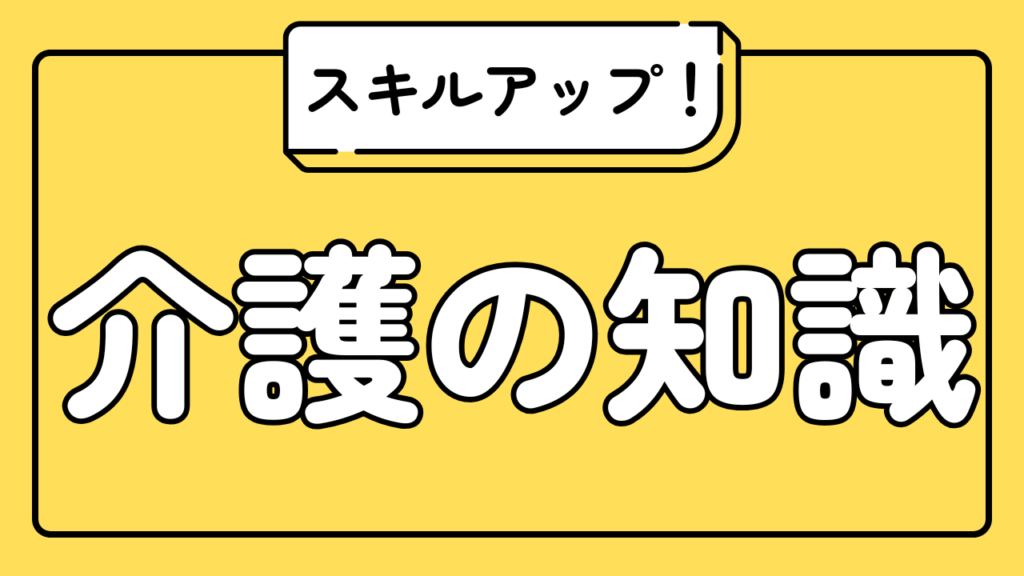


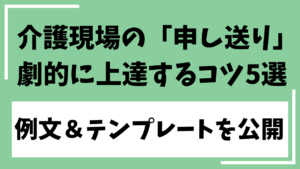


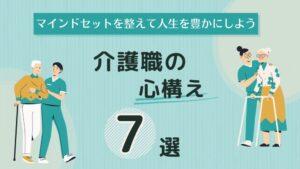
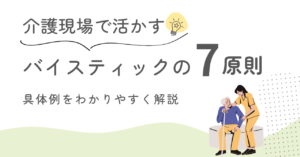


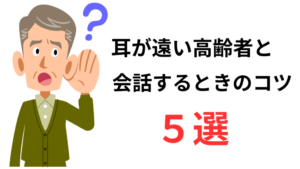


コメント