介護現場で15年以上働いていますが、この「介護職って変な人が多くない?」という質問、本当によく耳にします。
うちの妻も言っています。
結論から言うと、「介護職に変な人はいるけど、他の業界にもいるでしょ」というのがぼくの答えです。
「介護職に変な人が多い」と言っている輩を論破、完全否定してやろうと、鼻の穴を膨らませてパソコンに向かったのですが、無理でした。
この記事では、介護職に変な人が多いと言われる「理由」と「付き合い方」について解説します。
関連記事はこちら
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載
なぜ「介護職に変な人が多い」と言われるのか?:3つの理由



前提として、介護職だけに変な人が多いわけではありません。どの業界にも変な人はいます。
そもそも「変な人」とはどのような人でしょうか?
ここでは、次のように定義します。
「変な人=常識がない人」
つまり、「なぜ介護職には常識がない人が多いのか?」というテーマについて、現役介護職の視点で紹介していきます。
理由1:誰でもなれる職業だから
これが最大の理由です。
介護職は、慢性的な人手不足という背景もあり、多くの施設で「未経験OK」「資格不問」の求人が出ています。
もちろん、意欲を持って未経験から飛び込んでくる素晴らしい方もたくさんいます。
ですが、入り口が広いぶん、他の業種ではコミュニケーションや協調性の面でうまくいかなかった人も入職しやすいのです。
ぼくも現場で見てきましたが、スキルや知識は後からいくらでも教えられます。
でも、その人の根本的な「性格」や「常識」を変えるのは無理です。
本当、無理ゲーです。
結果として、多様な人材が集まるがゆえに、「一般企業では見かけないタイプの人」の割合高くなってしまうのかもしれません。(オブラートに包む限界)
わかりやすく言えば、「誰でも採用するから、変な人が増えていくんだよ!」というわけです。



トイレの後に手を洗わない職員。
感染症対策の観点から(それ以前の問題だが)「トイレの後は手を洗ってもらえますか?」とお願いしても、彼は「は?なんで?」みたいな顔をします。
ちなにみ、日本人ですよ。
これまで、彼の人生には、トイレの後に手を洗う習慣や文化がなかったのでしょう。
何度か言えば、手を洗うのですが、こちらが油断していると手を洗わずに自分の持ち場に戻っていくのです。
彼が去った後に、ドアノブをアルコール消毒しています。
ストレスと仕事が増えるんです。
理由2:ビジネスマナーを求められないから
介護現場は、一般的なオフィスワークとは全く異なる環境です。
- 名刺交換をしない
- 社外の人とメールでやり取りすることが少ない
- (施設にもよりますが)服装や髪型が比較的自由
このように、いわゆる「ビジネスマナー」や「ビジネス敬語」を厳しく問われる場面が極端に少ないんです。
もちろん、利用者さんやご家族への「丁寧な言葉遣い」は必須ですよ。
ですが、ビジネスシーンでの「報・連・相(報告・連絡・相談)」の徹底や、社会人としての立ち居振る舞いを学ぶ機会が少ないまま現場に出る人もいます。
そのため、本人に悪気はなくても、タメ口が抜けなかったり、時間を守る意識が低かったり、TPOをわきまえない言動をしてしまう人が、「常識がない」と見られてしまうケースがあります。
TPOとは、場所や状況に合わせた服装や立ち振る舞いのこと。



事務員さんがいないときに、たまたま近くで鳴った電話に出たパートさん「はい、もしもーし」
いやいや、自宅の電話じゃないんだから……



職場の会議に、ビーチサンダル&麦わら帽子で参加するツワモノ。
会議室に現れたとき、麦わらの一味かと思いました。
理由3:メディアの影響
これは介護職全体にとって、とても悲しい理由です。
テレビのニュースで介護が取り上げられる時って、どんな内容が多いでしょうか?
残念ながら、「感動的な話」ではなく「施設での虐待」や「職員による不祥事」といったネガティブな報道の方が目立ってしまいがちです。
こうした一部の不適切な事例が繰り返し報道されることで、「介護の現場=何か問題がある場所」「介護職=ストレスで変になっている人」という強いイメージ(ステレオタイプ)が世間に刷り込まれてしまいます。
ぼくたち介護職の大半は、日々真面目に利用者さんと向き合っています。
でも、たった一つの衝撃的なニュースが、業界全体のイメージを悪くしてしまう。
これは現場にいる人間として、とても悔しいことだと感じています。



「やさしいでおなじみの介護職員が、裏ではこんな悪いことしてまっせ」というギャップが話題性を生むわけですからね。
視聴率のためとはいえ、モヤモヤする……
ニュースで事件を報道するとき、会社員ではなく、わざわざ「介護職員」と報道されるのもなんだかなぁ。
ニュースを見た妻が、ボソッと「また介護士」とつぶやく……
常識がない介護職の特徴と付き合い方



「介護職に変な人が多い」と言われる理由はいろいろありますが、現場で働くぼくたちを実際に悩ませるのは、「あの人、社会人としてどうなの?」と感じる同僚の存在ですよね。
あなたの職場にもいませんか?
ここでは、特に現場で遭遇しがちな「常識がない」と感じる3つの特徴と、付き合い方について、深掘りしていきます。
デリカシーがない
介護の仕事は、利用者さんの身体やプライバシーに深く関わる仕事です。
だからこそ、一番求められるスキルと言ってもいいかもしれません。
【特徴】
- 利用者さんに対して:
- 排泄や入浴介助中に、平気で他の職員と世間話をする。(利用者さんが羞恥心を感じていることに気づかない)
- 利用者さんの容姿や病気、家族関係について、本人の前で(または他の利用者さんがいる前で)平気で話題にする。「〇〇さん、また太った?」とか「息子さん、全然会いに来ないわね」など。
- 同僚に対して:
- 人の給料や家庭環境、恋愛事情など、プライベートなことをズケズケと聞いてくる。
- 人が気にしているコンプレックスを、平気でいじる。
なぜデリカシーがないのか?
これは、「相手の立場に立って物事を想像する力」が欠けていることが原因です。
心理カウンセラーの視点から見ると、「これを言ったら相手がどう感じるか」という想像力が働かない、あるいは、他者への関心が低い(または自己中心的)な傾向があると考えられます。
また、介護現場特有の「慣れ」もあります。
ぼくたち介護職は、毎日、排泄や裸に触れることが「日常業務」です。
この「日常」に慣れすぎてしまい、利用者さんにとってはそれが「非日常」であり「羞恥心を伴うもの」だという感覚がマヒしてしまうことがあるんです。
上手な付き合い方・対処法
あなた個人に向けられる場合: まともに取り合ってはダメです。
プライベートなことを聞かれたら、「そういう話はちょっと…」「ご想像にお任せします」と笑顔でスルーしましょう。 相手は悪気なく(あるいは面白がって)踏み込んでくるので、こちらが感情的に怒ると余計にエスカレートします。「この人に言っても無駄だな」と思わせるのが一番です。
利用者さんへの言動が問題な場合: これは「個人の問題」ではなく「チームの問題」です。
もしあなたが後輩なら、先輩やリーダーに「先ほどの〇〇さんへの声かけですが、ご本人が気にされているようでした。別な言い方を検討しませんか?」と相談する形で伝えます。
もしあなたが先輩なら、「あの言い方は、〇〇さんが悲しむからやめようね」と、「相手(利用者さん)の感情」を主語にして具体的に指導します。
デリカシーがない介護職の特徴は次のとおり
- 不用意な一言:利用者さんの体型・物忘れ・失禁をネタっぽく言う/あだ名呼び。
- 声量・場所を選ばない:廊下や食堂で個人情報・失敗談を大声で共有。
- 時間帯無視の頼み方:食事・排泄介助の最中に長い相談や雑談を始める。
- 境界線があいまい:初対面でタメ口、急に身体へ触れる、私物や家族事情に踏み込む。
- “正しさ”の押しつけ:本人の希望より手順や自分のやり方を優先(「それ違うから!」と即否定)。
- 冗談の線引きが甘い:失敗を笑いに変えるが相手は傷つく(“いじり”が常態化)。
- プライベート暴露:本人の前で家族の愚痴や金銭の話題を出す。
報連相ができない
介護現場の「報連相」は、利用者さんの命と安全に直結する、最も重要な業務の一つです。
報連相ができない人は、はっきり言って介護職に向いていません。
【特徴】
- 報告しない(隠す):
- 利用者さんを転倒させてしまった、薬を飲ませ忘れたなど、自分に不都合なミスを隠蔽する。
- 「これくらい大丈夫だろう」と自己判断し、利用者さんの小さな体調変化(微熱、いつもより食欲がない等)を報告しない。
- 連絡しない(共有しない):
- ご家族から受けた伝言(「明日〇時に面会に来る」など)を、次のシフトの職員に申し送りをしない。
- 業務の手順を勝手に変えたのに、誰にも連絡しない。
- 相談しない(独断で動く):
- いつもと違う対応が必要な場面(例:急な体調不良)で、リーダーや看護師に相談せず、自分流の対応をしてしまう。
なぜ報連相ができないのか?
- 責任感の欠如: 「怒られたくない」「面倒くさい」という自己保身が、利用者さんの安全より優先されてしまうタイプ。
- 楽観的すぎる(危機感の欠如): 「まぁ、大丈夫でしょ」と物事を軽く捉えすぎ、その情報がどれほど重要かを理解できないタイプ。
- プライドが高い: 「人に聞くのは恥だ」と思い込み、相談せずに独断で動いてしまうタイプ。
上手な付き合い方・対処法
これは、デリカシーの問題より深刻です。
なせなら、事故に直結するからです。 毅然とした態度で臨む必要があります。
- 「報連相の重要性」をチーム全体で再確認する: ミスが発覚したら、個人を責めるだけでなく、ミーティングなどで「なぜ報連相が必要か」をヒヤリハット事例として共有します。 「報告が遅れると、最悪の場合こういう事故につながる」という共通認識をチームで持つことが重要です。
- 「報告しやすい仕組み」を作る: ミスを報告しても高圧的に怒鳴りつけるような上司がいると、誰も報告しなくなります。 ミスは「個人の責任」だけでなく「チームの課題」として捉え、**「報告してくれてありがとう。じゃあ次どう防ぐか考えよう」**という雰囲気(心理的安全性)を、特にリーダー層が意識して作ることが大切です。
- その人には「確認」を徹底する: 報連相ができない人と組む時は、こちらから「さっきの〇〇さんの件、どうなりましたか?」「何か変わったこと、ありませんでしたか?」と、先回りして確認するしかありません。 面倒ですが、事故が起きてからでは遅いのです。
時間にルーズ
介護現場は、分刻みのスケジュール(入浴介助、食事、排泄ケアなど)で動いています。
一人が遅れると、全体の業務が滞り、他の職員だけでなく利用者さんにも迷惑がかかります。
【特徴】
- 遅刻が多い:
- 始業時間に平気で遅れてくる。悪びれる様子もない。
- 休憩時間が長い:
- 決められた休憩時間(例:60分)を平気でオーバーする。
- ケアがダラダラと長い:
- 一つのケアに時間をかけすぎ、次の予定がどんどん押していく。(※丁寧なのと遅いのとは違います)
- 利用者さんとの私語が長すぎて、業務が進まない。
なぜ時間にルーズなのか?
- 計画性のなさ: 業務の全体像を把握できておらず、「この時間までにこれを終わらせないと、次が困る」という逆算ができない。
- 当事者意識の欠如: 「自分が遅れても、誰かがカバーしてくれるだろう」という甘えがある。
- 優先順位がつけられない: 今やるべきことより、自分のやりたいこと(例:特定のお気に入りの利用者さんとの会話)を優先してしまう。
上手な付き合い方・対処法
- まずは「事実」を伝える: 「〇〇さんが遅れると、ぼく(私)がその分〇〇さんの業務もやることになって、時間通りに終わりません」と、具体的に誰がどう困るのかを伝えます。 「時間にルーズだよね」という人格否定ではなく、「行動」が「業務」に与えている影響を淡々と伝えましょう。
- 時間管理を「見える化」する: その人が特に遅れがちな業務(例:入浴介助)があるなら、「入浴は1人〇分まででお願いします」「〇時までには必ずホールに戻ってください」と、具体的な時間を設定してリマインドします。
- 改善しない場合は上司に相談: 何度も注意しても改善されない場合は、勤怠の問題であり、公平性の問題です。(真面目にやっている人が損をするため) 「〇〇さんが休憩時間を〇分オーバーすることが多く、その間のナースコール対応などで業務に支障が出ています」と、リーダーや上司に報告し、組織として指導してもらいましょう。



連絡なしに40分遅刻してきた職員に、遅刻した理由を聞くと、
「記憶をなくしていました」とのこと。
「えっ?どういうこと?」「お酒を飲み過ぎたってこと?」
いいえ、家を出てからの記憶がないんです。
「どうやって職場まで来たの?」
気づいたら職場にいました。
マジメな顔で、このようなやり取りが繰り広げられる。
結局、代わりの職員がすでに勤務していたし、遅刻してきた職員には帰ってもらいました。
そして、翌日から音信不通に……。
よくある質問【Q&A】
- 職場の人間関係が嫌すぎて辞めたいです。私がおかしいのでしょうか?
-
あなたがおかしいわけでは、決してありません。 介護はチームプレーです。人間関係が悪い職場で良いケアはできませんし、あなたが我慢し続ける必要もありません。
ただし、「その人一人」が問題なのか、「職場全体の文化」が問題なのかは見極めてください。
もし職場全体が「おかしい」と感じるなら、それは「転職」を考えるサインです。介護の職場は星の数ほどあります。あなたに合う場所は必ず見つかりますよ。
- 次に働くなら、変な人がいない職場を見極めたいです。
-
100%見極めるのは難しいですが、確率は上げられます。 ぼくがおすすめするのは、「見学」の際に「職員同士の会話」をよく観察することです。
- 職員同士が笑顔で挨拶しているか
- 申し送りの雰囲気がピリピリしていないか
- リーダーや上司が、部下に対して高圧的でないか
利用者さんへの態度だけではなく、職員間の「空気感」を見てみてください。 雰囲気が良い職場は、研修がしっかりしていたり、離職率が低かったりする傾向があります。
まとめ
「介護職に変な人が多い」というイメージは、「業界の構造」や「メディアの影響」によって作られてしまいました。
でも、15年以上現場にいるぼくが断言します。
それ以上に、マジメで、やさしくて、情熱を持った介護職が圧倒的に多いです。
一部の目立つ人に振り回されて、介護という仕事そのものを嫌いにならないでほしいです。
「変な人は嫌いでも、介護職のことは嫌いにならないでください!」
と、前田敦子のように叫んで終わりたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
では、また。
=== 追伸 ===
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
あなただけに「介護士の悩み」をピンポイントで解決する方法を紹介します。
介護転職に失敗しないコツはこちら
https://kaigo-ozisan.com/lp/recruitment-agent/
あなたの悩みをピンポイントで解決
介護士の悩み・疑問【Q&A】
悩みを解決してスッキリしませんか?




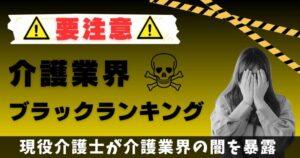
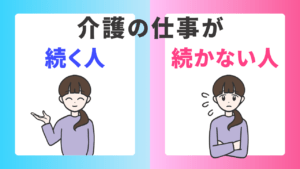

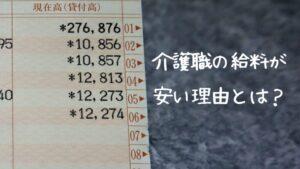





コメント