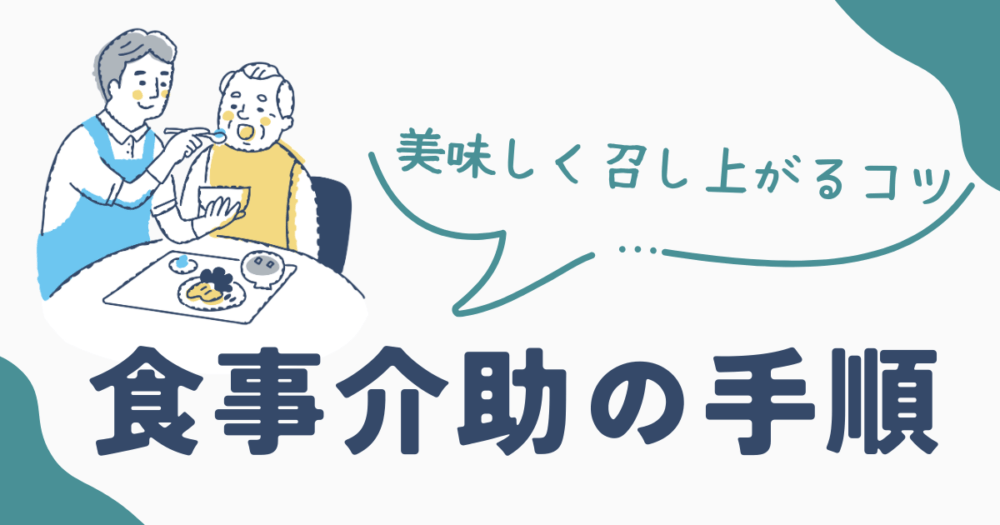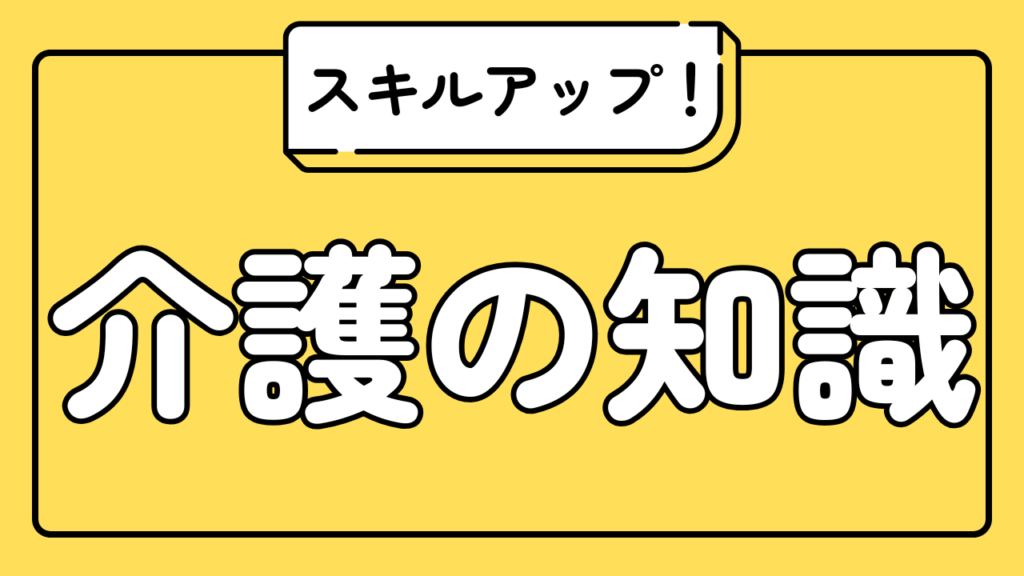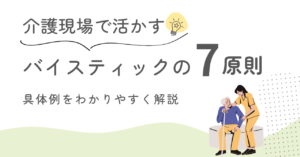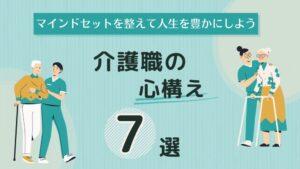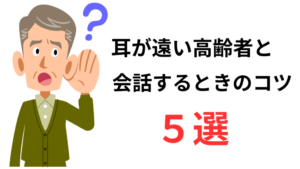介護士
介護士食事介助って、ただ食べさせればいいの?




むせたり、食べこぼしたりしないためには?




介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんが安心して美味しく食事を楽しめる食事介助のコツを解説します。
- 食事介助は「手順を守る」「安全を第一にする」「無理のない声かけ」がポイント
- スムーズに進めるコツは、準備・姿勢・コミュニケーションにある
- やってはいけないNG行動を避けることで、利用者さんも介助者も安心できる
食事は、利用者さんにとって栄養補給の時間であると同時に、日々の楽しみのひとつ。
しかし、介助の仕方を間違えると、誤嚥や食欲低下の原因になってしまうことも。
適切な姿勢や食事の進め方、声かけひとつで、食事の時間はもっと快適になります。
また、「ついやってしまいがちだけどNGな食事介助」も併せて紹介。
些細なミスが利用者さんの負担になることもあるため、しっかりポイントを押さえておきましょう。
美味しく、安全に、楽しい食事の時間をつくるための秘訣を、現場経験をもとに詳しく解説します!
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY



詳しくはトップページのプロフィールに記載
食事介助の基本手順



- 準備:手洗い・口腔ケア・誤嚥を防ぐ姿勢作りが基本。
- 提供:「小さじ一杯」を目安に、下からスプーンを運び、飲み込みを確認する。
- 食後:口腔ケアと、食後30分の安静姿勢で逆流・誤嚥を防ぐ。
食事介助は、準備から食後まで、一連の流れとして捉えることが大切です。
一つひとつのステップに、安全に美味しく食べるための意味があります。
食事前の準備
まずは、落ち着いて食事を始められる環境を整えましょう。
- 手洗い・消毒:介助者自身の手を清潔にすることは、感染症予防の基本です。
- 口腔ケア:食事の前に口の中をきれいにします。唾液の分泌を促し、味覚をはっきりさせる効果があります。また、口の中の雑菌が食べ物と一緒に気管へ入る「誤嚥性肺炎」のリスクを減らすことにも繋がります。軽くうがいをしたり、口腔ケア用のスポンジで清掃したりしましょう。
- 姿勢の調整:ここが最も重要です。椅子に座れる方は、深く腰かけてもらい、足の裏が床にしっかりとつくように調整します。少し前かがみの姿勢が、飲み込みやすい理想の角度です。ベッドで食事を摂る場合は、リクライニングを45〜60度以上に起こし、首が後ろに反らないようにクッションなどで支えます。
準備がちゃんとしてないと、介助が始まってからバタバタしてしまって、利用者さんもこちらも余裕がなくなる。ぼく自身“ あ、あれ忘れた!”という経験が何度もあり、10分前には終わるように余裕をもって準備しています。
- 食事用具はあらかじめ置き場所を固定しておくと、準備ミスが減る。
- 利用者さんが使い慣れている食器や箸を使うと、拒否されにくくなる。
提供の仕方
利用者さんのペースを大切に、一口ずつ丁寧に進めていきます。
- 一口の量:ティースプーン1杯程度が目安です。多すぎると口の中で処理しきれず、誤嚥の原因になります。
- スプーンの使い方:スプーンは、利用者さんの口元へ、斜め下から運びます。上からだと、顎が上がってしまい、むせやすくなるからです。スプーンを口の奥に突き立てず、下唇にそっと乗せるような感覚で。利用者さんが自ら唇を閉じるのを待ってから、水平に引き抜きましょう。
- ペースの配慮:一口食べたら、ゴクンと飲み込んだことを必ず確認します。口の中に残っていないか、喉の動きを見て確認しましょう。「次、いきますね」と声をかけると、お互いのペースが作りやすいです。
食後のケア
食事が終わっても、まだ介助は終わりではありません。
- 口の中の確認:食事のあと、頬の内側や上顎などに食べ物が残っていないか確認します。残っていると、後で誤嚥する原因になります。
- うがい・歯磨き:可能な範囲で口腔ケアを行い、口の中を清潔に保ちます。
- 安静姿勢の保持:食後すぐ横になると、胃の中のものが逆流しやすくなります。少なくとも30分は、座ったままか、ベッドを上げたままの姿勢で過ごしてもらいましょう。
“ごちそうさま”で終わりではないのを、いつも思い出します。口の中に残っていないか確認して、歯磨きやうがいをして、姿勢を整える。これをやるかどうかで誤嚥したり胃がムカムカするかが違ってきます。
- 食事後30分は横にしない。座った姿勢またはベッドを少し起こした状態を保つと逆流防止になる。
- 食後の口腔ケアで“舌の上”や“頬の内側”の食べかす見落としがち。鏡や指で軽く触って確認を。
食後の服薬介助のコツと注意点
服薬介助のコツ
- 飲み込みやすい姿勢を整える
背もたれを少し起こし、顎を軽く引いた姿勢にすると、薬が喉に通りやすくなる。 - 一度に多く渡さない
錠剤やカプセルは1~2錠ずつ少量の水で飲んでもらうと安全。 - 水分の工夫
水が苦手な方は、医師の指示の範囲でゼリーやとろみ水を活用すると誤嚥予防になる。 - 声かけを忘れない
「これから薬を飲みますね」と説明してから渡すと安心感がある。
注意点
- 誤嚥リスクに配慮
むせやすい方には、少量の水+間を置くことを徹底。 - 口腔内の確認
飲み込んだと思っても頬にため込んでいる場合があるので必ず確認する。 - 禁止されている飲み方は避ける
砕いてはいけない薬や、牛乳と一緒に飲むと効果が変わる薬もあるため、医師・薬剤師の指示を守る。 - 急かさない
「早く飲んで」と急かすとむせや事故につながるので、利用者さんのペースを尊重する。
薬を飲むのが苦手な方は、本当に毎回ドキドキします。飲んだと思っても口に残っていたり、粉でむせたり。だから“少しずつ・確実に”が大事。
薬を飲んだふりをして、ゴミ箱に捨ててしまう方もいるので注意が必要です。
関連記事はこちら
食事介助をスムーズに進めるコツ



手順通りに進めても、なぜかうまくいかない…。
そんなときは、3つのコツを意識してみてください。
利用者さんのペースに合わせる
介助者の都合で「はい、次」「はい、これ」と進めてしまうのはNGです。
ぼくたちも、急かされながら食べるご飯は美味しくないですよね。
咀嚼(そしゃく)して、嚥下(えんげ)するまでの時間は、人それぞれです。
喉の動きをしっかり見て、口の中が空になってから次の一口を運ぶ。
この「待つ」時間が、信頼関係を築き、安全にも繋がります。
姿勢と環境を整える
基本手順でも触れましたが、姿勢は本当に大切です。
椅子が合わずに体が傾いていたり、足がぶらぶらしていたりすると、体に余計な力が入り、うまく飲み込めません。
- テーブルの高さは適切か
- 部屋は明るいか
- テレビの音が大きすぎないか
といった環境への配慮も、食事に集中してもらうための大切なポイントです。
姿勢が悪い方だと、むせたり飲み込めなかったりで、食べる意欲がそがれてしまう。
だから少し手間でもサポートして背中や腰を整えるようにしています。利用者さんの“楽”を最優先したいですね。
- 肘がテーブルにつくと手が安定し、食べこぼしが減る。
- 座面の高さを調整できる椅子やクッションを使うと、顎が上がったり前かがみになったりするのを防げる。
声かけで安心感を与える
心理カウンセラーの視点からも、声かけは非常に重要だと感じています。
「〇〇さん、次はお魚ですよ。美味しそうですね」
「ゆっくりで大丈夫ですよ」
「よく噛めていますね」
といったポジティブな声かけは、利用者さんの不安を和らげ、食事への意欲を引き出します。これから何が口に入るのかを伝えることで、心の準備もできます。
“これからお魚ですよ”“ゆっくりでいいですよ”と声をかけると、利用者さんの顔がほっとする瞬間があります。
無言で食べさせてしまうと“怖い”“何をされているのかわからない”と思われるので注意しましょう。
- 食材や味について“どんな匂いがするか”“どんな見た目か”を伝えると五感が刺激されて食が進む。
- 相手の名前を呼ぶと、自分が尊重されている感じが強まり安心する。
絶対に避けたいNG行動



良かれと思ってやったことが、実は危険な介助だった、というケースは少なくありません。
これだけは避けてほしいNG行動です。
- 無理やり食べさせる:「栄養をつけないと」という気持ちはわかりますが、口をこじ開けて食べさせるのは絶対にいけません。誤嚥のリスクが非常に高いだけでなく、利用者さんの尊厳を深く傷つけます。
- 早すぎるスピード:介助者の焦りは、利用者さんに伝わります。飲み込みを確認せずに次々と口に運ぶのは、窒息に繋がりかねない危険な行為です。
- 不適切な姿勢で介助する:寝かせたままの状態で食事をさせるのは、最も危険です。重力で食べ物が気管に流れ込みやすくなります。必ず上半身を起こしましょう。
- 利用者さんの気持ちを無視した対応:介助者が無言だったり、テレビを見ながら片手間に介助したり…。そういった態度は、食事の時間を「作業」に変えてしまいます。「美味しく食べてほしい」という気持ちが伝わることが、何よりのスパイスです。
慣れてくると急ぎがちになるけれど、焦って間違いを起こすと後でしんどくなる。
職場で“ゆっくり・確認しながら”という風に声を掛け合うようにしています。
- むせは見える誤嚥だけど、“見えない誤嚥(不顕性誤嚥)”もあるため、表情や呼吸に注意を。
- 利用者さんが飲み込みにくそうな時は、とろみ調整を検討する。
食事介助でよくある失敗と改善ポイント



ぼくも新人時代はたくさんの失敗をしました。
よくある失敗例と、その改善策をご紹介します。
- 口に食べ物を詰めすぎてしまう
「小さめ一口」に改善- ついつい一口の量が多くなってしまう…。これは「早く食べさせてあげたい」という気持ちの表れかもしれません。でも、ぐっとこらえて、「ティースプーンに軽く一杯」を徹底するだけで、むせ込みは格段に減ります。
- 水分を一気に飲ませてしまう
「とろみ」や「少量ずつ」に変更- お茶などの水分は、固形物よりも速く喉に流れるため、実は誤嚥しやすいのです。コップでゴクゴク飲ませるのは危険。スプーンで少量ずつ提供するか、必要であれば「とろみ剤」を使って、喉を通過するスピードをゆっくりにしてあげましょう。
- 無言で食べさせてしまう
「声かけで安心感」を意識- 介助に集中するあまり、つい無言になってしまうことがあります。でも、食べさせてもらう側は、次に何が来るのか、熱くないか、不安でいっぱいです。「次は温かいお味噌汁ですよ」の一言があるだけで、安心して口を開けてくれます。
新人さんが“早く食べさせてあげたい”という気持ちから一口が大きくなりがちですが、何度か失敗を見てきて、むせる回数が減ったのは“一口を小さく・待つ時間を取る”を徹底した後でした。失敗は次へのヒントになります。
食事介助で大切にしたい心構え【3選】



技術や手順も大切ですが、同じくらい「心構え」も重要です。
1.「尊厳を守る」介助の姿勢
たとえ介助が必要であっても、相手は人生の先輩です。
子どもに話しかけるような言葉遣いは避けましょう。
エプロン(よだれかけ)を使うときも、「口元が汚れないように、素敵なエプロンをつけましょうね」といった配慮のある言葉を選びたいですね。
ここがポイント!
「もし自分が逆の立場だったら、どうしてほしいだろう?」と想像することです。
【具体例】
- 言葉遣いを子ども扱いにしない
- NG例: 「はーい、あーんして。じょうずだねー」
- OK例: 「〇〇さん、次はお豆腐です。柔らかくて美味しいですよ。お口を開けていただけますか?」
- 赤ちゃん言葉や、過度な褒め方は、相手の自尊心を傷つけることがあります。丁寧な言葉遣いを基本にしましょう。
- 目線の高さを合わせる
- 立ったまま上から見下ろすように介助すると、相手は威圧感や不安を感じます。椅子に座るなどして、できるだけご本人と同じか、少し下からの目線になるように心がけましょう。目線が合うだけで、安心感が全く違います。
- 食事用エプロンへの配慮
- 「よだれかけ」という言葉は使わず、「エプロン」や「お食事の時の前掛け」などと言い換えましょう。「素敵なお洋服が汚れないように、エプロンをつけさせていただきますね」と一言添えるだけで、相手の気持ちは大きく変わります。
- 「何の説明もなく口に運ぶ」のはNG
- 目が見えにくい方ならなおさらですが、いきなり口に食べ物を運ばれるのは怖いものです。「次は、温かいお味噌汁ですよ」「少し酸っぱい和え物です」など、メニューを伝えながら介助することで、心の準備ができ、味わう楽しみも生まれます。
“今日はこの順番で食べたい”と言われたり、“こっちの方が楽”と好みを教えてくれる方もいて、その声をできるだけ尊重するように心がけてる。
介助が一方通行にならないことが大事だと思います。
2.「できることは自分で」引き出すサポート
すべてを介助者がやってしまうのは、実は親切ではありません。
- スプーンを持つことができれば、手を添えて口まで運ぶのを手伝う。
- お茶碗に手を添えることができるなら、それを支える。
ほんの少しでも自分でできることがあると、それはその方の自信と喜びに繋がります。
ここがポイント!
介助者は「主役」ではなく、あくまで「サポーター」であるという意識を持つことです。
【具体例】
- スプーンや箸を持ってもらう
- たとえうまくすくえなくても、スプーンを「握る」ことができるなら、ご本人に握ってもらい、介助者はその手を下から支えて口まで運びます。「自分の手で食べた」という感覚が、とても大切になります。
- お茶碗に手を添えてもらう
- 麻痺などで片手しか動かせない場合でも、動く方の手をお茶碗に添えてもらうだけで、「食事に参加している」という意識が生まれます。「〇〇さん、こちらの手でお茶碗を支えていただけますか?」と声をかけてみましょう。
- 「選んでもらう」機会を作る
- 「お魚とお肉、どちらから召し上がりますか?」「お茶にしますか?お水にしますか?」
- このように、ささいなことでもご本人に選んでもらう(自己決定)場面を作ることは、その方の意思を尊重する大切な関わりです。食事の主導権がご本人にあることを示せます。
- 食後の口拭き
- 濡らしたおしぼりを渡し、まずはご自身で口元を拭いていただく。拭き残した部分を「仕上げをさせてくださいね」と拭いて差し上げる。こうした一つひとつの積み重ねが、その方の「まだまだできる」という気持ちを支えます。
3.「失敗しても責めない」温かい対応
食事中にむせたり、食べ物をこぼしたりすることは、誰にでも起こり得ます。
そんなとき、「あーあ」とため息をついたり、焦った態度を見せたりしてはいけません。
「大丈夫ですよ、ゆっくりいきましょうね」「気にしないでくださいね」と、笑顔で対応することが、利用者さんの安心感に繋がります。
ここがポイント!
介助者の「心の余裕」が、相手の「心の安心」に直結すると知ることです。
【具体例】
- 食べ物をこぼしてしまった時
- NG例: 「あーあ、こぼれちゃった…」とため息をつく。無言で片付ける。
- OK例: 笑顔で「大丈夫ですよ、誰にでもありますから。気にしないでくださいね」と声をかけ、サッと拭く。「お洋服は汚れていませんか?」とご本人を気遣う一言も大切です。
- むせてしまった時
- 介助者が慌てると、ご本人はもっとパニックになります。まずは「大丈夫ですよ」と落ち着いて声をかけ、背中を優しくさすります。少し前かがみの姿勢をとってもらい、落ち着くまで待ちましょう。介助者の冷静な態度が、一番の安心材料です。
- 食べるのに時間がかかる時
- 時計をチラチラ見たり、イライラした態度を見せたりするのは絶対にNGです。疲れているのかもしれないし、噛むのに時間がかかっているのかもしれません。「ゆっくりで大丈夫ですよ」「少し休憩しましょうか?」と声をかけ、相手のペースを尊重しましょう。
食事介助の具体例:ケースごとの対応



利用者さんの状態によって、介助の方法も少しずつ変えていく必要があります。
- 誤嚥しやすい方 → とろみをつける・ゆっくり介助
- 飲み込む力が弱い方には、食べ物をペースト状にしたり、水分にとろみをつけたりする工夫が有効です。そして、何よりも一口ごとに飲み込みを確実に確認し、通常よりも時間をかけてゆっくり介助することを徹底します。
- 食欲がない方 → 盛り付け工夫・声かけで誘導
- 食欲がないときは、無理強いは禁物です。量を減らして、彩りよく盛り付けるだけでも「食べてみようかな」という気持ちになることがあります。「一口だけでも、味見しませんか?」と、好きなものから勧めてみるのも良い方法です。
- 自力で少し食べられる方 → 必要な部分だけ補助
- お箸やスプーンは持てるけれど、うまくすくえない、という方には、お皿を手で支えたり、すくいやすいように食べ物を集めてあげたりします。腕が疲れてきたら、途中から介助に切り替えるなど、その方の「今できること」に合わせたサポートを心がけましょう。
よくある質問(Q&A)
- 食事介助のときに一口の量はどのくらい?
-
小さじ1杯(ティースプーン1杯)程度が目安です。利用者さんの口の大きさや、飲み込む力に合わせて調整しますが、基本は「少なめ」を意識してください。
- 水分を与えるときの注意点は?
-
一気飲みは誤嚥の大きな原因になります。必ずスプーンで少量ずつ提供するか、吸い飲み(ストロー)を使う場合も、一口ずつ区切って飲んでもらうようにしましょう。必要に応じて、医師や看護師に相談の上、とろみ剤を使用するのが安全です。
- 食事を嫌がるときはどうすれば?
-
まずは無理に食べさせないことが大前提です。「今は食べたくない」という意思表示を尊重しましょう。体調が悪いのかもしれませんし、何か他に原因があるかもしれません。時間を少しずらしてみたり、「じゃあ、この果物だけどうですか?」など、好きなものを少しだけ勧めてみたりするのも一つの方法です。
まとめ
食事介助は、ただ食べ物を口に運ぶだけの「作業」ではありません。
利用者さんの「食べたい」という気持ちに寄り添い、安全を守りながら、食事の楽しみを支える、とても専門的で温かいコミュニケーションです。
- 正しい手順を守る
- 安全な環境を整える
- 「美味しく食べてほしい」という思いやり
この3つが揃ったとき、食事の時間は、利用者さんにとっても、介助するあなたにとっても、豊かでかけがえのないひとときになるはずです。
この記事が、あなたの食事介助のヒントになれば、ぼくは心から嬉しく思います。
あなたを応援しています。
次に読むオススメの記事はこちら