当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
 介護士
介護士介護施設の早番業務ってどんな流れなの?




入浴介助って大変そうだけど、実際はどんな感じ?




介護士歴15年以上の筆者が、介護施設の早番業務について徹底解説します。
介護士を目指す方や、これから現場に入る方にとって、1日のスケジュールがわからないと不安になりますよね。
でも、大丈夫。
しっかり流れを把握すれば、業務はスムーズに進められますよ。
入浴介助は、時間配分やチームワークが重要。コツをつかめば、負担を減らしながら効率よく対応することができます。
今回は、早番&入浴介助のタイムスケジュールを公開。
朝のスタートから入浴介助の流れまで、現場目線で詳しく解説します。
この記事を読めば、仕事のイメージがぐっとクリアになりますよ!
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY



詳しくはトップページのプロフィールに記載
早番の1日の流れ
ぼくが勤務している、介護付き有料老人ホームでの早番の業務です。
1フロア18名の利用者さんが入居されていて、1日に8名の入浴を介助しています。
- 7:00出勤
朝食前の準備(お茶出し、利用者さんを食堂までご案内)
- 8:00朝食
配膳・下膳、食事介助、食後の服薬介助、口腔ケア、排泄介助、食堂の清掃
あわせて読みたい

 【保存版】食事介助の手順 美味しく召し上がるコツとNGな介助 食事介助って、ただ食べさせればいいの? むせたり、食べこぼしたりしないためには? 介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんが安心して美味しく食事を楽しめる食事介助...
【保存版】食事介助の手順 美味しく召し上がるコツとNGな介助 食事介助って、ただ食べさせればいいの? むせたり、食べこぼしたりしないためには? 介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんが安心して美味しく食事を楽しめる食事介助... - 9:00入浴介助
午前の部スタート



- 11:30休憩(1時間)
- 12:30昼食後のケア
食後の服薬介助、口腔ケア、排泄介助、食堂の清掃
- 13:30入浴介助
午後の部スタート
- 15:30入浴介助終了
浴室の清掃、後片付け、クリーニング伝票記入、パソコンで介護記録の入力、引継ぎ



- 16:00退勤
お疲れさまでした!
このような流れです。
早番の業務は入浴介助がメインになります。
一般浴であれば1名30分~40分ほど。
機械浴であれば1名50分ほどです。
入浴介助のポイント



- 職員の服装は半袖にハーフパンツ
- 首からタオルをかけて汗を拭く
- 水分をこまめに補給しながら脱水に注意
入浴介助には「一般浴」と「機械浴」があり機械浴は「特浴」と呼んでます。
一般浴というのは家庭のお風呂場の壁に手すりが付いている環境を想像してください。
歩行可能で介助があれば浴槽に入れる利用者さんは一般浴です。
機械浴(特浴)とは?
- 立位が困難の利用者さんが対象。
- ストレッチャーに寝たまま入浴できる。
- ボタンの上下でストレッチャー操作をして大きな特殊浴槽に入る。
浴槽のお湯を入れ替えたり介助以外にも時間がかかることがあるので、慣れるまでは計算しながら進めないと時間が無くなります。
メリットとしては1対1の介護に専念できるので、初心者でも対応しやすいです。
ヒートショックに注意して浴室や脱衣所の温度を調整しましょう。
(※ヒートショックとは急激な温度差により血圧が上下に変動して心臓や血管に被害を及ぼす現象)
浴槽のお湯の温度は41℃以下に調整しましょう。
副交感神経が作用されてリラックス効果が期待できます。
バスタオルを使用して利用者さんの肌の露出が最小限になるように心がけましょう。
羞恥心に配慮した介助が大切です。
床が濡れて転倒事故が起きやすいので特に注意が必要です。
入浴介助の流れを6ステップで解説
1. 事前準備
- 利用者さんの健康状態を確認
- バイタルサイン(血圧、脈拍、体温)をチェック。
- 体調不良や異変がないかを確認。
- 医師の指示や入浴可否リストを確認。
- 浴室の準備
- 浴室と脱衣所を適温にする(22〜25℃が目安)。
- 浴槽の水温を38〜40℃に設定し、滑り止めマットや手すりの確認。
- タオル、シャンプー、石鹸、着替え、介護用パッドを用意。
- 必要な機器を準備
- 移乗リフトやシャワーチェアを確認・設置。
- 利用者さんに必要な補助器具を準備。
2. 脱衣と浴室への誘導
- 利用者さんに声かけ
- 「これからお風呂に入りましょう」など、安心させる声掛けを行う。
- 入浴に抵抗がある場合は、気持ちを聞きながら優しく促す。
- 衣服の脱衣を介助
- プライバシーに配慮し、必要な部分だけを順に脱がせる。
- 利用者さんのペースに合わせ、肌寒くならないようタオルで体を覆う。
- 浴室へ移動
- 歩行が可能な場合は手を添えて移動を補助。
- 移乗リフトや車椅子を使用する場合は、安全確認をしながら操作。
3. 入浴の介助
- 入浴前の確認
- 再度水温を確認(熱すぎない、ぬるすぎない)。
- 利用者さんの体調に変化がないかチェック。
- 洗体・洗髪の介助
- 利用者さんの希望を聞きながら、体を順番に洗う。
- 頭→上半身→下半身の順が基本。
- 必要に応じてスポンジや洗浄用ブラシを使う。
- 利用者さんの希望を聞きながら、体を順番に洗う。
- 浴槽でのリラックス
- 安全を確認しながら浴槽にゆっくりと入れる。
- 利用者さんが気分良く過ごせるよう、定期的に声掛けを行う。
- 入浴中の観察
- 顔色、表情、呼吸、会話の様子をチェック。
- のぼせや体調変化があればすぐに浴槽から出す。
4. 入浴後のケア
- 浴槽からの移動を介助
- 転倒防止のため手すりや介助用具を使用し、安全に浴槽から出す。
- 足元が滑らないよう注意。
- 体の拭き取り
- 体をタオルで素早く拭き取り、冷えないようにする。
- シワや皮膚の間も丁寧に拭く。
- 着替えの介助
- 利用者さんの体調や疲労を考慮しながら、スムーズに着替えを手伝う。
- 体温が下がらないよう素早く行う。
5. 入浴後の体調確認と記録
- 体調の再確認
- 入浴後のバイタルサインを再チェック。
- 疲労や異常がないか会話を通じて確認。
- 水分補給の促進
- 脱水を防ぐために水分を摂るよう促す。
- 記録の作成
- 入浴時間、体調の変化、皮膚の状態などを記録シートに記載。
6. 後片付け
- 浴室内の清掃(浴槽や床の消毒、リフト機器の清掃)。
- 使用済みタオルや衣服の処理。
- 次の利用者のための準備を行う。
このように、事前準備からフォローアップまでを丁寧に行うことで、利用者さんが安心して入浴できる環境を提供できます。
よくある質問【Q&A】
- 1フロアの入居人数と1日の入浴人数の目安は?
-
うちの施設では「1フロア18名」「1日に8名を入浴介助」です。
- 一般浴と機械浴(特浴)の違いは?
-
一般浴=歩行可能で介助により浴槽入浴できる方。機械浴=立位困難な方向けで、ストレッチャーで入れる大型浴槽を使用します。
- 1人あたりの所要時間の目安は?
-
一般浴で30〜40分、機械浴で約50分が目安です。
- 入浴前の“数値”目安(室温・湯温)は?
-
室温(浴室・脱衣所)は22〜25℃、湯温は38〜40℃が目安です。
- 服装・体調管理のコツ(介助者側)は?
-
半袖+ハーフパンツなど動きやすい服装、タオル常備、こまめな水分補給で脱水に注意しましょう。
- 利用者さんのプライバシー配慮はどうする?
-
バスタオルで露出を最小限にし、羞恥心に配慮。転倒を防ぐため床の濡れにも注意します。
- 入浴中の観察ポイントは?
-
顔色・表情・呼吸・会話の様子を継続観察し、のぼせや体調変化があれば中断します。
- 入浴後の対応は?
-
速やかな体拭きと着衣、体調再チェック、水分補給、入浴時間や皮膚状態などの記録です。
まとめ
今回は「早番の入浴介助とタイムスケジュール」について解説しました。
おさらいすると、次のとおりです。
- 7:00出勤
朝食前の準備(お茶出し、利用者さんを食堂までご案内)
- 8:00朝食
配膳・下膳、食事介助、食後の服薬介助、口腔ケア、排泄介助、食堂の清掃
あわせて読みたい

 【保存版】食事介助の手順 美味しく召し上がるコツとNGな介助 食事介助って、ただ食べさせればいいの? むせたり、食べこぼしたりしないためには? 介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんが安心して美味しく食事を楽しめる食事介助...
【保存版】食事介助の手順 美味しく召し上がるコツとNGな介助 食事介助って、ただ食べさせればいいの? むせたり、食べこぼしたりしないためには? 介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんが安心して美味しく食事を楽しめる食事介助... - 9:00入浴介助
午前の部スタート



- 11:30休憩(1時間)
- 12:30昼食後のケア
食後の服薬介助、口腔ケア、排泄介助、食堂の清掃
- 13:30入浴介助
午後の部スタート
- 15:30入浴介助終了
浴室の清掃、後片付け、クリーニング伝票記入、パソコンで介護記録の入力、引継ぎ



- 16:00退勤
お疲れさまでした!
早番業務は、
- 早起きがキツイ
- 入浴介助で体力を消耗する
というマイナスのイメージがあるかもしれません。
しかし、一方で、1対1の対応で介護に集中できるため、初心者の介護士でも仕事を覚えやすいというメリットもあります。
介護初心者なら早番業務から覚えるのがオススメです。
最後まで読んでくれた、あなたを応援しています。
では、また。

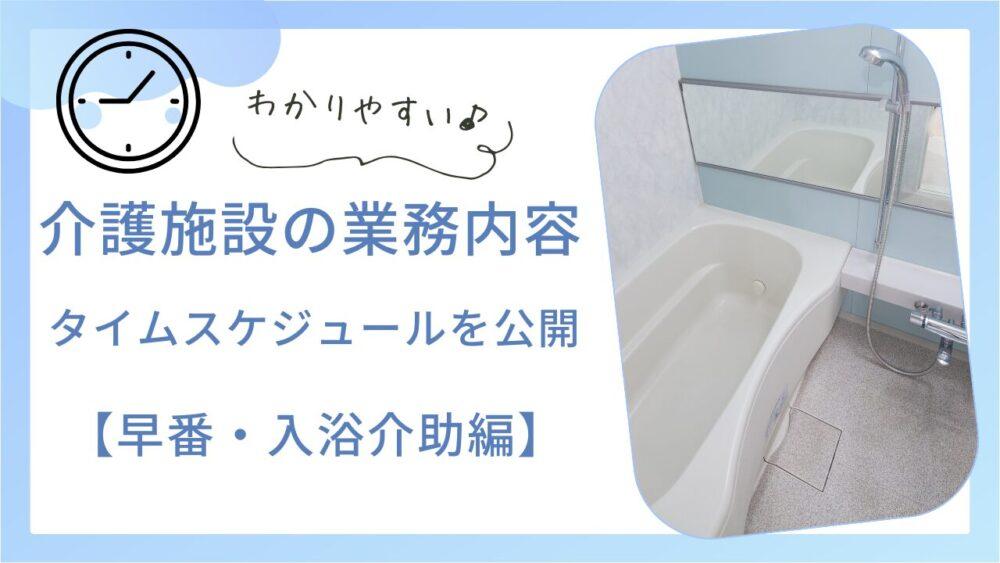
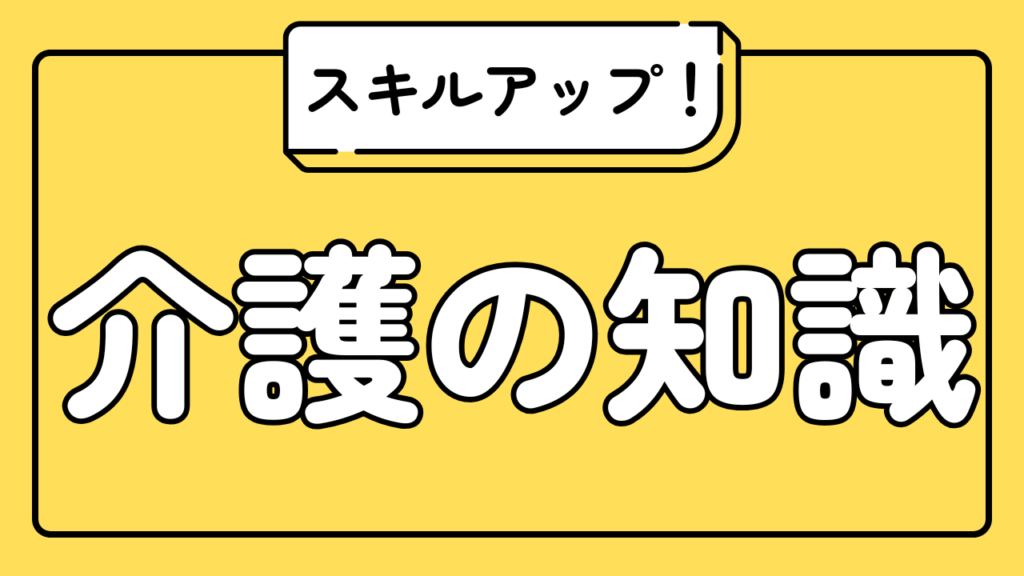



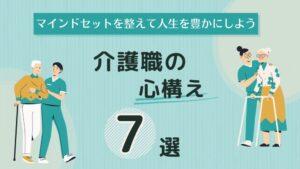
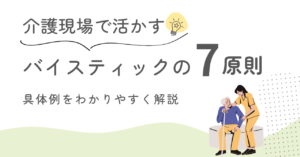


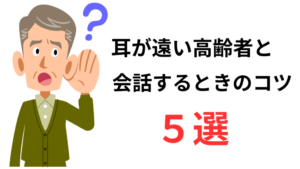




コメント