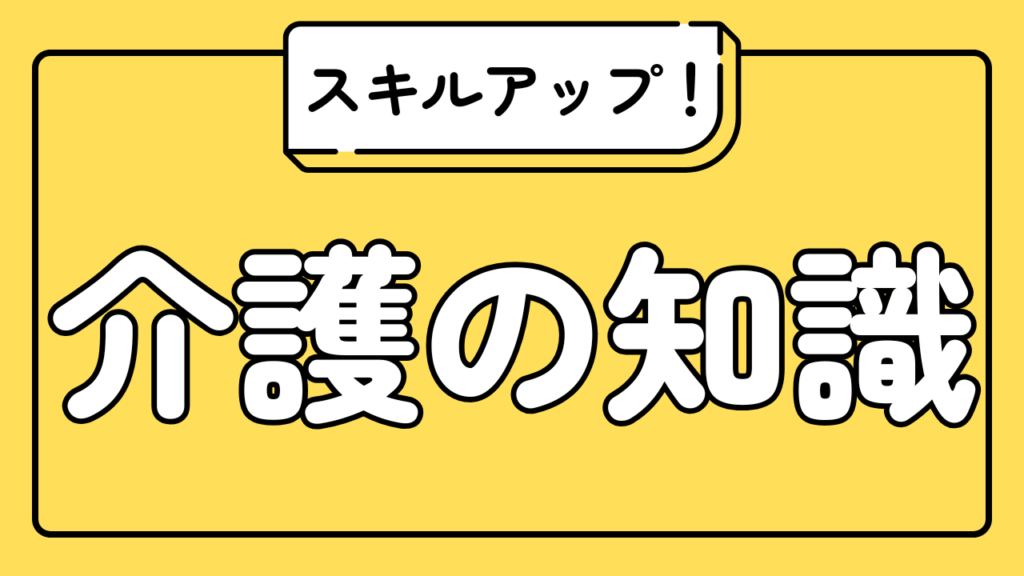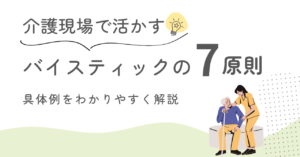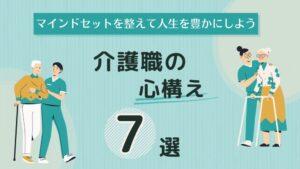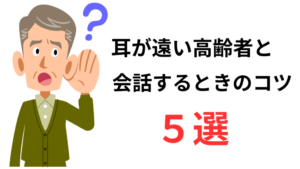介護を始めたばかりのあなたは、
「ちゃんとやらなきゃ」
「失敗できない」
と、不安でいっぱいかもしれませんね。
大丈夫です。
たくさんの技術を覚える前に、たった一つ、大切なことがあります。
それは介護する側の「姿勢」です。
この記事では、ぼくが現場でずっと大切にしてきた、介護の基本10選と、すぐに使える具体的なコツをお伝えします。
- 利用者さんを「できるだけ自分でできるように支える」視点に立つと、安全と尊厳が両立しやすい。
- 迷ったら「①安全 ②説明 ③同意 ④ゆっくり」の順番で進める。
- 介助のうまさは“技術”だけでなく、“態度・言葉・準備”で決まる。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載
介護する側の基本姿勢【10選】



難しく考えなくて大丈夫です。
まずはこの10個を、一つでもいいので意識してみてください。
- あいさつ・名乗り・目線を合わせる
- できていることを見つけて言葉にする
- 「今から何をするか」を短く伝える
- 必ず同意をとってから触れる
- できる部分は任せ、足りない部分だけ手伝う
- ゆっくり・一動作ずつ・数える
- 痛み・不安のサインを観察し、すぐ中止できる構え
- うまくいかない時は介助者がやり方を変える
- できたら具体的にほめて終える
- 後片づけと振り返りをセットにする
1.あいさつ・名乗り・目線を合わせる
部屋に入るときは「〇〇です、おはようございます」。
話すときは、ベッドなら膝を曲げるなどして、相手の目線の高さに合わせましょう。
基本ですが、一番効果があります。



【具体例】
(ベッドで横になっている田中さんの部屋に入りながら)
あなた:「田中さん、こんにちは。ヘルパーの鈴木です。今、お部屋に入ってもよろしいですか?」
(ベッドサイドに膝をつき、田中さんと目線を合わせながら)
あなた:「今日の体調はいかがですか?」
ここがポイント!
立ったまま見下ろすのではなく、少し体をかがめたり、椅子に座ったりして、相手と同じ高さの目線で話すことを心がけましょう。
2.できていることを見つけて言葉にする
「今日は顔色が良いですね」
「ご自分でここまで起きられたんですね!」
など、できている部分、良い部分を見つけて伝えましょう。
誰だって、ほめられると嬉しいものです。



【具体例】
(朝、着替えの介助をしている場面で)
あなた:「佐藤さん、おはようございます!ご自分でパジャマのボタンをここまで外されたんですね。すごいです!」
(食事の場面で)
あなた:「高橋さん、今日はお茶をこぼさずに全部飲めましたね。素晴らしいです!」
ここがポイント!
当たり前だと思えるようなことでも、言葉にして伝えることで、ご本人の「まだできる」という自信につながります。
3.「今から何をするか」を短く伝える
「これから、お着替えをしますね」のように、目的をシンプルに伝えます。
一度に多くの情報を伝えると、混乱させてしまうことがあります。



【具体例】
あなた:「伊藤さん、これから起床後の身支度をしますね。まずはお顔を拭きましょうか」
(NG例:一度に伝えすぎる) 「伊藤さん、これから顔を拭いて、歯を磨いて、服を着替えて、それから食堂に行ってごはんを食べますよ!」 → これでは、何から手をつければいいか分からなくなってしまいます。
ポイント
一つの動作が終わったら、「次は〇〇をしますね」と、その都度伝えるようにしましょう。
4.必ず同意をとってから触れる
「お背中に手をあててもいいですか?」と、体に触れる前には必ず許可をもらいましょう。
これは、相手の心へのノックです。



【具体例】
(車いすへの移乗介助の場面で)
あなた:「渡辺さん、立ち上がるのを支えるために、お背中に手を回してもよろしいですか?」
(相手がうなずくのを確認してから、ゆっくりと触れる)
あなた:「失礼します。ゆっくり支えますね」
ここがポイント!
「いいですか?」と問いかけ、相手のうなずきや「いいよ」という言葉、あるいは表情の変化を確認してから次の行動に移る習慣をつけましょう。
5.できる部分は任せ、足りない部分だけ手伝う
全部やってあげるのが介護ではありません。
「歯ブラシに歯磨き粉はつけられますか?」と聞き、できない部分だけを「では、ここだけお手伝いしますね」とサポートします。



【具体例】
(洗顔の介助をしている場面で)
あなた:「中村さん、タオルを絞るのは難しいですか?では、絞るところだけお手伝いしますね。お顔を拭くのはご自分でできそうですか?」
(中村さんが自分で顔を拭くのを見守る)
あなた:「はい、きれいになりましたね!」
ここがポイント!
「どこまでならできますか?」と質問し、ご本人ができる範囲を見極めることが大切です。少し時間がかかっても、じっと待つ姿勢が信頼につながります。
6.ゆっくり・一動作ずつ・数える(「いち・に・さん」)
急かすのは禁物です。
立ち上がる時など、「いち、にの、さん!」と声をかけると、お互いのタイミングが合いやすくなります。



【具体例】
(ベッドから立ち上がる場面で)
あなた:「小林さん、足元はしっかり床についていますね。では、掛け声に合わせて立ちますよ。準備はいいですか?せーの、いち、にの、さん!」
(ゆっくり力を合わせて立ち上がる)
ここがポイント!
一つひとつの動きを「まず、お尻を少し前に出しましょう」「次にお辞儀をしますね」と分解して言葉にすると、相手も次の動きを予測しやすくなります。
7.痛み・不安のサインを観察し、すぐ中止できる構え
顔をしかめる、体に力が入るなどの小さなサインを見逃さないようにしましょう。
「痛みますか?」と確認し、いつでも中断できる心構えでいましょう。



【具体例】
(腕を動かすリハビリの介助中に、相手の表情が少し歪んだのを見て)
あなた:「あ、木村さん、今のお顔は少し痛そうでした。この角度はつらいですか?」
木村さん:「……ああ、ちょっと」
あなた:「分かりました。すぐにやめましょう。無理は禁物ですからね。角度を少し緩めてみましょうか」
ここがポイント!
常に「何かあったら、いつでも中断できる」という心構えでいましょう。その余裕が、相手の安心感につながります。
8.うまくいかない時は介助者がやり方を変える
相手を責めてはいけません。
「〇〇さんが悪い」のではなく、「このやり方が合わなかっただけ」と考え、「じゃあ、こっちの方法で試してみませんか?」とやり方を変えましょう。



【具体例】
(食事介助で、スプーンを口に運んでもなかなか開けてくれない場面)
(心の声NG例):「なんで食べてくれないんだ…」 → (心の声OK例):「スプーンが合わないのかな?それとも、まだお腹が空いていないのかも」
あなた:「鈴木さん、このスプーンは大きすぎますか?少し小さいものに変えてみましょうか。それとも、先にお茶を一口飲みますか?」
ここがポイント!
一つの方法に固執せず、「時間帯を変える」「道具を変える」「声かけを変える」など、色々な選択肢を試してみるゲームだと考えてみましょう。
9.できたら具体的にほめて終える
「〇〇さんの協力があったので、スムーズに終わりましたね。ありがとうございます!」と、感謝と具体的な賞賛の言葉で締めくくると、次につながります。



【具体例】
(トイレ介助が無事に終わって)
あなた:「山田さん、最後までご自分の足でしっかり立っていられましたね!おかげでズボンの上げ下げがとてもスムーズにできました。ご協力ありがとうございました!」
(NG例:ただ終わらせるだけ) 「はい、終わりましたよ」
ここがポイント!
「すごいですね」だけでなく、「〇〇を頑張ってくださったので、△△がうまくできました」と具体的に伝えることで、相手の自己肯定感が高まります。
10.後片づけと振り返りをセットにする
使ったものを片付けるだけでなく、「さっきはここがうまくいったな」「次はこうしてみよう」と、短く振り返る習慣をつけると、あなたの介護スキルはどんどん上がっていきます。



【具体例】
(介助が終わり、使った車椅子などを片付けながら)
あなた(心の声):「さっきの移乗、車いすの角度が少し遠かったな。もう少しベッドに近づけた方が、斎藤さんも動きやすかったかもしれない。よし、午後はそうしてみよう」
(他のスタッフへの申し送りで) 「午前中の斎藤さんの移乗ですが、少しやりづらそうだったので、午後は車いすの角度を30度くらいにしてみようと思います」
ここがポイント!
失敗を責めるのではなく、「次はどうすればもっと良くなるか?」という視点で振り返ることが、あなたの成長に直結します。
技術より先に「姿勢」を整えると、9割のトラブルは防げる



介護と聞くと、難しい技術や専門知識が必要だと思っていませんか?
もちろん、それも大切です。
でも、もっと大切なのは、介護をするあなたの「姿勢」なんです。
ぼくの経験上、介護現場でのトラブル、たとえば「急に怒り出す」「介助を嫌がる」といったことの9割は、技術不足ではなく、介助する側の姿勢が原因で起こります。
大切なのは、この3つです。
- 先回りしすぎない
- できることを奪わない
- 失敗を責めない
ご本人の「自分でやりたい」という気持ちを尊重する。
この姿勢が土台にあれば、自然と協力関係が生まれます。
具体的には、次の6つのステップを意識するだけで、介護は驚くほどスムーズになります。
- 観察
- 声かけ
- 同意
- 小さく試す
- 見守る
- ほめる
この流れを意識するだけで、相手を尊重する姿勢が伝わり、多くの問題は自然と解決に向かいます。
なぜ介護の姿勢が大事なのか?:4つの理由を解説



「でも、なんでそんなに姿勢が大事なの?」と思いますよね。
理由は4つあります。
- 尊厳:自分で決める権利を守るほど協力が得られやすい
誰だって、自分のことは自分で決めたいものです。たとえ体が不自由になっても、その気持ちは変わりません。
「次は〇〇をしますね、よろしいですか?」と一つひとつ確認するだけで、「あなたを尊重していますよ」というメッセージが伝わり、不思議と協力してくれるようになります。 - 安全:焦り・無言介助が事故の引き金
「早くしなきゃ」という焦りや、何も言わずに体を触られることは、相手をとても不安にさせます。
不安になると、体に余計な力が入り、転倒などの事故につながりやすくなります。
ゆっくり、一つひとつの動作を言葉にしながら行うことが、実は一番の安全対策なんです。 - 信頼:説明と同意で不安が減り、拒否も減る
これから何をされるか分からないのは、とても怖いことです。
「右腕を少し上げますね」と説明し、「いいですか?」と同意を得る。
この積み重ねが「この人は自分を傷つけない、安心できる人だ」という信頼につながり、介助の拒否がぐっと減ります。 - 継続:介助者の心がすり減りにくい(燃え尽き予防)
全部やってあげようとすると、介助する側は疲弊してしまいます。
「姿勢」を大切にすると、「これはご本人に任せよう」「ここまで手伝えば大丈夫」という線引きができるようになります。
頑張りすぎないことで、あなたの心を守り、結果的に介護を長く続けられるようになります。
NG例→OK言い換え(そのまま使えるフレーズ集)



つい言ってしまいがちな言葉を、ちょっと変えるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。
- NG:「ちょっと我慢してください」
OK:「痛くない速さでいきますね。もし痛かったら、すぐに教えてください」 (相手に主導権があることを伝える) - NG:「早くしてください」
OK:「いっしょにゆっくりいきましょう。まず右足から動かしてみますね」 (ペースを合わせ、次の行動を具体的に示す) - NG:「できないですよね?」
OK:「どこまでならご自分でできそうですか?難しいところは手伝いますね」 (できることを前提に質問し、自尊心を守る) - NG:無言で体に触る
OK:「失礼します。手をお借りしますね。少し冷たいですが、右肩に触れますよ」 (触る場所と状況を具体的に予告する) - NG:「転ぶからダメです」
OK:「お一人だと心配なので、安全のために手すりを使ってみませんか?」 (禁止ではなく、代替案を提案する)
詳しく知りたい方はこちら
まず整える“準備の基本”



介護は、始まる前の「下ごしらえ」で8割が決まると言っても過言ではありません。
事故や拒否を減らすための準備の基本です。
- 環境:床のすべり・足元の物をどかす・手すりの位置
まず、動くルートに物がないか確認しましょう。
カーペットの端がめくれていないか、床に水がこぼれていないか。
当たり前のことですが、一番大切です。 - 道具:紙おむつ・手袋・タオルなど“手の届く範囲”に
介助の途中で「あ、あれがない!」と離れるのはとても危険です。
必要なものはすべて、手を伸ばせば届く範囲に準備してから始めましょう。 - 動線:ベッド高さ/車いす位置/足の置き場の確保
ベッドは介助しやすい高さに調整し、車いすは移乗しやすい位置に置きます。
ご本人の足がどこに着地するかもしっかりイメージしておきましょう。 - 声かけ順序:①挨拶 ②目的 ③手順 ④同意 ⑤開始合図
この順番を意識するだけで、相手は安心して介助を受け入れやすくなります。
①こんにちは、〇〇です。
②トイレに行きましょうか。
③まずベッドに座ってから、車いすに移りますね。
④よろしいですか?
⑤では、動きますよ
という流れです。
動作別・介護「基本の型」



ここでは、複雑な技術ではなく、最低限の「型」だけご紹介します。
詳しく介助技術を知りたい方はこちら
立ち上がり
- 足を引く→前に体重→手で支える→「いち・に・さん」で合図
椅子やベッドから立つときは、ご本人のかかとを少し膝の方へ引いてもらうと、力が入りやすくなります。お辞儀をするように体を前に傾けてもらい、合図で立ちます。
移乗(ベッド⇄車いす)
- 角度は30〜45度/フットサポートとブレーキ確認/小さく回す
ベッドと車いすの角度をつけすぎないのがコツです。
必ずブレーキをかけ、足置き(フットサポート)を上げておきます。
大きく動かすのではなく、お尻を軸に小さく回転するイメージです。
更衣・トイレ介助
- 片方ずつ・引っ張らない・痛みのある側は後から
服を脱ぐときは、痛みや麻痺のない「健側(けんそく)」から。
着るときは、痛みや麻痺のある「患側(かんそく)」からです。
「脱健着患(だっけんちゃっかん)」と覚えます。
引っ張らず、衣類をたぐり寄せて介助しましょう。
食事介助
- 座位90°前後・一口量を小さく・むせたら中断と姿勢調整
椅子に深く座ってもらい、少し前かがみの姿勢が理想です。ティースプーンに乗るくらいの量を、ゆっくりと口に運びます。もしむせたら、すぐに中断し、お辞儀をするように少しうつむいてもらいましょう。
さらに詳しく知りたい方はこちら
ケース別・声かけと対応(初心者がつまずく場面)



介護をしていると、どうしても困ってしまう場面が出てきます。
そんな時のヒントです。
- 入浴を嫌がる
「お風呂に入りましょう」と真正面から伝えると、拒否されやすいことがあります。
拒否されたときは、「選べる形」で提案してみましょう。
「お昼からにしますか?夕方にしますか?」
「今日は体を拭くだけにしましょうか?」
など、相手に決定権を渡すことで、受け入れてもらいやすくなります。 - 怒りやすい
まずは物理的に少し距離を取り、深呼吸しましょう。
そして、「〇〇だったんですね」と短い言葉で気持ちを代弁(共感)します。
少し落ち着いたら、「では、こうするのはどうでしょう?」と提案する、という順番が効果的です。 - 認知症のある方
その方が長年続けてきた過去の習慣に合わせると、うまくいくことがあります。
たとえば、朝早く起きて活動する方だったなら、介助も朝中心にする。
台所に立つのが好きだった方なら、食事の準備を少し手伝ってもらう、などです。 - せかす家族への対応
他のご家族から「もっと早くできないの?」と言われることもあるかもしれません。
せかされたときは、感情的にならず「安全のために、この順番で行っています」と簡潔に、毅然と説明しましょう。
介助者のメンタルを守る方法



介護は、介助するあなたの心が健康であってこそ続けられます。
自分を守ることも、大切な介護の一部です。
- 3つのS:Sleep/Share(相談)/Small win(小さな成功の記録)
1.睡眠をしっかり確保すること。
2.一人で抱え込まず、誰かに相談すること。
3.「今日は笑顔が見られた」といった小さな成功を自分でほめてあげること。
この3つを意識してみてください。 - ヒヤリは“責めずに共有”:再発防止は「人ではなく手順を見る」
「ヒヤリとした」「ハッとした」出来事があった時、犯人探しをしてはいけません。
「誰が」ではなく「なぜ起きたか(手順の問題)」に焦点を当てて共有することで、チーム全体の安全性が高まります。 - 申し送りの型:事実→気づき→次回の工夫(30秒で言える形)
他のヘルパーさんや家族に状況を伝える時は、「〇〇がありました(事実)。△△と感じたので(気づき)、次回は□□してみようと思います(工夫)」という形で伝えると、簡潔で分かりやすくなります。
介護職のメンタルケアはこちら
初心者介護士あるある→改善の実例



- 例1:無言で立たせて拒否→「声かけ→同意→合図」で成功
急いでいたAさんは、おじいさんの腕を無言でぐいっと引いて立たせようとしたら、強く拒否されました。
そこで次に、「これから立ちますね、いいですか?せーの、いち、に、さん!」と声かけを徹底したところ、スムーズに立てるようになりました。 - 例2:急がせて転びかけ→「環境整備+一動作ずつ」で安定
Bさんは、おばあさんをトイレに急がせてしまい、床のマットに足を引っかけて転びそうになりました。
それ以来、介助の前には必ず足元を確認し、「まず座りましょう」「次に右足を前に」と一つの動作ずつ声をかけることで、安定して移動できるようになりました。 - 例3:全部やってあげて意欲低下→「任せる部分を決めて回復」
良かれと思って食事から着替えまで全部手伝っていたCさん。しかし、利用者さんはどんどん元気がなくなっていきました。
そこで、「お茶碗を持つ」「服のボタンを一つだけ留める」など、できる部分を任せるようにしたところ、少しずつ表情が明るくなりました。
介護士のあるあるはこちら
よくある質問(Q&A)
- 時間がなくて、どうしても丁寧にできません
-
お気持ちはよくわかります。でも、一番事故につながるのは“急ぎ”と“焦り”です。もし本当に時間がない時でも、「①挨拶」「②(触れる前の)同意」「③(動く時の)合図」の3点だけは死守してください。これだけでも、事故のリスクは大きく減らせます。
- 怒られてばかりで怖いです
-
つらいですよね。それは、あなたが悪いわけではありません。人を変えるのは難しいですが、“やり方”は変えられます。まずは距離を取る、声のトーンを少し低くしてみる、介助の時間帯を変えてみる、2つの選択肢を提案してみるなど、環境やアプローチを少しずつ調整してみましょう。
- 家族からの要求が強くて困っています
-
「安全を最優先に考えているため、この手順で行わせていただきます」と、専門家としての意見を短く、冷静に伝えましょう。そして、行ったことや言われたことを簡単に記録に残しておくと、後々のトラブル防止にもつながります。
- 介助中に失敗したらどうすればいいですか?
-
まずは、すぐに動作を中止し、ご本人とあなたの安全な姿勢を確保(リセット)してください。そして、「ごめんなさい、今のやり方は良くなかったですね」と素直に謝り、「今度は別のやり方をいっしょに試してみませんか?」と提案しましょう。あなたもご本人も、誰も責めないことが大切です。
- 専門知識がなくて、ずっと不安です
-
大丈夫です。誰もが最初は初心者です。まずはこの記事で紹介した「姿勢・準備・手順の型」を意識してみてください。それだけで十分です。分からないこと、困ったことがあれば、一人で悩まずに、必ずケアマネジャーさんや先輩のヘルパーさんなどに質問してください。頼ることも大切なスキルです。
まとめ
今回は、介護の技術よりもっと大切な「姿勢」についてお話ししました。
- 結論:先回りせず、奪わず、責めない姿勢がトラブルを防ぐ
- 基本は「観察→声かけ→同意→小さく試す→見守る→ほめる」の流れ
- 準備と声かけで、事故と拒否は減らせる
- うまくいかない時は、相手ではなく「やり方」を変える
- 介助するあなた自身の心を守ることを忘れない
完璧な介護を目指す必要はありません。
大切なのは、目の前の相手を一人の人間として尊重し、「どうしたら、その人らしくいられるだろう?」と考え続ける姿勢です。
この記事が、あなたの手助けになれば嬉しいです。
頑張るあなたを応援しています。
では、また。
次に読むオススメの記事はこちら