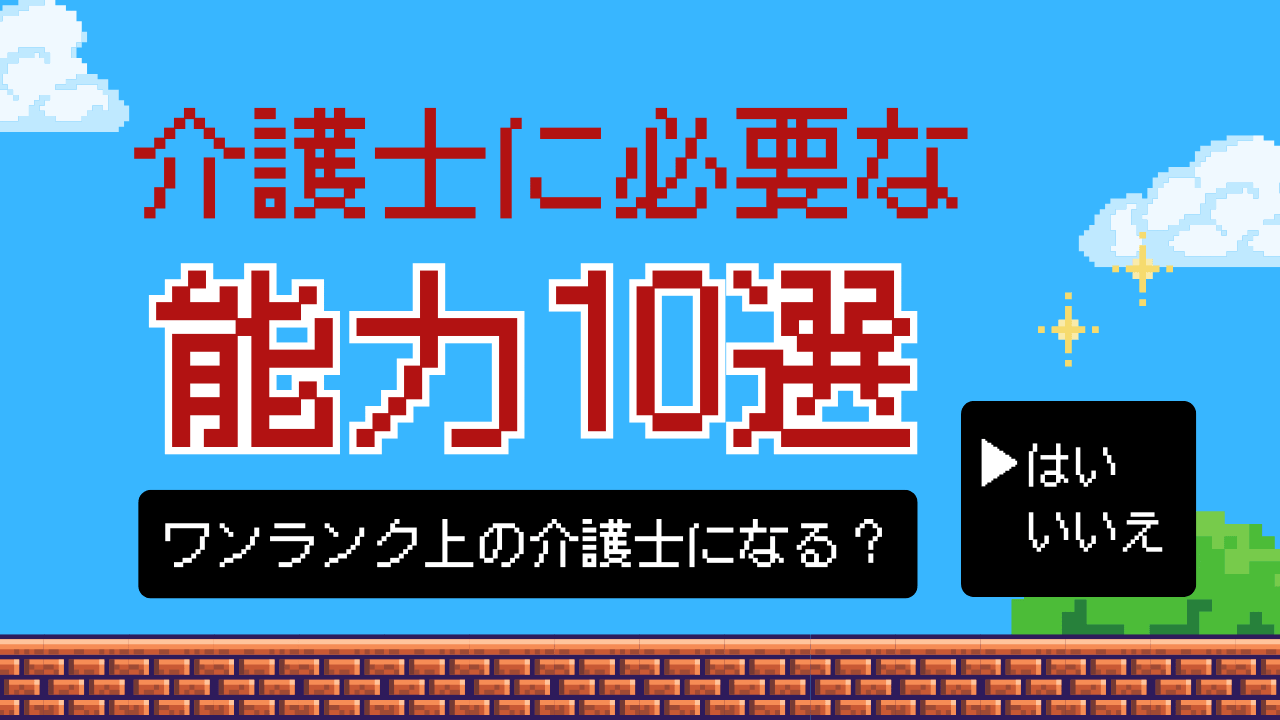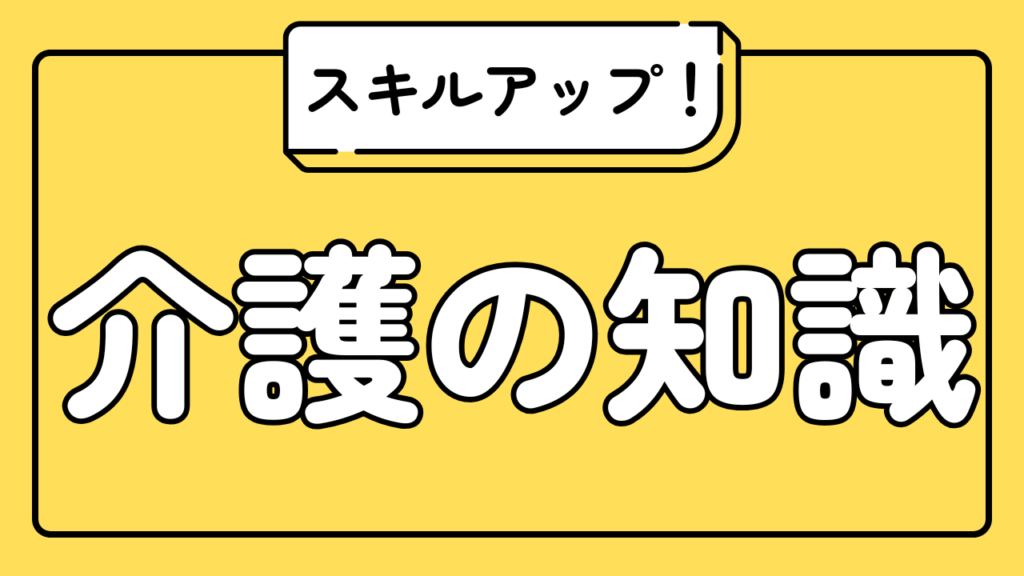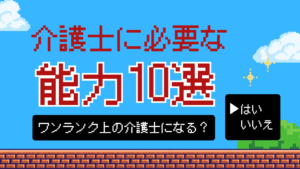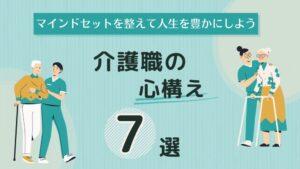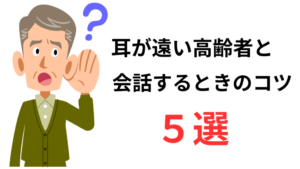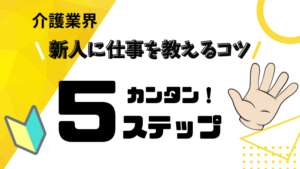当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
 介護士
介護士もっと信頼される介護士になりたい……




スキルアップするには、何を身につければいい?
介護士歴15年以上の筆者が、プロの介護士が持っている10の能力を厳選して紹介します。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー



詳しくはトップページのプロフィールに記載
介護士に必要な能力【10選】
①観察力(小さな変化に気づく力)
観察力とは、利用者の「いつもと違う」状態に気づく力です。
なぜなら、言葉で不調を訴えられない方も多く、ぼくたちが見つける小さな変化が、事故の予防や体調急変の早期発見に直結するからです。
これは、利用者の命と健康を守るための最も基本的なセンサーです。
現場の具体例
- 「いつも完食するAさんの食事量が、今日は2割ほど残っている」
- 「Bさんの歩行を見ると、いつもより歩幅が狭く、少し足を引きずっているように見える」
- 「Cさんと会話中、一瞬だけ表情が曇った。何か心配事があるのかもしれない」
能力の伸ばし方
一日の中で、バイタル、食事、排泄の場面で「いつもと違うな」と感じたことを、最低3件メモする習慣をつけましょう。数字だけでなく、表情や様子の変化を書き留めるのがコツです。
②コミュニケーション力(傾聴・声かけ)
利用者さんと、ただ話すのは素人です。
プロは、相手の話を深く聴き(傾聴)、こちらの意図を相手が受け入れやすい言葉に変換して伝えます。
「傾聴」や「声かけ」がうまいと、利用者さんから信頼され、ケアへの協力が得やすくなります。
その結果、介助拒否を減らすことができるのです。
関連記事はこちら
現場の具体例
- NG例:「(急いでいる時に)〇〇さん、早くしてください!」
- OK例:〇〇さん、この後のお茶の時間、楽しみですね。その前に、上着を着るのをお手伝いしてもいいですか?」
能力の伸ばし方
「でも」「だめ」「早く」といった否定語や命令語を、提案や共感の言葉(「〇〇してみませんか?」「〇〇なんですね」)に言い換えることを意識しましょう。
一日一回、意識するだけで変わります。
関連記事はこちら
③記録力・報連相(短く、抜け漏れなく)
起きた出来事を、客観的な事実に基づいて簡潔かつ正確に伝え、記録する力です。
介護は24時間365日のチームプレー。
ぼくたちが見た情報を正確に共有することが、夜勤のスタッフや次の日の担当者を守り、結果的に利用者の安全を守ることになります。
現場の具体例
急変時の報告で「SBAR(エスバー)」というフレームワークを使います。
- S (Situation): 状況「〇〇さんが居室で転倒しました」
- B (Background): 背景「トイレに向かう途中、足がもつれたようです」
- A (Assessment): 評価「右膝に擦り傷がありますが、意識ははっきりしています」
- R (Recommendation): 提案「看護師に状態の確認をお願いします」
能力の伸ばし方
記録を書く際に、「時刻/起きた事実/自分の対応/利用者の反応(結果)」というテンプレートを意識して、3分以内に書く練習をしましょう。
主観(〜だと思う)ではなく、客観(〜していた)で書くのがポイントです。
関連記事はこちら
④判断力・優先順位付け(安全>尊厳>快適の順で)
複数の業務や利用者の要求が同時に発生した際、何が最も重要かを見極め、行動の順番を決める力です。
介護現場ではナースコールが同時に鳴ることも日常茶飯事。
判断軸がブレると、大きな事故を引き起こします。
現場の具体例
- Aさん「転びそう!」とふらついている(安全)
- Bさん「お茶がほしい」(快適)
- Cさんのシーツが汚れている(尊厳・快適)
上記の場合、①転倒リスクへの対応 → ③汚れたシーツの交換 → ②配茶 の順に対応するのが適切です。
能力の伸ばし方
業務を始める前に、「今日の利用者さんの中で、特に転倒や体調変化のリスクが高いトップ3」を自分の中でメモしておきましょう。
つねにリスクの高い方を意識することで、いざという時の判断が早くなります。
⑤リスク予測・安全管理(ヒヤリを減らす)
「こうしたら危ないかもしれない」と事前に危険を察知し、事故(インシデント)を未然に防ぐための環境整備や声かけをする力です。
起きてしまった事故への対応より、事故を起こさせない環境づくりがプロの仕事です。
関連記事はこちら
現場の具体例
- 利用者がベッドから起き上がる前に、ベッド柵がきちんと下がっているか、ナースコールは手の届く位置にあるかを確認する。
- 食事介助の前に、食形態(刻み食、ミキサー食など)が本人に合っているかを再度確認する。
- 床が濡れていたら、すぐに拭く。
能力の伸ばし方
出勤時や休憩明けに、5分だけ「環境ラウンド」を行いましょう。
「床につまずく物はないか?」
「濡れている場所はないか?」
「車いすのブレーキはかかっているか?」
など、確認する習慣をつけるのが効果的です。
⑥ボディメカニクス・介助技術
ボディメカニクスとは、最小限の力で、安全かつ安楽に利用者を介助するための身体の使い方の技術です。
介助技術は、僕たち自身の腰痛を予防し、介護職を長く続けるために不可欠なスキルです。
また、正しい技術は利用者の身体的負担も軽減します。
関連記事はこちら
現場の具体例
- ベッドから車いすへの移乗介助で、自分の腕力だけで持ち上げず、重心を低くし、利用者の身体を密着させ、てこの原理を使って体重移動を誘導する。
- 滑りの良いスライディングシートやグローブを活用し、摩擦抵抗を減らす。
能力の伸ばし方
一日一回、どんな介助でもいいので、「荷重は体幹(お腹まわり)で支え、腕は誘導に使うだけ」と意識して実践してみましょう。
この意識だけで、身体への負担は大きく変わります。
⑦感染対策・衛生管理
ウイルスや細菌から、抵抗力の弱い高齢者を守るための知識と実践力です。
特に集団生活の場では、一人の感染があっという間に拡大する可能性があります。
当たり前のことを、当たり前に、全員が実践することが施設全体の安全に繋がるのです。
現場の具体例
- ケアの前後、利用者さんに触れる前後など、WHOが推奨する「手指衛生5つのタイミング」で必ず手指消毒を行う。
- 汚染された手袋を外す際に、手袋の表面を素手で触らないように、正しい手順で外す。
動画引用:東京都立病院機構 院内感染対策情報②「手指衛生のタイミング」
能力の伸ばし方
施設の流し台に、「手洗い15秒以上」を意識するためのチェック表やイラストを掲示しましょう。
毎日見ることで、無意識レベルで正しい習慣が身につきます。
⑧認知症理解・行動心理(BPSDの背景を見る)
認知症の中核症状によって引き起こされる行動・心理症状を「BPSD」といいます。
BPSDを、問題行動として捉えるのではなく、その裏にあるご本人の「不安」「混乱」「訴え」として理解しようとする視点が大切です。
なぜなら、背景を理解することで、利用者さんとケンカにならず、本当に求めているニーズに応えることができるからです。
現場の具体例
- 徘徊(独り歩き):ただ歩き回っているのではなく、「何かを探している」「トイレの場所がわからない」「家に帰らなければという不安」などが背景にあるかもしれない。
- 帰宅願望:本当に家に帰りたいのではなく、「夕食の準備をしなければ」といった長年培われた役割を果たしたいという欲求の表れかもしれない。
能力の伸ばし方
気になる言動があった際、次のように考えてみましょう。
- 「ご本人はどう考えている?」
- 「何を心配している?」
- 「ぼくたちに何を期待している?」
を推測し、翌日のケアで仮説を試してみると、関わり方が変わります。
⑨チームワーク・協働(役割分担と感謝の言葉)
介護の仕事は、一人では決して完結しません。
他の職員と円滑に連携し、情報を共有し、互いの仕事を補い合う力です。
良いチームは、個々の職員の負担を減らし、施設全体のケアの質を向上させます。
現場の具体例
- 入浴介助が得意な人と、レクリエーションが得意な人が、互いの強みを活かして役割分担する。
- 忙しい時間帯に手伝ってもらった際、申し送りの場で「〇〇さん、先ほどは手伝ってくれて助かりました。ありがとうございます」と、全員の前で感謝を伝える。
能力の伸ばし方
勤務前の3分間で、その日のメンバーと役割分担を確認しましょう。
たとえば、
「今日はこの時間、私が〇〇さんを見守りますね」
「午後の排泄介助は一緒にお願いします」
といった感じです。
⑩学習習慣・アップデート力
介護保険制度や加算のルール、そして科学的根拠に基づいたケアの技術は、日々変化・進歩しています。
常に新しい知識を学び、自分のケアをアップデートし続ける姿勢が重要です。
実は、学ぶ人ほど介助が楽になり、仕事の質も上がります。
現場の具体例
- 口腔ケアやポジショニング、摂食嚥下(えんげ)に関する新しい知見を研修で学び、現場のケア方法を改善する。
- 新しい福祉用具の情報をキャッチし、利用者の自立支援に繋がる提案をする。
能力の伸ばし方
週に1回、朝礼などの場でアウトプットしましょう。
雑誌で読んだこと、研修で学んだことなど、どんな小さな情報でもいいので、全員で共有する仕組みを作ると、自然と学ぶ文化が育ちます。
よくある勘違い|「優しさだけあれば大丈夫?」



「介護は優しさや思いやりが一番大事」とよく言われます。
もちろん、それは大前提であり、ぼくたちの仕事の核となる部分です。
しかし、優しさだけでは、利用者の安全を守ることはできません。
- 正しい知識に基づいた「安全管理」
- チームで利用者を支えるための「記録と報連相」
この土台があって初めて、あなたの優しさが本当の意味で活きてくるのです。
プロの介護士とは、「優しい人」であると同時に、「利用者の生活と安全をマネジメントできる専門職」なのです。
新人がつまずくポイントTOP5と回避策



- 記録に主観(~だと思う)が多い
- 回避策: 「事実(何時何分、誰がどこで何をした)→自分の対応→利用者の反応(結果)」の順番で書く型を身につける。
- 声かけが命令形・指示形になる
- 回避策: 「~しましょうか?」「AとB、どちらがいいですか?」と選択肢を提示し、相手に選んでもらう形を意識する。
- 焦って一人で仕事を抱え込む
- 回避策: 「すみません、少しだけ手伝ってもらえませんか?」と早めにヘルプを出す練習をする。抱え込む方が、結果的にチームに迷惑がかかることを知る。
- 利用者全員に完璧に対応しようとする
- 回避策: 「安全>尊厳>快適」の優先順位を常に意識する。全員に100点は無理。まずは全員の安全を確保することが最優先。
- 「見て覚えろ」で何をしていいか分からない
- 回避策: 先輩に同行する際、「今は何のために、何をしていますか?」と目的を確認する質問をする。目的がわかると、動きが理解しやすくなる。
現場の声
(男性/30代/介護福祉士) 最初の頃は、力任せの介助で腰を痛めかけた。でも、ボディメカニクスを学んでからは本当に楽になった。自分の身を守る知識こそ、長くこの仕事を続ける秘訣だと思う。利用者さんにも「あなたの介助は安心できる」と言ってもらえた時は、本当に嬉しかったですね。
(女性/20代/新人介護士) 認知症の方への対応で悩んで、毎日泣きそうでした。でも先輩が「行動には全部理由があるんだよ」と教えてくれて。記録を見ながら「この方は夕方になると不安になるから、少し早めにお茶に誘ってみよう」とチームで考えて実践したら、穏やかに過ごしてくれる時間が増えたんです。一人で悩まなくていいんだって思えました。
今日からできる5ステップ(行動計画)



この記事を読んで「なるほど」で終わらせないために、今日からできる具体的なアクションプランを5つ紹介します。
- “いつもと違う”をメモする: (観察力UP)
- 一度だけSBARを意識して報告する: (報連相UP)
- 出勤時に5分間の安全ラウンドを行う: (リスク予測UP)
- 否定語を提案語に一度だけ言い換えてみる: (コミュニケーション力UP)
- 何か一つ、学んだことを誰かに30秒で話す: (学習習慣UP)
SBARは、医療や介護の現場で使われる「報告・連絡・相談の伝え方の型」です。
相手に短く・正確に・抜けなく情報を伝えるための方法で、次の4つの頭文字を取っています。
| 項目 | 意味 | 伝える内容のポイント |
|---|---|---|
| S:Situation(状況) | 今の状況を伝える | 「何が起きているのか」を一言で伝える例:「○○さんがトイレで転倒しました。」 |
| B:Background(背景) | 背景・経過を伝える | 「これまでの経過」や「なぜ今そうなったか」例:「昨晩からふらつきがありました。」 |
| A:Assessment(評価) | 自分の考え・判断を伝える | 観察や記録から自分なりに分析した内容例:「右足に痛みがあり、骨折の疑いがあります。」 |
| R:Recommendation(提案) | どうしてほしいかを伝える | 相手に求める行動を明確に例:「至急、看護師さんの確認をお願いします。」 |
介護の基本【チェックリスト】



【新人介護士向け】基本のチェックリスト
■ 観察・記録
- [ ] 食事、水分、排泄の量と様子を記録したか?
- [ ] 「いつもと違う」と感じたことを最低1つ記録・報告したか?
- [ ] 記録は主観(~と思う)ではなく、客観的な事実で書いたか?
■ 安全管理
- [ ] 介助の前に、利用者の足元に障害物がないか確認したか?
- [ ] 車いすやベッドのブレーキはかかっているか確認したか?
- [ ] 食事介助の前に、正しい食形態か再確認したか?
■ 声かけ・コミュニケーション
- [ ] 何かをお願いする時、命令形ではなく提案・依頼の形で伝えたか?
- [ ] 利用者が話している時、作業の手を止めて少しでも耳を傾けたか?
- [ ] ケアの前に「今から〇〇しますね」と一声かけたか?
■ 感染対策
- [ ] ケアの前後、自分のタイミングで手指消毒をしたか?
- [ ] 手袋やエプロンは、利用者ごとに交換したか?
- [ ] 咳やくしゃみをする時、腕で口元を覆ったか?
■ 腰痛予防
- [ ] 介助の時、自分の身体を相手に近づけたか?
- [ ] 膝を曲げて、重心を低くすることを意識したか?
- [ ] 小さな動きでも、自分の腕力だけに頼らなかったか?
よくある質問(Q&A)
- 未経験でも、これらの能力は本当に身につきますか
-
はい、大丈夫です。ほとんどの能力は、才能ではなく「技術」と「習慣」です。この記事で紹介したようなテンプレートやチェックリストを使って一つひとつ実践すれば、1〜2か月で必ず“抜け漏れ”が減り、成長を実感できます。
- 10個の中で、一番大事な能力は何ですか?
-
ズバリ「観察力」と「報連相(記録力)」です。この2つが全ての土台になります。利用者の小さな変化に気づき、それをチームに正確に伝えることができれば、大きな事故を防ぎ、他のスキルも自然と育っていきます。
- コミュニケーションがもともと苦手なのですが…
-
無理に雑談上手になる必要はありません。まずは、業務に必要な声かけから始めましょう。この記事で紹介した「言い換え表(否定語→提案語)」をポケットに入れて、一日3フレーズでも読んで意識するだけで十分です。相手を尊重する姿勢が伝わることが大切です。
- 毎日忙しくて、学ぶ時間がありません。
-
長時間の勉強は必要ありません。おすすめは「1日30秒の学び共有」です。同僚に「こんな記事読んだよ」と話すだけでも立派な学習です。インプットよりも、共有する仕組みを作ることが、継続のコツです。
- 腰痛が不安で、介護職に踏み出せません。
-
とても重要で、正直な不安だと思います。自己流の介助が一番危険です。「①正しいボディメカニクスを学ぶ」「②スライディングシートなどの福祉用具を積極的に使う」「③一人で無理せず、同僚に協力を求める」この3点セットで、身体への負担は劇的に下げられます。
まとめ
今回は、介護士に必要な10の能力について、ぼくの経験を交えながらお話ししました。
たくさんの能力があって大変だと感じたかもしれませんが、最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。
まずは「いつもと違う」に気づく観察力と、それをチームに伝える報連相から。
この2つを意識するだけで、あなたの仕事は確実に変わり始めます。
介護の仕事は、チームで利用者の生活を支える、専門性とやりがいに満ちた仕事です。
この記事が、あなたのためになれば幸いです。
では、また。