「新人が入っても、すぐに辞めてしまう…」
「教育しているつもりなのに、なぜか定着しない」
「現場が疲弊していて、新人を育てる余裕がない」
管理者やリーダー、教育担当のあなたなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
大切に育てたいと思っていた新人が、ある日突然「辞めます」と切り出す。
あの瞬間の、胸が締め付けられるような感覚は、何度経験しても慣れるものではありませんよね。
この記事は、そんなあなたのために書きました。
ぼく自身の経験と、心理カウンセラーとしての知見を総動員し、なぜ新人が3か月以内に辞めてしまうのか、その根本原因を解き明かします。
そして、「今日から何をすればいいのか」が具体的に分かる、実践的な予防策と育成の仕組みを、まるごとお伝えします。
この記事を読み終える頃には、早期離職を減らし、新人が安心して成長できる職場をつくるための、確かな道筋が見えてくるでしょう。
まずは結論
新人が辞める主因は次の3つです。
- 期待ギャップ
- 教育不足
- 人間関係
これから詳しく解説していきます。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載
【結論】新人が「すぐ辞める」3つの原因は〈期待ギャップ/教育設計の欠如/人間関係〉



新人が辞める理由はいろいろありますが、突き詰めると、次の3つに集約されます。
- 期待ギャップ: 「こんなはずじゃなかった」という理想と現実の乖離。入職前に抱いていたイメージと、実際の業務内容や職場の雰囲気との間に大きな溝がある状態です。
- 教育設計の欠如: 「何を見て学べばいいか分からない」「放置されている」という孤立感。場当たり的なOJTや、体系化されていない教育体制が、新人の不安と無力感を増大させます。
- 人間関係: 「質問しづらい」「先輩が怖い」「ここに居場所がない」という心理的なストレス。ミスを過度に責められたり、気軽に相談できる相手がいなかったりする環境では、新人は心を閉ざしてしまいます。
これらの問題を解決するために、ぼくたちの現場が取り組むべきことは、実はシンプルです。
「やめること」と「始めること」を明確にすれば、道は見えてきます。
- やめること:
- 耳障りの良いことだけを伝える採用活動
- 「見て覚えろ」式の丸投げOJT
- 新人のミスを人前で叱責すること
- 始めること:
- RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)の導入:採用段階で、仕事の良い面も大変な面も、ありのままに伝える。
- “最初の90日”オンボーディング計画の策定:3日、7日、30日…と段階を踏んだ教育計画で、着実な成長をサポートする。
- 心理的安全性の向上:メンター制度の導入や、ポジティブな「言い換え」指導で、何でも話せる雰囲気をつくる。
なぜ新人は短期離職するのか?(心理・組織・現場の3層で分解)



新人の「辞めたい」という気持ちは、決して一つの原因だけで生まれるわけではありません。
心理、組織、そして現場の要因が、複雑に絡み合って生まれます。
それぞれの層で何が起きているのか、分解して見ていきましょう。
心理要因:自己効力感の低下/ミス恐怖/承認の不足
新人は「ここでやっていけるだろうか」という不安と、「役に立ちたい」という期待を胸に入職します。
しかし、専門用語が飛び交い、目まぐるしく状況が変わる現場で、自分の無力さを痛感します。
これが自己効力感の低下です。
「自分は何もできないダメな人間だ」と感じてしまうんですね。
さらに、失敗に対して過度に厳しいフィードバックを受けると、ミスへの恐怖が生まれます。
挑戦する意欲が削がれ、
「言われたことだけやろう」
「余計なことはやめておこう」
と萎縮してしまいます。
そして決定的なのが承認の不足です。
小さな「できた」を見つけてもらえない、頑張りを認めてもらえない。
「ありがとう」の一言がない。
こうした環境では、働くモチベーションそのものが枯渇してしまうのです。
組織要因:OJT不在/役割と期待の曖昧さ/評価とフィードバックの遅さ
組織として「人を育てる仕組み」がなければ、新人は大海に一人で放り出されたような気持ちになります。
教育担当者が日によって違ったり、教え方がバラバラだったりするOJTの不在は、新人を混乱させる最大の要因です。
また、「新人として、いつまでに、何ができるようになればいいのか」という役割と期待が曖昧なままだと、本人は何を目標に頑張ればいいのか分かりません。
そして、入職して1か月、3か月経っても、正式な評価やフィードバックの場がないと、「自分は正しく成長できているのか?」という不安が募ります。
この「放置されている感」が、組織への不信につながります。
現場要因:夜勤投入の早さ/業務量の過多/記録・多重タスクの負荷
心理や組織の問題に加えて、介護現場ならではの物理的な負荷も、新人の心を折る一因です。
特に、十分なスキルや自信が身につかないうちの早すぎる夜勤投入は、強烈なプレッシャーと不安を与えます。
日勤でも、他の職員と同じ過多な業務量をいきなり任されると、一つひとつのケアが雑になり、ミスを誘発します。
利用者さんと向き合う余裕もなく、ただ業務に追われる日々に、「何のために介護職になったんだろう」と疑問を感じ始めます。
さらに、観察、ケア、そして記録という多重タスクの負荷も、新人にとっては大きな壁です。
先輩たちのスピードについていけず、サービス残業で記録を終える…なんてことが続けば、心身ともに疲弊してしまいます。
早期離職が起きやすいタイミングと兆候(1週・1か月・3か月)



新人の離職リスクには、高まりやすい「時期」と、その前に現れる「兆候」があります。
これらを把握しておくことで、手遅れになる前の一手を打つことができます。
時期別に現れやすいリスク
- 入職~1週間:現場の空気・説明不足で不安増
- この時期は、とにかく「不安」が最大の敵です。「挨拶しても返してくれない」「専門用語が分からず会話に入れない」「誰に質問していいか分からない」といった、ささいなことで疎外感を感じます。職場の「空気」に馴染めず、ここで心が折れてしまうケースは少なくありません。
- ~1か月:業務を“ひとりで回す”段階の失敗体験
- 少しずつ独り立ちを求められるこの時期。移乗介助での失敗、利用者からの厳しい言葉、報告・連絡・相談の漏れなど、具体的な失敗体験が心をえぐります。「自分には向いていないのかもしれない」という思いが強くなる危険な時期です。
- ~3か月:人間関係・シフト疲労・報酬不満の顕在化
- 業務に少し慣れてきた頃、今度は別の問題が顕在化します。特定の先輩との人間関係の悩み、不規則なシフトによる心身の疲労、そして「これだけ大変なのに、給料はこれだけか」という報酬への不満です。入職時の緊張感が薄れ、現実的な問題に直面する時期と言えます。
退職の前兆
新人が「辞めたい」と決意する前には、必ず何らかのサインが出ています。
ぼくたち管理職やリーダーは、この小さな変化を見逃さないことが重要です。
一種の“見える指標”として、チェックリスト化しておくことをお勧めします。
- 勤怠の変化: 遅刻や当日欠勤が増え始める。
- コミュニケーションの変化: 口数が減る、朝の挨拶の声が小さい、職員間の雑談の輪に入らなくなる(同僚回避)。
- 業務態度の変化: メモを取る回数が減る、質問がなくなる、指示待ちになる。
- 表情・様子の変化: 表情が硬くなる、笑顔が消える、休憩室で一人でスマホばかり見ている。
これらのサインが複数見られたら、危険信号です。
【予防策】最初の90日が勝負!:オンボーディング計画(3-7-30-60-90日)



場当たり的な教育をやめ、「最初の90日」を大切にデザインすることが、定着率アップの鍵です。
これは、新人が組織にスムーズに溶け込み、戦力化していくまでを支援する「オンボーディング」という考え方です。
オンボーディングとは、新人が早く組織に順応し、活躍できるようにサポートする一連の取り組みのことです。
3日:安心感づくり(歓迎・ペア紹介・業務地図)
- 目標: 「ここは安心して働ける場所だ」と感じてもらう。
- 到達指標: 全職員の顔と名前が一致し、気軽に挨拶ができる。トイレや休憩室の場所が分かる。
- 実践: 歓迎の気持ちを込めたウェルカムボードの設置。教育担当だけでなく、ペアを組む先輩や同僚を紹介する。「業務の全体像(業務地図)」を見せ、今はどの部分を学んでいるのかを明確にする。
- 面談質問例: 「何か困っていること、分からない場所はないですか?」「少しは慣れましたか?」
7日:OJT段階化(観る→一緒に→一人で→振り返る)
- 目標: 基本的な業務の流れを理解し、見守りの下で実践できる。
- 到達指標: 指導者の見守りがあれば、基本的な日中の流れ(起床介助、食事介助など)を一人で実施できる。
- 実践: OJTを「①指導者が見せる(観る)→②一緒にやってみる→③一人でやってみる(見守りあり)→④振り返る」というサイクルで段階的に進める。
- 面談質問例: 「一週間働いてみて、一番大変だと感じたことは何ですか?」「逆に、少しできるようになったと感じることはありますか?」
30日:小さな成功体験(担当固定/役割の明確化)
- 目標: 担当する利用者さんとの関係を築き、「役に立っている」実感を得る。
- 到達指標: 特定のご利用者(2~3名)の担当として、その方のケアプランや個別性を理解し、主体的にケアを実践できる。
- 実践: 比較的安定している利用者さんの担当に固定し、「〇〇さんのことは、△△さん(新人)に任せるね」と役割を明確にする。小さな成功(例:「〇〇さんが心を開いてくれた」)をチーム全体で称賛する。
- 面談質問例: 「担当の〇〇さんについて、何か気づいたことや、もっとこうしたいと思うことはありますか?」「仕事のやりがいは感じられていますか?」
60日:夜勤投入の適正化(先輩ペア固定/難ケース回避)
- 目標: 不安を最小限にして、夜勤業務を安全に遂行できる。
- 到達指標: 必須スキル(チェックリスト参照)をクリアし、先輩とペアで夜勤を2~3回経験する。
- 実践: 夜勤投入前に、日勤帯で緊急時対応のシミュレーションを行う。最初の夜勤は、必ず指導経験豊富な先輩とペアを組み、医療的依存度の高い方や、不穏行動のリスクが高い方の対応は避ける。
- 面談質問例: 「初めての夜勤、どうでしたか?一番不安だったことは何でしたか?」「次の夜勤までに、何か確認しておきたいことはありますか?」
90日:評価・面談・次目標の合意
- 目標: 3か月間の成長を客観的に振り返り、次のステップに向けた目標を共有する。
- 到達指標: 評価シートに基づき、できるようになったこと・今後の課題を上長と本人が共有し、合意できる。
- 実践: 正式な評価面談の場を設ける。できたことを具体的に褒め、課題は「一緒にどう乗り越えるか」という視点で伝える。次の3か月の目標(例:レクリエーションの企画、特定の委員会への参加など)を一緒に設定する。
- 面談質問例: 「この3か月で、一番成長したと感じる点はどこですか?」「今後、どんな介護職員になりたいですか?そのために、私たちがサポートできることは何でしょう?」
【入職前にやるべきこと】期待ギャップを埋めるRJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)



早期離職の最大の原因である「こんなはずじゃなかった」を防ぐには、採用段階での正直な情報提供、つまりRJP(Realistic Job Preview)が不可欠です。
RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)とは、「現実的な仕事情報の事前開示」のことです。採用時に、求職者に対して業務内容や組織環境の良い面だけでなく、厳しい面もリアルに伝えることで、入職後のギャップを最小限に抑えます。
つまり、会社の良い面だけを伝えて採用しても、働いて悪い面を知って辞めていくということです。
症状の重い日/忙しい時間帯も“見せる”
見学や面接では、つい落ち着いた時間帯を選びがちです。
しかし、あえて食事や排泄介助で最も慌ただしい時間帯や、認知症の方のBPSD(行動・心理症状)が出ている場面なども、許可を得た上で少しだけ見せることが大切です。
「私たちの仕事には、こういう大変な瞬間もあります」と正直に伝えることで、覚悟が生まれます。
できること・できないことの線引き
「うちは残業ゼロです」「人間関係は最高です」といった、現実と乖離したアピールは禁物です。
「残業は月平均〇時間程度あります」「職員同士、意見がぶつかることもありますが、必ずケア会議で話し合って解決しています」のように、できないことや課題も正直に伝え、どう向き合っているかを示すことが信頼につながります。
“1日の流れ”動画・職員座談会・職場体験の設計
- 1日の流れ動画: 若手職員に協力してもらい、出勤から退勤までのリアルな仕事風景をスマホで撮影・編集した短い動画を見せる。
- 職員座談会: 年齢や経験の近い先輩職員と、応募者が気軽に話せる場を設ける。「実際、何が一番大変ですか?」といった本音の質問に答えてもらう。
- 職場体験(シャドーイング): 半日~1日、職員の「影」のように付き添い、実際の業務を間近で見てもらう。ケアの実践はさせず、観察に徹してもらうことで、職場のリアルな空気を感じてもらいます。
【職場体験チェックリスト&同意事項】
見学者に渡すチェックリストとして、
- 職員の表情はどうか
- 利用者さんと職員の会話の内容
- 職場の清潔さ
などを確認してもらうと、より深い理解につながります。
また、守秘義務に関する同意書は必ず取り交わしましょう。
【教育と支援】OJTの標準化/メンター制度/心理的安全性づくり



新人が安心して成長するためには、「教育の質」と「人間関係の質」が大切です。
OJT手順書:観察→模倣→実践→振り返り(各10~20分の短サイクル)
「見て覚えろ」ではなく、標準化された手順でOJTを進めます。
ぼくのおすすめは、一つの業務(例:車椅子への移乗)を、短いサイクルで繰り返す方法です。
- 観察(10分): まず指導者がやってみせる。「今から〇〇さんの移乗をします。ポイントは3つです」と要点を宣言してから実践する。
- 模倣(10分): 「じゃあ、今度は一緒にやってみましょうか」と、指導者が補助しながら新人にやってもらう。
- 実践(10分): 「次は一人でやってみましょう。すぐそばで見ているので、安心して」と、見守りの下で実践させる。
- 振り返り(5分): 「今の移乗、すごくスムーズでしたね。特に〇〇の動きが良かったです。次は△△を意識すると、もっと楽になりますよ」と、すぐにフィードバックする。
この短サイクルを繰り返すことで、新人は着実にスキルを習得し、自信をつけていきます。
メンターの役割・NG(叱責・陰口・放置の禁止)
メンター(相談役の先輩)は、技術指導をするOJT担当者とは別に、精神的なサポート役を担います。
- 役割: 仕事の悩みだけでなく、プライベートな相談にものる「お兄さん・お姉さん」的な存在。週に1回、15分程度の「メンター面談」を設定し、新人が溜め込んでいる不安や不満を吐き出す場をつくる。
- NG行動の徹底:
- 叱責の禁止: メンターは味方であり、叱る役ではありません。
- 陰口の禁止: 他の職員や新人の悪口を絶対に言わない。
- 放置の禁止: 忙しくても、意識的に声をかける。
声かけテンプレ(行動+根拠+称賛/訂正の言い換え例)
声かけの質が、新人の自己効力感を大きく左右します。
ぼくが心理カウンセラーとして意識しているのは、「具体的に、ポジティブに」伝えることです。
- 【称賛の例】
- (NG)「いいね!」→(OK)「さっきの〇〇さんへの声かけ、目線を合わせて話していたから、〇〇さんも安心してましたね。素晴らしいです」
- 【訂正の言い換え例】
- (NG)「なんで報告しなかったの!」→(OK)「あの件、もし先に一言相談してくれたら、ぼくも一緒に考えられたんだけどな。次からは、迷ったらすぐに声をかけてね」
- (NG)「やり方が違う!」→(OK)「そのやり方もあるんだね!もしよかったら、こっちの方法だと腰の負担が減るから、一回試してみない?」
【勤務設計】夜勤投入のタイミング/シフト公平性/ペアリング



不規則で負担の大きい勤務は、離職の直接的な引き金になり得ます。
特に夜勤は慎重な判断が必要です。
初夜勤までの必須項目(チェックリスト)
いきなり夜勤に入れるのは絶対にNGです。
以下の項目をクリアできているか、本人と指導者の双方で確認するチェックリストを作成しましょう。
- 担当フロア全員の顔と名前、基本的な特性を理解している
- バイタルサインの異常値を理解し、報告できる
- 主要な移乗介助を一人で(または適切な福祉用具を使って)安全にできる
- 介護記録を一人で時間内に書くことができる
- 緊急時(急変、火災、地震)の連絡先と初期対応マニュアルを理解している
負荷の波を平準化(“最初の山”を避ける配置)
新人のうちは、連休明けや、特に手のかかるご利用者が多い日など、業務負荷が高いと予測されるシフトからは意図的に外す配慮が必要です。
最初の3か月は、「深夜勤→休み→早番」のような、心身への負担が大きいシフト組みも避けるべきです。
フェア感の担保(希望聴取→理由説明→合意)
シフトの不公平感は、職員全体の不満につながります。
希望休はできる限り聴取し、もし通らない場合は、必ずその理由を説明することが大切です。
「〇〇さんが研修で、△△さんも希望休だから、今回はごめんね」と一言伝えるだけで、納得感は大きく変わります。一方的なシフト提示ではなく、説明と合意を心がけましょう。
【安全と尊厳】ハラスメント・暴力への対応



残念ながら、介護現場では利用者さんやそのご家族から、暴言・暴力・セクシャルハラスメントなどを受けることがあります。
新人がこのような事態に遭遇したとき、組織が全力で守る姿勢を示すことが、何よりも重要です。
その場の安全確保→報告→記録→ケア会議
- その場の安全確保: 新人をすぐにその場から離し、他の職員と交代する。一人にしない。
- 上長への即時報告: どんなに些細なことでも、必ず上長に報告するよう義務付ける。
- 客観的な事実の記録: 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確に、感情を交えずに記録する。
- 緊急ケア会議の開催: 関係者で状況を共有し、組織としての対応を協議する。
被支援者・家族への説明/職員保護/外部窓口
組織として、毅然とした態度で対応します。
状況に応じて、ご利用者本人やご家族に事実を伝え、改善を求めます。
職員を守るためには、担当を一時的に外したり、複数名で対応したりする措置が必要です。
また、職員が精神的なショックを受けた場合は、産業医や外部のカウンセリング窓口につなぐ体制も整えておきましょう。
【通報・相談ラインの明示】 直属の上長に言いにくい場合を想定し、「さらにその上の上長」や「本部の相談窓口」など、複数の相談ルートを明記したカードを配布しておくと、新人は安心できます。
【早期介入】退職の前兆を見つけたときの対応:48時間以内に介入しよう



「あれ?」という前兆を見つけたら、スピードが命です。
問題が深刻化する前に、48時間以内に介入する仕組みを作りましょう。
- 観測: チェックリストに基づき、「遅刻が増えた」「口数が減った」などの兆候を客観的に観測する。
- 即時声かけ: 「最近、少し元気ないように見えるけど、何かあった?」と、その日のうちに、人目につかない場所で声をかける。
- 1on1面談(15分): 翌日までに15分程度の短い面談時間を確保する。
- マイクロ調整: 面談で出てきた課題に対し、すぐにできる小さな調整を行う(例:ペアを組む相手を変える、次のシフトを少し楽にするなど)。
- 再評価: 1週間後、再度短く面談し、状況が改善したかを確認する。
面談質問リスト(事実→感情→ニーズ→合意)
この面談は、詰問の場ではありません。本人の気持ちに寄り添い、解決策を一緒に探すための時間です。
- 事実の確認: 「最近、〇〇ということがあるように見えるんだけど、何か業務で困っていることはあるかな?」
- 感情の傾聴: 「そうか、それは大変だったね。その時、どんな気持ちだった?」
- ニーズの探索: 「もし、ぼくたちに何かできることがあるとしたら、どんなことだろう?」
- 解決策の合意: 「じゃあ、まず明日から〇〇を試してみるのはどうかな?」
【やってはいけない】新人指導のNG行動集



良かれと思ってやっていることが、実は新人の心を折っているケースは少なくありません。
これらの行動は、今日から意識してやめましょう。
- 公開叱責: みんなの前でミスを指摘する。
- →代替行動: 後で個別に、事実と改善策を冷静に伝える。
- “できて当たり前”の前提: 「こんなことも知らないの?」という態度。
- →代替行動: 「これは専門的なことだから、知らなくて当然だよ。今から説明するね」と前置きする。
- 曖昧な指示: 「あれ、やっといて」「適当によろしく」
- →代替行動: 「〇〇さんの排泄記録を、15時までに、このフォーマットで入力しておいてください」と具体的に指示する。
- 丸投げ・放置: 「じゃあ、あとよろしく」と言って、その場を離れる。
- →代替行動: 「まずは一人でやってみて。終わったら必ず声をかけて。一緒に確認しよう」と伝える。
- 陰口・無視: 新人がいないところで噂話をする。挨拶を返さない。
- →代替行動: 良いところを見つけて、本人の前でもいないところでも褒める。意識して挨拶する。
【ケース別対処】属性・雇用形態・配属別のつまずきと対応



新人と言っても、背景は様々です。
属性に合わせた「最初の一歩」を工夫することで、つまずきを減らすことができます。
10代・20代未経験/元・別業界からの転職
- つまずきポイント: 社会人としての基礎マナー(報告・連絡・相談など)や、介護への理想と現実のギャップ。
- 最初の一歩: 介護技術の前に、「職場のルール」や「報告のタイミング」を具体的に教える。成功体験を積ませ、こまめに褒めて自己効力感を育む。
中途ベテラン(前職ルールとの衝突)
- つまずきポイント: 前の職場のやり方に固執し、「うちのやり方」に反発する。
- 最初の一歩: まずは相手の経験に敬意を払い、「〇〇さんのいた施設では、どうやっていたんですか?」と傾聴する。その上で、「うちではこういう理由で、この方法を取っているんです」と根拠を丁寧に説明する。
外国籍スタッフ(言語・文化・手順の視覚化)
- つまずきポイント: 言葉の壁によるコミュニケーション不足。介護観や文化の違い。
- 最初の一歩: 難しい漢字にはルビを振る。手順書は写真やイラストを多用して視覚化する。「やさしい日本語」で、ゆっくり、はっきり話す。各国の文化を尊重し、学び合う姿勢を見せる。
夜勤専従・短時間パート(連続性の担保)
- つまずきポイント: 他の職員との情報共有が不足し、孤立しやすい。断片的な情報でケアに入り、ミスが起きやすい。
- 最初の一歩: 専用の連絡ノートや、ITツール(LINE WORKSなど)を活用し、情報共有の仕組みを強化する。月に一度は日中のミーティングに参加してもらうなど、意図的に接点を作る。
【現場で使える付録】テンプレ・チェックリスト一式
これらのツールを現場で活用することで、教育の標準化と抜け漏れ防止が可能です。
H3-1. 3-7-30-60-90日オンボーディング表
| 時期 | 目標 | 主な取り組み | 面談での確認事項 |
| 3日 | 安心感の醸成 | 職員紹介、館内案内 | 困っていることはないか? |
| 7日 | 基本業務の理解 | OJT(観る→一緒→一人) | 一番大変な業務は? |
| 30日 | 成功体験 | 担当利用者の決定 | 仕事のやりがいは? |
| 60日 | 夜勤デビュー | 夜勤スキルチェック、ペア夜勤 | 夜勤への不安は? |
| 90日 | 振り返りと次目標 | 評価面談、次ステップ設定 | 3か月での成長点は? |
OJT記録フォーマット
- 業務名: 車椅子への移乗
- ①観る: 指導者がポイントを説明し実践(□チェック)
- ②一緒に: 指導者と新人で実践(□チェック)
- ③一人で: 新人が一人で実践(見守りあり)(□チェック)
- ④振り返り: できた点、次の課題をフィードバック(コメント記入)
1on1面談スクリプト(10問セットから抜粋)
- 最近、仕事でうまくいったことは何ですか?
- 逆に、ちょっと難しいなと感じていることはありますか?
- 体調や睡眠はしっかりとれていますか?
- 職場の人間関係で、何か気になっていることはありませんか?
- 何か、私(上司)に手伝えることはありますか?
新人観察チェックリスト(前兆シグナル)
- □ 遅刻・欠勤が(以前より)増えた
- □ 挨拶の声が小さい、または挨拶がない
- □ 質問や相談がなくなった
- □ 表情が硬く、笑顔が見られない
- □ 休憩時間に一人でいることが増えた
RJP見学チェックリスト&同意テンプレ
- 見学チェック項目: ①職員同士の会話の雰囲気は? ②ご利用者の表情は穏やかか? ③忙しい時間帯の職員の動きはどうか?
- 同意事項: 私は、見学中に知り得た個人情報(ご利用者、職員に関する情報)を、決して口外しません。(署名欄)
よくある質問(Q&A)
- どのタイミングで夜勤に入れるのが適切?
-
本人の習熟度と自信が大前提ですが、目安として入職後2~3か月後です。日勤業務を一人で回せ、緊急時対応を理解してから、必ず経験豊富な先輩とのペア勤務で始めましょう。
- 新人のミスが続くときの声かけは?
-
まず「大丈夫?」と心身の疲労を確認し、決して感情的に叱らないでください。「なぜミスが起きたか」を本人と一緒に振り返り、「次はこうしてみようか」と具体的な対策を一緒に考える姿勢が大切です。
- メンターは誰が向いている?兼務は?
-
年齢が近く、傾聴力があり、ポジティブな姿勢の3~5年目くらいの先輩が理想です。技術指導をするOJT担当者とは別の職員が担当し、役割を分けることで、新人は本音を話しやすくなります。
- 定着率の目安と改善の測り方は?
-
まずは「入職後3か月以内の離職率」を指標にしましょう。例えば、年間10人採用して3人が3か月以内に辞めたら離職率30%です。オンボーディング計画導入後、この数値がどう変化したかを半年、1年単位で追跡します。
- ハラスメントを受けた新人の保護と記録の仕方は?
-
最優先は、本人をその場からすぐに離して安全を確保し、一人にしないことです。記録は、5W1Hを使い、客観的な事実のみを時系列で淡々と記述します。本人の精神的ケアを第一に考え、組織として対応しましょう。
- 短時間パートの教育をどう設計する?
-
勤務時間が短くても、情報共有とOJTの仕組みは必須です。連絡ノートやITツールで「前回の勤務からの変更点」を必ず共有し、出勤時に短時間のOJTサイクル(観る→やる→振り返る)を計画的に組み込みましょう。
- 外国籍スタッフの教育のコツは?
-
手順書をイラストや写真で「見える化」すること、そして「やさしい日本語」を使うことが基本です。文化的な背景の違いを尊重し、「日本ではこうする理由」を丁寧に説明すると、理解が深まります。
まとめ
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
新人がすぐに辞めてしまうのは、本人の根性がないからではありません。
- 期待とのギャップ
- 教育の仕組みの欠如
- 人間関係
という、ぼくたち受け入れ側の問題が大きく影響しています。
しかし、これらは現場の工夫で必ず改善できます。
新人が「ここで働き続けたい」と思える職場は、既存の職員にとっても働きやすい職場のはずです。
では、今日から何を始めればいいか。
まずはこの3つから試してみませんか?
- 朝の挨拶+一言の声かけ: 出勤してきた新人に、「おはよう!昨日はよく眠れた?」と、プラスアルファの声かけをしてみてください。
- OJTの段階化を意識する: 何か一つ教えるときに、「まず見ててね」とやって見せることから始めてみてください。
- 週に1回、5分の雑談タイム: 業務の話でなくても構いません。「最近どう?」と、短くてもいいので、1対1で話す時間を作ってみてください。
小さな一歩が、あなたの職場を、そして介護の未来を、きっと変えていくと信じています。
ぼくも、現場の一員として、あなたの挑戦を心から応援しています。
では、また。

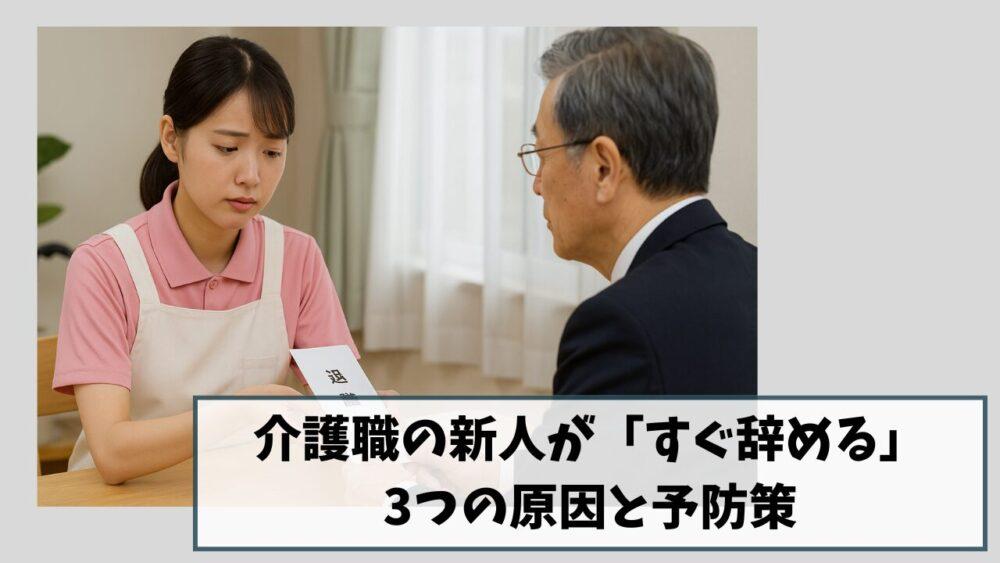

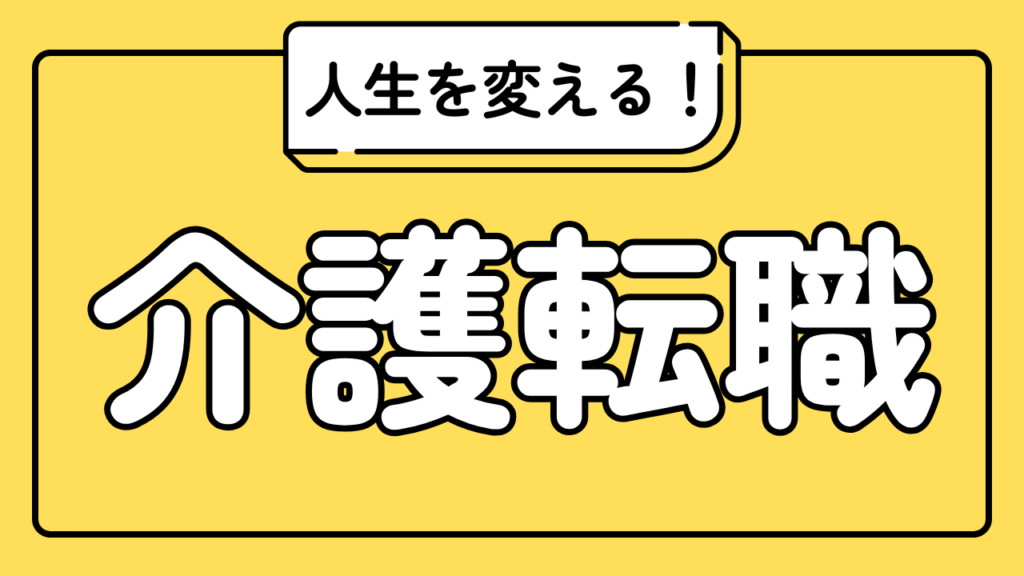






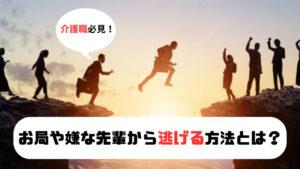
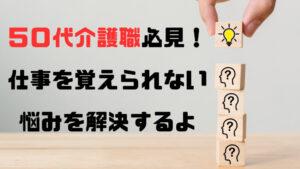
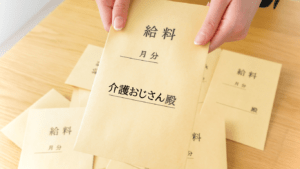
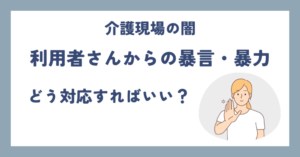

コメント