 介護士
介護士また、あの先輩と一緒のシフトか…
朝、出勤前にシフト表を見て、思わずため息をついてしまう。
介護の仕事自体は好きだし、ご利用者さんの笑顔を見るのは何よりのやりがい。
でも、特定の先輩の言動ひとつで、その日の気力をごっそり持っていかれる…。
介護現場で15年以上働いているぼくも、そんな経験を何度もしてきました。
あなただけではありません。
これは、多くの介護職が通る道なんです。
よくある悩みの具体例
- 高圧的な物言い: 「なんで、そんなこともできないの?」「前に教えたよね?」と、皆の前で必要以上に強く叱責される。
- 理不尽な指摘: その先輩の「やり方」が全てで、少しでも違うと「勝手なことしないで」と怒られる。マニュアル通りなのに…。
- 責任転嫁・丸投げ: 面倒な業務や難しいケースを押し付けてきて、うまくいかないと「あなたのやり方が悪い」と責任をなすりつけられる。
- 陰口・無視: 他の職員と自分の噂話をしたり、挨拶しても無視されたりする。明らかに自分だけ態度が違う。
- 指示が曖昧: 「あれ、やっといて」と曖昧な指示なのに、後から「なんでこうやったの?」と文句を言われる。
一つでも当てはまるなら、あなたは今、相当なストレスを抱えているはずです。
そのままだと、仕事へのモチベーションが下がるだけでなく、心身の健康を損なうことにもなりかねません。
この記事では、あなたが苦手な先輩との関係でこれ以上消耗しないための、具体的で実践的な方法を解説します。
感情論で「気にしないように頑張ろう」と無理をするのではなく、「仕組み」と「スキル」で自分を守る技術が手に入ります。
読み方ガイド
この記事はかなり具体的で、ボリュームもあります。
あなたの状況に合わせて、必要な部分から読んでみてください。
- 今すぐ現場で使える言葉や動き方を知りたい方は、「今日からできる即効テク」へ。
- 誰に、どう相談すればいいか手順を知りたい方は、「相談フロー」へ。
- 具体的な言い方の例を見たい方は、「テンプレ集」をご活用ください。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY



詳しくはトップページのプロフィールに記載
関連記事はこちら
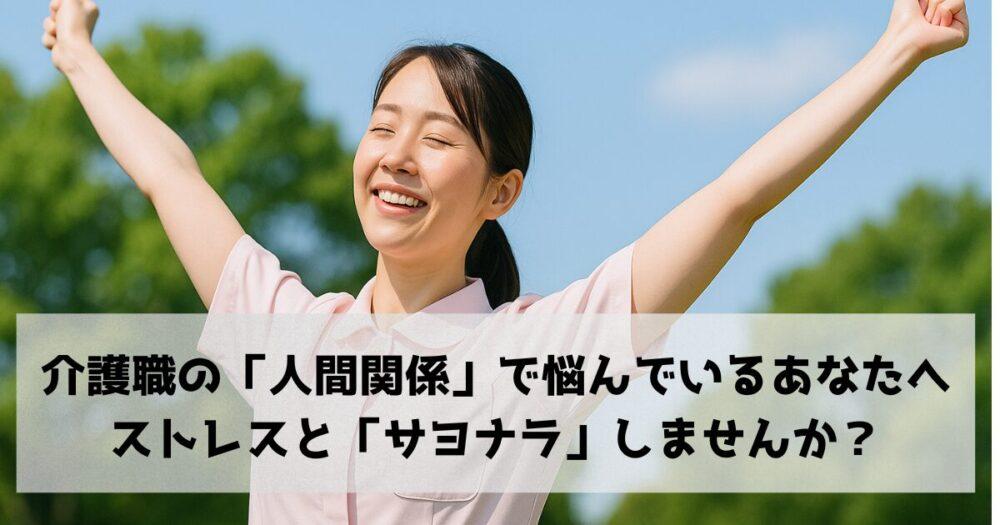
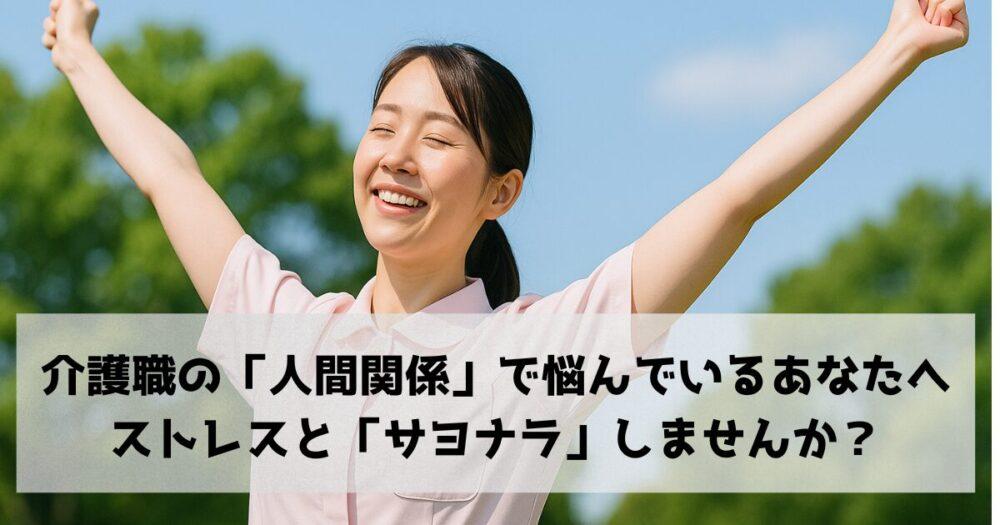
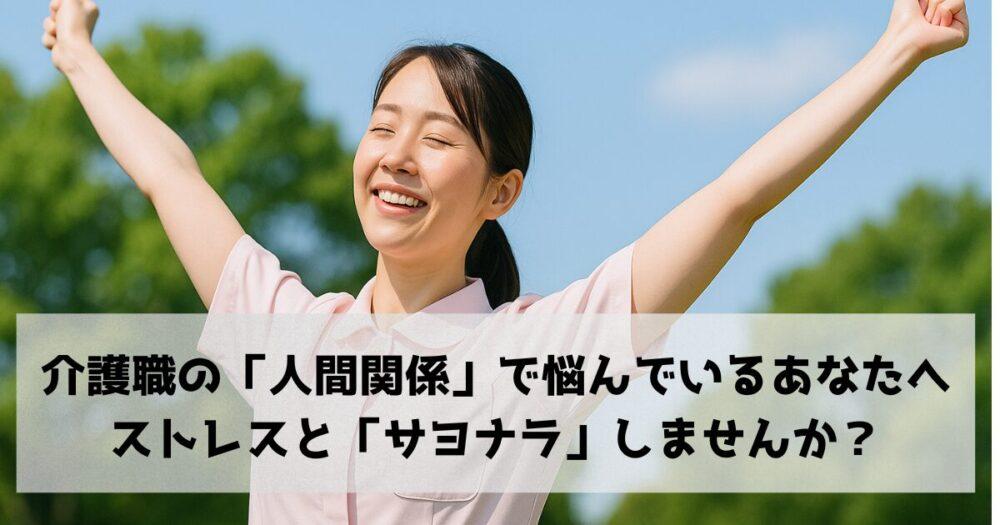
苦手な先輩のストレス対処法【4ステップ】



結論から言います。
苦手な先輩によるストレスから抜け出すための最短ロードマップは、次の4つのステップを順番に、かつ同時に進めることです。
感情で戦うのではなく、冷静な戦略で自分を守りましょう。
ステップ1|距離を取る
ねらい:ムダに近づかない。心の体力を守ります。
- これは「無視」ではありません。自分を守るバリアです。
- 次の3つを先に決めて固定します。
- 関わり方:必要な話だけにする/仕事の話だけにする
- タイミング:朝の申し送りのときだけ話す など
- 方法(チャネル):口頭よりメモやチャットを使う
- 事例:
- 「連絡はチャットにお願いします」
- 「この件は午前の申し送りで確認します」
ステップ2|記録する(事実だけ)
ねらい:気持ちではなく、事実で自分を守る。
- 「怒りのメモ」ではなく、客観的なメモにします。
- 形(フォーマット)を同じにすると続けやすいです。
- ①いつ(日時)
- ②どこで/だれと
- ③何があったか(言葉・行動)
- ④影響(仕事が止まった/心がつらい など)
- ⑤自分の対応(伝えた/上司に相談 など)
- 事例:
- 7/28 14:10 休憩室/A先輩/「遅い」と大声。配膳が3分遅れ。利用者さん対応が遅れた。自分は「次回は先に声をかけます」と返答。記録。
ステップ3|相談する
ねらい:一人で抱えない。正しく助けを借ります。
- いきなり一番上の人に行くより、信頼できる順で。
- 同僚(事実を一緒に確認)
- リーダー/主任(対応の相談)
- 管理者(仕組みや配置の調整)
- 必要なら外部相談(労務相談窓口など)
- 相談するときはステップ2の記録を見せるとスムーズです。
- 伝え方の型:
- 「事実:〇〇がありました。影響:□□でした。希望:次回は△△にしたいです。ご相談させてください。」
ステップ4|技術で対応(言い方&動き方)
ねらい:“強すぎず弱すぎず”上手に伝え、巻き込まれない。
A. 言い方(アサーティブ)の型
- お願い:「今2分いいですか。◯◯の件は書面で確認したいです。」
- 境界線:「その言い方は困ります。仕事の手順の話に戻してください。」
- 提案:「次回からは、始業前に指示をまとめてチャットでください。」
- 断る:「この方法では安全が保てません。手順書どおりで進めます。」
B. 巻き込み回避の“動線”づくり
- 連絡は記録が残る方法(チャット・メール)に統一
- 指示はメモで再確認(「受け取りました。こう進めます」)
- 担当・期限・方法を見える化(共有ボード/カレンダー)
- 第三者を入れる(報連相に上長や同僚をCC)
4ステップまとめ
- ①距離のルールを守る
- ②事実の記録を続ける
- ③相談の階段で助けを借りる
- ④言い方と動き方で巻き込まれない
この4ステップを同時に少しずつ続けると、感情で戦わずに冷静に自分を守ることができます。
なぜ「感情論」より「仕組み+スキル」が有効なのか



「もっとうまくやらないと」
「自分が我慢すれば…」そう考えていませんか?
でも、問題の本質はあなたの“感情の持ち方”だけにあるわけではありません。
人間関係の摩擦は再現性のある「場面」で起きる
苦手な先輩とのトラブルは、ランダムに起きるわけではありません。
- 申し送りの時
- ケアの方法で意見が違う時
- 忙しい時間帯
など、特定の「場面」で繰り返し発生する傾向があります。
つまり、その場面ごとに「こう動く」「こう言う」という対処法をあらかじめ用意しておくことで、感情が揺さぶられる前に対処できるのです。
介護現場特有のストレス
介護現場は、ストレスが生まれやすい構造をしています。
- 多職種連携: 価値観の違う専門職が一緒に働く難しさ。
- シフト制: 生活リズムが不規則になり、心身が疲れやすい。少人数になる夜勤では逃げ場がない。
- 緊急対応: 予測不能な事態が多く、常に緊張を強いられる。
- 権限の曖昧さ: 「誰の指示が最終決定なのか」が不明確で、板挟みになりやすい。
こうした環境が、個人のストレスを増幅させます。
つまり、あなたが「苦手」と感じるのは、個人の相性だけでなく、この環境要因も大きいのです。
だからこそ、個人の気合だけでなく、仕組みで解決する視点が必要です。
反応しない技術
理不尽なことを言われた時、カッとなって言い返したり、逆に黙り込んでしまったりするのは、感情的な「反応」です。
感情的な反応は、相手にさらなる攻撃の口実を与えたり、「何を言っても平気な相手」だと思わせたりして、事態を悪化させてしまいます。
大切なのは「反応」するのではなく、一呼吸おいて、意図的に「対応」すること。
そのために、感情の波に乗りこなす技術が必要なのです。
“苦手”か“ハラスメント”か?:見分けるためのチェック表



「自分が未熟なだけかも…」と悩む前に、その言動が指導の範囲を超えていないか、冷静にチェックしてみましょう。
健全な指導とハラスメントの境界線
| 〇 健全な指導 | × ハラスメント |
| 業務の改善を目的に、具体的に指摘する | 「だからお前はダメなんだ」と人格を否定する |
| みんなの前で注意するが、フォローもする | 大勢の前で見せしめのように、執拗に叱責する |
| 失敗の理由を問い、再発防止策を一緒に考える | 理由も聞かずに一方的に罵倒する |
| 仕事の能力について、客観的な事実を伝える | 容姿や家族など、業務に関係ないことを揶揄する |
| 難しい業務を任せ、成長を期待しサポートする | 到底できない量の仕事や、わざと失敗するような仕事を押し付ける |
この境界線は、「あなたの成長につながるか(業務関連性・育成意図)、それとも心を傷つけるだけの個人攻撃か」です。
記録に残す(誰が・いつ・どこで・何を・どの言葉で・結果)
もし「ハラスメントかも」と感じたら、次の6つの観点でメモを取り始めましょう。スマホのメモ帳で構いません。
- 誰が (Who): その先輩の名前
- いつ (When): 年月日、時間(例:7月30日 14:15頃)
- どこで (Where): スタッフルーム、〇〇さんの居室前など
- 何を (What): 具体的にされたこと(例:報告書を目の前で破られた)
- どの言葉で (Which): 言われた言葉をそのまま記録(例:「こんなの報告書じゃない」と言われた)
- 結果 (Result): その結果どうなったか(例:他の職員の前で屈辱を感じ、書き直すのに1時間かかった。精神的に落ち込み、頭痛がした)
相談するべきサイン
次のような兆候が見られたら、一人で抱え込まず、すぐに信頼できる上司や窓口に相談するべきサインです。
- 人格否定: 「バカ」「死ね」など、存在を否定する暴言。
- 継続的な業務阻害: 必要な情報をわざと与えない、仕事を押し付けるなど、明らかに業務に支障が出ている。
- 安全リスク: 利用者さんやあなたの安全を脅かすような指示や行動がある。
今日からできる即効テク:現場でのストレスを減らす具体策



理屈はわかっても、現場ではとっさの対応が難しいもの。
ここでは、今日からすぐに使える具体的なフレーズや行動を紹介します。
言い方テンプレ(DESC法)
感情的にならず、冷静に、かつ誠実に自分の要求を伝えるためのフレームワークが「DESC(デスク)法」です。
- D (Describe): 客観的な事実を描写する
- E (Express/Explain): 自分の気持ちや考えを表現・説明する
- S (Specify): 具体的な提案・要望を伝える
- C (Choose): 相手の反応によって、どうするか選択肢を示す
依頼・断り・訂正・お願いのフレーズ集
- 理不尽な叱責に訂正を入れたい時
(D)「先ほど『何度言っても覚えない』と仰いましたが、その件について伺うのは今日が初めてです。」
(E)「そのように言われると、まるでぼくが話を全く聞いていないようで、とても悲しい気持ちになります。」 (S)「もし可能でしたら、今一度、正しい手順を教えていただけますでしょうか。」
(C)「もし難しいようでしたら、〇〇リーダーに確認いたします。」 - 曖昧な指示に確認を入れたい時
(D)「先ほど『あれ、やっといて』とご指示がありましたが、」
(E)「ぼくの認識がずれているとご迷惑をおかけしてしまうので、」
(S)「具体的に『〇〇の件を、△△まで進める』という認識で合っているか、確認させていただけますか。」 - 仕事を丸投げされそうになった時
(D)「今、〇〇の介助記録と、△△の準備を抱えております。」
(E)「その業務も引き受けると、どちらも中途半端になり、ミスにつながる可能性があります。」
(S)「恐れ入りますが、優先順位をご指示いただくか、他の方にお願いすることは可能でしょうか。」
トラブル回避の方法
「言った」「言わない」のトラブルを避けるため、意図的に記録に残るコミュニケーションを心がけます。
- 口頭で指示を受ける: まずは普通に話を聞きます。
- メモで復唱確認: 「失礼します。聞き間違いがないようにメモを取りながら確認させてください」と言って、目の前でメモを取る。
- 申し送り表・連絡ノートに転記: 「先ほど〇〇先輩からご指示いただいた件、申し送りノートにも記載しておきますね」と、公式な記録媒体に残す。
- (あれば)チャットツールで確認: 「先ほどの件、念のためチャットでも共有いたします」とダメ押しする。
この「記録に残す」という姿勢を見せるだけで、相手は無責任な言動をしにくくなります。
確認するべき3つのポイント
曖昧な指示は、トラブルの元です。必ず次の3点を確認する癖をつけましょう。
- 主語の確認: 「そのご指示は、〇〇先輩個人のご判断ですか?それとも施設の公式な方針でしょうか?」
- 期限の確認: 「その作業は、いつまでに完了すればよろしいでしょうか?」
- 優先順位の確認: 「今やっているAの作業と、新しく指示されたBの作業、どちらを優先すべきでしょうか?」
距離の作り方
- 頻度・時間: 休憩時間をずらす、業務上不要な会話は早めに切り上げる。
- 場所: スタッフルームなど、密室になりやすい場所での接触を避ける。用事があるなら、オープンなデイルームなど人目のある場所で話す。
- 1対1回避: 報告・連絡・相談をする際は、なるべく他の職員がいるタイミングを見計らう。「〇〇さんと一緒にご報告に伺います」と、第三者を巻き込む。
自分を守る「おまじない」
カッとなりそうな時、落ち込みそうな時に、心の中で唱える短い言葉を用意しておきましょう。
反応を数秒遅らせるだけで、冷静になれます。
- 「これは、相手の問題であって、ぼくの問題ではない」
- 「はいはい、事実だけ記録、事実だけ記録」
- 「反応しない、反応しない。ただ、対応するだけ」
- 「大丈夫。ぼくはちゃんとやっている」
職場の仕組みで解決:中期的な改善策



個人のスキルだけでは限界があります。
職場全体を働きやすい環境に変えていく視点も持ちましょう。
申し送り・手順の標準化(曖昧さを減らすフォーマット例)
「あの人のやり方」ではなく、「施設のやり方」を確立することが重要です。
リーダーや管理者に、「業務の属人化を防ぎ、新人さんも含めて全員が同じ品質のケアを提供できるように、申し送りや手順書のフォーマットを統一しませんか?」と提案してみましょう。
【提案フォーマット例】
- 項目: 利用者名/時間/内容/特記事項/担当者
- ルール: 曖昧な表現(「適宜」「しっかり」など)を避け、具体的な数値や行動で記述する。
メンター/第三者配置(1on1・同席・三者面談の活用)
「先輩とのコミュニケーションで悩んでいるので、一度リーダー(主任)にも同席していただいて、業務の進め方についてすり合わせをさせていただけませんか?」とお願いするのも手です。
第三者が入るだけで、相手の言動が客観的になり、冷静な話し合いがしやすくなります。
シフト・担当再編(接触点を最小化する)
上司に相談する際、「可能であれば、〇〇さんとは別のユニットやシフトにしていただくことはできませんか」と具体的に要望を伝えることも選択肢の一つです。
その際は、感情的に「嫌だから」ではなく、「業務効率を上げるため」「より良いケアに集中するため」という前向きな理由を添えましょう。
評価・面談を活かす
定期的な人事評価や面談は、絶好の機会です。
自分の目標設定の際に、「チーム内での円滑なコミュニケーション」といった項目を入れ、その達成のために「先輩との関わり方で悩んでいる点があり、ご相談したいのですが…」と切り出せば、上司も公式な課題として受け止めやすくなります。
相談フロー:円滑な相談のやり方



証拠も揃え、いざ相談するとなった時の具体的な手順です。
相談の順番(同僚→リーダー/主任→管理者→人事等)
- 信頼できる同僚: まずは一番身近な味方を見つけ、客観的な意見をもらいます。感情的な愚痴に終始せず、「こんなことがあったんだけど、どう思う?」と冷静に事実を伝えます。
- リーダー/主任(直属の上司): 最初に相談すべき公式な相手です。現場の状況を一番よく理解しています。
- 管理者(施設長・部長): 直属の上司に相談しても改善が見られない場合、さらにその上の上司に相談します。
- 本社人事・コンプライアンス窓口: 施設内で解決が難しい場合や、ハラスメントが深刻な場合は、法人の相談窓口を利用します。
- 外部の相談先: それでも解決しない場合の最終手段です。
伝え方テンプレ(事実→影響→要望→代替案の順で)



上司に相談する際は、感情的に訴えるのではなく、ビジネスライクに、かつ困っていることが明確に伝わるように構成します。
【相談テンプレ】
「〇〇リーダー、今少しよろしいでしょうか。〇〇さんとの業務上の関わり方についてご相談があります。
(事実) 先週から、〇〇さんから指示を受ける際に、『こんなことも分からないのか』といった厳しい言葉を使われることが続いています。
また、昨日15時には、ぼくが作成した介助記録について、他の職員もいる前で『全く意味がない』と指摘を受けました。(※用意した記録メモを見せながら)(影響) そのような状況が続き、精神的に萎縮してしまい、本来であればすぐに確認すべきことでも質問をためらうようになってしまいました。このままでは、利用者様へのケアに必要な情報連携にミスが起きるのではないかと懸念しています。
(要望) つきましては、一度リーダーにも間に入っていただき、〇〇さんとぼくの3人で、業務上の報告・連絡・相談のルールについて、改めて確認する場を設けていただけないでしょうか。
(代替案) もし三者面談が難しいようでしたら、まずはリーダーに、〇〇さんへ業務指示の出し方について、ご助言いただくことは可能でしょうか。」
面談の記録術
相談した際は、必ず「何を話し、何が決まったか」を記録に残します。
可能であれば、面談後に「本日の面談内容について、認識の齟齬がないよう、メモを共有させていただきます」とメールなどで送付すると確実です。
- 合意事項: 「〇〇については、△△というルールで進める」
- 担当者・期限: 「この件は、〇〇リーダーが、△月△日までに対応する」
- 再確認日: 「1週間後の△月△日に、再度状況についてお話しする時間を設ける」
外部の相談先の考え方
職場内で解決が難しい場合は、外部の力を借りましょう。
- 探し方: 「〇〇県 労働相談」などで検索すると、各都道府県の労働局が設置している「総合労働相談コーナー」が見つかります。無料で、専門の相談員が対応してくれます。
- 匿名性と守秘義務: これらの公的機関は、匿名での相談も可能で、守秘義務があります。安心して相談できますが、「会社に指導してほしい」など具体的な対応を望む場合は、実名を明かす必要が出てくることもあります。
心を守るセルフケア



消耗しきってしまう前に、自分で自分の心を手当てする方法も知っておきましょう。
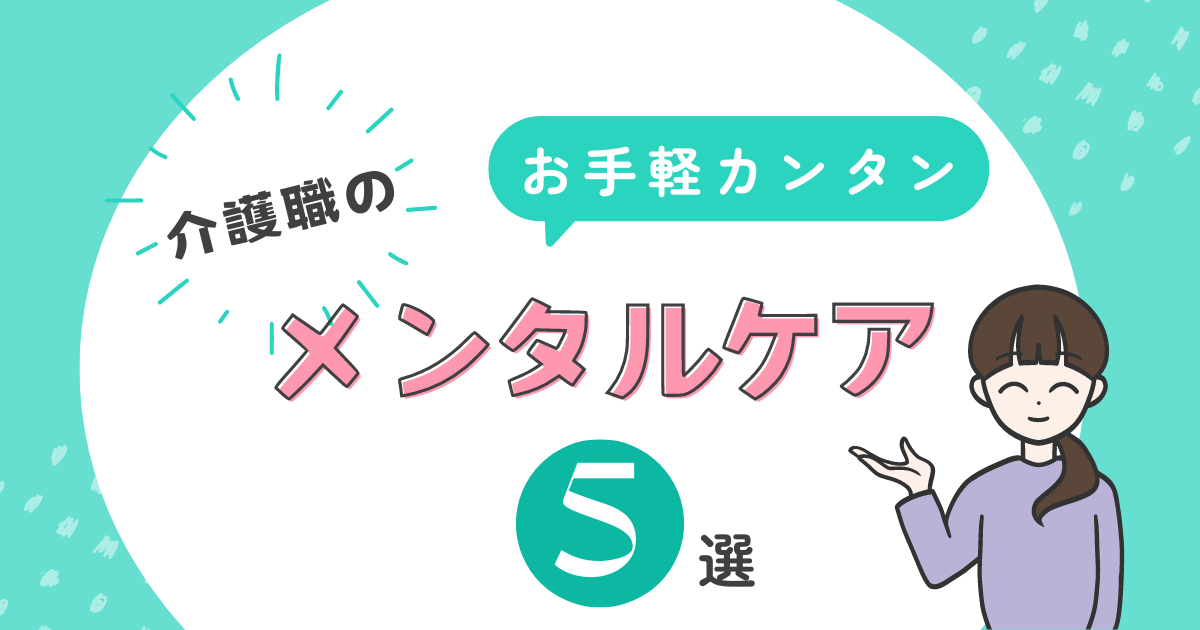
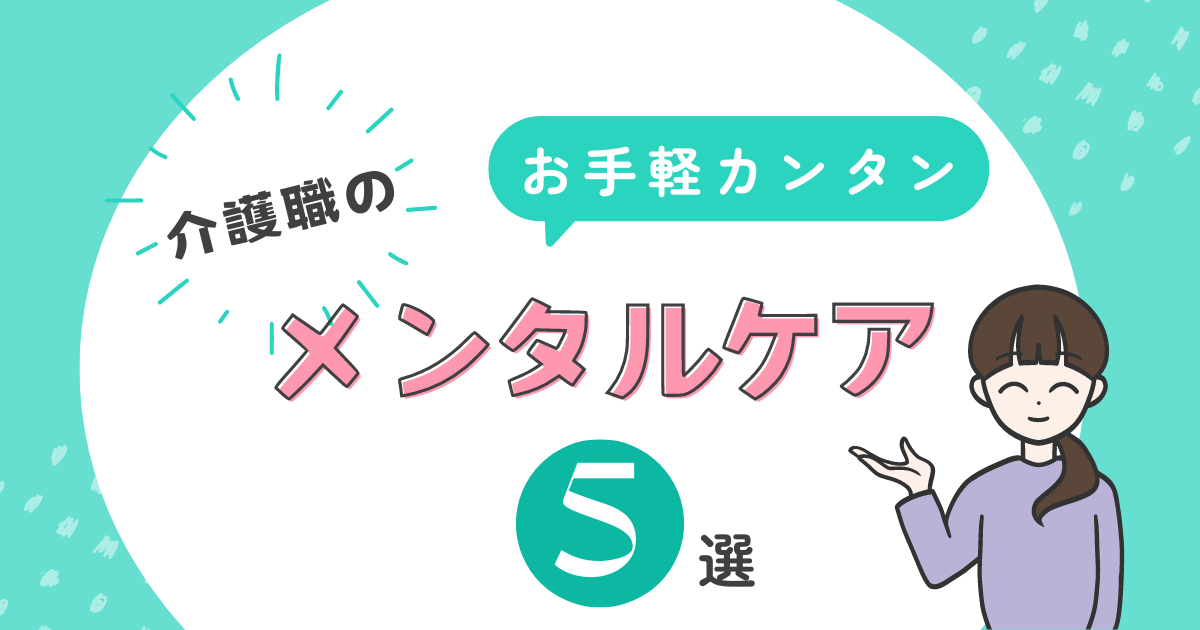
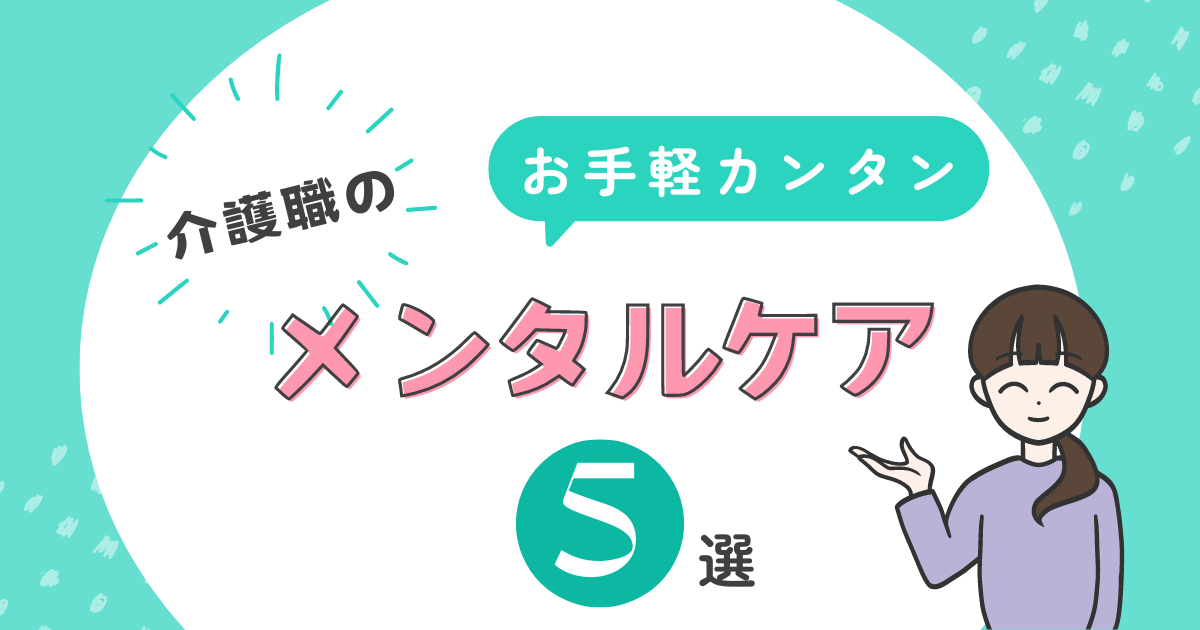
「事実/解釈/反応」を3行で分けて書くメモ法
嫌なことがあると、頭の中で事実と自分の感情がごちゃ混ぜになります。
これを意識的に切り分けるだけで、冷静になれます。
- 事実: 先輩に「仕事が遅い」と言われた。
- 解釈: (ぼくはなんてダメなんだろう。嫌われているに違いない。)
- 反応: (胸が苦しい。落ち込む。もう辞めたい。)
書き出してみると、「嫌われている」というのは、あくまで自分の「解釈」であって、「事実」ではないことに気づけます。
変えられるのは「解釈」と「反応」の部分です。
1分呼吸とマイクロ休憩(交代時の合図・許可の取り方)
気持ちが高ぶったり、落ち込んだりした時は、トイレなどで1分だけ時間を取り、深くゆっくりとした呼吸を繰り返します。「4秒吸って、7秒止めて、8秒で吐く」など、自分なりのリズムでOKです。
その場を離れる際は、「すみません、少しお手洗いに行ってきます」と一声かければ問題ありません。
趣味・回復行動の最小単位(5分でできる回復リスト)
疲れて帰ってきて「何もする気力がない…」という日でもできる、ごく小さな回復行動のリストを作っておきましょう。
- 好きな音楽を1曲だけ聴く
- 温かいお茶を一杯、ゆっくり飲む
- ベランダに出て5分だけ外の空気を吸う
- 好きな漫画を3ページだけ読む
「5分だけ」というのがポイントです。
ハードルを下げることで、心のエネルギーを少しだけ充電できます。
シチュエーション別の対処法(ケーススタディ)



陰口・噂話に巻き込まれる
先輩が誰かの悪口を始めたら、「そうなんですね…」と曖昧に相槌を打ちつつ、「あ、すみません、〇〇さんをコール対応しないと!」など、業務を理由にそっとその場を離れます。
絶対に同調したり、自分の意見を言ったりしてはいけません。
理不尽な指摘・当てつけ
「これはマニュアルに沿って実施しましたが、何か変更点がありましたでしょうか?」と、個人のやり方ではなく、組織のルールを盾にして質問で返します。
相手の土俵に乗らず、あくまで業務確認のスタンスを崩さないのがコツです。
丸投げ・責任転嫁
指示を受けた時点で、
「この業務の責任者は〇〇先輩という認識でよろしいでしょうか?」
「もし判断に迷うことがあれば、ご相談させていただきたいので、よろしくお願いします」
と、責任の所在を言葉にして確認しておきます。
指導が厳しいだけのパターン
本当に悪意はなく、ただ伝え方が不器用なだけの先輩もいます。
その場合は、
「ご指導いただき、ありがとうございます。次に活かしたいので、具体的にどの部分を、どう改善すればよいか、教えていただけますか?」
と、前向きに、かつ具体性を求める質問で返すと、相手も冷静に教えるモードに切り替わりやすくなります。
安全を脅かす指示
「このやり方では、利用者さんが転倒するリスクが高い」
「衛生的に問題がある」
など、利用者さんや職員の安全に関わると判断した場合は、その場で業務を中断する勇気が必要です。
「申し訳ありません。この方法では安全を確保できないと判断しました。すぐにリーダーに報告し、指示を仰ぎます」と毅然とした態度で伝え、即座に報告しましょう。
これはあなたの義務でもあります。
心理学に基づいたコミュニケーション技法



ぼくがこの記事でお伝えしていることは、単なる精神論ではありません。
心理学や組織論に基づいた、再現性のある技術です。
DESC法/アサーティブの基本要素
自分も相手も尊重する、誠実で対等な自己表現の方法です。
言いにくいことを我慢してストレスを溜める(ノンアサーティブ)のでもなく、攻撃的に相手を打ち負かす(アグレッシブ)のでもない、第三の道です。
NVC(非暴力コミュニケーション)の観察→感情→ニーズ→リクエスト
NVCは、相手への共感と、自分自身の内なる声に耳を傾けることを重視するコミュニケーション手法です。
- 観察(Observation): 評価や判断を交えずに、起こっている事実だけを見る。
- 感情(Feeling): それを見て、自分がどう感じているかを認識する。
- ニーズ(Needs): その感情の根底にある、自分の大切な願い(ニーズ)に気づく。
- リクエスト(Request): そのニーズを満たすために、相手に具体的なお願いをする。
この考え方は、感情的な対立を避ける上で非常に役立ちます。
職場ストレスの予防策
- 一次予防: ストレスの原因そのものを取り除く(例:職場の仕組み改善、業務標準化)。この記事でいう「職場の仕組みで解決」がこれにあたります。
- 二次予防: ストレスに気づき、早期に対処する(例:セルフケア、相談スキル)。「即効テク」や「セルフケア」が中心です。
- 三次予防: ストレスで心身に不調をきたした人へのケア(例:休職、専門治療)。ここまで進む前に、一次・二次予防で食い止めることが何より重要です。
裏目に出るNGな対応



良かれと思ってやったことが、裏目に出ることもあります。
次の行動は避けましょう。
- 証拠を残さない: 口頭でのやりとりのみで、記録がないと「言った・言わない」の水掛け論になり、誰も助けてくれません。
- 感情的な応酬: 相手と同じ土俵で怒鳴り合っても、何も解決しません。あなたの立場が悪くなるだけです。
- 同僚を味方に付ける前に直談判: 一人で戦いを挑むのは無謀です。まずは周囲の状況を確認し、客観的な事実を集め、相談できる味方(上司含む)を確保してから動きましょう。
- 被害の一般化: 「みんな迷惑してるんです!」と主語を大きくすると、「あなたはそうでも、他の人は違う」と反論されやすくなります。あくまで「“私は”こう感じ、業務に“こういう”支障が出ています」と、自分を主語にして伝えましょう。
体験談と成功パターン



介護職Aさんのケース:3週間で摩擦が半減したメモ術
Aさんは、指示が曖昧な上に気分で言うことが変わる先輩に悩んでいました。
そこで、指示を受けるたびに「すみません、復唱しますね」とメモ帳を開き、
①指示内容、②期限、③優先順位をその場で読み上げて確認するようにしました。
最初は嫌な顔をされたそうですが、3週間続けると、先輩の側が曖昧な指示を出すこと自体が減り、無用な摩擦が劇的に半減したのです。
介護職Bさんのケース:巻き込み回避動線+第三者同席で改善
Bさんは、特定の先輩から常に面倒な利用者さんの対応を押し付けられていました。
そこで、まずリーダーに「業務の平準化について相談したい」とアポイントを取り、「誰がどの業務をどれだけやっているか」を客観的に記録したメモを持参。
感情的に訴えるのではなく、「このままでは特定の職員に負荷が偏り、ケアの質の低下が心配です」と伝えました。結果、リーダー同席のもとで業務分担を見直す話し合いの場が設けられ、状況が改善されたのです。
よくある質問(Q&A)
- 先輩に反論するとさらに関係が悪化しませんか?
-
「反論」ではなく、「提案」や「確認」という形で伝えるのがポイントです。DESC法のように、相手への配慮を示しつつ、客観的な事実とこちらの要望をセットで伝えることで、単なる感情的な反発だと思われにくくなります。関係が悪化することを恐れて何も言わずにいると、相手は「何を言っても許される」と認識し、状況はさらにエスカレートする可能性が高いです。
- どこからがハラスメント?証拠は何が有効?
-
「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること」がハラスメントの基本的な考え方です。人格否定、暴力、孤立させるなどの行為は明確なハラスメントです。有効な証拠は、①いつ、どこで、誰に、何を言われ、どうされたかを詳細に記録したメモ(継続性が重要)、②暴言等の録音データ、③同僚の証言、④医師の診断書などです。
- 相談しても変わらない時、異動・転職はいつ判断?
-
段階を踏んで相談しても(リーダー→管理者→人事など)、組織として全く動いてくれない、改善の兆しが見えない場合。そして、心身に不調(眠れない、食欲がない、頭痛が続くなど)が出始めたら、それはあなたの心と体が発している限界のサインです。我慢し続けるメリットはありません。あなたのキャリアと健康を守るために、異動や転職を真剣に検討すべきタイミングです。
- 夜勤の少人数帯で逃げ場がない時のコツは?
-
夜勤帯は特に精神的な距離の確保が重要です。①必要最低限の業務連絡以外は関わらない、②仮眠・休憩時間はきっちり分け、別々の場所で過ごす、③何かあった時のために、緊急連絡先やオンコールのリーダーの連絡先をすぐ取れる場所に置いておく、といった対策で物理的・心理的な安全地帯を作りましょう。「自分を守る合言葉」も夜勤では特に有効です。
- 新人の自分が言っても通りません……どう進める?
-
新人のうちは、真正面から意見を言うのは難しいかもしれません。まずは、「教えてください」というスタンスを徹底しましょう。「〇〇というやり方もあるとマニュアルで読んだのですが、先輩がなさっている方法の意図を勉強のために教えていただけますか?」と質問の形で伝えることで、相手のプライドを傷つけずに問題提起ができます。また、メンターや指導担当の先輩、同期など、相談しやすい味方を一人でも見つけることが最初のステップです。
まとめ
ここまで長い文章を読んでくださり、本当にありがとうございます。
あなたの辛い気持ちが、少しでも軽くなっていれば嬉しいです。
最後に、明日からできることを3つに絞りました。
全部やろうとせず、まずは一つからで大丈夫です。
①テンプレ1つ覚える
「言い方テンプレ(DESC法)」の中から、自分が一番使えそうなフレーズを1つだけ選び、お守りのように覚えておきましょう。いざという時に、あなたを守る武器になります。
②記録を始める
スマホのメモ帳で構いません。「いつ、誰に、何をされたか」という事実の記録を、今日から始めてみてください。これは誰かに見せるためだけでなく、あなた自身の頭を整理し、客観的に状況を把握するための大切な作業です。
③相談の約束を取る
一人で抱え込まないでください。
信頼できる同僚やリーダーに、「少しご相談したいことがあるのですが、明日の休憩時間に5分だけお時間いただけますか?」と、具体的な日時を指定して約束を取り付けましょう。
「いつか相談しよう」では、永遠にその日は来ません。
あなたは一人ではありません。
あなたの介護という仕事への想いが、一人の苦手な先輩のせいで潰されてしまうのは、あまりにもったいない。
どうか、あなた自身を一番に大切にしてください。
心から応援しています。

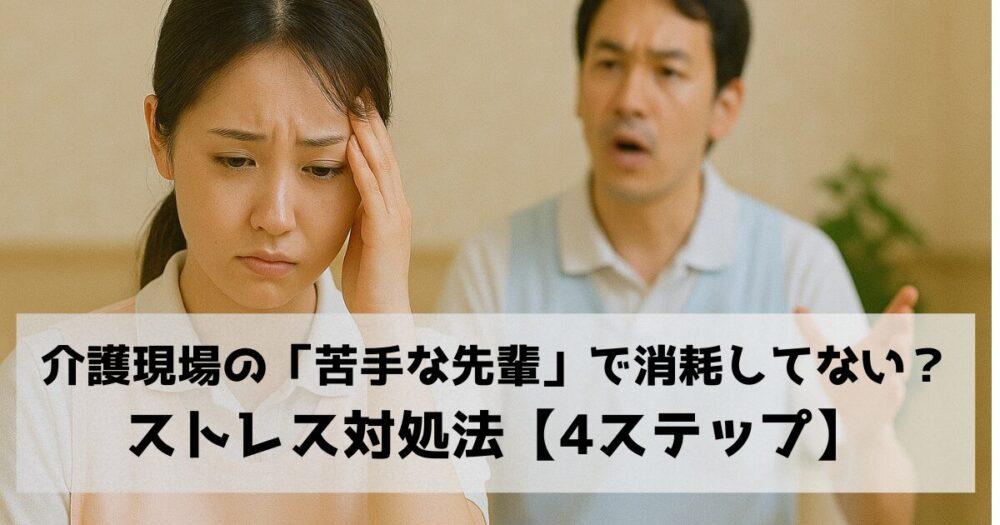

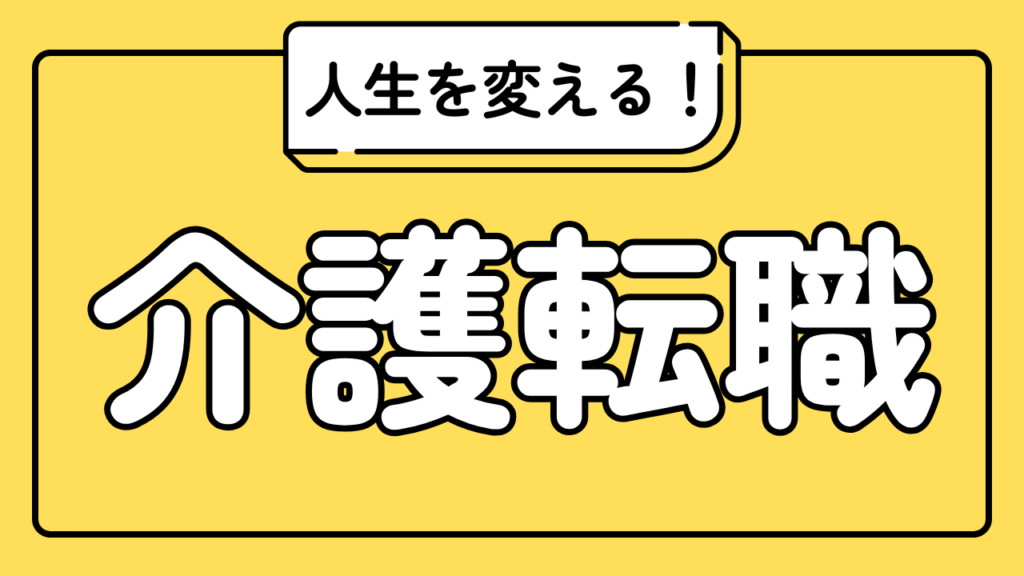

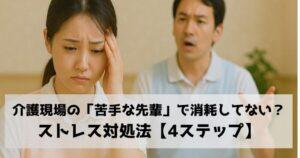



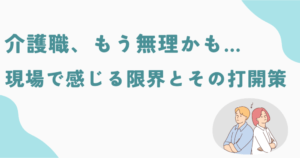
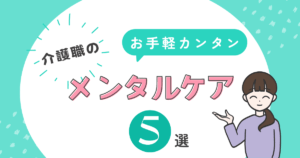




コメント