介護現場で頭を悩ませる問題のひとつが、
利用者さんの「おむつ外し」ですよね。
おむつを外して、尿汚染。
下手をすれば、便汚染……
シーツ交換や着替えでイライラ、
つい「どうして!」と声を荒らげたくなってしまう……
その気持ち、痛いほどわかります。
でも、ちょっとだけ視点を変えてみませんか?
まず結論、
おむつ外しを減らす方法は次のとおり。
- 不快感をゼロに近づける!「ジャストフィット装着術」
- 寝る前の1分で変わる!「パジャマの着せ方」
- 行動を先回りする!「就寝前のトイレ習慣」
- 手の寂しさを解消する!「安心グッズ」を活用
- 「もぞもぞ」を見逃さない!「声かけ」による予防
この記事では、ぼくが15年以上の介護現場で試行錯誤してきた、具体的な対策を5つ紹介します。
イライラするのではなく、理由を探って先回りする。
そんな視点で、毎日のケアを楽にするヒントが見つかれば嬉しいです。
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー
【発信・活動】
・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信
https://x.com/@kaigo3939
・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解
https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo
・note:介護現場の裏話&試験対策
https://note.com/gentle_ferret775
・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)
通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく
https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載
【厳選】おむつ外しを減らす方法5選



おむつ外しは、ご本人からの「サイン」です。
おむつ外しの根本原因にアプローチできる、効果的な5つの方法はこちら。
- 不快感をゼロに近づける!「ジャストフィット装着術」
- 寝る前の1分で変わる!「パジャマの着せ方」
- 行動を先回りする!「就寝前のトイレ習慣」
- 手の寂しさを解消する!「安心グッズ」を活用
- 「もぞもぞ」を見逃さない!「声かけ」による予防
詳しく見ていきましょう。
1. 不快感をゼロに近づける!「ジャストフィット装着術」
【なぜ効果的?】
おむつ外しの最大の原因は「不快感」です。
蒸れ、かゆみ、食い込みといった不快感をなくせば、外そうと思うきっかけ自体が生まれません。
これは全ての基本です。
【具体的なやり方】
- ① サイズの再確認: まず、おむつの袋に書いてある「ヒップサイズ」とご本人のサイズが合っているか確認します。特に痩せたり太ったりした後は、サイズが合わなくなっていることがあります。
- ② “指1本”のゆとりチェック: テープを留めた後、お腹周りや足の付け根(鼠径部)に、指が1本スッと入るくらいの余裕があるか確認します。きつすぎても、ゆるすぎても違和感の原因になります。
- ③ 装着時の“シワ伸ばし”: おむつを体に当てた後、お腹側とお尻側の両方から、手のひらで優しくなでるようにして、おむつと肌の間のシワをしっかり伸ばします。シワがあるだけで、ゴワゴワして気持ち悪いものです。



メーカーによって同じMサイズでも微妙に形が違います。
もし今のものがしっくりこないなら、別のメーカーのサンプルを試してみるだけで、驚くほどフィットすることがありますよ。
ダメもとで試してみましょう。
2. 寝る前の1分で変わる!「パジャマの着せ方」
【なぜ効果的?】
無意識に手が伸びてしまっても、物理的におむつに触れにくくする、シンプルかつ非常に効果的な方法です。
【具体的なやり方】
- ① 上着をズボンに入れる: パジャマの上着の裾(すそ)を、ズボンの中にしっかりと入れ込みます。
- ② ズボンをおへその上まで引き上げる: ズボンのウエストゴム部分を、おむつの上部がすっぽり隠れるくらい、おへその上あたりまでしっかり引き上げます。
- ③ 仕上げに「腹巻き」をプラス: ①と②の上に、薄手の腹巻きを一枚巻きます。これにより、ズボンがずり下がってくるのを防ぎ、お腹から手が入り込む隙間がなくなります。
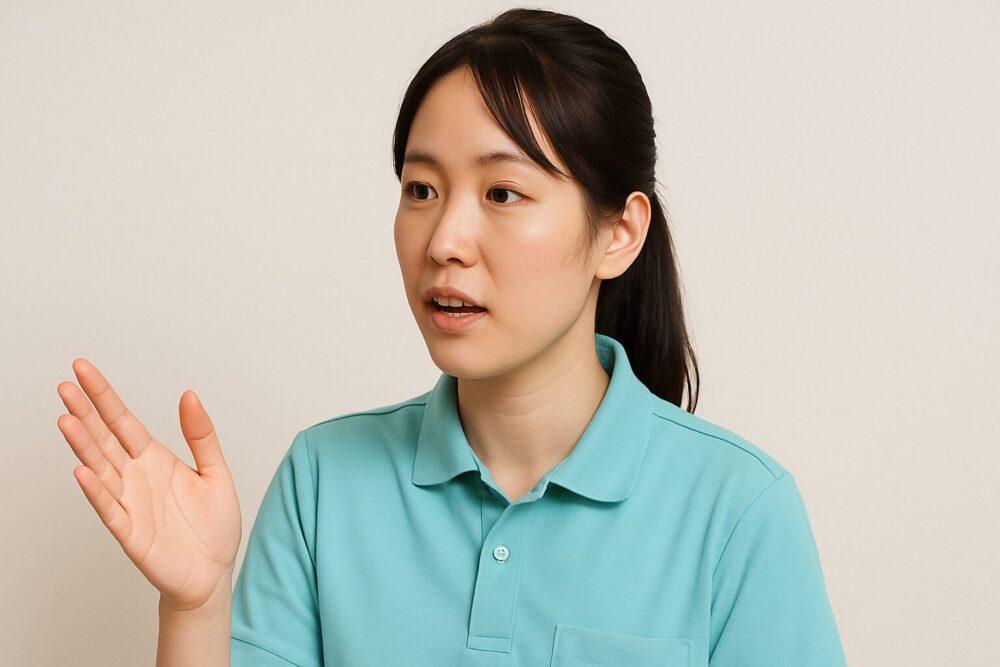
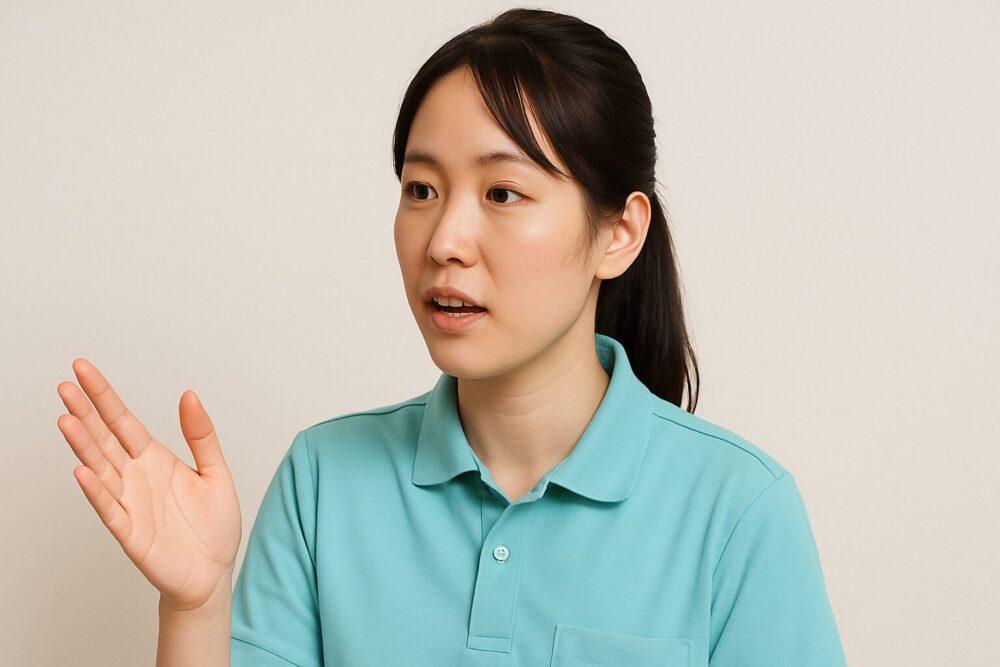
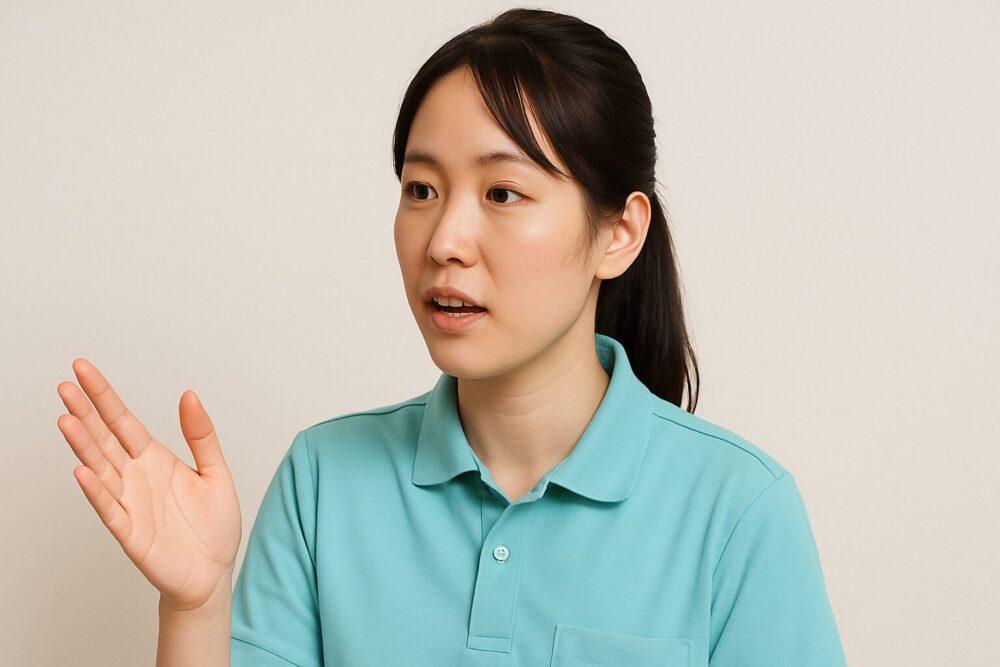
腹巻きは、締め付けの強くない、綿素材などの肌に優しいものがおすすめです。
「お腹が冷えなくて気持ちいいですよ」と声をかけながら装着すると、ご本人も受け入れやすくなりましたよ。
3. 行動を先回りする!「就寝前のトイレ習慣」
【なぜ効果的?】
「トイレに行きたい」という生理的な欲求が、おむつを外す行動に繋がるケースが多いです。
寝る前に排泄を済ませておくことで、夜中に尿意や便意で目覚める可能性をぐっと減らせます。
【具体的なやり方】
- ① 就寝時間の30分~1時間前に: 「そろそろ休みましょうか。その前に、お手洗いに行っておくと、夜ぐっすり眠れますよ」と優しく誘います。
- ② トイレに座るだけでもOK: 尿意がなくても、便座に座ることで排泄が促されることがあります。焦らせず、数分間リラックスできる時間を作りましょう。
- ③ 毎日の“儀式”にする: これを毎日の習慣にすることで、「寝る前はトイレに行くものだ」というリズムが体に染みつき、ご本人も安心して眠りにつきやすくなります。



もしトイレ誘導を拒否された場合は、無理強いしないのがポイントです。
「おむつが気持ち悪くないかだけ、ちょっと見てもいいですか?」と、おむつのチェックに切り替えるなど、柔軟に対応しましょう。
4. 手の寂しさを解消する!「安心グッズ」を渡す
【なぜ効果的?】
特にやることがなく、手持ち無沙汰な時に、無意識に体を触ってしまうことがあります。
その手に、何か心地よい「仕事」を与えてあげることで、意識をそらすことができます。
【具体的なやり方】
- ① 柔らかいものを渡す: 肌触りの良い、小さなぬいぐるみやクッション、丸めたタオルなどを「これ、よかったらどうぞ」と手渡します。
- ② ご本人の“お気に入り”を探す: 人によって、ツルツルしたものが好きな方、ふわふわしたものが好きな方など好みがあります。色々試して、その方が落ち着く「安心グッズ」を見つけてあげましょう。
- ③ ミトンは最終手段と心得る: 手指の動きを完全に封じ込めるミトンは、ご本人にとって大きなストレスになります。まずは、こうした代替物で注意をそらす方法を試してください。ミトンの使用は身体拘束になるので注意しましょう。



昔、編み物や手芸をされていた方なら、毛糸の玉を渡すだけでも落ち着かれることがあります。
その方の人生背景を知ることが、最適なグッズを見つける最大のヒント。
もう一度、利用者さんの情報ファイルを開いて、生活歴をチェックしてみましょう。
5. 「もぞもぞ」を見逃さない!「声かけ」による予防
【なぜ効果的?】
おむつを外す行動は、いきなり始まりません。
その前に必ず「手が股間に伸びる」「ベッドの上で何度も体勢を変える」といった小さなサインがあります。
このサインの段階で介入することで、おむつ外しを未然に防げます。
【具体的なやり方】
- ① サインに気づく: いつもと違う様子、そわそわ、もぞもぞした動きにアンテナを張ります。
- ② 否定せず、共感する: 「どうしましたか?」「なんだかお腹のあたりが気持ち悪いですか?」と、ご本人の不快感を代弁するような言葉で話しかけます。
- ③ 具体的なケアを提案する: 「少しお洋服を直しましょうか」「おむつの中、蒸れてないか見てみますね」と、これから何をするかを伝え、安心感を与えながら確認します。



声かけは「監視」ではなく「見守り」です。
「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージが伝わることが一番大切。
やさしい口調と眼差しを意識するだけで、ご本人の反応は全く違ってきますよ。
ユマニチュードというフランスのケア技法がおすすめ。
詳しくはこちら【常識が変わる!?】ユマニチュードというフランスのケア技法
場面別のおむつ外し予防策



おむつ外しは、どの場面で起きるかによって、ご本人が感じている「不快」や「不安」の種類が違います。
場面ごとの気持ちに寄り添って、ピンポイントで対策していきましょう。
場面1:【夜間】気づいたらベッドの上で外している…



夜中に目が覚めたとき、ご本人はこんな気持ちかもしれません。
- ご本人の気持ち
- 「なんだかお尻が気持ち悪いな…重たいし、濡れてて冷たい…」
- 「暑くて蒸れる…。かゆいな…」
- 「トイレに行きたい気がする…どうすればいいんだろう?」
- 「目が覚めちゃったけど、することがないな…」(手持ち無沙汰)
▼具体的な予防策
- 就寝前の「トイレ誘導」を徹底する
寝る前に排泄を済ませておくことは、夜間の対策で最も重要です。
「これをすれば、夜中に起きる回数が減りますよ」と伝え、習慣化を目指しましょう。尿意がなくても便座に座るだけで安心感につながります。 - 夜に最適な「吸収量」のパッドを選ぶ
漏れを心配して厚すぎるパッドを着けると、それ自体が蒸れやかゆみの原因になります。逆に薄すぎると、一度の排尿で不快感がMAXに。
ご本人の夜間の尿量に合った、「厚すぎず、薄すぎない」ジャストな吸収量の製品を選びましょう。 - 「腹巻き+パジャマ」で物理的に触りにくくする
パジャマの上着をズボンに入れ、ズボンをしっかりおへその上まで引き上げます。
その上から一枚、伸縮性のある腹巻きをするだけで、お腹から手を入れる隙間がなくなり、無意識に触ってしまうのを防げます。
場面2:【日中の座位】車椅子や椅子に座っている時に外してしまう…



日中、活動が少ない時間帯。ご本人はこんな風に感じているかもしれません。
- ご本人の気持ち
- 「ずっと座ってると、股のあたりが圧迫されて苦しい…」
- 「お尻が蒸れてきて、なんだか気持ち悪いな…」
- 「やることがなくて暇だな…つい、気になるところに手が伸びちゃう…」
▼具体的な予防策
- 座り心地を「クッション」で見直す
長時間座ることで起こる股間の圧迫や蒸れは、大きな不快感です。
体圧を分散してくれるクッションを使ったり、時々お尻を浮かせるように声かけをしたりして、圧を逃がしてあげましょう。 - 「手作業」で意識をそらす
手持ち無沙汰は、おむつに意識が向く大きな原因です。
その方の得意なことや好きなことに合わせて、「タオルをたたむ」「毛糸を丸める」「雑誌をめくる」など、両手を使う簡単な作業をお願いしてみましょう。
手元に集中することで、おむつのことを忘れてくれます。 - 「時間」で区切ってトイレに誘う
ご本人がサインを出す前に、「2時間経ったので、一度トイレに行きませんか?」というように、時間を決めてトイレに誘導する「スケジュール排泄」を取り入れます。
時間を決めてトイレに誘導することにより、不快感がピークに達する前に対処できます。
場面3:【入浴後・更衣直後】着替えたばかりなのに、すぐに外そうとする…



お風呂上がりでさっぱりしたはずなのに、なぜ?ご本人はこんな繊細な感覚を抱いているかもしれません。
- ご本人の気持ち
- 「体はポカポカなのに、おむつがひんやりして気持ち悪い!」
- 「まだ肌が少し湿ってるのに、ピタッとくっついて不快だ…」
- 「服を着る前に、何か変なものを付けられた…」(違和感)
▼具体的な予防策
- 体を「しっかり乾かす」ことを徹底する
特に鼠径部(そけいぶ)や臀部(でんぶ)のくぼみなど、水分が残りやすい場所は、柔らかいタオルで優しく押さえるように、しっかりと水分を拭き取ります。
肌がサラサラの状態だと、不快感が大きく減ります。 - おむつを「人肌」に温めておく
清潔なおむつを、着ける直前に少しだけ温めておく、非常に効果的な方法です。
清潔なタオルの上に置いたり、少しの間、自分の服の中に入れておくだけでOK。肌に触れた時の「ヒヤッ」とする衝撃をなくしてあげます。 - 「温かいひざ掛け」でワンクッション置く
おむつを着けたら、すぐにズボンを履かせるのではなく、まず腰から下に温かいバスタオルやひざ掛けをかけてあげます。
「まずは温まりましょうね」と声をかけ、1〜2分リラックス。肌がおむつの感触に馴染むのを待ってから、ゆっくりと着替えを進めましょう。
事例で学ぶ:おむつ外し改善ビフォー→アフター



実際にぼくの現場であった事例を2つ、ご紹介します。
事例① 夜間のおむつ外しが頻繁だったAさん
- ビフォー:
漏れを心配し、夜間用の厚手パッドを使用。
しかしサイズが微妙に合っておらず、寝返りでズレてしまい、その違和感からおむつを外してシーツを汚染していた。
居室に訪れると、尿汚染したパッドがベッド柵にかけてありました…… - アフター:
Aさんの体型に合うジャストサイズのテープ型おむつに変更。Lサイズ→Mサイズへ。
パッドは夜間用でも少し薄手のものに。1000cc→600ccに変更。
就寝前のトイレ誘導を徹底し、念のため薄手の腹巻きをプラス。
→ 結果、夜間の汚染はほぼゼロになりました。
事例② 日中、車椅子で座っているとパッドを外してしまうBさん
- ビフォー:
日中は穏やかに過ごしているが、ふと気づくとおむつに手を入れてしまう。
器用に尿取りパッドを抜き取り、床にポイっと捨ててしまう。 - アフター:
車椅子のクッションを体圧分散効果の高いものに変更。
おむつのギャザーが食い込まないよう、装着時に丁寧に確認。
さらに、Bさんが好きなぬりえやタオルたたみなど、手先を使う作業をお願いするようにした。
→ 結果、意識が手元の作業に向き、おむつを触る行動がなくなりました。
今日からできる:おむつ外しを減らす環境づくり



ご本人の不快感を取り除くのと同じくらい効果的なのが、「物理的におむつに触りにくくする」環境づくりです。
意識がそこに向かないように、少しだけ工夫してみましょう。
目に入れない・手が届きにくい配置
無意識に手が伸びてしまうのを防ぐ、簡単な工夫です。
- 就寝前に衣類を整える: パジャマのズボンのゴムを、おむつの上までしっかり引き上げ、上着の裾をズボンの中に入れる。これだけで、お腹周りから手が入りにくくなります。
- 重ね着の活用: パジャマの上下の上に、薄手の腹巻きやロンパース型の介護肌着を一枚加えるのも有効です。
特に背中側で留めるタイプは、ご自身で外しにくい構造になっています。
ご自分では脱げない「つなぎ服」を着せるのは身体拘束になるので注意が必要です。
寝具と動線の見直し
特に夜間、目が覚めたときに手持ち無沙汰で触ってしまうことがあります。
- ベッド柵の近くに物を置かない: サイドテーブルなどを少し離し、寝返りを打ったときに手がすぐおむつにいかないようなレイアウトを試してみましょう。「手が遊ばない」環境が大切です。
触っても外れにくい工夫
もし触ってしまっても、カンタンには外れないようにする工夫も有効です。
- テープの留め方を工夫する: テープタイプのおむつの場合、下のテープを少しきつめに「ハの字」に留め、上のテープを平行にしっかり留めることで、ズレにくく、剥がしにくくなります。
- おむつカバーやオーバーパンツの併用: リハビリパンツの上からゆったりとしたオーバーパンツを履いてもらうだけで、直接おむつに触れる機会を減らせます。
装着とサイズのコツ:不快感を作らない
おむつ外しの最大の原因である「不快感」を、そもそも作らないための基本です。
毎日している作業だからこそ、一度見直してみませんか?
サイズをチェック
「たぶん合っているはず」という思い込みが、実は不快感の原因かもしれません。
- 太もも周りに、指が1本スッと入るくらいの余裕はありますか?
- 立った状態で、おむつの中心が股間の中心からズレていませんか?
この2点だけでも、フィット感はかなり変わります。
装着手順の型(基本の確認)
正しい装着が、ヨレやズレ、食い込みを防ぎます。
- ギャザーをしっかり立てる: おむつを広げたら、まず内側にある立体ギャザーを指でしっかり立てます。これが横漏れを防ぐ防波堤になります。
- 体の中心に合わせる: ご本人の背骨とおむつの中心線を合わせます。
- シワを伸ばす: お腹側をかぶせたら、鼠径部に沿ってシワをしっかり伸ばします。シワは皮膚トラブルの原因にもなります。
- テープは下から上に: 下側のテープを斜め上に、上側のテープを平行に留めるのが基本です。
吸収体の選び方
漏れを心配して厚いパッドを選びがちですが、それが逆効果になることも。
- 厚すぎは蒸れの原因に: 必要以上の吸収量のパッドは分厚く、通気性が悪くなりがち。これが蒸れやかゆみにつながり、おむつ外しの引き金になります。
- 薄すぎは漏れによる不快感: 当然ですが、吸収量が足りないとすぐに濡れてしまい、冷たさや不快感で外したくなります。
交換の頻度や尿量に合わせて、最適な吸収量の製品を選ぶことが重要です。
関連記事はこちら
声かけ・置き換え:外す理由を先回りで消す



物理的な環境や装着方法と合わせて行いたいのが、心理的なアプローチです。ご本人の気持ちを先回りして、外す以外の行動に導いていきましょう。
使える声かけ例(尊厳を守る短文)
長々とした説明は必要ありません。安心感を与える短い言葉が効果的です。
- おむつ交換の際、手が伸びてきたら
- 「お腹、きつくないですか?少し整えますね」
- (否定せず、ケアの一環として触れていることを伝える)
- 就寝前や、もぞもぞしているサインを見つけたら
- 「寝る前に、一度トイレに行っておきましょうか?」
- (行動を提案し、選択肢を示す)
手指の“暇つぶし”で注意をそらす
特に認知症の方の場合、手持ち無沙汰から無意識に体を触ってしまうことがあります。そのエネルギーを別のものに向けさせてあげましょう。
- 安全な代替物を渡す: 柔らかいクッションや、肌触りの良いタオルなどを握ってもらう。
- ナイトミトンは最後の手段: まずは、本人が心地よいと感じる代替物を探すことから始めましょう。
ルーティン化
毎日の行動を一定にすることで、ご本人に見通しと安心感を与え、おむつを意識する時間を減らします。
- 就寝前のルーティン例:
- 整容(歯磨きなど) →
- トイレ誘導 →
- パジャマに着替えて装着チェック →
- コップ一杯の白湯を飲む(脱水予防と入眠儀式) →
- 肌触りの良いタオルなどを手に渡す
このような一連の流れを作ることで、スムーズに入眠しやすくなります。
【事例で学ぶ】おむつ外しがあった時のNG対応3選



発見した瞬間の私たちの対応一つで、ご本人の気持ちは大きく変わります。
ついやってしまいがちですが、関係を悪化させ、根本解決から遠ざかってしまう代表的なNG対応を3つご紹介します。
NG対応①:「どうして?」「また!」と感情的に叱る・問い詰める
発見した時、シーツや衣類の汚れを目の当たりにして、どっと疲れが…。
つい、「どうして?」「また!」と感情的になりがちです。
- 【具体例】
- 「どうしてこんなことするんですか!」
- 「もう、またやったんですか!さっき替えたばかりなのに!」
- 強い口調で「だめでしょ!」と言いながら、ご本人の手をパシッと払ってしまう。
- 【なぜNGなのか?】
この対応は、ご本人に「恐怖」と「不安」しか与えません。
ご本人は、悪気があって外したわけではないことがほとんどです。
不快だったり、トイレに行きたかったり、何か理由があっての行動なのに、それを頭ごなしに否定されると、「この人は私のことを分かってくれない怖い人だ」と認識してしまいます。
結果として、職員を避けるようになったり、隠れておむつを外すようになったり、不安からさらにBPSD(行動・心理症状)が悪化することさえあります。信頼関係が崩れてしまう、最も避けたい対応です。 - 【じゃあ、どうすれば?】
まずは一呼吸。「汚れている」という事実と、「ご本人の人格」を切り離して考えましょう。
そして、「あら、外しちゃいましたね。気持ち悪かったですか?大丈夫ですよ、一緒にきれいにしましょう」と、まずは起きた事実を受け入れ、安心させる言葉をかけます。
原因を探るのは、落ち着いて片付けた後で大丈夫です。
関連記事はこちら
NG対応②:周りに聞こえるように言って、恥をかかせる
他の利用者さんや職員がいる前で、恥ずかしさを感じさせるような言動をしてしまうケースです。
- 【具体例】
- 大きな声で「〇〇さん、おむつ外しちゃったから、シーツ交換お願いしまーす!」と同僚に伝える。
- ご本人に「見てください、こんなに汚れちゃって。これじゃあ食堂に行けませんよ」と、みんなの前で諭すように言う。
- 【なぜNGなのか?】
これは、ご本人の「尊厳」と「羞恥心」を深く傷つける行為です。
認知症があっても、プライドや恥ずかしいという感情はしっかりと残っています。
人前で失敗を指摘されるのは、誰だって辛いですよね。
このような対応をされると、ご本人は自尊心を失い、心を閉ざしてしまったり、無気力になってしまうことがあります。
「どうせ自分はダメなんだ」と感じさせてしまい、リハビリやレクリエーションへの意欲を削いでしまうことにも繋がります。 - 【じゃあ、どうすれば?】
発見したら、まずは静かにカーテンを閉めたり、他の利用者さんから見えない場所に移動したりして、ご本人のプライバシーを確保します。
同僚に協力を頼む時も、耳元で「〇〇さんのシーツ交換をお願いできますか」と、状況が周りに分からないように配慮します。
ケアの基本である「尊厳の保持」を、一番に考えましょう。
NG対応③:原因を探らず「つなぎ服」などの身体拘束に頼る
対策を考えることをせず、すぐに行動を制限する「モノ」に頼ろうとしてしまう考え方です。
- 【具体例】
- カンファレンスで「もう何度も続くので、つなぎ服(介護用の拘束衣)を使いましょう」と安易に提案する。
- ご家族に「外してしまうので、ミトン(手袋型の拘束具)の使用を許可していただけませんか?」と、他の対策を十分に試す前に打診する。
- 【なぜNGなのか?】
身体拘束は、介護における「最終手段」です。
ご本人の不快感という根本原因を放置したまま、力で行動を封じ込めるのはNG。 無理やり行動を制限されると、ご本人は極度のストレスを感じ、別の不穏な行動(大声を出す、暴れるなど)を引き起こす可能性があります。
また、長期間の使用は心身機能の低下を招きます。これはプロのケアとは言えません。 - 【じゃあ、どうすれば?】
「なぜ外してしまうんだろう?」と、チームで原因を探ることから始めます。
「夜間に多いね」「このズボンを履いた日だね」「レクリエーションがない暇な時間帯だ」など、記録をもとにパターンを分析します。
サイズの見直し、衣類の工夫、トイレ誘導の徹底など、拘束に頼る前に、やるべきことがたくさんあります。
予防を仕組みにする:チェックリスト



個人の頑張りだけでなく、チーム全体で取り組むことで、おむつ外しの予防はより確実になります。
就寝前のチェックリスト
誰が対応しても同じ水準のケアができるように、指差し確認できるリストです。ぜひ現場で使ってみてください。
- サイズは合ってる?
- ギャザーはしっかり起きてる?
- 鼠径部(そけいぶ)にシワはない?
- 上着をインして、ズボンはおむつの上まで被せた?
- ベッド周りに、すぐ手に取れる物はない?
共有ノート項目テンプレ
もし、おむつ外しが起きてしまったら……
失敗は次の対策を立てるための貴重な情報です。
「なぜ」を分析するために、以下の項目で記録を残しましょう。
- 「いつ」: (例:深夜2時頃)
- 「どこで」: (例:ベッドの上で)
- 「外す前の様子」: (例:もぞもぞして眠れていない様子だった)
- 「装着状態」: (例:パッドが尿で重くなっていた、テープが緩んでいた)
- 「取った対策」: (例:新しいおむつに交換し、腹巻きを着用してもらった)
- 「その後の様子」: (例:落ち着いてすぐに眠った)
介護用品の選び方



様々な介護用品がありますが、それぞれの特徴を理解して使い分けることが大切です。
パンツ型・テープ型の使い分け
- パンツ型: ご自身でトイレに行ける方、立位が安定している方向け。着脱が楽な反面、ご自身でも下げやすいという側面も。
- テープ型: 寝て過ごす時間が長い方向け。体型に合わせてしっかりフィットさせられるのが利点。外しにくさの工夫もしやすいです。
カバー・腹巻き・ロンパース型肌着の活用ポイント
これらは「おむつを隠す」ための道具です。
物理的に触れにくくするだけでなく、「おむつを着けている」という意識を薄れさせる効果も期待できます。
伸縮性があり、肌に優しい素材のものを選びましょう。
取り替えやすさ vs 外されにくさのバランス
介護のしやすさだけを考えると、シンプルな服装が一番です。
しかし、おむつ外しを防ぐためには、一手間かける必要があります。
スタッフの負担と、ご本人の快適さや失禁予防のメリットを天秤にかけ、施設やチームで最適な方法を見つけていくことが大切です。
チームでの再発防止:情報共有と配置の標準化



「あの人が担当の日は大丈夫なのに…」とならないために、ケアの方法を標準化しましょう。
申し送りで共有する“短い一言”の型
忙しい申し送りの時間でも、的確に伝わる工夫です。
- 良い例: 「〇〇さん、夜間は就寝前トイレ誘導と腹巻き併用で、朝まで汚染なく過ごせています」
- NG例: 「〇〇さん、おむつ外し注意です」 (→具体的にどうすればいいか不明)
成功事例を共有することで、チーム全体のケアの質が上がります。
物品の定位置と写真管理
「誰がやっても同じ環境」を再現するために。
- ベッド周りのレイアウト(サイドテーブルの位置など)を決めたら、スマホで写真を撮ってファイルに貼っておく。
- 使用するパジャマや腹巻きなども、写真を撮って「このセットで」と示しておくと、新人スタッフでも迷わず同じケアができます。
まとめ
おむつ外しは、ご本人からの「不快だ」「トイレに行きたい」「なんだか落ち着かない」という、言葉にならない大切なサインです。
そのサインを見つけたら、「なぜだろう?」と考えることから始めてみてください。
- 不快感をゼロに近づける!「ジャストフィット装着術」
- 寝る前の1分で変わる!「パジャマの着せ方」
- 行動を先回りする!「就寝前のトイレ習慣」
- 手の寂しさを解消する!「安心グッズ」を活用
- 「もぞもぞ」を見逃さない!「声かけ」による予防
大変な仕事ですが、一つの工夫がご本人の快適さと、私たちの負担軽減に繋がります。
この記事が、あなたの現場のヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。
頑張るあなたを応援しています。

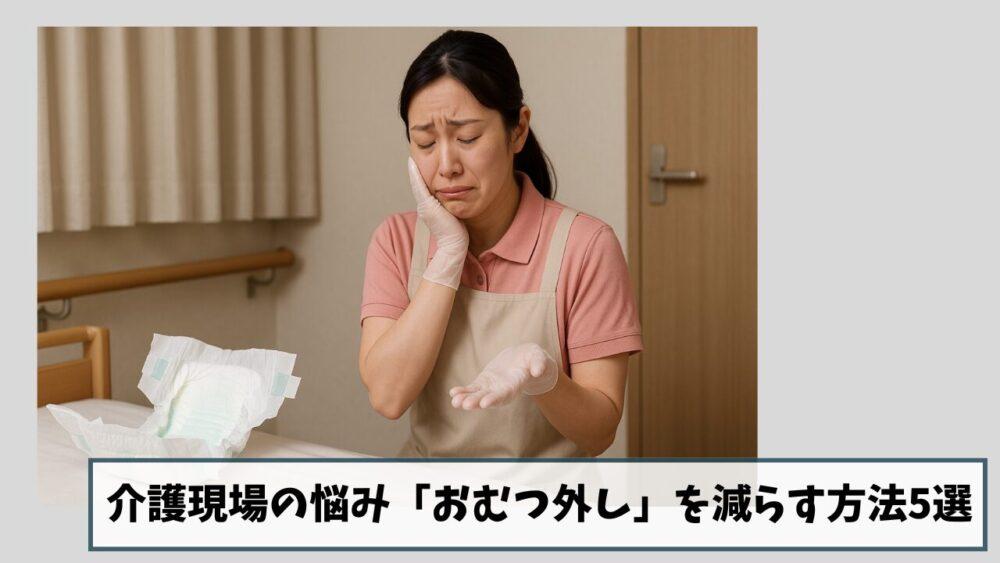
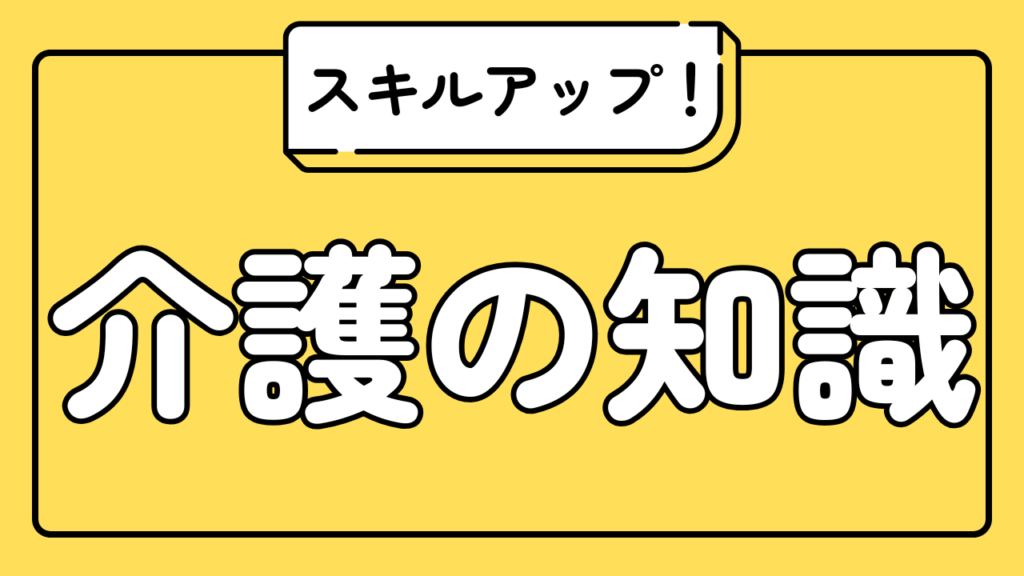






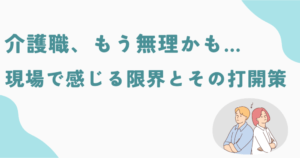
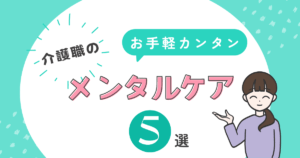




コメント